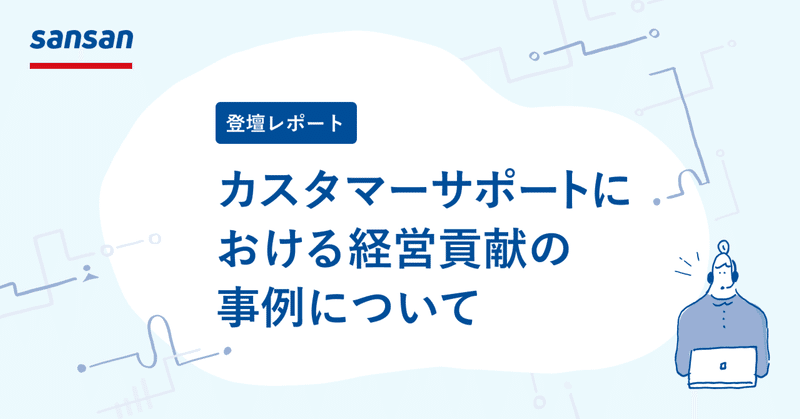
カスタマーサポートにおける経営貢献の事例について〜セミナー登壇レポート〜
こんにちは、Technical Support の 野口 です。
Zendeskさんよりお誘いを受け、一般社団法人日本コールセンター協会主催の「CCAJコンタクトセンター・セミナー2023」で、スピーカーとして登壇してきました。
▼セミナーサイトはこちら
https://ccaj.or.jp/event/contact_20230216.html
セッション概要
モデレーター:Zendesk 長谷川さん
スピーカー:FABRIC TOKYO 佐々木さん、Sansan 野口
お題は『現場担当者が語るカスタマーサポートにおける経営貢献の事例』、FABRIC TOKYOさん、Sansan、2社ともに経営貢献としての “顧客の声” への取り組みを紹介しました。
カスタマーサポートはコストセンターと言われがちで、経営貢献として明確な指標を打ち出せている企業は少ないんじゃないかな、と思っています。そんな中で試行錯誤ではありますが “顧客の声” をプロダクトに還元することは、カスタマーサポートの経営貢献の1つになりうると考えています。
セッション詳細
"顧客の声"とは
「要望です」と言われることだけが要望ではありません。
ユーザーがつまづいた点や勘違いした点は、プロダクトに改善の余地があります。
ユーザーの大きな声も小さな声も適切にプロダクトにフィードバックすることで、プロダクトをユーザーに近づけましょう。
上記はTechnical Support の 行動指針の中にある一文です。
「要望です」とはっきりと言われるわかりやすい声だけを拾い上げるのではなく、問い合わせのもととなったユーザーの “わかりにくい点” や “困った点” を声として拾い上げることがTechnical Support の役割の1つとして考えています。

顧客の声をプロダクトに還元する仕組み
具体的になにをやっているのかと言うと、問い合わせ対応時にオペレーターが問い合わせ1件ずつにラベリングをしていて、そのデータを月次で集計してプロダクトに届けています。
この業務のことを私たちは “プロダクトフィードバック” と呼んでいます。

Technical Supportでは月に数千件を超える問い合わせに対応しています。
この "量の多さ" がTechnical Support の強みであると考えています。
お客様の「この機能をもっとこうして欲しい」や「この画面がわかりにくい!」といった要望としてわかりやすい声は、営業担当やカスタマーサクセス担当が拾い上げ、詳細をヒアリングしてプロダクトチームに展開しています。
Technical Supportが同じことをやっても、要望の深さでは敵わないので、ならばTechnical Supportの強みである、量に着目しました。
ユーザーから問い合わせが来る、それはイコール “プロダクトにわかりにくい点がある” と考えています。
プロダクトの “なに” が改善されれば、問い合わせは発生しなくなるのかという観点でラベリングをしています。
このラベリングの詳細については今度別の記事でご紹介できればと思います。
FABRIC TOKYOさんのお話
顧客から企業に対して向けられた意見や要望を総称したものをVoice of Customer、通称VOCと呼びますが、このVOCを文化にするために今までの試行錯誤した経験を紹介されていました。
苦情対応でチーム全体が疲弊してしまっている状態から、全社に顧客の声を届け、改善実行まで成し遂げるまでには多大な苦労があったとのこと。
「わたしたちは単なる苦情処理班ではない」というフレーズがとても力強かったです。
ビジネスカジュアルジャケットは通常ジャケットと内ポケットの数が異なることから、苦情に発展することが多かったようですが、これを「通常ジャケットと同じ仕様にする」ではなく「選択式にする」という解決策を見出し、今では同じご意見はゼロになったとのこと。
この解決策は、複数にまたがる関係部門と議論を交わした結果生まれたものとのことで、「全社に顧客の声を届ける」重要さを示しています。
おわりに
FABRIC TOKYO 佐々木さんのお話は、BtoC、BtoB の違いはあれど、カスタマーサポートならではの共通項が多かったです。特に、顧客の声を吸い上げるためには、問い合わせをみんなで1件ずつ確認する等の時間のかかる泥臭い作業が必須であるという点に共感しました。
一方で、セミナーに参加いただいた受講者からは、「期待する内容ではなかった」というご意見もいただきました。経営貢献というキーワードに対しては各社が模索していて定石がないと改めて感じました。
今後もSansanの取り組みをみなさまに発表する場があれば事例としてお話しさせていただくと共に、事例となるような施策を推進していきたいと思います。

Sansan Technical Support と意見交換していただける方がいればお気軽にご連絡ください。
Sansan Technical Support 大谷・野口
sg@sansan.com
