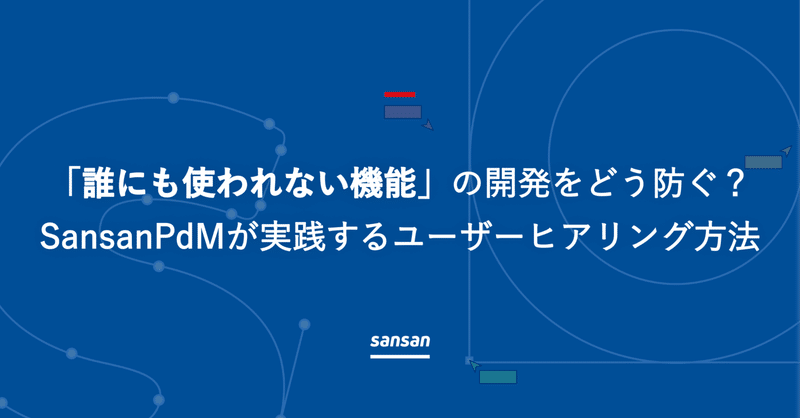
「誰にも使われない機能」の開発をどう防ぐ?SansanPdMが実践するユーザーヒアリング方法
こんにちは。営業DXサービス「Sansan」のプロダクトマネジャー(PdM)をしている佐々木です。
最近、新しいメンバーが何人か加わり、ユーザーヒアリングの方法についてよく質問されるようになりました。
PdMは顧客の課題を見つけるために、頻繁にユーザーヒアリングを行います。しかし、ヒアリングの方法が間違っていると、誤った情報に基づいてプロダクトを開発してしまうことがあります。
そこでこの記事では誤ったユーザーヒアリングを防ぐために、私が普段から気をつけていることを3つ紹介します。
①事実だけを集める
PdMの方であれば一度は耳にしたことがあるくらい書籍やWebの記事などで謳われている内容ですが、私自身も非常に重要なことだと思います。
ただ、これが思ったより難しい。例えば、ユーザーがある機能を欲しいと言った場合、これも一種の事実です。しかし、この中にはユーザーの「解釈」が含まれていることがあります。
事実:ユーザーが特定の機能を使おうとして、タスクを完了できなかった回数や、操作にかかった時間等具体的なデータ
解釈:「使いにくい」という主観的な感想
この場合、ユーザーから解釈だけでなく事実を詳しく聞き出す必要があります。効果的な方法は、ユーザーにその時の出来事を詳しく説明していただくことです。具体的には、どの画面で何をしようとしていたのか、実際に何をしたのかを、画面を共有しながら教えてもらいます。これは、その人の仕事を明日から自分が行える解像度で理解することがポイントです。(参考:UXリサーチの道具箱)
また、これを行うためには、実際にその仕事をしている人に話を聞くことが大切です。よくある間違いは、その仕事をあまり知らない人に話を聞いてしまうことです。例えば、実際にはその仕事をしていない上司や、サービスの窓口担当者に話を聞いてしまうと、彼らの解釈が入り込んでしまい、結果的に事実を正確に把握できなくなってしまうことがあります。
そのため、誰に話を聞くかをしっかりと選ぶようにしています。
②課題を聞かない。理由をすぐに聞かない。
ヒアリングで気をつけていることが2つあります。
1つは「これって課題ですか?」と聞かないこと、もう1つは「なぜですか?」とすぐに聞かないこと、です。
まず1つ目の「これって課題ですか?」と聞かない、についてですが、ヒアリング対象者に「これって課題ですか?」と聞くと、高い確率で「課題です」と返ってきます。これは、ユーザーが自分の課題を明確に把握していないことの方が多く、言われてみたら課題かもと思い、「はい、課題です。」と答えるためです。この情報を鵜呑みにすると、ユーザーがそこまで課題に感じていない課題を取り組むことになってしまいます。なので私は課題と思うか否かを直接聞かないようにしています。
もう1つの「なぜですか?」とすぐに聞かない、についてですが、これはなぜ気を付けているかと言うと、人はいきなり理由を問われると「ついそれっぽい理由を言ってしまう」ことがあるからです。
例えばこれは実際の私の体験談ですが、上司の西場から「佐々木さんは今日青色のシャツを着ていますが、それはなぜですか?」と問われました。私は「青色のシャツが好きなのでこれを選びました」と答えました。
しかし実際は、その日の朝いつもより起床する時間が遅れたため、着替える時間を短縮するために目の前に干してあった青色のシャツを選んだ、が本当の理由です。
このようにヒアリング対象者は意図せず誤った理由を伝えてしまうことがあります。これを防ぐために、ユーザーヒアリングを行う際はまず当時の状況を細かく聞くようにします。ユーザーも実際に起きたことを聞かれるので、答えやすいです。その状況を思い出してもらった状態で「なぜですか?」と聞くようにしています。この順番を意識することで本当の理由を確かめられるスピードが速まります。
③確証バイアスに気を付ける
確証バイアスという言葉をご存知でしょうか。認知心理学や社会心理学における用語で、仮説や信念を検証する際にそれを支持する情報ばかりを集め、反証する情報を無視または集めようとしない傾向のことを指します。
例えば、あるプロダクトマネジャーが新機能の追加を顧客の要求で決定したとします。開発中のユーザーテストで否定的なフィードバックがあったにもかかわらず、新機能の成功を強く信じていたため、これらの意見を「ユーザーがまだ新機能の価値を理解していないからだ」と解釈し、適切な評価や対処を行わないことがあります。これが確証バイアスの一例です。
このように確証バイアスに陥ると偏った情報しか集まらないので、事実をもとに意思決定できなくなります。
そのため、確証バイアスに自分が陥っていないか注意しています。一方でただ意識しているだけだと、意図せずこのバイアスに陥りそうなことがあるので、以下2点の方法でそれを防いでいます。
クリティカルシンキングを間に挟む
第三者の意見を確認する
まずは自分自身でヒアリング内容や集めた情報を批判的に見ていきます。具体的には「これって本当かな?」「反対の立場だったらどうだろう?」「情報を正しいとする客観的な根拠は何?」などを自分自身に問いかけています。
また上司や一緒に企画を進めるデザイナーやエンジニア、また他のPdMにヒアリングで集めた内容を確認してもらうことで確証バイアスに気づくことも多いので、確かめる工程を挟むようにしています。
おわりに
ユーザーヒアリングは、様々な職種の方が仕事に取り入れていると思います。私のこれまでのプロダクトマネジメントの経験から、失敗を振り返りながら学んだ点を3つ紹介しました。もし、ユーザーヒアリングの方法に迷っている方がいれば、この記事が参考になれば嬉しいです。また、この記事に対して他にアドバイスや意見があれば、ぜひ教えてください。
先日PdM1年目の成長と挑戦というイベントに登壇しました。
登壇資料を貼っておきますので、興味のある方は是非ともご確認ください。
関連情報
Sansan株式会社のプロダクトマネジャーについての情報を集約しています。Sansanのプロダクトづくりに興味がある方は、ぜひご確認ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
