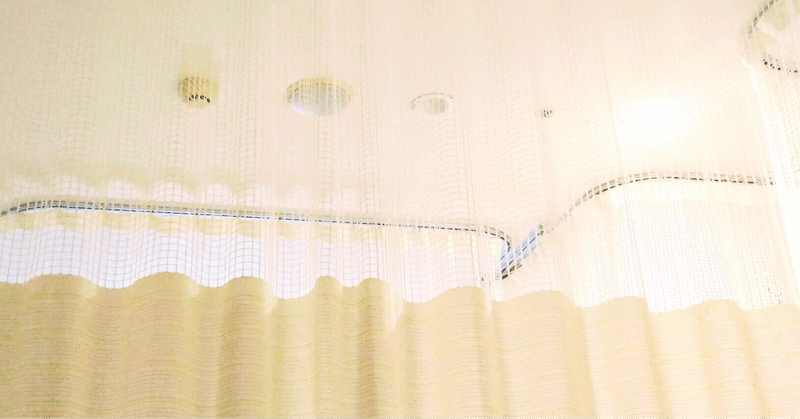
植物人間の妻 4【連載 記憶の記録】
2010年12月20日 遅い朝
救急車はデコボコしたアスファルトの上をゆっくりゆっくりと走った。
「頭に振動がいかないように慎重にゆっくり走りますから」
救急隊員の言葉通り、普通に運転すれば二、三分で着く道のりを十分近く掛けて病院へ向かったと思う。私にはもっともっと長く長く感じられたが。
救急車の窓から、12月の空が見えた。
冬の空の澄みきった濃い蒼さが目に染みる。雲一つない晴天。
ボンヤリと私は思っていた。
ユーミンの『悲しいほどお天気』って本当なんだな…
どうやら私の脳は想像を越える危機に遭遇した時、他の思考回路に逃げ込むらしい。
夢…なんじゃないかな
夢だったらいいな
それにしても嫌味のように突き抜けるような蒼い蒼い空だった。
病院に到着するとバタバタと夫はストレッチャーで運ばれて行った。
「奥さんは此処で待っていて下さい!」
救急処置室の前の長椅子を指差された。
「はい」
あ、夫の実家に連絡しなくちゃ。
夫の実家と私達の住むマンションは、まさにスープが冷めない距離にあった。この時になって、やっと夫の両親に連絡していない事に気付いた。
「もしもし〜、〇〇ですっ!」
大きな勢いのあるいつもの義父の声だった。
「今日子ですけど、〇〇さんが倒れて今、市立病院に居るんです……」
「うん、うん、分かった!僕が行くよ!」
義母は友人と出掛けていて留守だった。
市立病院の看護師さんの対応が落ち着いていたので、私は少し安心していた。
思った程、大した事ないのかも…
夫は救急処置室からCTを撮る為に運ばれて行った。
磨かれたリノリウムの床が無機質に光り、長く長く続いていた。
何もする事のない私は長椅子に腰掛け、床を見ながら足をプラプラ揺り動かしていた。子供のようにプラプラプラプラ…と
きっと大丈夫、あの人は大丈夫。
いつものように「ただいま〜」って帰って来る。
どの位待っただろう。
バタバタバタバタ…
一人の看護師さんが大きな音を立てて走って来た。
「〇〇さん、〇〇さんの奥さんはいますかぁ〜?」
大勢が座る待合室の方へ向かって叫んでいる。
「はい、此処にいますけど」
私は看護師さんの視線の下に居た。
「直ぐに処置室に入って下さい!先生がお話しがあるそうです!」
急に緊迫した空気が流れ出した。さっきとは明らかに雰囲気が違う。
此処から私の記憶は色を失い白黒の世界になっている。救急処置室のドアのノブを回してから、其処を出るまでずっと…
義父も到着していた。夫の幼なじみのJちゃんも血相を変えて入って来た。
「〇〇は?〇〇が倒れたって?」
義父、Jちゃん、私の三人が並んで、医師とCT写真が写し出される画像に向かって座った。
医師は夫の脳が映し出された一枚の写真を差しながら
「ここ!ここの黒い部分、分かりますか?」
三人は一斉に身を乗り出す。私は一応コクンと頷いてみせたが、あまり分からない。
「ここが損傷部分です」
静かにゆっくりと話す医師。
分かった!それは分かったから何とかしてあげて〜!!カーテンを一枚隔てただけの向こう側で夫が苦しみ暴れている音が聞こえ続ける。私との距離は1メートルも離れていない。
ドタンバタン
看護師さん達が必死に取り押さえようとしている気配が伝わる。
「おそらくこの部分に大動脈瘤があったと思われます」
「は、はい、それで」
「ここが破裂して、くも膜下出血を引き起こしました」
あ、知ってる。夫の姉の夫、夫の義兄が数年前にくも膜下出血で倒れてこの病院で手術を受けた。今は回復して仕事にも復帰している。
私は一縷の望みを得た気持ちになった。義兄には何の後遺症も見られなかった。くも膜下出血なら治る!その望みを一瞬で粉々に砕いたのは医師の言葉だった。
「かなりの出血ですし、〇〇さんは場所が悪い…」
「場所?」
「ここが生命を司る部分です…ここに出血が広がると…」
何か難しい説明をされたが覚えていない。
とにかく心臓が止まる!呼吸が出来なくなる!
つまり死ぬのを待つだけらしい。
「先生、手術は?手術はしてくれないんですか?」
夫の命が掛かっている。夫の命を奪われるより怖いものは私には何も無かった。
「奥さん、手術の出来る病院が近くに無いんですよ」
ガタンッ!
大きな音を立てて、私は病院の安っぽい椅子から立ち上がっていた。
「じゃあ、先生は、このまま何もしないで見殺しにされるんですか?」
ドタバタとカーテンの向こうで、生きる為に夫は一人で闘っている。その命の叫びが脈々と私に伝わって来る。
「降圧剤を点滴して、落ち着いたら転院されて手術を」
「先生、さっき心臓が止まるって、おっしゃったじゃないですか!!それで治るんですか!!」
「いえ、可能性は残念ながら…」
ザーッ
カーテンが開いて看護師が先生に近付いて言った。
「先生!右眼の瞳孔が、開きました!!」
瞳孔が開くと死が近い事は私も知っていた。
それでも夫は大きな音を立てて暴れ続けている。よほど痛く苦しいのだろう。
私は更に叫んでいた。
「先生!助けて下さい。ドクターヘリでも何でも使って、日本中、あの人を手術してくれる病院を探して下さい!!お金なら私が一生掛けて払いますから!!」
この人は説得出来ないと思ったのか、遂に医師は陥落した。パソコンを駆使して手術の出来る病院を探し始めた。
医師の手が止まった。
「奥さん、ありましたよ。〇〇市の日赤病院の脳神経外科の手術室が一つ空いています!」
医師も、もうこれ以上我儘で失礼な嫁と膝を突き合わせていたくなかったのだろう。満足気に微笑んだ。普段オタクで大人しい自分の何処にあんな力があったのか分からない。
降圧剤の点滴をぶら下げたまま、夫は高速道路を使って救急車で搬送される事になった。
医師は
「誰か男の人の付き添いを」
と指示した。私が余程、酷い顔をしていたのだろう。ぶっ倒れるとでも思ったのかもしれない。
「奥さん、途中でご主人の心臓が止まるかもしれません。だから…」
「分ってます、大丈夫です。先生、ありがとうございました」
本当に心からのお礼と共に頭を下げた。
付き添いは義父が、かって出てくれた。
ストレッチャーで運び出される夫の肩に触れて
「直ぐ後を追って行くから、頑張っててよ」
声を掛けた。夫の身体が発した熱が汗になり白い湯気となって立ち昇っていた。
私は救急車が見えなくなるまで見送っていた。
(あとがき)
あのまま医師が言うように静かな死を迎える事を選択すれば良かったのか、生きる為に手術を選択した私の判断が合っていたのか、今はもう夫に聞く事は出来ない。
私の人生の中でこの選択が一番の究極の選択だった。
結果として私の選択が、夫に辛い七年半の闘病生活を与えてしまったのだと思っている。
でも少なくとも私自身には正しい選択だったと思う。私の我儘に夫が付き合ってくれただけなのかもしれないが、七年半の間、私は毎日夫の顔を見ていられた。
返事は無くても、其処に愛する人の温もりを感じていられた。七年半は私が夫に「さよなら」を告げるのに必要な時間だった。人生で最高に贅沢な時間を夫は私にプレゼントしてくれた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
