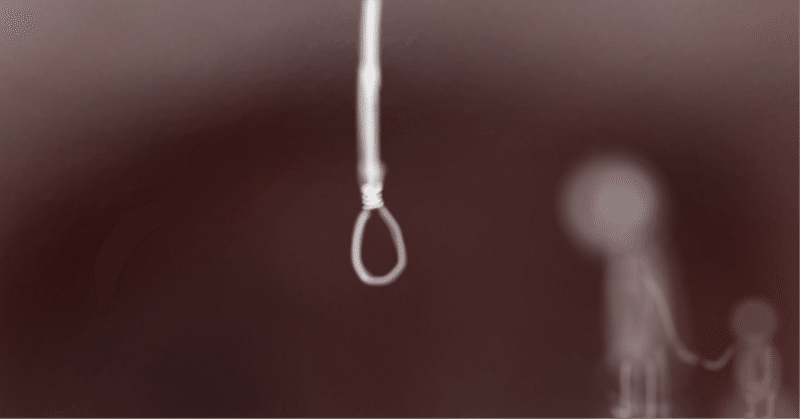
「妖の唄」〜実話に基づくヒト編 1〜
私の友人の実話です。
繊細な部分にも触れますので職業、場面設定、年齢等は変えてあります。でも起こった事は出来るだけ忠実に書きたいと思っています。
「妖のうた」〜実話に基づくヒト編 1〜
「今まで、ありがとう…」
まるでそう言うように父は最期に店の中を見渡したらしい。
らしいと言うのは、父の両親、私の祖父母に聞いた話しだからだ。祖父母は早朝に階段を下りて来て、自宅の中にある店舗の前で立ち止まった父の足音を聞いていた。祖父母の寝室は一階の店舗と隣接した所に位置していた。不審には思ったが、別に気にも止めずに寝直したそうだ。
父は何十年も小さなこの町の小さな店で、パンを焼き続けて私達姉妹を育ててくれた。
祖父の代からの町の小さなパン屋さんとして、それなりの需要があり人気もあった。ところが、近年「高級食パンの店」や「お洒落なチェーン店」が、駅前に進出してきて、客足はすっかりそちらに流れてしまった。
父は年老いたお客さんの為に作りたくない昔ながらの「あんぱん」や「クリームパン」を焼いて、毎日小銭を稼いでやりくりしていた。
ところが2020年に中国から始まった「コロナ」が日本をも襲った。時の総理「安倍晋三」氏が発令した緊急事態宣言で、年寄りだった店の常連客は全く外出をしなくなった。
それでも父は毎日毎日、パンを焼いた。
私は幼い頃、祖父と父が焼く甘いパンの香りで目覚めるのが好きだった。母は朝早くから台所に立って、祖父母と父の朝食の支度をする。高齢な祖父母は「パン屋」なのに和食を食べたがった。私にはコーンポタージュと父が焼いたパンが食卓に出てくる。
私が一番幸せだった頃の記憶に残る風景だ。
それが一回りも歳の違う妹が出来てから、私の生活は一変した。
あ、言い忘れたが私は生まれつき「聴力」が殆どない。普段は全く聞こえていないのだと思う。でも、そもそも「音」というものが分からなかったから、不便を感じたことはなかった。母が私と一緒に手話を覚えてくれたし、父や祖父母とは文字やジェスチャーで会話をしていた。
それが健聴者の妹が生まれてから、祖父母の愛情は妹にばかり向けられるようになった。聞こえなくても私には分かった。私を見る目と妹へ向けられる目が明らかに違っていたから。
ろう学校の中学一年生の時に私は思いきって「人工内耳」の手術を受けた。音を聞いてみたいという気持ちがもちろん一番だったが、妹が祖父母の愛情を一身に受ける姿を見て妹のように愛されたいと思ったのも事実だ。
手術は無事に成功した。でも私が聞いている「音」が、健聴者の聞いている音とは違うらしい事に気付くのに時間は掛からなかった。せっかく痛い手術を受けたのに私の周りは何も変わらなかった。でも両親だけは、そんな私を変わらずに愛し続けてくれた。
それから数十年の月日が流れた。父のパン屋は赤字続きで倒産寸前だったらしい。
その事実を私が知ったのは父が自死した後だった。
あの日…
冬の朝4時前、辺りはまだ暗い。夜の闇に包まれていた。
「今まで、ありがとう」
店を見渡すと父は二階の自宅へ続く狭い階段を上って、一番太い梁にロープを掛けた。
そして……
骸になった父の姿を最初に見つけたのは、老いた祖父だった。足の悪い祖母に変わって洗濯物を干しに階段を上った所で
「あ……」
ぶらぶらと宙に揺れる父の両足が見えたのだと言う。
「なんて事をしてくれたんだ!」
祖父は足の悪い祖母を呼び、二人がかりで冷たくなった父を下ろした。
二人がどんな気持ちだったのか、聞いていないから分からない。
当時、私は職を求めて東京で暮らしていた。
父の訃報の報せを見て、私が帰宅した時には既に妹とその旦那が全ての葬儀を取り仕切っていた。
ああ、妹は二十歳でかなり歳上の男性と結婚していた。
あの時ほど、私の耳が聞こえたら…
と思った事はない。
母?
妹夫婦の策略によって父と離婚させられていた。
何故、そんな事をしたかって?
母は妹の結婚を猛反対していた。そして、あの二人にとって、しっかり者の母の存在は邪魔だったからだ。
ずっと頑張って私達を育ててきてくれたのに、父の葬儀はお粗末極まりないものだった。
玄関の上り口にそのまま置かれた棺、払いの膳さえない寂しい葬儀だった。
その見すぼらしい葬儀が終わるか終わらないかのうちに近所中に地響きのような音が、鳴り響いた。
もちろん、私にはその音は聴こえなかった。
祖父の代から続いたパン家の看板が、妹の旦那の友人によって取り外され始めた。
重機が、けたたましい音を立てたらしい。
何が起こったのか?
払いの膳の代わりに妹夫婦から出された398円のスーパーの蕎麦を食べていた弔問客が家の外へ飛び出した。私も続いて外へ出た。
目の前で、父が大切に守ってきたパン屋の看板が剥がされていった。
何故、今?
酷い…
どうして、そんな事が出来るの?
喪服の中の膝がガクガクと震えて、立っているのがやっとだった。
でも、これは妹夫婦の計画のほんの序章に過ぎなかった。
つづく
【後記】
私がこの話を書こうと思ったのは、二年程前。
亡くなった物語の中の「父」と言うのは、私の主人の幼馴染の方だった。
実は物語の中の「私」が帰省した時、直ぐに「父」に会わせてもらえなかった。
「お父さんは何処に居るの?」
と妹にラインで聞いても返事は、なかなか送られて来ない。
「お通夜」の日程を妹に尋ねても「警察が来てるから」「忙しいから」「お姉ちゃんが帰って来ても邪魔になるから」と帰宅を許されなかった。
私に救いを求めてきた彼女(物語の中の私)と一緒にスタバでお茶をしながら、ずっと彼女の妹からの「葬儀の日程」のラインを二人で待っていた。
一日半(彼女は前日から待っていた)待たされた挙げ句に妹から届いたラインは「〇〇はうるさいから、通夜に出なくていい!」と云う乱暴なものだった。
彼女は私の目の前で楽しそうなスタバのお客様の中で、一人号泣した。
「何かが可怪しい」
私は何の力にもなれない代わりに彼女の話しを小説として書く事を約束した。二年前の事だ。彼女との沢山のラインのやりとり、使ったノートの山…。
あるブログで出来るだけ事実に忠実に再現したつもりだった。
でも今回また、この話しを書こうと思ったのは「妖」と言う題材をもらった時に、真っ先にこの出来事が私の頭をよぎったからだ。改めて今の私の視線で書いてみたいと思った。ヒトの心に潜む闇、または「妖」の話しを…。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
