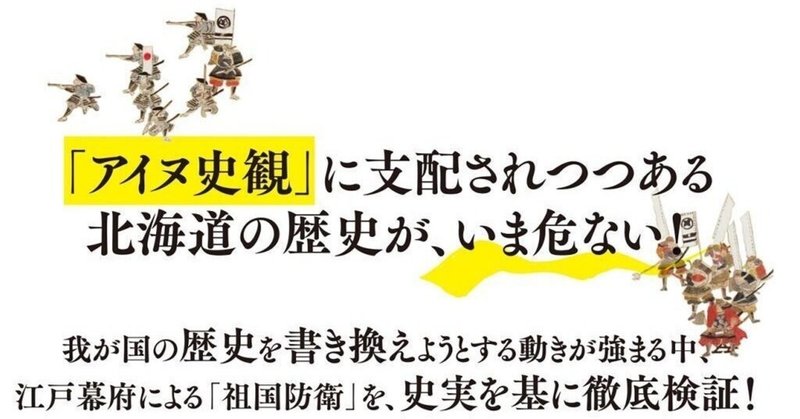
2023.8.28 【全文無料(投げ銭記事)】文科省に潜む歴史テロリスト
今回の記事は、中村恵子著『江戸幕府の北方防衛-いかにして武士は「日本の領土」を護ってきたのか』の文献を参考に、『日本と北海道の関係』というテーマで書き綴っていこうと思います。

本記事を読んで頂ければ、
・アイヌに関するプロパガンダ
・北海道の歴史
などが分かってくるのではないかと思います…。
全文無料ですので、最後までお読み頂ければ幸甚です。
北海道への歴史攻撃
「北海道は元々先住民族アイヌのもので、日本人はそれを侵略収奪した」
というプロパガンダ攻撃が強まっています。
その一つが札幌市にある『北海道百年記念塔』の解体です。

“百年”とは1868年に“蝦夷地”から“北海道”に改称し、近代的開発が始まってから100年を経たことを意味します。
先人の慰霊と開拓への感謝を込め、未来に向けて更に発展を祈る道民の気持ちを体現した記念塔です。
北海道庁は、この塔が老朽化が進んでいることを理由とし、多くの道民が知らないうちに解体工事を始めてしまいました。
しかし、建築専門家のグループからは、
「塔体は健全である」
と結論が出されています。
また、今後50年間に必要な維持費は、平成25年の調査では4億円(年
800万円)だったのが、平成29年には突如20億円という数字が出され、その根拠も開示されていないと報道されています。
令和2(2020)年に小樽文学館で、企画展『塔を下から組む』という展示会があり、次のような展示がなされていました。


北海道百年記念塔と判る塔の周りに浮遊する髑髏の数々、百年記念塔の下に埋もれる髑髏、塔がぐにゃりと下を向き、うなだれているような作品。
どれも気持ちの悪い思いをさせるものだ。
正に、“北海道の百年は先住民族アイヌを虐殺してきた歴史”というプロパガンダ展示です。
北海道では、中国人による大規模な土地買収が報じられていますが、疑り深い筆者は、このプロパガンダ攻撃と中国人による土地買収が、軌を一にした動きのように見えてなりません。
鎌倉以来、日本の統治の下にあった北海道
この“歴史戦”に勝つには、先人が北海道、千島列島、樺太の防備と開発に、どのような苦闘をしてきたのか、日本国民が知ることです。
そのための好適な図書が、中村恵子氏の『江戸幕府の北方防衛-いかにして
武士は「日本の領土」を護ってきたのか』です。
日本は、北辺の防備のために千島列島や樺太の探検をした最上徳内、近藤重蔵、間宮林蔵の三英傑が挙げられますが、今回は氏の本を参考に江戸幕府と松前藩及び東北諸藩の苦闘の跡を辿ってみたいと思います。
北辺の開拓と防備は江戸時代から行われていたのです。
蝦夷地が日本国の統治に組み入れられたのは、源頼朝による鎌倉幕府開設の頃です。
鎌倉幕府が津軽安藤氏を『蝦夷管領』に任命しました。
安藤(後に安東)氏は室町幕府からも蝦夷地統治を任されています。
その後、安東家の配下にあった蠣崎氏が、秀吉から蝦夷地支配の『朱印状』を得ます。
更に徳川家康が天下を取ると、蝦夷地統治を認める『黒印状』を受け取り、松前氏に改名しました。
これが江戸時代に蝦夷地を治めた松前藩の始まりです。
興味深いのは、秀吉の朱印状では、
<アイヌのほか、松前の一般庶民に対して乱暴を働いてはならない>、
家康の黒印状では、
<アイヌに対しての非道な行いは固く禁止する>
と、あったことです。
秀吉も家康も戦国時代を終わらせ天下太平を目指しましたが、そこではアイヌも一般庶民の一部として、その安寧を図る統治方針が示されていました。
蝦夷地と本州を結んだ松前船
江戸時代半ば以前の北海道では米が穫れなかったので、松前藩は“商い”を経済基盤としていました。
その当初の形態は『城下交易制』で、中村氏はこう解説しています。
・・・城下にアイヌが来て、それぞれお得意の藩士のところに行き、持ってきたラッコの皮や鮭、鷹などと、日本各地から運ばれてきた米、酒、鉄製品、木綿着、塩などを、その藩士を通じて交換し、藩士はそれを商人に売って、生活の糧を得ていた。
商人は、藩士から購入した商品を船で運び、港々で売却して利益を得ていた。
アイヌと和人の関係は、平等で平和なものであったという。
こうした交易が大規模に発展して『北前船』が登場しました。
北前船は大阪を出発し、瀬戸内海を通過し、下関から日本海に出て、日本海沿岸を伝いながら、北海道最南端の松前まで行きます。
その途中の寄港地で、土地の産物を仕入れるのです。
大坂で砂糖や酒、日用雑貨、瀬戸内海では塩や木綿、島根では鉄、越前では和紙や刃物、加賀では漆器や瓦、石材、酒田では米や紅花等々。
蝦夷地でそれらを売った後、鰊粕、鮭、昆布、干ナマコ、干アワビ、フカヒレなどを買い、帰り道に立ち寄る港々で、これらを売ります。
当初、北前船を経営したのは近江商人で、彼らの哲学は“売り手よし”“買い手よし”“世間よし”の『三方よし』です。
近江商人の活躍により、本州と北海道はそれぞれの産物を発展させ、交易によって各地の生活水準も向上していきました。
蝦夷地と本州の文化交流
北前船は各地の民謡、芸能、生活習慣、食文化などの交流を促しました。
松前の3湊の一つ、江差は繁栄し、民謡の王様として全国大会まで開かれている『江差追分』は信濃追分を源流としています。
370年続く江差町の姥神大神宮渡御祭は、京都の祇園祭の流れを汲むとされています。
また蝦夷地の水産物は、日本の食文化発展に大いに貢献しました。
蝦夷地でしかとれない昆布から、大坂や京の料理人が昆布だしを作り出し、和食の基本を築きました。
近江、北陸では蝦夷地の昆布を使った昆布巻き、おぼろ昆布、昆布じめ、大坂では昆布の佃煮など、たくさんの昆布の加工品が生まれました。
こうした文化交流は、アイヌの生活も豊かにしました。
九谷焼、輪島塗、会津塗など交易で得た漆器を宝物として大切にし、各地の郷土資料館のアイヌ文化コーナーには、必ずアイヌ所有物として漆器が飾られています。
上方の質の良い古着や、木綿の端切れ、木綿糸も、綿花の生産ができない蝦夷地における北前船交易品の人気商品でした。
古着や木綿はアイヌにも人気で、アイヌ衣装に本州の古着木綿を入れ込むのが、お洒落だったそうです。
“商人大名”松前藩と北前船は、蝦夷地と本州各地の産業を発達させ、それらを交易で結び、各地域の文化を育みました。
彼らによって、蝦夷地は日本全国の産業ネットワークの重要な一部となったのです。
蝦夷地は政治的には鎌倉時代から、経済的には江戸時代から日本の一部となったと言えるでしょう。
アイヌ酷使を防ぐための幕府施策
当初の城下交易制では、和人とアイヌは平等で平和的に交易していましたが、やがて上級藩士に“場所”(商い場)を知行地として与え、彼らはそこに年に数度、船を仕立てて出かけ、アイヌと物々交換で交易を行い、それを商人に売って生計を立てるようになりました。
寛政年間(1789~1801年)には、蝦夷地全体で85箇所の“場所”がありました。
しかし、江戸時代中期になると商品が多様化し、武士では応じきれなくなって、“場所”の権利を商人に委ね、商人は知行主の藩士に運上金を払って“場所”を運営するという“場所請負制”に変化していきました。
商人たちはアイヌに漁網を使って魚を捕ることを教えましたが、それは同時に、アイヌを対等な交易相手から、場所請負人に使役される労働者の立場に変えてしまいました。
商人の中には、藩や藩士に貸した多額のお金を早く回収しようと、アイヌを酷使する者も出てきました。
その不満が爆発したのが、寛政元(1789)年5月に起きた『クナシリ・メナシの戦い』といわれています。
後にロシア南下の危機によって、幕府が松前藩単独では対応できないと考え、寛政11(1799)年、蝦夷地を直接支配するようになると、場所請負制は維持されたものの、幕府松前奉行が全てを把握し、管理する体制としました。
アイヌ酷使を防ぐための施策でしょう。
幕府の蝦夷地支配の方針は、
・蝦夷地は日本の領土であるから護る。
・そこに住む和人、蝦夷人は日本人であるから撫育(支援、育成)する。
そして、アイヌの風俗を変えたり、農耕を薦めることは禁止、彼らの産業の支援は今までの水準を維持するというもので、アイヌの生活文化を尊重するものでした。
東北諸藩から蝦夷地防備の出兵
寛政11(1799)年、幕府は蝦夷地を直轄統治するようにしましたが、実際の警備は東北の津軽藩、南部藩に命じました。
南部藩は各500人の足軽を根室、国後、択捉の勤番所に、津軽藩は砂原、択捉に配備しました。
文化3(1806)年と翌年にかけて、ロシア軍艦が樺太や択捉島の番所を襲った文化露寇の後は、さらに大規模な出兵命令が出されました。
津軽藩、南部藩に加え、仙台藩、会津藩、南部藩にも北海道、千島列島、樺太の各地に、それぞれ数百人規模を配備させたという記録が残っています。
津軽藩は、知床半島の北側、斜里にも100名を送っています。
その記録を当時22歳の足軽だった斎藤勝利が綴っており、警備兵たちの労苦がどのようなものだったのかを伝えています。
彼らは文化4(1807)年5月26日に津軽藩を出発し、6月4日、箱館に到着。
その日と翌日にかけて、東北諸藩の合計1万4000名もの兵が箱館に着いています。
斎藤勝利ら100人は、まず北海道本島北端の宗谷まで570kmを徒歩で行き、そこの津軽藩の会所で新たな宿舎などを建ててから、今度は勤務地である東端の斜里に、330kmも歩いて向かいます。
斜里に着いたのは7月29日、出発の2ヶ月後でした。
そこでの幕府の会所の役人が最上徳内でした。
彼らは山の木を伐採して、自分たちの住む陣屋3箇所、物置所、稽古所などを建てます。
こうした長距離移動と重労働をこなした彼らの忍耐強さには驚かされます。
しかし、津軽藩士たちも想像しなかった寒さが襲い掛かります。
10月になると日に日に寒さが強くなり、持っていった着替えも建物も、厳寒の地にふさわしくなく、藩士たちは動揺する。
そんな時、幕府の松前奉行所から藩士たちに薬、酒、御肴料が届くのである。
11月になると大海一面に氷が張りだし、海が凍るということは全く知らなかったので会所役人に問うと、去年も同様で、もっと寒くなると答え、一同難儀なことと騒ぎ、その通り海の氷の上に氷が張り山のようになったので、
驚くばかりである。
100人中72人が病死
寒さで次第に体力を失い、そのうえ野菜不足から浮腫病を発症し、毎日のように藩士は亡くなっていきます。
しかし、その中でも、次のような心温まる光景もありました。
食事、水くみをする者がいなくなったので、弁慶というアイヌの青年を雇った。
はじめは言葉が判らず、勘違いで大笑いすることがあったが、次第に通訳もできるのではという状況になった。
4月には海の氷も溶け始めました。
6月24日、帆船が来て、450石積み千歳丸が到着次第、斜里を引き揚げよとの命令書がもたらされました。
船の風待ちのあいだ、檜で高さ2間・7寸角1本の墓標を工藤氏が作り、病死者72名の俗名を斉藤勝利本人が席次順に書き、工藤、斎藤、郷夫2人の4人で墓所へ行き、持参の角柱を建て、墓所の土72人分を紙に包み、名前を記して箱に入れ、帰国の際、斉藤が各自の家に届けることにした。
墓標に向かい、引き払いを仰せつけられて出立する旨を申し唱え、各自へ水を供え、思わず涙にむせんだ。
出発時100人の一行のうち、斜里で72人も亡くなっていたのです。
恐らく東北諸藩の他の駐屯地でも、同様の悲劇が起こっていたことでしょう。
斜里町では、近年にこの事実が知られると、昭和47(1972)年に『津軽藩士殉難慰霊の碑』が建立され、これが機縁となって弘前市と斜里町が姉妹都市となり、毎年共同での慰霊祭が催されるようになりました。
文科省にも潜む歴史テロリスト
冒頭で、
「北海道は日本の領土ではなかった」
というプロパガンダが進められている事を述べましたが、その歴史攻撃は教育現場でも行われています。
その一つとして、令和2(2020)年から使用されている小学校の東京書籍版の教科書では、江戸時代初期の日本地図で、本州以南は赤く塗りながら、北海道以北は白く塗った地図が使われました。
生徒が見れば、北海道以北は日本ではなかったと思い込むでしょう。
教科書会社の元々の原稿では、北海道も北方領土も本州以南と同様、赤く塗っていたのですが、“児童が誤解する恐れのある図”という検定意見がつき、北海道と北方領土を白くする修正を行って検定に合格したということです。

自民党でも、これを問題として、文部科学省から事情を聴いたようですが、訂正はなされず、この教科書がそのまま使われました。
北海道以北を日本領土ではなかったように扱う歴史テロリストは、文科省の中にも潜んでいるようです。
こういう歴史テロと戦うためにも、我々日本国民は北海道、千島列島、樺太の開拓と防備に命を懸けた先人の労苦を偲ばなければなりません。
最後までお読み頂きまして有り難うございました。
投げ銭して頂きましたら次回の投稿の励みになります!
ここから先は
¥ 170
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
