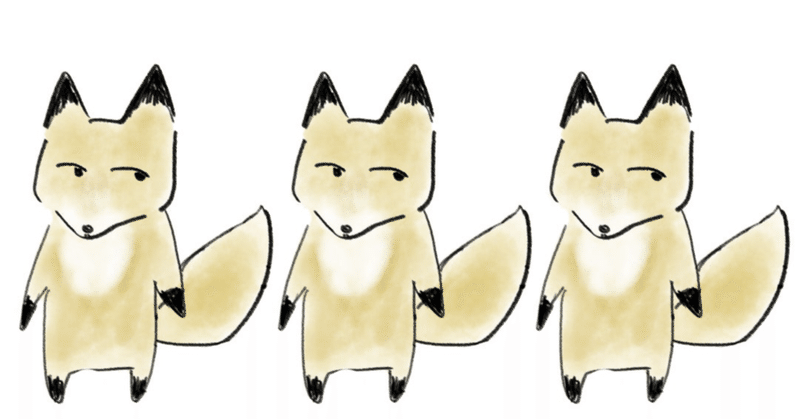
『ごんぎつね』の読みで「心の通い合い」をテーマにすべきだろうか
■二つの指導案と小学校の授業で扱うテーマについて
検索でヒットするトップページの『ごんぎつね』の指導案が「心の通い合い」を作品のメインテーマにしている。その他のいくつかの指導案を確認しても心の通じ合いをテーマに据えている(ただし、据えていない指導案もある)。まず、「心の通じ合い」をテーマにした指導案を引用して様子をみよう。
いたずら好きのひとりぼっちの小きつねごんと同じくひとりぼっちになった兵十が登場する物語である。主人公のごんは兵十の母親の死をきっかけに、兵十をなぐさめ、喜ばせようと行動するが、その思いもむなしくごんの心は兵十には届かない。それどころか、最終的には兵十から撃たれてしまう。このようにこの物語は心を通じ合わせることのできない悲しさを描いている。
最終アクセス2023/1/10
学習課題「兵十にうたれてぐったりと目をつぶったままうなずいたごんや兵十の様子から、二人の心は通じ合ったと言えるのだろうか。」について聴き合い、友だちの考えを受け入れることで、自分の考えを広げたり、深めたりすることができると考える。
二宮元 2020/11/27
http://www.fuku-c.ed.jp/schoolhp/elharuyo/framecenter/2013.09.27Ajigyou/sidouan/s4.pdf
最終アクセス2023/1/10
この二つの指導案は、同じ「心の通じ合い」をテーマにしているが、物語の焦点が別である。「兵十に撃たれてしまう」を物語の焦点とする前者の指導案、「ぐったりと目をつぶったままうなずいた」を物語の焦点とする後者の指導案と、それぞれ別の解釈を生み出す指導案になっている。なぜ別の解釈が生まれるのかに関しては後でみるが、同じテーマで有りながら別の解釈が生まれるようなテーマは、小学生の授業で扱うテーマとして相応しくないと感じる。
もちろん、本来は、読み取るテーマは何であっても良いし、どこに焦点を置いて読むのかも自由で良い。同じテーマで別の解釈が生まれたって構いはしない。読書は自由なのだから好きに読んだらよいと思う。
しかし、小学生の授業で扱うなら解釈に揺れが生じるようなテーマは選択しない方がよいと考える。そんな解釈の自由度の高いテーマの読みは大学に入ってからで十分と思う。なぜそんな自由度の高い読みかできるのか、なぜいくつもの解釈が間違いとしてではなく並立できるのかを明確に理解できる文学能力が身にいた段階になってはじめて、授業のような場で解釈の自由度の高いテーマでの読みをしたらよい。
この方針は他教科でいえば数学などが典型だが、数学の授業では生徒の数学能力の発達にあわせて自由度を高めた数学の対象を扱う方針を取っている。大学数学のような自由度の高い世界に小学生を放り込んだりしない。国語の授業も同じ方針で行うべきではないだろうか。なるべく解釈揺れが生じないテーマを授業では選択すべきじゃないだろうか。
大人であり、文学を読むことの教育もある程度以上には受け、さらには『ごんぎつね』を幾度も読み返している、引用の指導案を書いた小学校の教師同士でさえ、同じテーマで解釈が分かれている。小学生同士ならなおさら分かれるだろう。
小学校の授業において生徒がお互い異なる妥当な解釈をしている際、教室での絶対的な権威者である教師と同じ解釈こそが「正しい解釈」で教師の解釈と異なる解釈はたとえ妥当な解釈であっても「間違った解釈」との印象を生徒に植え付ける(注意喚起するが、妥当ではない解釈をする小学生は数多く居る。教師とは異なる妥当な解釈の存在は、別に教師と異なる全ての解釈が妥当な解釈なのだということを意味しない)。たとえ、教師が解釈は色々あるよと教示しても小学生の文学能力では、教師とは異なる解釈であっても妥当な解釈であり得ると信じ切ることはできない。
そんな小学校の授業の特質を踏まえた上で、授業で取り扱うテーマを選択すべきではないかと私は思う。
■「心の通じ合い」をテーマにした読みでの2通りの解釈
前節で2つの指導案を挙げた。その際に、同じテーマでも焦点の置き所が違う事で別の解釈が生まれると述べた。前節の主旨とは異なるため詳細に触れなかったので、以降において、同じテーマでも焦点の位置を変えると解釈が変わることを詳しく見ていきたい。
■結末の2通りの悲劇性
『ごんぎつね』において、ごんと兵十の間の心の通じ合いをテーマにすると、結末の悲劇性の解釈が大きく2つに分かれる。ラストシーンにおいて、ごんが頷く前の「心を通じ合わせることのできない」に焦点を置くのか、頷いた後の「心を通じ合わせることができた」に焦点を置くのかで悲劇性が変わってくる(=悲しさの原因が変わる)。前者であれば結末の悲劇性の本質は「すれ違う悲しさ」にある。後者であれば結末の悲劇性の本質は「喪失の悲しさ」にある。
この二つの悲劇性の違いにピンとこない人もいるかもしれないので、通俗的なラブソングで譬えよう。前者は「あなたとは分かり合えなかったから傷つけた。それが悲しい」という悲恋に、後者は「あなたと恋人になったと思ったら、あなたはいなくなった。それが悲しい」という悲恋に擬えることが出来る。後者に関して説明を加えると「恋人がいなくなった原因は自分の行為にある」としてもそれは悲劇性を高めるだけで、その性質を変える訳ではない。ともかく、ごんが頷く前と後のどちらに焦点をおくかで、結末の悲劇がどういう悲劇か解釈が変わってくる。
■焦点の違いの意味
読みの焦点をごんが頷く前と後のどちらに置くかで「心の通じ合い」について許される解釈も当然ながら変わってくる。
「心が通じ合わなかった」からこそ「兵十がごんを撃つ=ごんが兵十に撃たれる」という決定的事件が起きるのであり、その後に死にゆくごんと心が通じ合ったとしても通じ合わなかったとしてもその運命は覆らない。つまり、物語の焦点を「生と死が反転」するポイントにおくのだから、その時点での心の通じ合いの状態である「心が通じ合っていない」が重要で、その後の心の通じ合いの状態はさほど重要でないので、心が通じ合ったのだと解釈しても心は通じ合わないままだったのだと解釈してもよい。本文を引用して具体的に言おう。
ごんを、ドンとうちました。ごんはばたりとたおれました。
『ごんぎつね』の物語が「生と死が反転」するこの一点に収束していく「心の通じ合い」をテーマにした物語なのだと読解するなら、この時点での「すれ違い」こそが重要なので、その後のごんと兵十の関係の解釈には自由度がある。つまり、頷く前に焦点をおいたなら、頷いた後に心が通じ合っている解釈も心が通じ合っていない解釈もどちらでも許される。ごんが頷いた後、兵十が火縄銃を取り落とし茫然自失になるほどの衝撃を受けているのは作中の事実であるが、その内心がどうであるかの解釈には自由度がある。
一方で、ごんが頷いた後に焦点を置くならば「心の通じ合い」をテーマにしている以上、心が通じ合う解釈のみが許される。逆に言えば、「心の通じ合い」をテーマにしつつ心が通じ合わない解釈をしたいのであれば、焦点はごんが頷く前に置かなければならない。『ごんぎつね』の物語が
ごんは、ぐったりと目をつぶったまま、うなづきました。
兵十は、火なわじゅうをばたりと取り落としました。
この一点に収束していく「心の通じ合い」をテーマにした物語なのだとしておきながら、このシーンを「コミュニケーションが成立して心が通じ合ったシーン」と解釈しないのであれば、物語がここに収束していくと考える理由が無い。ここで何か決定的な事件があったのだと解釈するからこそこのシーンに焦点を置く理由がある。そして、このシーンで決定的な何かが変わったとすると「心の通じ合いの状態が変わること」しか有り得ない。つまり、心の通じ合いの状態が反転したシーン、すなわち通じ合わなかった二人の心がここで通じ合ったことが描かれたシーンなのだとする解釈だけが、ここに焦点を置く「心の通じ合い」をテーマにした読みでの解釈になる。
■補論:ごんの頷きは自分の思い込みと兵十が思い込んでいるとの解釈
この記事における本筋とはすこし離れるが、以下の事にも触れておく。以前の記事の註に書いた内容なのだが、再び述べておく。
本文において、ごんが意思疎通可能な存在であると兵十が認識できいると明言できる記述はないため、兵十が「本当は錯覚の類と自覚しているが、単に首を動かしただけのごんの動作をごんが頷いたのだと自分は受け取っている」との認識でいるのだとの解釈も可能である。この解釈は言ってみれば現実世界で我々がペットの猫に話しかけた際の鳴き声を「ペットの猫が返事した」と感じても、猫との十全な意思疎通の結果の返事とは考えないのと同じである。
※あなたの家の猫もひょっとしたらごんのような思考能力をもっているのかもしれませんよ。
■追記(2023.1.16)
当初、当記事の続きとして、指導案でのテーマを「心の通じ合い」にしたことによる歪みの指摘、テーマを指導案のテーマと類似の「交流」に変更にした場合の読み、また、新見南吉原作版(※1)から新実南吉自身の作品テーマを予測して『ごんぎつね』の技法的視点からの分析を行う予定であった。
当記事の続編を8000字ほど既に書いていたのだが、技法的視点からの分析を行うにあたって、新機軸ともいえるものが出てきたので、続編を書くのを一旦中止することにした。
ヒロなんとか氏(※正式なペンネーム。ヒロ某との匿名化ではない)が公開なさっている「物語の才能;面白いストーリーの作り方」(※2)に沿った形で、『ごんぎつね』の技法分析をした方が遥かに面白い分析が出来そうだ、との直観が働いたからだ。この「物語の才能;面白いストーリーの作り方」は受け売りなどではなくヒロなんとか氏のオリジナリティがふんだんに盛り込まれた考察なので、ぜひ読んで頂きたい。正直な所、私の分析を読まずとも各自が「物語の才能;面白いストーリーの作り方」を読んで、自分で『ごんぎつね』の技法分析を試みた方が面白いだろうとの印象すらある。
偶々、ハリウッドのシナリオライティングの概念であるミッドポイントを用いて話をしようとした際、概念の提唱者である脚本家のシド・フィールドの名前に確信が持てなかったので検索したら「物語の才能;面白いストーリーの作り方」に出会った。本当にこの出会いに感謝したい。
※1 教科書採用版と原作版で注目した違いは以下。
赤い鳥版(鈴木三重吉編)=教科書採用版
「ごんは、ぐったりと目をつぶったまま、うなずきました。」
新美南吉原作版
「ごんは、ぐったりなったまま、うれしくなりました。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
