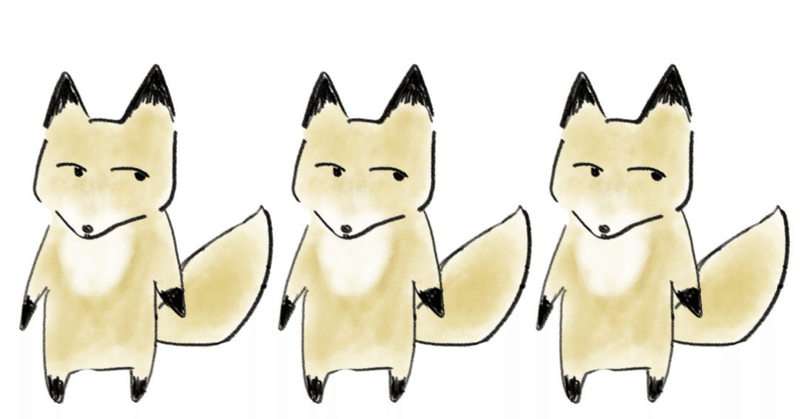
「ごんは撃たれて当然」の解釈とは
■はじめに
先の記事の追記でごんが撃ち殺されて当然と言い得る解釈があると書いた。今回はその解釈を述べていきたい。
■『ごんぎつね』の中の世界
『ごんぎつね』という作品は入れ子構造をしており、小きつねである「ごん」が居る世界は作品の冒頭で触れられている通り、作中作の世界である。
これは、わたしが小さいときに、村の茂兵(もへい)というおじいさんからきいたお話です。
この冒頭の文より、兵十とごんの世界は茂兵爺さんから聞いた話の世界であると分かる(※1)。つまり、兵十とごんの世界が架空世界であり得ることを語り手は始めに断っているのだ。もちろん、話が進めば狐のごんが人間的に振る舞うことから架空世界の話であることは明らかになるのだが、明白なフィクションであるごん以外は、私たち読者の世界と極めて類似しているように描写されている。しかし、私たちの世界の狐と大きく異なる狐であるごんの存在が当たり前とされていることだけが異質なのではない。もっと別な部分でも私たちの世界と兵十とごんの世界は違うのである。
■「ごん」という存在
人間と同様の思考能力・感情・善悪の判断・風習への理解等がある存在には、人間と同じ待遇が与えられてしかるべきとの価値観を読者である私たちは持っている。そして、本文のごんの能力に関する表現からごんは姿形が違うだけで全く人間と同様の存在であるように見える。そこから、ごんには人間と同等の待遇が与えられてしかるべきなのではないかとの印象が生じる。
だが、それは現代的価値観をもつ私たちだからこそ抱く印象であって、「我々と同様の思考能力・感情・善悪の判断・風習への理解がある存在であっても、我々と同様の待遇を与えるべきとはいえない」との価値観は、読者である私達の現実世界であっても存在した。典型的には奴隷解放前のアメリカにおける黒人奴隷に対する白人の価値観がそれである。
過去の現実世界ですらそうであるのに、ましてや別世界である兵十とごんの世界において、精神的能力が人間と同様であっても人間と同等の処遇をごんが受けるべきであるとの前提をおいて状況を理解することはできないのだ。
では実際に、兵十とごんの世界において、ごんがどういう存在であるかを示す箇所を確認してみよう。
兵十は、ふと顔を上げました。と、きつねが家の中へ入ったではありませんか。こないだうなぎをぬすみやがった、あのごんぎつねめが、またいたずらをしに来たな。
「ようし。」
兵十は、立ち上がって、納屋(なや)にかけてある火なわじゅうを取って、火薬をつめました。
そして足音をしのばせて近よって、今、戸口を出ようとするごんを、ドンとうちました。ごんはばたりとたおれました。
兵十は罪に対する罰としてごんを撃ったのではない。有害動物駆除を目的にして撃ったのだ。ごんは「害を与える存在」である見做されたから問答無用で射殺という手段で排除されたのだ。
このことは有害な存在と見做されたなら撃たれて当然の存在としての処遇をごんは受けていることを示している。
もちろん、現代の現実世界においても有害な人物を排除することはある。それでも危害の大きさや緊急度等に対応した、謝絶・注意・退去要求・警告・威嚇・実力行使等の段階のある排除の手段が選択される。つまり排除するにも排除される相手への配慮が必要なのだ。
だが、ごんはそのような配慮を受ける存在とは見做されていない。排除手段への配慮を必要としない相手へは、効率性によってのみ排除手段が選ばれる。例えば、現実世界で私たちの家にネズミが出たとき、ネズミを排除するため、粘着シート・ホウ酸団子・機械罠など様々な排除手段に頭を巡らせるかもしれないが、それは効率性の視点から選んているのであり、ネズミに配慮する視点から排除手段を選んでいるわけではない。ごんは排除手段に配慮してもらえるような存在ではないからこそ、兵十は問答無用でごんを射殺したのだ。
つまり、兵十とごんの世界において、ごんは人間(少なくとも兵十)にとって有益でなくとも無害でなければ共存できない存在なのだ。そして既に村人に散々イタズラしたごんは、有害な存在から有益ないしは無害な存在に変化した証しを立てることなくば撃たれて当たり前といえるのだ。
■仮に「ごん」を人間の孤児に変えると
ごんが前節で示したような存在である事は、ごんを人間の孤児に変えて物語を再構築すると逆説的に確認することができる。名前が「ごん」のままでは解説にあたって不便であるので「ハック」に変えておこう(※2)。少し長くなるが以下に再構築した物語を書こう。
『みなしごハック』
むかしは、わたしたちの村のちかくの、中山というところに小さなお城があって、中山さまというおとのさまがおられたそうです。
その中山から、すこしはなれた山の中に、ハックというみなしごがいました。ハックは、ひとりぼっちで、しだのいっぱいしげった森の中に穴をほって住んでいました。そして、夜でも昼でも、あたりの村へ出ていって、いたずらばかりしました。
(中略)
その明くる日もハックは、くりを持って、兵十の家へ出かけました。兵十は物置でなわをなっていました。それでハックは、うら口から、こっそり中へ入りました。
そのとき兵十は、ふと顔を上げました。と、ハックが家の中へ入ったではありませんか。こないだうなぎをぬすみやがった、あのみなしごハックめが、またいたずらをしに来たな。
「ようし。」
兵十は、立ち上がって、納屋にかけてある火なわじゅうを取って、火薬をつめました。
そして足音をしのばせて近よって、今、戸口を出ようとするハックを、ドンとうちました。ハックはばたりとたおれました。兵十はかけよってきました。家の中を見ると、土間にくりが固めて置いてあるのが目につきました。
「おや。」と、兵十はびっくりしてハックに目を落としました。
「ハック、お前だったのか。いつもくりをくれたのは。」
ハックは、ぐったりと目をつぶったまま、うなづきました。
兵十は、火なわじゅうをばたりと取り落としました。青いけむりが、まだつつ口から細く出ていました。(おわり)
物語を狐のごんから人間のハックに変えると、ハックへの兵十の対応の異常さが分かる。仮にイタズラの為に自宅に侵入しているとしても、ハックに警告も何も無しにいきなり射殺するのは、明らかに(現代人の感覚からすれば)逸脱行為である。
もちろん、ハックが重大犯罪をしているなら自衛の範囲だろう。だが、兵十の認識は「またいたずらをしに来たな」である。イタズラ程度では、自衛目的でも報復目的でも人間を射殺するのは過剰である。つまり、再構築した物語においていきなり兵十が射殺したことは(法律面ではなく)道義的な視点から言い訳ができない異常行動なのだ。
人間への対応であるならば異常行動になる「相手の射殺」であるが、(再構築したほうでない元々の)『ごんぎつね』の全文を見返しても当該行動が異常行動であると示す記述はない。兵十が異常行動を平然と行うような人格の持ち主であることを示す記述は無く、また異常行動をせざるを得ないような異常な状況の示す記述も無い。平凡な人格の持ち主の常識的な行動として「ごんの射殺」が描かれている。
つまり、兵十とごんの世界において「イタズラした狐への対応としての、ごんの射殺」は当たり前の事であると判断される価値観があるのだ。その中で、排除手段での配慮を受けることができず、また応報原則の枠外の存在としてごんは扱われている。すなわち、ごんは有害であれば手段を問わず排除されてしまう存在ということが示されている。
■ごんは無害な存在への転換の証を立てなければならない
ごんは兵十ら村人から駆除されるのを防ぎ、相互的な友好的交流を可能にするためには、有害な存在から有益ないしは無害な存在に転換したことを兵十らに知らせなければならない。なぜなら、相互的な友好的交流が成り立つ前提である身の安全を図るため、自らが駆除の対象外であることを示す必要があるからである。
さらにその前提として、無用の殺生を忌避する価値観を兵十がもっている必要がある。とはいえ、その辺りは心配無用で兵十がそのような価値観の持ち主であることは文中において示されている。その場面を確認しよう。
土間にくりが固めて置いてあるのが目につきました。
「おや。」と、兵十はびっくりしてごんに目を落としました。
「ごん、お前だったのか。いつもくりをくれたのは。」
ごんは、ぐったりと目をつぶったまま、うなづきました。
兵十は、火なわじゅうをばたりと取り落としました。青いけむりが、まだつつ口から細く出ていました。
さて、はじめ兵十は殺す意図をもって火縄銃を撃ったが、ごんとのやり取りの後、持っていた火縄銃を取り落とす程の衝撃を受け、落とした火縄銃を直ぐには拾えない程の茫然自失状態になっている。
これは、有害な存在ではなくなったごんを撃ってしまった事に対して、その他の事情も併せて撃つべきではなかったと兵十が強く感じている事を示している。この後悔の念の土台に無用の殺生を忌避する価値観が無ければ説明がつかない。
もちろん、恩(栗や松茸をくれたこと)を仇(銃で撃ったこと)で返した不義理への申し訳なさや有り得たかもしれない友好的交流を振り払ってしまったことの罪責感もあろう。それらが渾然一体となって茫然自失に陥らせているとはいえる。
だが、理由なく命を奪うことへの忌避感が兵十になければ、銃を取り落とすほどの衝撃を兵十が受けることはあるまい。すなわち、兵十は有害ではなくなった存在を問答無用で撃ち殺すような人間ではないのだ。
それゆえ、ごんは信頼回復のためのアクションを取るべきだったのだ。即座の謝罪が累積している村へのイタズラ行為ゆえに困難であったとしても、隠れて行っていた償い行為を何れかの時点で反省したごんの償いの実績として兵十らに気づかせる工夫をすべきだったのだ。そして、その実績のもと謝罪を行って信頼を回復させ、もはやごんは有害な存在ではなくなったのだと兵十らに確信させ、相互の友好的交流につなげていけばよかったのだ(※3)。
つまり、ごんはごんの立場で為すべきことを為さなかったゆえに撃たれたといえる。それは、兵十とごんの世界内での道理から判断して「ごんが撃たれるのは当たり前」との結論になる。それが悲劇であり、不幸な行き違いであることは間違いない。だが、過去の行いによって排除対象と周囲に認識されていた主体が、その周囲の認識を修正する具体的アクションを取っていないのであれば、周囲がその主体を排除する行動をとったことは当然の行動なのである。
■兵十の行動の正当性と、ごんが撃たれた事の不当性
兵十がおかれた状況・兵十の世界の常識に則って兵十がごんを撃った事を読者が一方的に責めるのは兵十にとって酷である。ごんの改心や償いの行動を兵十は知ることができなかったのだから、知ることの出来なかったごんの事情から、兵十の行動を咎めるのは公正とはいえない。
一方で、ごんが撃たれることは一点の曇りもなく当たり前といえるだろうか。ごんは善良な狐になる道半ばで射殺されたのだ。たとえ周囲には以前の有害な狐のままと認識されていようと、実態として善良な狐に成りつつあったのだ。そのような状況でごんが射殺されたことに対して、如何なる不当さも有りはしない断言できるだろうか。
もちろん、兵十とごんの世界での狐の有害動物駆除の基準では矯正可能性を考慮にいれないかもしれない。だが、矯正可能性を考慮に入れずに処断されることが当たり前と見做してもよいのだろうか。そこには何がしかの意味での不当さがないだろうか。
変わろうとした矢先に変わることが不可能となる事態は、兵十とごんの世界に限らず現実世界でも珍しくもないが、その事態は珍しくもない事態だから当たり前の出来事として平然と受け流せるような事態なのだろうか。ある種の憤りを飲み込んで諦念とともに受け入れるしかなくとも、飲み込み諦めたものに正義が一片も含まれていないのだろうか。
現実世界における少年犯罪で世間の議論を呼ぶものに矯正の余地の概念がある。被害者側のことを考えずに加害者の人権しか考えていないと槍玉にあがる概念ではある。また、いじめ問題ではいじめっ子の未来などいった言葉でいじめっ子の処分が軽くなるような加害者偏重の事態を生んでいる考え方と同根の概念だ。
しかし、そうであっても矯正の余地を少年法が守り教育界が重視したのは、現状がたとえ過剰であっても守るに足る正義が、(守るべき水準はともあれ)その中に含まれているからなのだ。善良な方向への変化の可能性に目を瞑り、その価値を無視することは不正義であり、決して当たり前のことではない。
ここで、すこし注意をしておきたい。兵十とごんの世界だけでなく我々が住む現実世界もそうであるが、世界は決して公正なだけの世界ではない。公正世界仮説を信じている人には受け入れがたいかもしれないが、世界には不正義なことも邪悪なことも満ち溢れている。人生にはいくらでも不条理な出来事は転がっており、人はそれに屈従し喘ぐ。だが、さして珍しくもない不条理な出来事に屈従しているからといって、それを「当たり前」とすることはないのだ。
■メタ的な視点を持つ読者の立場
有害動物駆除の原則により、駆除対象外の証しを立てなかったごんに関して、基本的に「撃たれるのは当たり前」と判断できるのはあくまでも兵十やごんの世界内に限った話である。
作品の外側の世界に住んでいる読者は、兵十やごんとは違う世界に住んでいる。つまり、兵十やごんの世界の規範・価値観から自由な立場にある。更に言えば、その兵十やごんの世界の規範・価値観自体を対象とした考察も可能な立場なのだ。そして更にそれをメタ的に考えていくことも可能だ。それを図式化すると以下だ。
0 行動A
1 「行動Aは当たり前」と判断
2 「上記1の判断をした価値観は○○」と判断
3 「上記2の判断をした価値観は○○」と判断
・
・
・
さて、読者がこのような立場にあることを理解すれば、「ごんは撃たれて当たり前」と言い得るのは、行動を直接判断している「1」のレベルの話であると理解できよう。そしてそれは兵十やごんの世界の判断である。繰り返すが、読者である我々は兵十やごんの世界の判断に拘泥する必要は無い。
「ごんが撃たれて当たり前」との判断を成り立たせている価値観は、決して当たり前ではない。あまりにもごんにとって不利な価値観なのだ。そして、その価値観のもと射殺されたごんに対して「ごんが撃たれて当たり前」と断じることは、冷酷であるといって差し障りない。
以上で説明してきたメタ的な視点をもつ読者の立場の話は、やや抽象的なので難しいかもしれない。そこで現実世界で起きている「アフガニスタンの名誉殺人」を例にとって説明しよう。アフガニスタンで起きた事件は以下だ(※4)。
女性は好きな男性との結婚を望んでいたが、家族は別の男性と結婚させたがっていた
この女性は家族の縁談を拒否し、警察署を訪れたが、警察に家族の元に帰された
兵士の兄が彼女を連れ帰り、名誉殺人として残忍に殺害した
アフガニスタンでは、警察や司法機関の関係者を含む多くの人々が、家族が選んだ男性以外の相手を選んだ女性には「名誉殺人」が罰としてふさわしいと考えている
さて、アフガニスタン社会(の一部)において上記の被害女性が殺害されることは当たり前である。その社会の規範や構成員の人々の価値観が名誉殺人の成立条件を定めており、被害女性はその名誉殺人の成立条件を満たしてしまったのだから、アフガニスタン社会において当たり前なのである。
だが、アフガニスタン社会の外側に生きている、AFP通信で事件を知った日本を含めた他の国々の人々からすると、そもそもそんな規範や価値観で被害女性が殺害されてしまうこと自体が正義に適っていないように感じる。その感覚を持てるのは、アフガニスタン社会の外側から「名誉殺人を成立させた規範や価値観」に疑いの目を差し挟み、評価し得るメタ的な視点を持っているからなのだ(※5)。
メタ的視点を持てる立場の人間が「アフガニスタン社会で被害女性は名誉殺人の成立条件を満たしてしまったんでしょ。なら、殺害されて当然じゃないの」と当該殺人事件を評したとしたら、その人間はあまりにも冷酷と言わざるをえない。「その社会の価値観に従えば当然」であっても、「そんな価値観に従わされることは当然ではない」のだ。
同様に『ごんぎつね』において「兵十とごんの世界の価値観からごんが撃たれることは当たり前」であるだろう。だがメタ的視点からは「ごんがその価値観で撃たれることは当たり前ではない」のだ。
■くだんの小学生の感想をみる
私が当記事と前の記事を書くきっかけとなった小学生の感想の原文を多少調べてみたが、原文自体を探し出すことはできなかった。(大人の)叔母らしき人物が姪の感想の要点として挙げたものが取り上げられ、話題となったようだ。叔母のものとされる書き込みをみよう。
全文まるまるは無理だから要点をかいつまむ
・やったことの報いは必ず受けるものだ
・こそこそした罪滅ぼしは身勝手で自己満足でしかない撃たれて当たり前
勿論身勝手やら自己満足なんてワード実際に使っちゃいないぞ
文章読んで端的に言うとそういいたいんだろうなってことな
特に二つ目が物議を醸しているらしい
ID:0SLw7FB7O
2013/5/08
まずは、前者の要点からみよう。先の記事でも触れた話なのだが、これは応報原則から見た感想だ。だが、応報原則は罪と罰のつり合いが取れていないといけない。うなぎをダメにした程度のイタズラはおろかこれまでに仕出かしたイタズラの罪を合計しても「ごんの死」という罰には届かない。つまり、ごんが撃たれたことは、応報原則からみて不当である。
後者の要点をみよう。これも先の記事で触れた話であるが、「無効な贖罪行為だから撃たれたのだ」という感想だ。だが、贖罪行為は罰を軽くする方向には働くが重くする方向には働かない。つまり、贖罪行為云々の前に、そもそも犯した罪が「ごんの死」に値する罪だったのかが問題にされなければならない。これは先述の通り、ごんの罪はごんの死に値しない。したがって、贖罪行為がこそこそしてようが、身勝手だろうが、自己満足だろうが、小学生が提起した問題意識からは「撃たれて当たり前」とはならない。
■補論:読者から見たごんの立場の気付きにくさ
ごんの立場に読者が気付きにくい構造についてみていこう。
兵十はひょいっと火縄銃を取り出してごんを撃ったのであるから職業イメージが銃と強く結びつく猟師だろうと読者に感じさせる(※6)。そこから、兵十とごんの関係は「猟師-狐」の関係であるとの思考枠組みが読者の中につくられる。
すると、現実世界においても猟師が狐を撃つことはありきたりな行為であるから、兵十がごんを撃ったこともありきたりな行為との認識が生まれる。もちろん、兵十の行為は兵十の世界でありきたりな行為なのだが、メタ的視点に立てる読者の立場でも、そこに違和感を感じることのない構造が生まれている。
また、兵十がごんを撃った後に事実を知って衝撃を受ける展開が、作中の登場人物である兵十とは共有し得ない一方的に殺され得るごんの立場の不当さを読者から覆い隠し、兵十と読者が共有する償い行為を理解されずに殺されたごんの情報の誤りによる不当さだけが読者の心に印象付けられるような効果を発揮している。
兵十とそれらを共有しない物語の展開だとすると、ごんの立場の不当さは覆い隠されはしなかっただろう。仮に『ごんぎつね』のラストシーンが以下だとすると、ごんの立場に注目する読者は少なくない思われる。
「ごん、お前だったのか。いつもくりをくれたのは。」
ごんは、ぐったりと目をつぶったまま、うなづきました。
兵十はフンッと鼻を鳴らすと、ごんを摘まみ上げ近くの草むらに投げ捨てた。
この改変したラストシーンだと読者は兵十に一切共感しない。兵十の価値観は自分達とは違うと痛感し、兵十とごんの世界の外側の価値観から「ごんが不当な扱いを受けていること」で生じる不快さに読者は向き合うことになるる。
つまり、物語の展開から兵十への共感が無くなれば否応もなく読者はメタ的視点に立ってごんが受けている不当さの正体に着目するのだ。
だが、逆に、物語の展開によって兵十への共感が生じるとき、兵十は自分達と同じであると考え、兵十の価値観に疑問を感じることなく、兵十の価値観を読者は共有してしまいがちになるのだ。
以上の二点が、読者が「ごんの立場の不当さ」に気づきにくい構造なのだ。我々は、我々の社会と共通の関係性からは「立場の不当さ」を感じることが難しく、また価値観に共感してしまえば価値観に潜む「立場の不当さ」を見つけ出すことが難しい。
我々の思考にはこのような陥穽がある。『ごんぎつね』を読むときに限らず、現実世界を考えるときにもこの思考の陥穽に注意していきたいものだ。
■さいごに:「ごんが撃たれるのは当たり前」の読みからの気付き
よくある読みからは、『ごんぎつね』のラストシーンにおいて、「ごんは兵十との友好的交流を求め、実際に行動していたにもかかわらず、誤解から兵十に撃たれてしまったこと」の悲劇性が注目される。しかし、今回の読みからは、もっと注目すべき点があったことが判明した。
ごんが、兵十と同じ人間すわなち我々の側の存在であれば、たとえ本当にイタズラの為に兵十の家に侵入したとしても、射殺されることは無かったであろうという点である。イタズラではなく本当は償いや贈与のためだったのに誤解されて射殺された悲劇に目を向けがちだが、我々には保障されているイタズラ程度では射殺されない権利を、姿形は違えど人間とほぼ同等の狐であるごんには認められていない悲劇が、ごんが生きて死ぬ世界にはある。
「兵十-ごんの関係性」は「猟師-狐の関係性」であり、兵十がごんに対して生殺与奪の権利を持っていることは従前に理解していたが、兵十が当然にごんに対する生殺与奪の権利を持っている事の異質さとその異質さが当然の事として疑問に持たれにくい構造をごんの世界が持っている事、そしてそのような世界でごんが生きて死んだ悲劇に、私自身が今回の読みをするまで気が付かなかった。
現実世界には、女性差別や人種差別を含め様々な差別は存在している。それらの差別の中に生きる人たちの悲劇性は、正に今回の『ごんぎつね』の読みにおけるごんの悲劇性と同じものがあると感じた。現象面に現れる明らかな差別とその差別による悲劇だけでなく、気づくことが困難な当然視されいる社会構造に埋め込まれた差別の存在とその社会に生きる悲劇に注目する必要性を『ごんぎつね』の読みで再確認した(※7)。
【註】
※1 茂兵爺さんや茂兵爺さんからごんの話を聞いた語り手の世界が、読者である私たちと同じ世界の住人かどうかは分からない(ちなみに、ごんはおろか茂兵爺さんすら語り手が創り出した架空の存在である可能性もある)。作中作冒頭部からは、ごんの物語の語り手が、伝聞ではあるが自分の世界における過去の実話として語っているのか、桃太郎の昔話のように「むかしむかし、あるところにお爺さんとお婆さんが居ました」式のフィクションにリアリティを持たせる工夫として「むかしは、わたしたちの村のちかく・・・『ごんぎつね』というきつねがいました」と語っているのか分からない。私たち読者の世界においては、人間の思考や感情、そして善悪の価値観を理解し、十全な言語によるコミュニケーションが可能な狐は居ないため、ごんと語り手世界を共有しているならば語り手は我々の世界の住人ではない。語り手が世界をごんと共有していないなら、語り手も私たちと同じ世界の住人と見做しても差支えは無い。
※2 もちろん、マーク・トウェイン『ハックルベリー・フィンの冒険』の主人公ハックルベリー・フィンより名前を拝借した。
※3 兵十とごんの世界において「ごんが人間と同様に言語による十全なコミュニケーション可能な存在である」と兵十が理解している明確な記述は文中には無い。「ごんが人間とコミュニケーション可能な存在であると兵十が理解していると読む」のが一般的であろうが、「コミュニケーションが本来は不可能な狐であるとの認識が兵十にはあるものの、コミュニケーションしているかのようなごんの外観上の動きから、兵十の勝手な推測で(偶々ごん本人の意図と一致している)ごんの意図を読み取った気持ちになっているのだと読む」ことも可能である。そして、後者の解釈の世界において「ごんが有害な存在から有益な存在に転換したこと」を証明する信頼回復行動は、「こっそりと栗や松茸などを兵十に贈り続け、兵十の方から気づいてもらうこと」が最適になる。その場合、ラストの結末はタイミングが悪くて生じた不幸な行き違いとなる。
※4 事件は2020年5月4日に起き、AFP通信が同月9日に伝えた。また、ニュース原文では内容に関して、伝聞も含んでいることを示す文になっているが、今回の解説においてはその内容が伝聞かどうかは重要ではないので、その伝聞であることを示す表現は割愛した。どこが伝聞か気になる人はまだネット上に残っているのでAFP通信の原文を検索して欲しい。
※5 もちろん、この「メタ的な視点でアフガニスタン社会の価値観を判断すること」を判断する、メタメタ的視点もある。同様にしてメタレベルを無限に上げていくことが原理的にはできる。とはいえ、無限後退していくメタ的視点の考察は哲学者に任せる類のもので、現実問題として有用なのは2つか3つ程度メタレベルを上げた考察だろう。
※6 兵十が猟師であると明確に示す文はない。状況証拠によって兵十は猟師だろうと判断できる。その判断について説明していこう。まず、兵十が火縄銃を所持していることもさることながら、保存状態が悪ければ湿気ってしまい使用に耐えなくなる黒色火薬を、すぐさま利用可能な状態で兵十は物置に保持している点が重要である。日常的に黒色火薬を兵十が使用しているのでなければ、簡便な密閉手段のないこの時代の人間が、すぐさま利用可能な状態の黒色火薬を準備することはできない。特筆すべき所もない村に居住している日常的に黒色火薬を使う立場の人間は猟師以外考えにくい。また、兵十の火縄銃の取り扱いの手腕でみても猟師であろうと推測できる。ごんが家に入ったことを目撃した兵十は、ごんが栗をおいて家を出るまで(ただし、単にごんが栗を置いただけでは余りにも時間が短すぎるので、ごんは家の中で少し考え事でもしてたのだろう)の間に、物置から火縄銃を取り出し、火薬と弾丸を詰め、火縄銃の火縄に火をつけて、戸口に銃口を向けて狙いをつける準備をしているのである。このような熟練の早業を猟師以外の人間が持っているとしたら、それは武士以外ありえない。だが、兵十が武士ではないのは明らかである。したがって、兵十は猟師であろうとの推測が成り立つ。もちろん、猟師一本ではなく半農半猟の生活ではあろうだろうが。
※7 フェミニストの一方的な言動には、私は眉を顰めることが多いのだが、やはり男性が当然視している女性差別はあるだろうし、その女性差別の環境下で生きる女性の悲劇はある(同時に同様の構造を持つ男性差別とその環境下に生きる男性の悲劇もある)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
