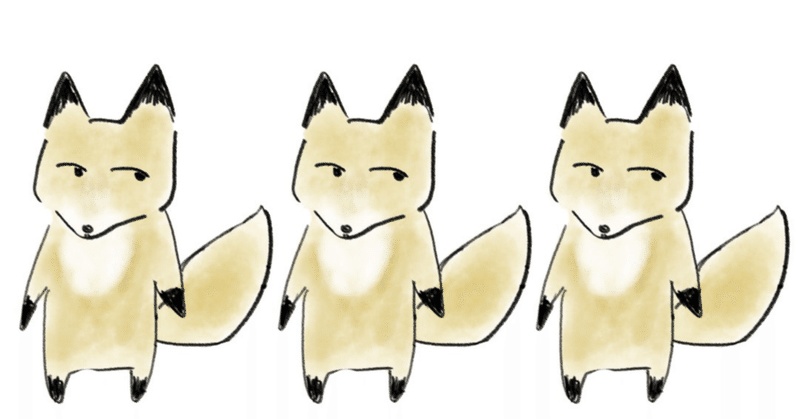
「ごんは撃たれて当たり前」は『ごんぎつね』を習う小学生の解答としてなぜ間違いだったのか
はじめに
表題の問題を語る前にまず「国語」の教科についてみたい。そして文学国語が何を学んでいるかの確認の上で『ごんぎつね』の国語における読解と件の小学生の何が問題だったのかをみていきたい。
国語のなかの二つの教科
現代文には2種類の分野がある。論理国語と文学国語だ。教科書の題材にある評論は前者に、小説は後者に属する。小学生の国語では、この二つは授業時間も教科書そしてテストも「国語」の括りだが、全く別の教科と言ってよい。譬えれば、数学と歴史が同じ授業時間・教科書・テストで扱われているようなものだ。扱っている対象がまるで違う。評論は文そのものを扱っているのに対し、小説は人間の心情・感情を扱う。よく「文章で表現されているものを読解する」というがこの二つの読解は全く違うものだ。それを理解せずに同一の行為であると勘違いしていると、国語はちっとも分からないとなる。
国語における評論と小説は生徒に何を学習させようとしているのかを見るにあたって、評論自体や小説自体の相違点をみるのではなく、テストの設問や授業での生徒への問いかけで何を学習させたいかを見ていきたい。
■国語の評論の読解とテスト
以下の問題文と設問を用いて国語の評論の読解とテストの
問題文 リンゴ・イチゴ・モモはバラ科であり、トマト・ピーマンはナス科である
設問1 上の文章でナス科として挙げているものは何か
――解答:トマトとピーマンである
設問2 上の文章は何について書かれているか
――解答:果物・野菜の分類について書かれている
設問には典型的には上の二つの類型がある。設問1は内容把握、設問2は要旨把握と呼ばれる種類の問題だ。
内容把握は、直接的に文章に書かれた文字通りの内容を問う。したがって文中の「トマト・ピーマンはナス科」という直接的な記述から解答する。ただし、実際の問題文の記述においては、設問とは関係のない説明的文章が挟まる、単一の文ではなく複数の文にまたがるといった形で、解答の根拠となる問題文の記述がすぐさま特定できないように難易度を上げている。とはいえ、文中に設問に対応する直接的な記述が存在する。つまり、対応する内容の文を探し出せるかを確認している。
要旨把握は、問題文の記述を文章外の知識を使用して要約する能力を問う。具体的にみよう。問題文中に登場するリンゴ・イチゴ・モモ・トマト・ピーマンに関して、それらが果物・野菜であると判断するのは問題文に書かれていない知識を用いている(※1)。そしてリンゴ・イチゴ・モモをバラ科とし、トマト・ピーマンをナス科とするのは分類するという行為であると判断するのもまた問題文には書かれていない。このような問題文に書かれていない、判断の前提となる知識を用いて問題文の記述を解釈していくのが、要旨把握という問題類型である。つまり、期待される水準での解釈の前提となる概念を一般常識としてもっているか、知っている概念を具体的に理解して概念化・具体化できるかが問われる。
評論の設問は文そのものを扱っている。すなわち「文に書いてあること/書いていないこと」を判別できるかを問い、回答者の文と意味の対応関係への理解・知識を設問で確認している。つまり、国語の評論の授業では文と意味の対応についての読解力を身につけさせようとしている。
■国語の小説の読解とテスト
文中に直接書いていないことを読解する問題が、国語の小説のテスト問題で出題される。このとき、登場人物がおかれた状況・行動でそのような状況における心情・情緒に関する知識を用いて登場人物の心情・情緒を推測して問題を解いていく。
教科として小説――文学国語――の学習において、「或る状況において湧いてくる心情・情緒、そして心情・情緒に基づく行動」が、教科で習得される知識になる。つまり、理科におけるオームの法則などの物理法則や生物の細胞についての知識、歴史における年号や出来事や時代背景の知識などと同じく教科学習で得られるものとなる。どんな状況で人は喜び・悲しみ・怒るのか、また喜び・悲しみ・怒りの行動とはどのような行動か、人間の多彩な心情・情緒にはどんなものがあるか。これを学ぶのが小説――文学国語――である。
しばしば文学国語の教育で共感力を養うと言われることがある。これに関して「共感力」の語感から「(自分が体験しなくとも)相手と同じような感情が湧く力」のようなイメージある。そういう力も共感力なんだろうが、文学国語の学習で得られるものは「心情・情緒に関する知識」であり、文学国語で得られる共感力とはその知識に基づく心情・情緒に関する具体的な理解である。
具体的にそれがどんなものであるのかに関して、以降で見ていきたい。
『ごんぎつね』の読解
小中高で学ぶ小説・物語は、学年が上がるにつれて、分り易い単純な感情から複雑で説明しがたい感情へと段階を踏んで難しい感情を扱うようになる。さらに、その年齢で課題になる感情がテーマになっている小説・物語が教材になっている。
表題に挙げた小4の教材の『ごんぎつね』は、猟師の兵十にイタズラをした狐の「ごん」が償いをするが誤解され撃ち殺される、というストーリーだ。イタズラをした後のごんの後悔、償いを理解してもらえないごんの感情、誤解で仕返しをした兵十の後悔など、つまり「イタズラをめぐる心情」がテーマだ。自身が「(小学生中高年で発達上の課題になる)イタズラ」に関わったとき、たとえ自らの感情は「ごん/兵十」のようでなくとも「他者の感情はどうなのか」が、この作品で得られた知識から理解できるようになる。
例えば、ラストシーンの「『ごん、お前だったのか。いつも栗をくれたのは』(中略) 兵十は、火縄銃をばたりと、とりおとしました。」を読んで、ある小学生自身は「ごんを撃ち殺したから、もう栗はもらえないなという残念な気持ち」になり、それが彼の心情だとしても、「大抵の人は『誤解したまま取り返しのつかない仕返しをして後悔する気持ち』になる」というものが、「(他者の)心情・情緒に関する知識」として正しいものになる。たとえ自分自身はそう感じなかったとしても(少なくとも他者は)そのような気持ちになる、というのを知識をして習得する(※2)。
趣味の読書ではなく教科としての文学国語を学習する意味は、上記のような形で「共感力」を得るためであると私は思う。
ごんぎつねを読んだ子が「撃たれて当たり前」と書いてなぜ間違いとされたか
結論を先に書いてしまうと、ごんぎつねを読んだ子が「こそこそした罪滅ぼしは身勝手で自己満足でしかない、撃たれて当たり前」といった読み方をしないようにするための科目が文学国語といえるからだ。
科目としての文学国語のテストは「"(世の中の大半の人である)一般人"の『状況Xにより感情Yが生じて行動Zとして表れる』という関係」の知識が問われているのであり、「個々の生徒自身の感想」の正誤を問うている訳でないということだ。つまり、作者ないしは出題者が意図する感情が”正しく”湧き上がったかどうかを判定しているのではなく、たとえ解答の感情が生徒自身に生じなくとも「(一般的な)他者がどう感じ得るか」を正確に指摘できるかを問うている、と言える(※3)。もっとも、生徒自身に湧き上がった感情が一般的な他者と同様のものであった場合、自身の感情を前提に回答しても正答にはなる。とはいえ、文学国語は自分の感情について問うているのではないことに気が付かないと文学国語の授業が何をやっているかいつまでも理解できないままだろう。
■「ごんは撃たれて当たり前」の感情を文学国語では扱えないか?
「こそこそした罪滅ぼしは身勝手で自己満足でしかない、撃たれて当たり前」という感情もまた文学国語の教科の範囲で十分に教材になり得ることだ(※4)。
くだんの小学生の感情の源は「報復は正当である」という意識だ。ごく自然な感情であるし、応報原則自体は間違っていない。それこそカントの刑法に関する思想はこれに基づく。しかし、決して報復は無制限に許されるわけではない。カントの応報原則はもちろんのこと、太古のハンムラビ法典に「目には目を、歯には歯を」とあるように、「罪に見合った罰」でなければならない。
では、ごんの犯したイタズラと報復によるごんの死は「罪に見合った罰」だったのか。天秤は釣り合っていたのか。
兵十の母の死の間際に兵十がよきこと(ウナギを御馳走すること)をするのをごんが結果的に不可能にしたのは、ごんが撃ち殺されなければならないほどの重大な罪だったのか(※5)。文学国語として「件の小学生の感想を教材として指導」するにあたっては、こういった応報原則もテーマになる。さらにはアリストテレスが著書『弁論術』で述べたように「復讐が甘美に感じる人間の感性」についても説明し、「一般的に自分の感情が赴くままに行動することはよい結果にならないこと」をもテーマにしなければならない。
また、兵十(猟師)とごん(狐)の社会的な関係性――猟師は狐に対して生殺与奪を握る一方的な立場――に注目して、ごんぎつねの寓話的解釈「兵十は親、ごんはその子供のアレゴリーである」を示し、子供のイタズラに対して親が重傷を負うほどの罰を与えたとしても、「それは当たり前」なのかを考えさせるような指導も可能だ(小4には教育的に悪いと思うが)。
『ごんぎつね』をイタズラに関する親子の寓話として解釈したとき、「こそこそした罪滅ぼしは身勝手で自己満足でしかない、撃たれて当たり前」との感想が如何に冷酷な感想であるかを、文学国語の指導者は説明しうる。
■小学生自身の限界を示す「撃たれて当たり前」の感想
「こそこそした罪滅ぼしは身勝手で自己満足でしかない、撃たれて当たり前」との小学生の感想は、常識に囚われない斬新な感想で素晴らしいのではないか、との意見が出ることもある。そのことに関して私の考えを述べていこう。
小学生が自分の感想を述べたとき、文中で述べられた登場人物たちの様々な事情にシッカリ注目できておらず、目に付いた特定の事情のみを重視して評価を下す行為は、さして特異なものではない。
こういう譬え話は誤解を生むかもしれないが、絵画において下手糞なうちはデッサンの狂った絵を描く。この初心者のデッサンの狂った絵画と正確なデッサンが描ける実力を持った上でのピカソの絵のようなデフォルメされた絵画を混同するのは美術の理解を妨げるように(もっとも絵画の造詣が深くないとピカソの絵と初心者の絵の違いが理解できなかったするが)、小説の解釈もまた小学生の独自の解釈と文芸批評家の斬新な解釈を区別し、評価基準を異にすべきなのだ。
■感想「こそこそした罪滅ぼしは身勝手で自己満足でしかない」への批評
「こそこそした罪滅ぼしは身勝手で自己満足でしかない、撃たれて当たり前」との感想がなぜダメなのかを『ごんぎつね』の作品自体に即してみていこう。
小学生の感想の前段である「こそこそした罪滅ぼしは身勝手で自己満足でしかない」に着目すると、ごんが贖罪を継続するなかでの描写でごんが身勝手というべき心境に陥っていることがわかる。またごんの贖罪を知っていれば悲劇的結末で兵十が後悔する羽目に陥らなかったであろうから贖罪をオープンにしなかったことは身勝手と言えなくもない。更には、ごんの贖罪を知らなかったからこそ兵十はごんを撃ち殺したのだからオープンにしなかった贖罪は自己満足に過ぎなかったと言えなくもない(ただし、それを知った兵十が後悔している点で、ただの自己満足とは片付けられない)。つまり、『ごんぎつね』の本文から「こそこそした罪滅ぼしは身勝手で自己満足でしかない」と読解すること自体は正しい読みといえる。
さて、身勝手な贖罪や自己満足である贖罪であったがゆえにごんが撃ち殺されて当然であると言い得るには、そもそも撃ち殺されて当然の罪をごんが犯していなければならない。それというのも贖罪行為は罪への処罰を軽くする方向には働くが罪を重くする方向には働かないからだ。つまり、有効な贖罪なら死罪にならなかったが、無効な贖罪だったので死罪になったのだといえる状況になければならない。では、ごんが犯した罪とはなんだったのだろうか。
『ごんぎつね』を注意深く読むとわかるが、実は、ごんがイタズラで台無しにしたうなぎが兵十のおっかあに食べさせるためのうなぎだというのはごんの予想でしかない。つまり、おっかあの死への客観的な意味でのごんの直接的・間接的な関係の有無は文中からは全く分からない。したがって、ごんの死を正当化する応報原則の天秤におっかあの死を載せることができない。また兵十へのイタズラでも応報原則からみてごんの死は重すぎる(※追記)。
つまり、ある意味で人間相互と同じ関係性を持ちうる存在であるごんに対して、「ごんは死に値する行為をしたから撃ち殺されたのだ」とは到底言えない。そうなると、イタズラで死んだうなぎとごんは同等の存在だったのだとして、ごんの死を正当化するぐらいしか手はない。『ごんぎつね』の内容でそんな解釈は可能なのだろうか?天才的批評家ならごんの死を説得的に正当化しうる解釈を生み出すかもしれないが、ちょっと私には想像しかねる(※追記)。
件の小学生の感想を斬新と評価する人たちは、もし文芸批評家が「ごんは撃たれて当たり前」との批評を出すとしたときに為さねばならないことを理解していない。死の重さを全く軽視している。
国語嫌いを生み出す授業
今の日本の教育において小説内の結果に至った因果関係のたどり方を学ばせる必要はある。そのやり方を授業でしっかり教えている教員ばかりではないとの印象がある。小説の授業は「小説を解釈」すべきだ。そして小説の解釈は論理的な営為である認識が必要だ。よい文学にはロジックはあることが多く、それを国語の授業で体系的に学ぶ仕組みがほぼ無いのではないだろうか。
全体あるいは一つの段落を読んだ印象だけから「○○と感じました」と生徒がなんとなく感想を述べる、それに対して教師が「好ましい/好ましくない感想だね」と評する(実際の言い回しとしては「正しい/間違っている」と評してそうな印象がある)ことをやっているのではないか。「なぜ、そういう感想に至ったのか。その感想は正当であり得るか」に対する批判的視野を欠いた授業が、国語嫌い・小説嫌いを生み出している可能性がある。
さいごに
小説を読むときの解釈枠組み「状況により感情が生じ行動を起こす」は、状況が原因で感情が生まれ、感情を原因として行動があらわれるという連鎖する二つの心理的な因果関係を前提にしている。
「状況から生じる感情とは何か」
「感情が生じる状況とは何か」
「感情によって起こされる行動とは何か」
「行動から窺える感情とは何か」
という原因と結果の組み合わせだけでなく、それらの因果を引き起こす「人間の感性・知性の傾向、善悪・正邪・美醜の価値、社会の慣習・規範・偏見など」といった、私たちを取り巻く世界の力について小説から知る事ができる。文学が科学とは異なった形であっても私たちの世界の真理を明らかにしようとする真摯な取り組みであるという視点を持てば、小説内の因果関係を重視するのは当然である。
■追記:「ごんは撃ち殺されて当然」は可能
・また兵十へのイタズラでも応報原則からみてごんの死は重すぎる。
・天才的批評家ならごんの死を説得的に正当化しうる解釈を生み出すかもしれないが、ちょっと私には想像しかねる
上のように大上段に振りかぶっておきながら、「ごんは撃ち殺されて当然」を可能にする解釈があり得ることを私自身が発見してしまった。つくづく大言壮語すべきではないと汗顔の至り。しかも、2023/1/1に当記事を書いて、そのたかだか3日後の2023/1/4にその発見するなんて。この解釈が可能な読みは近日中に別記事にて示したいと思う。ちなみに、その解釈は兵十とごんを「親-子」として捉える寓話的解釈の再検討と記事中の文章のなかで座りの悪かった以下の文を削除の検討(既にその箇所からは削除した)した際に発見した。
『ごんぎつね』の悲劇的結末で贖罪行為は相手に伝わるようにしなさいとの教訓を引き出すことは斬新でも難しいことでもない。
【註】
※1もちろんこのときに、ひねくれて解釈すれば「リンゴ・イチゴ等々は誰かが飼っている猫の名前だ。果物・野菜ではない」と強弁しうる余地は形式論理学的にはあり得る。だが、特段そのような解釈をしなければならない文がないのであれば、そのようなアクロバティックな解釈をしないように国語の評論の授業では指導される。
※2もちろん、『ごんぎつね』を読んで感情移入し、負の感情を齎すから「イタズラはやめよう」「誤解での報復は止めよう」と道徳的教訓を得てもいい
※3もちろん趣味で鑑賞する分には個人の自由なんですけどね。
※4現実的な話としては小4の発達程度および授業時間の関係でほぼ不可能※5後述するが、兵十のおっかあに食べさせるためのウナギだったかどうかはごんの推測にすぎない
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
