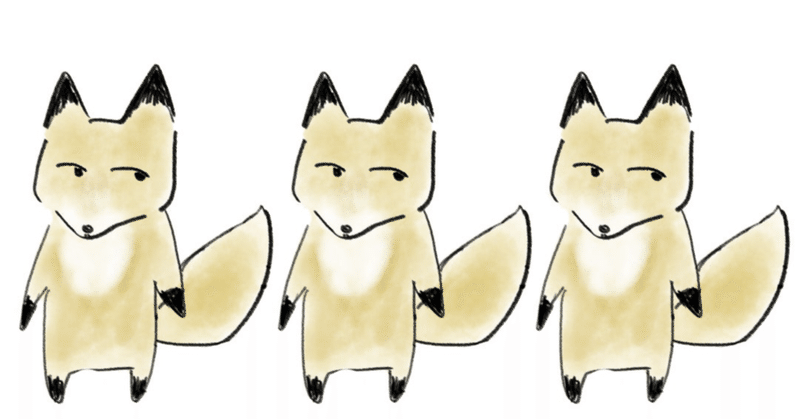
『ごんぎつね』の技法分析(5)
1.2.4当初の目的とは違うものを手に入れる(中)
前回の記事「1.2.4 当初の目的とは違うものを手に入れる(上)」では、悲劇作品のストーリーの型に関して、ヒロなんとか氏の「物語の才能」が推奨するストーリーの型とは異なる型もあることを確認し、『ごんぎつね』が「物語の才能」が推奨するストーリーの型ではない点に注意を促した。また、ヘミングウェイ『老人と海』の主人公の当初の目的とはなにか、最終的に主人公が得たものとは何かを確認することで、ストーリーにおいて「当初の目的とは違うものを手に入れる」ことの重要性を見た。
「当初の目的とは違うものを手に入れる(中)」においては、オモテとウラのストーリーの違いをしっかりと見ていきたい。
まず、オモテのストーリーとは何か、そしてウラのストーリーとは何かを確認する。その上で梶井基次郎『檸檬』を見ていく。そして、梶井基次郎『檸檬』を詳しくみていくことでウラのストーリーの重要性と作品の理解におけるテーマの重要性を確認する。
オモテのストーリー全般とウラのストーリー全般
この節で取り上げる作品は梶井基次郎の『檸檬』である。とはいえ、いきなり『檸檬』を見ていくのは難しい面もある。そこでオモテのストーリーおよびウラのストーリーとは何かをまず見ていきたい。
さて、オモテのストーリー全般について改めて確認しよう。オモテのストーリーとは作品の題材のストーリー展開である。これまで登場した作品で具体的に見てみよう。
『楢山節考』なら題材「姥捨て」のストーリー
『高慢と偏見』なら題材「ジェントリ階級の結婚」のストーリー
『罪と罰』なら題材「殺人事件」のストーリー
『スペードの女王』なら題材「賭博」のストーリー
『野菊の墓』なら題材「旧家の結婚」のストーリー
『長距離走者の孤独』なら題材「長距離走」のストーリー
上記のように列挙してみると把握できると思うが、客観世界の出来事の流れがオモテのストーリーである。
次に、ウラのストーリー全般を見よう。ウラのストーリーとは作品のテーマのストーリー展開である。だが「作品のテーマとはなんぞや?」という疑問も湧くであろうから、主観世界の出来事の流れがウラのストーリーであるとの観点で、先に挙げた作品のウラのストーリーを取り出してみよう。
『楢山節考』なら「親子愛」のストーリー
『高慢と偏見』なら「偏見からの解放」のストーリー
『罪と罰』なら「ナポレオン主義からヒューマニズム」のストーリー
『スペードの女王』なら「ナポレオン主義による破滅」のストーリー
『野菊の墓』なら「純愛」のストーリー
『長距離走者の孤独』なら「道具的存在に堕することへの反抗」のストーリー
上記の例においてウラのストーリーが、テーマと密接に関係し、転や結のパートでの主人公を駆動させている形で、オモテのストーリーと重なっていくことが確認できるだろう。
ともあれ、オモテのストーリーとは大まかにいえば客観世界の出来事の流れであり、ウラのストーリーとは大まかにいえば主人公の主観世界の出来事の流れである。これをおさえた上で、梶井基次郎『檸檬』を見ていこう。
■『檸檬』:ウラのストーリーの重要性
オモテのストーリーと当初の目的
『檸檬』のオモテのストーリーを一言で表すなら「散歩して檸檬を買って本屋にその檸檬を置いて立ち去るストーリー」といったものになる。客観的観点からの主人公の動きはこの通りなのだが、流石にこれでは何が何やら訳が分からない。もう少し「当初の目的」が判明する形でオモテのストーリーを示そう。
主人公は近頃は鬱々として以前楽しめた音楽や詩や絵画が楽しめない。ある日、京都の町を散歩し、途中でお気に入りの果物屋で檸檬を買う。買った檸檬を握ってその冷たさに快くなり、また臭いを嗅ぐ。そのことで気力を得て、近頃は足が遠のいていた丸善に立ち寄って画集を眺めるが、なぜか集中できない。挙句の果てに画集をゴチャゴチャと積み上げて、その上に檸檬を置き、そのまま丸善を立ち去る。
さて、上記を読んで主人公の「当初の目的」が分かっただろうか。主人公は以前楽しめた音楽や詩や絵画が楽しめないことに悩んでいる。したがって、また元通りに音楽・詩・絵画を楽しめるようになることが当初の目的である。
この当初の目的を果たすために主人公は京都の街を放浪する。だが、一向に当初の目的は達成できない。
ある日、主人公は散歩の途中で檸檬を買ったことで気分が良くなり、丸善に寄って以前と同様に画集が楽しめるかどうか確かめるチャレンジをする。だが、やはり画集を眺めても憂鬱になるばかりで、一向に当初の目的は達成できそうにない。
実際のところ、絵画・音楽や趣味的小物あるいは風景に関する審美的感覚が変化してしまったので、昔に好きだった音楽・詩・絵画・趣味的小物等を受け付けなくなっているのだ。ただし、そのことはウラのストーリーで判明する。
ウラのストーリーとオモテのストーリーが重なり合い、主人公は自分の間違いに気付く。その気付きは「積み上げた画集の上に檸檬を置く」ことで得られる。その気付きから、かつての審美的感覚の下で美を感じていた対象に決別するため、檸檬を爆弾に見立てた空想をする。積み上げた画集の上に檸檬を置いたままにして、それらを檸檬が爆破する空想で愉快になりながら主人公は丸善から立ち去るのだ。
ウラのストーリーとテーマ「審美的感覚」
オモテのストーリーの解説の節でも触れたが、梶井基次郎の『檸檬』という作品は、オモテのストーリーだけだと「だからどうした」という感想しか持てない作品である。ウラのストーリーが分からないとサッパリ理解できない作品である。それだけにウラのストーリーの重要性がハッキリする作品でもある。
主人公は最初の時点では間違っている
まず、冒頭の段落をみよう。
えたいの知れない不吉な塊が私の心を始終圧えつけていた。焦躁と言おうか、嫌悪と言おうか――酒を飲んだあとに宿酔があるように、酒を毎日飲んでいると宿酔に相当した時期がやって来る。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した肺尖カタルや神経衰弱がいけないのではない。また背を焼くような借金などがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ。以前私を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった。蓄音器を聴かせてもらいにわざわざ出かけて行っても、最初の二三小節で不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが私を居堪らずさせるのだ。それで始終私は街から街を浮浪し続けていた。
この部分から窺える主人公の最初の時点の間違った自己認識を通俗的に要約しよう。
「正体不明のモヤモヤで音楽や詩が楽しめなくなった。決して病気や借金のせいで楽しめなくなったんじゃない」
だが、これは主人公が大事なことを見落としたために生じた間違った考えである(※1)。このことに関しては既にみてきた「物語の才能」の該当部分を引用しよう。
主人公は承の前半で間違ったことをします。なぜ間違えるのかというと、大事なことを見落としているからです。
この見落としのせいで主人公は壁にぶち当たり苦しみます。
では、主人公はなにを間違っているのか、結論を先に示そう。
「モヤモヤがあるから以前楽しめた音楽や詩や絵画が楽しめない」ではなく、「以前楽しめた音楽や詩や絵画が楽しめないからモヤモヤしている」のである。そして、なぜ以前楽しめた音楽や詩や絵画が楽しめないのかと言えば、主人公の審美的感覚が変化してしまったからなのだ。
つまり、主人公は因果関係を逆に捉えているのである。
実際は、主人公の審美的感覚か変化してしまったために以前楽しめた事物が楽しめなくなっているのだが、そのことに気づいていないためにモヤモヤしている。楽しめなくなった理由がわからないためにモヤモヤしているのであって、正体不明のモヤモヤが原因で楽しめなくなったのではない。モヤモヤは結果であって原因ではないのだ。
このことを確かめるために、以前の審美的感覚と現在の審美的感覚がどのようなものであるか、本文から調べてみよう。そして、主人公が何を見落としているために間違っているのかを見ていこう。
以前の主人公の審美的感覚
まず、以前の状態の主人公の審美的感覚について以下で確認しよう。
以前私を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった。蓄音器を聴かせてもらいにわざわざ出かけて行っても
生活がまだ蝕まれていなかった以前私の好きであった所は、たとえば丸善であった。赤や黄のオードコロンやオードキニン。洒落た切子細工や典雅なロココ趣味の浮模様を持った琥珀色や翡翠色の香水壜。煙管、小刀、石鹸、煙草。私はそんなものを見るのに小一時間も費すことがあった。そして結局一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢をするのだった。
以前にはあんなに私をひきつけた画本がどうしたことだろう。一枚一枚に眼を晒さらし終わって後、さてあまりに尋常な周囲を見廻すときのあの変にそぐわない気持を、私は以前には好んで味わっていたものであった。
この3つの引用部で注目するのは以下の各部分である。
蓄音器を聴かせてもらいにわざわざ出かけて行っても
私はそんなものを見るのに小一時間も費すことがあった。そして結局一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢をする
あまりに尋常な周囲を見廻すときのあの変にそぐわない気持を、私は以前には好んで味わっていた
主人公の以前の審美的感覚を明示するのが3.である。正確に言えば審美的感覚を明示するというよりも何に美を見出すかという美的対象の構図を明示する。つまり構図でみると「美的対象-周囲」いうように、美的対象は自分の身の周りから乖離した存在であるというのが、以前の認識=感覚である。
そうであるからこそ、身近に無い蓄音機で音楽を聴き、自分が手に入れることのない品を小一時間も見て回り、周囲を見廻すときのあの変にそぐわない気持ちを好んでいるのである。
それは『檸檬』第2段落での表現を借りると「よそよそしい表通り」の美を以前の主人公は好んでいたと言えるのである。
現在の主人公の審美的感覚
以前との対比的表現で、現在の主人公の審美的感覚がどうなっているかを表現すれば、「どこか親しみのある裏通り」の美を現在の主人公は好んでいるのである。
そ れは以下で直接的に示されている。
何故だかその頃私は見すぼらしくて美しいものに強くひきつけられたのを覚えている。風景にしても壊れかかった街だとか、その街にしてもよそよそしい表通りよりもどこか親しみのある、汚い洗濯物が干してあったりがらくたが転がしてあったりむさくるしい部屋が覗いていたりする裏通りが好きであった。雨や風が蝕んでやがて土に帰ってしまう、と言ったような趣きのある街で、土塀が崩れていたり家並が傾きかかっていたり――勢いのいいのは植物だけで、時とするとびっくりさせるような向日葵があったりカンナが咲いていたりする。
すなわち、自分の身の周りの美こそが主人公にとっての美になってきているのだ。そのことが第2段落よりもハッキリわかる以下の部分で確認しよう。
その果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店であった。そこは決して立派な店ではなかったのだが、果物屋固有の美しさが最も露骨に感ぜられた。果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあって、その台というのも古びた黒い漆塗りの板だったように思える。何か華やかな美しい音楽の快速調(アッレグロ)の流れが、見る人を石に化したというゴルゴンの鬼面――的なものを差しつけられて、あんな色彩やあんなヴォリウムに凝り固まったというふうに果物は並んでいる。青物もやはり奥へゆけばゆくほど堆高く積まれている。――実際あそこの人参葉の美しさなどは素晴しかった。それから水に漬けてある豆だとか慈姑だとか。
現在の主人公は、青果店の人参葉、水に漬けた豆、クワイに美を見出していく。これは以前の主人公が美を感じていた「赤や黄のオードコロンやオードキニン。洒落た切子細工や典雅なロココ趣味の浮模様を持った琥珀色や翡翠色の香水壜。煙管、小刀、石鹸、煙草」といった小物類と比較すると非常に対照的だ。以前に美を感じていた小物は生活とは遊離した存在であるのに対し、現在の主人公が美を感じる人参、豆、クワイは生活に密着している。
ただし、身近なモノすべてに主人公は美を感じているわけではない点に注意したい。つまり、日常の雑多な事物の中から引き立てられるように美的感覚を呼び覚ます事物が出現するといった形なのだ。このことは以下の引用を見ると判明する。
またそこの家の美しいのは夜だった。(中略)そう周囲が真暗なため、店頭に点けられた幾つもの電燈が驟雨のように浴びせかける絢爛は、周囲の何者にも奪われることなく、ほしいままにも美しい眺めが照らし出されているのだ。裸の電燈が細長い螺旋棒をきりきり眼の中へ刺し込んでくる往来に立って、また近所にある鎰屋の二階の硝子ガラス窓をすかして眺めたこの果物店の眺めほど、その時どきの私を興がらせたものは寺町の中でも稀だった。
あるいは、先に見た箇所にもそれが示されている。
土塀が崩れていたり家並が傾きかかっていたり――勢いのいいのは植物だけで、時とするとびっくりさせるような向日葵があったりカンナが咲いていたりする。
これらは、日常的な生活のなかでハッと出会い、そして雑多で猥雑なものの中から自らが気づく美であり、洒落た店舗でディスプレイされた品々やレコード盤や画集といった誰かにセレクトされた美とは異なる美である。
そして、現在の主人公の審美的感覚によって見て取られる美は、高価さといった虚飾からも自由である。ただし、以前の主人公はそうではなかった。先に挙げた引用を再び見よう。
私はそんなものを見るのに小一時間も費すことがあった。そして結局一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢をするのだった。
以前の主人公の審美的感覚は、買えなかった「赤や黄のオードコロンやオードキニン。洒落た切子細工や典雅なロココ趣味の浮模様を持った琥珀色や翡翠色の香水壜。煙管、小刀、石鹸、煙草」と同じ高価な小物に属する「一等いい鉛筆」を手に入れて悦に入るのが美的生活と感じるような感覚だったのだ。
だが、高価さといった虚飾から自由になって美を感じるようになった主人公は、安っぽいものであろうが、そこに自分が感じる美があれば心惹かれるようになる。それを示すのが以下の部分だ。
私はまたあの花火というやつが好きになった。花火そのものは第二段として、あの安っぽい絵具で赤や紫や黄や青や、さまざまの縞模様を持った花火の束、中山寺の星下り、花合戦、枯れすすき。それから鼠花火ねずみはなびというのは一つずつ輪になっていて箱に詰めてある。そんなものが変に私の心を唆った。
また上記の引用は、主人公の審美的感覚が、複雑さや精妙さではなく、シンプルさにこそ価値を置くように変わってきていることを示す。単純な色の縞模様、また、それらが束ねられた有様に感じる美は、「洒落た切子細工や典雅なロココ趣味の浮模様を持った琥珀色や翡翠色の香水壜」や画集の中の絵画の色使いや造形と比較して実に単純である。だが、現在の主人公はそこに美を感じる。複雑な美よりも単純な美に心惹かれるようになってきているのだ。
さらに現在の主人公は、美的体験に身体性を求めるように変わってきている。肉体からの直接的感覚が美的体験において重要であるとの審美的感覚になっているのだ。そのことが示されているのが以下の箇所である。
びいどろという色硝子で鯛や花を打ち出してあるおはじきが好きになったし、南京玉が好きになった。またそれを嘗めてみるのが私にとってなんともいえない享楽だったのだ。あのびいどろの味ほど幽かな涼しい味があるものか。私は幼い時よくそれを口に入れては父母に叱られたものだが、その幼時のあまい記憶が大きくなって落ち魄れた私に蘇ってくる故だろうか、まったくあの味には幽かな爽やかななんとなく詩美と言ったような味覚が漂って来る。
びいどろやおはじきや南京玉は本来的には嘗めるものではない。だが、主人公はそれを嘗め、その幽かな涼しい味から、そこに詩美を感じるのだ。肉体的感覚に根差す美を、びいどろやおはじきや南京玉から現在の主人公は感じ取っているのだ。
まとめると、現在の主人公の審美的感覚は、以下の対象を美しいと感じる感覚に変化しているといえよう。
どこか親しみのある裏通りの美 (総称)
生活に密着した美
自ら発見する美
虚飾から自由になった美
単純な美
肉体的感覚に根差す美
そして、これらに美を感じる事自体は主人公は当初から自覚はしている。
当初の段階で主人公が見落としている大事なこと
主人公は自分が美しいと感じる対象が変わったことの自覚はある。つまり、どこか親しみのある裏通りの美として総称される、生活に密着した美、自ら発見する美、虚飾から自由になった美、単純な美、肉体的感覚に根差す美に対して、それらが自分の審美的感覚に適う美であることの理解はある。
だが、その自分の審美的感覚の変化、あるいはその変化が齎す影響を、主人公は当初の段階では自覚していないのだ。
現在の主人公の審美的感覚に適う美は、以前の主人公のそれとは全く異なるものになった。だからこそ、以下の箇所ように主人公は感じる。
書籍、学生、勘定台、これらはみな借金取りの亡霊のように私には見えるのだった。
この箇所は次のことを意味している。
書籍は生活から遊離している。学生では誰かから与えられる存在でしかない。高価さという虚飾を追えば勘定台から返済の請求がくる。そのことが、現在の主人公にとって自分から美を奪っていく実体のない何かであるように感じられてしまう。
だが、これらのことは主人公の審美的感覚に適う美が変化したからこそ起きたことだ。主人公の感性は、よそよそしい表通りの美からどこか親しみのある裏通りの美を美しく感じる感性に変わった。すなわち、生活から離れた美から生活に密着した美に、誰かから与えらえる美から自ら発見する美に、高価さの虚飾を追う美から虚飾から自由になった美に、複雑な美から単純な美に、そして肉体的感覚に根差す美に、主人公が追う美の対象が変わったのだ。
つまり、何かに邪魔されたから、何かに奪われているから、以前感じていた美が感じ取られなくなったのではない。単純に主人公の審美的感覚が変わったから、以前の美的対象には魅力を感じなくなり、それらに接しても楽しみや快さや興奮が生じないのだ。
この単純だが大事なことを主人公は見落としている。
この大事な事を見落としているから、当初の主人公は「えたいの知れない不吉な塊」によって、以前には感じていた美が感じ取れなくなったと勘違いしているのだ。
そして、これは解釈次第ではあるのだが、主人公が作者の梶井基次郎自身、あるいは主人公が作家等の芸術家であるとするならば、この勘違いは自分が追求している美を勘違いしていることになるので、ひどいスランプに陥ることになる。更に言えば、以前に追求していた美を否定し打破することこそが、現在において自らが美しいと感じる美を打ち出す契機になる。それというのも、自分が追求すべき美は以前に感じていた美なのだと勘違いしたままだと、どうやっても現在の自分が納得する美は生み出せない。つまり、以前に感じていた美はいまの自分が表現したい美ではないと明確に否定できなければ、芸術家の主人公は一歩も前に進めず、閉塞感に囚われたままになるだろう。
ミッドポイント:檸檬を買う
ミッドポイントは「檸檬を買う」ところだ。まず、この檸檬が主人公にとってどのような美を持つのかを確認する。その後に、檸檬が主人公に散歩の時点で齎した効果と主人公の勘違いを見ていこう。
檸檬の美
買った檸檬には、現在の主人公が感じる美がすべて詰まっている。それを主人公は感じ取っている。そのことを以下の引用から確認しよう。
その重さこそ常づね尋ねあぐんでいたもので、疑いもなくこの重さはすべての善いものすべての美しいものを重量に換算して来た重さ
上記の「すべての善いものすべての美しいもの」とは、先にみたどこか親しみのある裏通りの美である。つまり、生活に密着した美、自ら発見する美、虚飾から自由になった美、単純な美、肉体的感覚に根差す美である。買った檸檬にそれらの美を見出していることを、『檸檬』本文に沿って順不同で見ていこう。
まずは、生活に密着した美と自ら発見する美の側面である。本文をみよう。
その店には珍しい檸檬が出ていたのだ。檸檬などごくありふれている。がその店というのも見すぼらしくはないまでもただあたりまえの八百屋に過ぎなかったので、それまであまり見かけたことはなかった。
檸檬一般はごくありふれたものである。そして、それをただのあたりまえの八百屋で見つけた。だが、その檸檬はその店では珍しくあまり見かけないものである。日常の何でもない所から主人公がピックアップした檸檬に主人公は美を感じるのだ。まさに、その買った檸檬が生活に密着した美と自ら発見する美を持つことを示す箇所である。
次に、単純な美の側面を見よう。それを示すのが以下の箇所である。
いったい私はあの檸檬が好きだ。レモンエロウの絵具をチューブから搾り出して固めたようなあの単純な色も、それからあの丈の詰まった紡錘形の恰好も。
この感性は花火が好きになった感性と同じである。花火についても「安っぽい絵具で赤や紫や黄や青」という単純な色や、「さまざまの縞模様を持った」「一つずつ輪になっていて箱に詰めてある」という単純な造形に美を感じている。主人公は単純な色、単純な造形に美を感じるのであり、買った檸檬はまさに、そのような単純な美を持っている。
そして、肉体的感覚に根差す美の側面を見よう。主人公が買った檸檬に肉体的感覚に依拠する美を感じている箇所は以下である。
その檸檬の冷たさはたとえようもなくよかった。(中略)握っている掌から身内に浸み透ってゆくようなその冷たさは快いものだった。
私は何度も何度もその果実を鼻に持っていっては嗅いでみた。(中略)。そしてふかぶかと胸一杯に匂やかな空気を吸い込めば、ついぞ胸一杯に呼吸したことのなかった私の身体や顔には温い血のほとぼりが昇って来てなんだか身内に元気が目覚めて来たのだった。……
実際あんな単純な冷覚や触覚や嗅覚や視覚が、ずっと昔からこればかり探していたのだと言いたくなったほど私にしっくりした
買った檸檬から感じる単純な冷覚や触覚や嗅覚や視覚に対して、「ずっと昔からこればかり探していたのだ」と言いたくなるほど主人公は美を感じている。まさに、檸檬が肉体的感覚に根差す美を持っていることをこの箇所は示している。
最後に、虚飾から自由になった美の側面を見よう。それを示す箇所が以下である。
汚れた手拭の上へ載せてみたりマントの上へあてがってみたりして色の反映を量ったり、
この引用箇所から、「(オードコロンやオードキニン、香水壜、煙管、小刀、石鹸、煙草などが買えないために)結局一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢」をしていた以前と比べて、身の丈に合わない虚飾のキラキラさから自由になって主人公が美を感じているのが窺える。
以上から分かるように、生活に密着した美、自ら発見する美、単純な美、肉体的感覚に根差す美、虚飾から自由になった美を買った檸檬は持っている。
檸檬が主人公に齎した散歩の時点での効果と勘違い
檸檬の美は、現在の主人公の審美的感覚にマッチした美であるからその美を主人公は感じることが出来る。そして、檸檬から現在の主人公が美として感じる美が与えらえているからこそ、美そのものからと美が感じられている自覚に、主人公は幸福さ、快さを覚えるのだ。そのことが書かれている本文の箇所を示そう。
・私は街の上で非常に幸福であった。(第10段落)
・胸一杯に呼吸したことのなかった私の身体や顔には温い血のほとぼりが昇って来てなんだか身内に元気が目覚めて来たのだった。(第12段落)
・私はもう往来を軽やかな昂奮に弾んで、一種誇りかな気持さえ感じ(第14段落)
・なにがさて私は幸福だったのだ。(第16段落)
買った檸檬の美と美が感じれれる自覚から主人公は幸福さや、活力、軽やかな興奮、一種の誇らしい気持ちを得ている。
だが、主人公は、まだまだこの時点では勘違いしたままである。
実際は、現在の主人公の審美的感覚にマッチした美であるから檸檬の美を感じているという単純な事態であるにもかかわらず、「始終私の心を圧えつけていた不吉な塊」が弛んだからこそダイレクトに檸檬の美を感じ取れるようになった事態なのだと勘違いしてしまうのだ。
主人公がそのように勘違いしている箇所を引用しよう。
始終私の心を圧えつけていた不吉な塊がそれを握った瞬間からいくらか弛んで来たとみえて、私は街の上で非常に幸福であった。あんなに執拗かった憂鬱が、そんなものの一顆で紛らされる――あるいは不審なことが、逆説的なほんとうであった。それにしても心というやつはなんという不可思議なやつだろう。
つまり、現在の主人公が感じる美が凝縮したような檸檬に接することによって、主人公には確かな変化が現れている。だが、主人公はその変化の正体がなんであるか、まだまだミッドポイントの時点では理解していないのだ。
転のパート:勘違いしたまま主人公は試行錯誤する
主人公は転のパートでは勘違いしたままである。このことを示すのが以下である。
どこをどう歩いたのだろう、私が最後に立ったのは丸善の前だった。平常あんなに避けていた丸善がその時の私にはやすやすと入れるように思えた。
「今日は一つ入ってみてやろう」そして私はずかずか入って行った。
もし、主人公に自分の審美的感覚の変化に関する自覚があれば、このような行動をとらない。丸善にあるのは「よそよそしい表通りの美」であって、そこには主人公が美しく感じる「どこか親しみのある裏通りの美」は無い。審美的感覚の変化に関する自覚があれば、丸善に自分の求める美はないと理解できるので、丸善に入ろうとはしないはずである。
審美的感覚は以前のままで、檸檬によって美を感じる阻害要因が薄れたと勘違いしているから、「今なら美を感じ取れるはずだ」と考えて丸善に入るのである。
だが案の定、以前は美しく感じた丸善に陳列された美に対して、主人公は美しさを(当然ながら)感じ取れない。主人公は懸命に以前感じられた美を確かめようとするが、徒労に終わる。その様子を本文から見よう。
香水の壜にも煙管にも私の心はのしかかってはゆかなかった。(中略)私は画本の棚の前へ行ってみた。画集の重たいのを取り出すのさえ常に増して力が要るな! と思った。しかし私は一冊ずつ抜き出してはみる、そして開けてはみるのだが、克明にはぐってゆく気持はさらに湧いて来ない。しかも呪われたことにはまた次の一冊を引き出して来る。それも同じことだ。それでいて一度バラバラとやってみなくては気が済まないのだ。それ以上は堪らなくなってそこへ置いてしまう。以前の位置へ戻すことさえできない。私は幾度もそれを繰り返した。とうとうおしまいには日頃から大好きだったアングルの橙色の重い本までなおいっそうの堪えがたさのために置いてしまった。
上記のある意味で無駄な努力によって判明する、丸善に陳列された美=以前の審美的感覚の下の美が感じ取れないことに、主人公はガッカリして、憂鬱になり、無力感を覚えてしまうのだ。
結の前半:第一のアイディア「丸善での裏通りの美の再現」
主人公は袂の檸檬を思い出したことでどんな着想を得たのか。
それは、丸善の中で「どこか親しみのある裏通りの美」を再現することだ。つまり、本の表紙の色を用いて、現在の主人公が美しいと感じる花火の色合い、すなわち「安っぽい絵具で赤や紫や黄や青や、さまざまの縞模様」の色彩を再現するのだ。そして、その天辺に檸檬を載せることで、現在の主人公にとっての美を完成させるのだ。
この作業は主人公に高揚を感じさせるのだった。そのことを本文からみよう。
私にまた先ほどの軽やかな昂奮が帰って来た。(第22段落)
軽く跳りあがる心を制しながら、(第23段落)
この主人公の高揚感は、当初主人公が考えていたような、えたいの知れない不吉な塊が私の心を始終圧えつけていたことで主人公が美を感じ取れなかったわけではないことを示す感覚的反応である。つまり、たとえ場所が丸善であっても、裏通りの美に接することのできる期待によって主人公は高揚を感じることができることを示している。
それでは、第1のクライマックスである、丸善での裏通りの美の再現を完成させ、それを眺めるシーンをみていこう。
見わたすと、その檸檬の色彩はガチャガチャした色の階調をひっそりと紡錘形の身体の中へ吸収してしまって、カーンと冴えかえっていた。私は埃っぽい丸善の中の空気が、その檸檬の周囲だけ変に緊張しているような気がした。私はしばらくそれを眺めていた。
引用箇所前半は、丸善の中で再現した裏通りの美が、以前に主人公が感じていた美とは完全に違う形の美として屹立していることを、「カーン」という擬音で表現されるように主人公が感じ取っているシーンである。
そして、丸善という表通りの場所での裏通りの美の現出が、変な緊張を生み出していることを、主人公は見て取る。
さらに、積み上げられた画集(=かつての美)と檸檬が据えられた城壁(=現在の美)とが眼前に二重写しで並べられることで、その二つが対比され、かつての美は現在の美とは異なると主人公は気づくのだ。
結の後半:第二のアイディア「かつての美との決別」
丸善に陳列されているような表通りの美は現在の自分が感じる美ではないと主人公はハッキリと自覚し、それらから決別する。それが行動に表れたのが以下のシーンである。
不意に第二のアイディアが起こった。その奇妙なたくらみはむしろ私をぎょっとさせた。
――それをそのままにしておいて私は、なに喰わぬ顔をして外へ出る。――
私は変にくすぐったい気持がした。「出て行こうかなあ。そうだ出て行こう」そして私はすたすた出て行った。
かつての美が陳列されている場所から立ち去ることは、それらが現在の自分の感じる美ではないとの認識を行動で示したものである。また、檸檬をのせた画集の城壁を放置して立ち去る主人公の行動は「自分の感じている裏通りの美を丸善で展示してやろう」という行動でもある。
更に興が乗った主人公は以下の空想もし始める。
変にくすぐったい気持が街の上の私を微笑ませた。丸善の棚へ黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けて来た奇怪な悪漢が私で、もう十分後にはあの丸善が美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなにおもしろいだろう。
私はこの想像を熱心に追求した。「そうしたらあの気詰まりな丸善も粉葉みじんだろう」
かつての自分が感じた美は現在の自分が感じる美とは違う、なぜこんな単純なことに気づかなかったのかと可笑しくなった主人公の気持ち、そして、丸善に陳列された表通りの美による桎梏が破壊されて自由になった主人公の爽快さを示すシーンである。
だがそれだけに留まらず、「檸檬の美=裏通りの美」が「丸善に陳列された美=表通りの美」を木っ端みじんにしたならばなんと痛快だろうか、と主人公は感じているのだ。つまり、それは丸善に来た人々が放置した檸檬から「檸檬の美=裏通りの美」を目撃するであろうとの空想からより過激に、黄金色に輝く檸檬爆弾によって人々の美意識の変革が起こることさえ空想しているのだ。
またこれは、本文の「埃っぽい丸善の中の空気」および「積み重ねた本の群」の表現をどう解釈するかにも左右されるが、これを「古臭い権威の集積」と解釈するならば、古臭い美の権威を打破する美のイノベーションを主人公は空想していることになる。
そして、ここが『檸檬』の第二のクライマックスとなる。
ラストシーン:新たな美の中に生きる主人公の今後の姿
『檸檬』のラストシーンをみよう。
そして私は活動写真の看板画が奇体な趣きで街を彩っている京極を下って行った。
「活動写真の看板画が奇体な趣きで街を彩っている」の表現から、裏通りの美で彩られた場所で今後は主人公が生きていくことが想像できる。このラストシーンは、主人公が今後はシッカリと自分が美と感じるものに足をつけて芸術活動していくだろうことを示している。
もちろん、クライマックスにおいて、かつての美と決別し、現在の自分が感じている美を主人公が自覚したことは表現されている。
だが、ラストシーンは言わば、武道などにおける残心なのだ。ラストシーンは、余韻を漂わせて今後の主人公の姿を感じさせる働きを持つパートである。そして、そんな機能を持つラストシーンにおいて、自分の美を掴んで芸術活動をしていくであろう主人公の姿がしっかりと描かれているのだ。
作品のテーマ:審美的感覚
これまで見てきたように、ウラのストーリーにおいては主人公の審美的感覚がテーマとして描かれている。そして、変化した審美的感覚によって「生活に密着した美、自ら発見する美、虚飾から自由になった美、単純な美、肉体的感覚に根差す美」が新たな価値ある美として主人公によって提示されている。それは、古臭く権威付けられた美などよりも瑞々しく活力を与える美であることが我々に示されている。
また、その新たな価値ある美を主人公が掴むまでの内面のドラマをウラのストーリーで『檸檬』は描き出している。
しかし、これは作品のテーマを掴まずにオモテのストーリーだけを追っていればサッパリ理解できないドラマだろう。この『檸檬』の構造によって作品におけるウラのストーリーの把握の重要性が感じ取れるのではないだろうか。
余談:『檸檬』の起承転結
『檸檬』の起承転結について少し注意がいる。この作品は「起のパート」がやたら長いのだ。
通常、起のパートは簡潔で短い。したがって大方の読者も「起のパートは短いものだ」との構えでいる。起のパートはストーリーが動き出すための状況説明であるので、起のパートが終わらなければストーリーが始まらない。
つまり、起のパートがやたら長い『檸檬』はストーリーがなかなか始まらないのだ。大方の読者にとって、「もうストーリーは始まっているだろう」と思う分量まで読み進んでも、まだストーリーは始めっていない。
『檸檬』を読んでもサッパリ理解できないという人が少なからずいるが、その人たちがサッパリ理解できない理由の一端は、この「起のパートの長さ」にあるのではないかと私は感じている(※2)。
因みに、『檸檬』の起承転結の各パートについて、私は以下のように認識している。
起:主人公の状況説明の箇所
分量:2700字程度(作品全体5100字程度)
「えたいの知れない不吉な塊が~その時どきの私を興がらせたものは寺町の中でも稀だった。」
承:檸檬を買って丸善に行くまでの箇所
分量:1100字程度
「その日私はいつになくその店で買物をした。~そんな馬鹿げたことを考えてみたり――なにがさて私は幸福だったのだ。」
転:丸善で画集を見ている箇所
分量:650字程度
「どこをどう歩いたのだろう、私が最後に立ったのは丸善の前だった。~私は以前には好んで味わっていたものであった。……」
結:丸善で檸檬を取り出して以降の箇所
分量:650字程度
「『あ、そうだそうだ』その時私は袂の中の檸檬を憶い出した。~京極を下って行った。」
以上から分かるように、起のパートが作品の半分以上の分量を占めている。ストーリーが展開するパートの方が短いといった作品は、そうそう見掛けるものではない。この辺りが『檸檬』の読解を難しくしているように私は感じる。
「当初の目的とは違うものを手に入れる(中)」のさいごに
「当初の目的とは違うものを手に入れる(中)」においては、梶井基次郎『檸檬』を詳しくみていくことでウラのストーリーの重要性と作品の理解におけるテーマの重要性を確認した。
また、「当初の目的とは違うものを手に入れる(下)」においては、『ごんぎつね』のオモテのストーリーとウラのストーリーの二枚合わせの構造を見ていくことにする。
(1.2.4 当初の目的とは違うものを手に入れる(下)につづく)
註
※1 ただし、初見においては天下り的に「最初の時点では主人公は間違っているハズ」と決めてかかるのは読みの態度としては正しい態度ではない印象を私は持っている。もっと言えば初見の読みで技法的観点から作品を読むのはツマラナイのではないかと私は思う。初見の読みは素直に読んでいく方が良い読書体験になると私個人は考えている。
※2 筆者が学んだ現代文の教科書には掲載されていなかったが『檸檬』が掲載されている教科書もあるため、かなりの人が『檸檬』を読んでおり、その中で私が見聞きした少なくない人が、「『檸檬』の読後感は、それがどうした、というものだった」と零していた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
