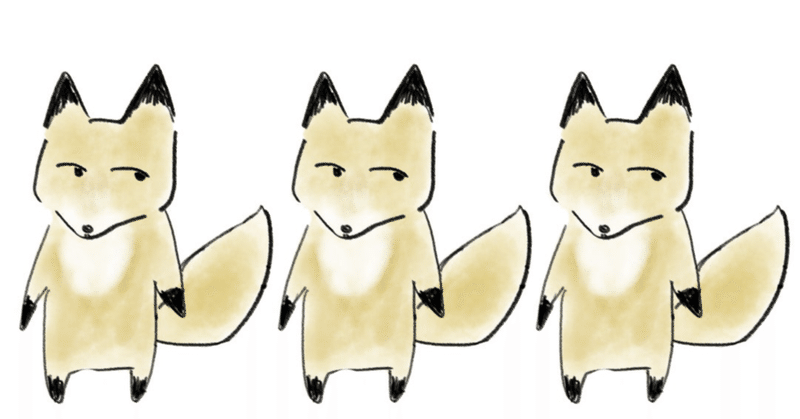
『ごんぎつね』の技法分析(1)
第1章 面白いとは?
「面白い映画や小説はなぜ面白いのか? 観客はいったい何を面白いと感じているのか?」この一番の基本部分がわかっていない人は、面白いストーリーを作れません。
ヒロなんとか氏の「物語の才能 - 面白いストーリーの作り方」では最初にこの章を持ってくる。「面白さ」は引用文において「この一番の基本部分」とあるように、映画や小説の価値の根底だ。また作者が「面白さ」を最も重視するのは、読者にとって根本的に重要な価値だからだ。
我々が古典や名作を呼ばれる作品を読み継いでいるのは「面白さ」がその作品にあるからだ。ツマラナイ作品は歴史の淘汰に耐えない。個々人レベルでは面白く感じる感じない色々あるだろうが、面白く感じる人が一定数で継続的に現れないならば「読み継がれる現象」を成立させる人がいない。
したがって、面白さは映画や小説の価値の根底となる。そして、それを最初に把握しておくことは、何より重要だと言ってよい。
1.1 面白いとは?物語の面白さとは結局のところ何か
面白さの正体だけは絶対押さえておきましょう。一番大事な基本です。
面白さの正体は非常に単純です。そのストーリーから感じる心地よさです。これによって観客はいい気分を味わい、満足感を得ます。
物語の面白さの正体というのは心地よさです。
引用文の「ストーリーから感じる心地よさ」に関して、当然ながら、春風駘蕩なハートフル・ストーリーや「めでたしめでたし」のハッピーエンド・ストーリーからの心地よさだけを指してはいない。また物語の面白さとは物語の愉快さや滑稽さなどを指していない。
当記事のシリーズでは『ごんぎつね』を「物語の才能」の枠組みで分析していくのだから、この「物語の面白さ」や「ストーリーから感じる心地よさ」が「物語の愉快さや滑稽さ」や「ハートフル・ストーリーやハッピーエンドストーリーの心地よさ」を指していないのは明らかだ。というよりも、それらを指していないからこそ、愉快さや滑稽さなどほぼ無い悲劇の『ごんぎつね』を「物語の才能」の枠組みで分析できるのだ。
別の作品、深沢七郎『楢山節考』でそのことを見てみよう。
「姥捨て」を題材にした作品全体に漂う閉塞感や非情なストーリーにも関わらず、そのストーリーで描かれた親が子を思い子が親を思う親子の情愛が私たちの胸を打つ。もちろん、『楢山節考』のストーリーから湧きおこる読者の感情に対して「心地よさ」と称することに抵抗を持つ人もいよう。だが、ストーリーでは、親と子はお互いに強く相手を思い遣って欲しいとの読者の願いを、登場人物の老母おりんと息子辰平は体現し、親子関係の理想を読者は見ることになる。つまり、ストーリーから生じた読者の願いを鮮烈な形で登場人物が叶えることの心地よさが『楢山節考』にはある。この心地よさが『楢山節考』の面白さである。
これから述べることを先取りしてしまったが、引用文にあるように「物語の面白さの正体というのは心地よさ」なのだ。
1.1.1 望んだとおりのことが起こると心地よさを感じる
観客は何によって心地よさを感じているのか?
この答えも非常に単純です。望んだとおりの展開になるからです。見たかったものがちゃんと出てくるからいい気分になります。
「こうなって欲しい」という観客の願いがちゃんと達成されるストーリー。それが面白いストーリーです。
観客の望んでいることがちゃんと起きる。それが面白いストーリーの正体です。非常に単純です。
これから上記のことが『ごんぎつね』ではどうなっているかを見ていこう。
『ごんぎつね』のストーリーから、読者は「ごんの気持ちに兵十は気づいて欲しい」との願いを強く持つ。そして、読者が望んだ通りの「兵十がごんの気持ちに気付く」との展開になる。つまり、読者の願いがちゃんと達成されている。見たかったものがちゃんと出てくるから読者は心地よくなる。このストーリー展開によって『ごんぎつね』は面白くなっている。
もし「川べりを歩いている手ぶらのごんを見つけた兵十が草陰に隠れながらごんを撃ち殺した」といったストーリー展開だと、読者が願いが達成されるストーリー展開とはいえない。そんなストーリー展開だと「うぇ!ごんは誤解されたまま死んで、兵十もごんを誤解したままごんを撃ち殺したぞ。ごんは狐で兵十は猟師だし、ごんはイタズラしていたから撃たれても仕方ないのかもしれないけど、まぁ現実は非情だね」と読者は一定の理解を示しつつも、望んだ願いがストーリーにおいて達成されず、なにやら居心地悪さを感じて物語に面白さを感じないだろう。ただし、「イタズラに対する報いがあるべきだとのストーリー展開」を望む読者が居ないではないので、多少の面白さはあるのかもしれない。
ともあれ、『ごんぎつね』は「兵十はごんの気持ちに気づいて欲しい」との読者の願いを達成するストーリーである。それゆえ読者に心地よさを感じさせる面白いストーリーなのだ。
1.1.2 なぜつまらないストーリーになってしまうのか
観客は興味がわかず「こうなって欲しい」という願望を発生させるまでには至っていません。願望自体が発生していないのだから「見たがっていたものを見せる」ということは当然不可能。観客には見たいものがないのだから。
見たいと思うようなものをちゃんと用意して、それを待ち望むようにさせないといけません。
失敗例にはそれがない。
幸福や悲劇を安易に出しても感動は生まれません。観客の心に願望を生み出せていないのだから機能しなくて当然です。
面白さのメカニズムは単純です。望んだとおりのことが起こるから観客は心地よい気持ちになる。それだけです。しかし難しいのは観客に「こうなって欲しい。こういうのが見たい」と思わせること。願望を持ってもらうこと。
こうした感情移入を発生させることが実は非常に難しい。みんなここでつまずいています。面白いストーリーを作るむずかしさはここにあります。
作品を読む側だとわざわざ駄作を読む必要はないので、読者には関係が無いように感じられる見出しだが、この節の内容もまた読者にとって知っておかねばならないことが示されている。一言で表すなら以下になる。
感情移入がなければ読者に「こうなって欲しい」との願望が起こらない。
これは、作品で用いられている技法を知ろうとする読者に「こうなって欲しい」と感じさせる感情移入はどのように起きているかを考える必要性を示している。
例えば、『ごんぎつね』の読者が「兵十にごんの気持ちが通じて欲しい」と望むのは、ごんに対する感情移入が読者に起きているからだ。感情移入を生じさせる要素とその働きは後の章などで詳しくみていくことになるから、この節では、『ごんぎつね』を改変し、こんな形なら感情移入は起こらないという思考実験を行おう。
さて、元々の『ごんぎつね』において、ごんは「兵十と仲良くなりたい」と思っている。兵十に栗や松茸を持っていくこともそうなのだが、以下の行動からごんの気持ちは明らかだ。
兵十のかげほうしをふみふみいきました。
上記の行動に表れているごんの気持ちは変化させず、他をかなり変えてみよう。
ゴン(カタカナ表記は改変後の主人公を示す)は、天涯孤独ではなく親や兄弟がいるキツネで、村人にイタズラもせず敵視もされていない、単に兵十と仲良くなりたい気持ちをもっているキツネであったとしよう。
ゴンは親狐と暮らす4兄弟の2番目の狐だ。近くの村に住む兵十は妹と二人暮らしをしていたが妹は少し前に隣村にお嫁にいった。ゴンは独りぼっちになってしまった兵十と仲良くなりたいと思って栗や松茸を兵十に持っていくことにした。兵十はびっくりしながらも喜んでゴンからの贈り物を受け取った。ゴンが兵十に「友達になって下さい」と頼んだら、兵十は「いいよ」とゴンに応えた。それから一人と一匹は仲良くいつまでも暮らしたとさ。
この改変ごんぎつねでは感情移入など起こらない。この物語を読んだとしても「ふーん、ゴンは兵十と仲良くなれて良かったね」と第三者的立場で思うが、全ての登場人物に対し、その人物の状況にも心情にも読者が感情移入することなどない。このことを、改変していない『ごんぎつね』と改変ごんぎつねを並べて確認してみよう。
天涯孤独のごんの境遇なら「なんて淋しい境遇なんだ。誰かとキチンと交流できないものか」との気持ちが湧く。
だがゴンはごんと違って家族がいる。その境遇からは「なんとか兵十と友達になって欲しい」などとの気持ちは湧かない。傍観者として「兵十と友達になれればいいね。でも兵十と仲良くなれなくても別の人と友達になってもいいし、家族も居るし平気じゃない?」と「そうなって欲しい」という強度の願いにはならない。
イタズラを止めて改心したごんには「ごんは改心したんだ。善良な狐になりつつあるんだ。分かってあげて欲しい」との気持ちが湧く。
しかし、元から善良な狐であるゴンに対しては「ゴンが善良であることはみんな知ってるよね。少なくとも悪い狐とは思われてない。改めて知ってもらわなきゃ!というほどでもないよね」といったように「こうなって欲しい」とまでの気持ちは出てこない。
償いに盗んだ鰯を投げ込んで失敗する、ごんが償いをしていることを兵十に告げていないなど兵十との仲の修復作業が順調に進んでいるとは言いかねる状態のごんには「償いが上手くいきますように、償いしていことを兵十にわかってもらえますように」との気持ちが湧く。
一方で、最初から兵十との友好関係を築くことができたゴンは「こうなって欲しい」と読者が願わなくとも元々望ましい状態にある上に、願うまでもなく普通に順調にいくだろうとの予測しか読者の頭に浮かばない。
ごんが栗や松茸を持って行っているのに「そりゃあ、神さまのしわざ」などと兵十が加助に吹き込まれているのを見ると「それはごんが持って行っているから、分かってあげて」との気持ちが湧く。
一方でゴンの贈り物はだれが贈っているか誤解の余地なく兵十は知っているため、願うまでもない。
兵十が償いの栗を持ってきたごんをイタズラしに来たと誤解して火縄銃で撃とうとするのを読むと「誤解だから!イタズラじゃないから!」との激しい感情が湧き誤解が解かれることを願う。
一方、ゴンが栗を持って行くと兵十にびっくりはされるものの喜ばれる。このとき読者は「まぁ喜ばれるだろうね」としか思わない。
撃たれて死にゆくごんをみるとき読者は「ああ、ごんが生きているうちに、せめて兵十は誤解を解いて」と感じそして願う。
一方、ゴンは兵十となんの障害もなく友達になる。それに対しては大した強度でもない「良かったね」との感想が読者に出るのみだ。
以上から分かるように、『ごんぎつね』においては感情を伴って「こうなって欲しい」と読者は強く願う。この願いの強さは引き起こされた読者の感情の強さに比例する。そして、願いの強さこそが、願いが達成されたときの読者が感じる心地よさの大きさとなり、『ごんぎつね』の物語の面白さになっているのだ。
一方で、「改変ごんぎつね」においては、読者は大して感情を喚起されず、感情移入が大して起こらない。感情移入が大して起こらないのだから、大して「こうなって欲しい」と読者は願わない。大して「こうなって欲しい」とは望んでいないのだから、達成されたときにも大した心地よさを生まない。そして、大した心地よさを生まないのならば、「改変ごんぎつね」は物語の面白さに欠ける代物である。
読者の感情移入がなければ読者に「こうなって欲しい」との願望が起こらない。延いては、感情移入が起こらない物語は面白くない物語になってしまう。逆に、読者の感情移入が起こるならば読者は「こうなって欲しい」との願望を抱く。そしてそれは物語を面白くさせることになるのだ。
補論1 事件単独での過激さや衝撃の大きさが読者の感情移入を大きくするとは限らない。
『ごんぎつね』では死が3度登場する。うなぎの死・おっかあの死・ごんの死と読者に対する強度を強めながら現れる。この「死」の衝撃の大きさが、読者の心を動かす強さとなり、「こうなって欲しい」との願いの強さにも繋がっている。
ただし、ここで一つ注意しておく。「(作品における)死のイベント単体」でも衝撃が大きいとはいえるのだが、むしろストーリーでの位置やテーマとの関係によって生じる衝撃の大きさの方が、「(死の)イベント」の衝撃の大きさにおいては重要だ。単体での衝撃の大きさは、そこまで重要ではない。
このことは現実世界において我々が感じる死の衝撃の大きさで考えてみるとよく分かる。
雑多なニュースをマスメディアから我々は見聞きする。このとき、死亡ニュースはそれ以外のニュースに比べて強いインパクトを持っている。だが、その死亡ニュースよりも身近な人の足の骨折の情報の方がより大きなインパクトを持っている。また、見知らぬ人同士であれば癌で亡くなった人の話よりも殺人事件の被害者の話のほうが大きなインパクトを持っている。しかし、遠い県でおきた猟奇的殺人事件よりも肉親の病死のほうが個人的には遥かに重要だ。このような我々の内面におけるイベントの評価は、イベント単独での衝撃度もさることながら我々個人とイベントとの関係性が決定的に重要である。
我々個人とイベントを物語に擬えて考えてみると、ストーリーにおけるイベントの位置、主人公とイベントとの関係性、イベントとテーマとの関係などで、イベントの評価すなわち衝撃度が変わってくる。パラレルに考えてみると、物語における様々なイベントもまた同様であって、ストーリーにおけるイベントの位置、主人公とイベントとの関係性、イベントとテーマとの関係などで、イベントの評価すなわち衝撃度が変わってくる。
つまり、物語において、文脈から切り離したイベント単独でその衝撃度の大きさを測ってはならない。
補論2 衝撃が小さくとも読者の感情移入を大きくできる
大した事件も起こらず心を大きく揺さぶる感動的出来事も無いストーリー展開であっても読者の感情移入を大きくできる。例えば、ジェイン・オースティンの『高慢と偏見』などが典型だ。
『高慢と偏見』は18世紀末から19世紀初頭のイギリスの田舎のジェントリ社会における女性の結婚事情(この時代の女性の遺産相続権がかなり重要)と恋のすれ違いを描いた恋愛小説だ。登場人物たちはそれぞれの立場で悩んだり騒いだりしているのだが、所詮コップの中の嵐にすぎない。
『高慢と偏見』を読んでいると「じれったいなぁ、とっととエリザベスとダーシーはくっ付けよ」と非常に強く感じる。ダーシーが高慢であるがゆえに素直になれなかったり、エリザベスに偏見があるためにダーシーを誤解したりしてすれ違うわけだが、あくまでもジェントリ階級のリスペクタブルの価値観の範囲内の話なので、何度も「そんなこと大したことない。二人はサッサとくっつけ」と読者に感じさせるのだ。
そして、ラストにおいて二人は結婚する。すなわち、読者の「二人は結婚して欲しい」との強い願いを達成させ、読者に達成の心地よさを感じさせて物語を面白くしているのだ。
つまり、大きな事件などなくとも「じれったさ」を感じさせることで強い感情移入を生み出している。もちろん、オースティンの物語の光景が眼前に浮かぶかのような精緻な人物描写の力も『高慢と偏見』においては大きい。しかし、1980年代の少女漫画が「じれったさ」で感情移入させる工夫をしており、それは『高慢と偏見』と同じ構造である。そして1980年代の少女漫画はその工夫で読者に感情移入させることに成功している。したがって、『高慢と偏見』において読者を感情移入させる力は、オースティンの人物描写の精緻さに帰するよりも、ストーリー展開における恋のすれ違いのじれったさに帰するべきだと私は思う。
この『高慢と偏見』における感情移入の成功から、読者を感情移入させるためには必ずしも作中の出来事の衝撃の大きさは必須のものではないと、理解できる。
1.1.3 承を抜くとどんな名作でも駄作になる
失敗作がつまらないのは主人公がただ頑張るだけの話だからです。
ストーリーに意味がありません。だから観客にとっても意味がなく、「こうなって欲しい」という願望を持てません。
その結果、感情移入が発生しないということに。
ストーリーに意味を与えましょう。テーマを用意しましょう。
ある程度の名作を選べば読者である我々の目には幸いなことに失敗作は入ってこない。つまり、名作を選んでいる限りにおいて「主人公がただ頑張るだけの話」を掴む心配をほぼしなくてよいのである。もちろん、三文小説やB級映画、濫造気味の漫画などで「主人公がただ頑張るだけの話」を掴んでしまうことはある。評価が定まっていない作品を鑑賞して「主人公がただ頑張るだけの話だなぁ」と感じたなら、自分の直感を信じて読むことや批評することを止めればよい。自分以外でその作品の良さを発見する人が出てからその人の批評をみて必要があれば読み返せばよい。
さて、ここで少し注意を喚起しておく。「物語の才能 - 面白いストーリーの作り方」は作者側から見た作品の話なので、上記の引用文は「感情移入が起こるすべての作品にストーリーに意味がありテーマが用意されている」ということを主張しているわけではない。ヒロなんとか氏が執筆にあたって推奨する「面白いストーリーの型」にはストーリーに意味がありテーマが用意されているというだけである。そのことをおさえた上で、「物語の才能 - 面白いストーリーの作り方」を導きの糸として「感情移入が起こる作品にはストーリーに意味がありテーマが用意されている」と仮定して読んでいくスタイルを取る。
とはいえ、『ごんぎつね』は明らかにテーマがあるから『ごんぎつね』を読むにあたってはその辺りはあまり気にしなくともよい。
では、テーマはどこから探せばよいだろうか。作者はどこにテーマを置くのだろうか。そこを示したのが以下である。
テーマを描いていくのは承の部分です。ストーリーというものは承を抜くとどんな名作でも駄作になります。
テーマを描いていく承のパートというのは実は非常に大事です。3つの失敗例がつならないのは承が抜けているから。起から転結へそのまま直行してしまっています。だから勝利にも意味がなくて面白くありません。観客も感情移入なんかしてくれません。
ストーリーを面白くする鍵を握っているのはテーマです。テーマを含む戦いの構図をしっかりと構築できたら、観客は感情移入してくれて「こうなって欲しい」という願望を持ってくれます。
つまり、『ごんぎつね』のテーマを探すなら承の部分で探せばよいというわけである。では、『ごんぎつね』の承とはどこからどこまでかを示そう。
ある秋のことでした。二、三日雨がふりつづいたそのあいだ、ごんは、ほっとして穴からはい出しました。
兵十が、赤い井戸のところで、麦をといでいました。兵十は今まで、おっかあと二人きりで貧しいくらしをしていたもので、おっかあが死んでしまっては、もうひとりぼっちでした。
「おれと同じひとりぼっちの兵十か。」
こちらの物置の後ろから見ていたごんは、そう思いました
つまり、『ごんぎつね』の承は、「一の途中」「二の全て」「三の最初」に跨る部分である。この部分は、ごんが兵十にイタズラを仕掛け、改心し、兵十に仲間意識を抱くまでを描いた部分である。この承の部分で注目するとなると以下の2箇所になる。
ちょっ、あんないたずらをしなければよかった。
「おれと同じひとりぼっちの兵十か。」
上からテーマを見出すなら「他者との交流」あたりとなるだろうし、下からテーマを見出すなら「親友を得ること」あたりになる。作者像の視点からは考えると「おれと同じひとりぼっちの兵十か。」からのテーマのほうがストーリーの意味との関係で『ごんぎつね』のテーマとして相応しい。つまり、「親友を得ること」が『ごんぎつね』のテーマになる。この辺りの詳細は、後の章で取り扱う話なので、今回はここまでにする。
次に以下を見ていこう。
ストーリーを面白くする鍵を握っているのはテーマです。テーマを含む戦いの構図をしっかりと構築
「ストーリーを面白くする鍵を握っているのはテーマ」という部分は、テーマを取り上げる章にて詳細に考察されているので、そこで確認しよう。したがって今回は「テーマを含む戦いの構図をしっかりと構築」について解説しよう。
「戦いの構図」とあるので、敵と闘争ないしは戦闘するイメージがあるかもしれない。実際、「物語の才能 - 面白いストーリーの作り方」の「承を抜くとどんな名作でも駄作になる」の節では、敵と闘争する構図を例として挙げている。
ただし、後の章との整合性を考えると、「戦いの構図」の意味内容は「敵と闘争する構図」といった狭義のものではなく、もっと広義の意味内容を持っている。すなわち「テーマに関することで、さまざまな障害や誘惑に打ち勝って努力する構図」といった意味内容が「戦いの構図」の意味内容である。
この「戦い」の語の用法は、他の事例でいえば「受験生として今年は戦い抜くぞ!」と気勢を上げるときの「戦い」の語の用法と同じである。受験生が誘惑や障害に負けず頑張るといった姿勢でいることを「戦い」と呼んでいるのと同様なのである。
『ごんぎつね』でいうならば、「兵十という友人を得るために、危険や困難をおして、償いなどを頑張る」といったものが『ごんぎつね』における「戦いの構図」となる。
第1章のさいごに
この章は面白いとは何かについての根本原理を解説した章である。途中過程を省略して、面白さの原理を振り返ると以下となる。
感情移入を発生させる戦いを用意→見たかったものが出てくる
以上が「物語の才能 - 面白いストーリーの作り方」でのヒロなんとか氏のまとめとなる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
