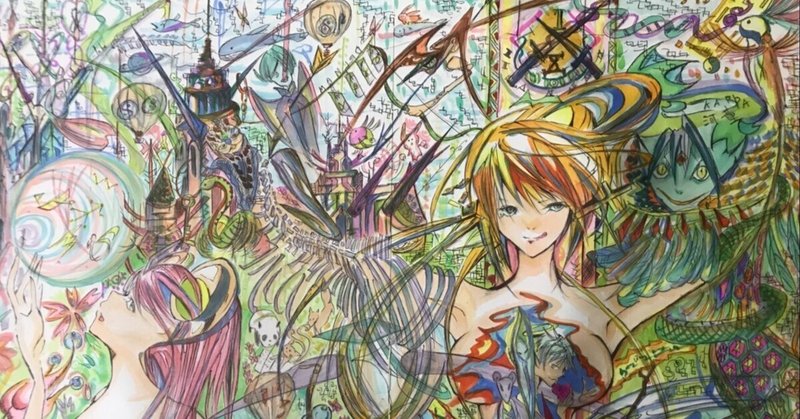
第59話≪ハル/TEU【蝶】の章⑥≫―風の森(かぜのもり)での神隠し―
『いわゆる峠は他国との風土と文化の接点であり、上り・下りの坂道は、「人生の峠道」である。また、時代は峠を開き、峠は時代を変える。変わらぬは峠を往き来する人々の飽くなき営みであり、その積み重ねが歴史である。』(*伝承【暗号化】S.I氏より)
いつからしか日本人は自国の伝統や歴史、昔すぐそばで生きていた動物、そして言語までも知らずして生きている時代になってしまってる。
アメンボって知ってる?
知らなーい!
…そっか…うーん…じゃあ今度雨の日に長靴をはいてみずたまりちゃぷちゃぷ歌いながら私とアメンボを探そう!
うん!!
「「指切りげんまん!」」
あやとりってしてる?
なぁにそれ?
みててね。ほら。こうやって…一本の糸を輪っかにするでしょう?これをこうやると…東京タワー!
わぁぁぁぁあ!!!面白い!僕もやりたい!
よし!あやとりは二人でもできるんだよ!こことここに指をそういれて…ひっくりかえして!
おわぁ!すごい!へぇ!一つの輪がこんなにも色んなものに変身するんだね!
うふふふっ。それは吊り橋だよ!
へぇー!
あの頃から誕生日というものを何回迎えたろう…
私は日々の仕事に忙殺され日本の本来の美しさを、大切なものをどこかに忘れてしまう自分に嫌気をさしていた。寒い風の中、パチンコやコンビニのライトに満ち、道路には車の排気ガスが舞う。都会の人はヒトとの繋がりというものを避け、街に闊歩する。逆に寂しさから知らぬ人との繋がりを温もりを感じることでしか孤独からの自身の存在を見いだせない類の人間同士の群れも街にひしめき合う。
わたしは見知らぬ人々に警戒心を抱いたままある街をあちこち転々と仕事の関係で独り住んできた。
廃れ汚れた街…冬の寒さも増して心は早く自宅の暖を求めていた。その時だ。
「ママ、これはなぁに」
可愛らしい小さな女の子の声の方向にハッと視線を向ける。まだよちよち歩きだした小さな女の子は道に並べ敷き詰められたタイルを小さな小さな人差し指で差し、まんまるのおめめはガラス玉のように輝いていた。
「それはねぇ、おんなじ板がね、こうやって並べてくれてるんだよ」
ベビーカーを止めて幼き子の母親が優しく小さな女の子にわかりやすくゆっくり優しい声色で説明する。
何故か、私はその光景に一瞬ハッと大きく目を見開き、足の速度をゆっくりにする。そして泣きそうになる、というより涙が流れていた。
小さなこどもの綺麗な好奇心ででた
『 ―Why? 』
―ねぇ、どうして?
それを見下さず卑下せず、産みの親が丁寧に説明する。本来ならばあって当たり前だった光景があまりにも久しぶりすぎて私の心は震え両目からぽろぽろ涙を流していた。
よかった…まだ…まだ…こういう『親子』がいて…こういう『光景』がこんな薄汚れた街にもあって…
アスファルトだらけの地面にもまだ、タンポポという草花が生きているのも目に入る。
次の日天気が良かったから散歩にでかけた。たまたま入ったお手頃価格のお寿司屋さんの隅っこに座る。
隣にご年配の方々がお食事をされていた。
割りばしを入れた長い長方形の紙を「こうやって折るのよ」と優しくご主人と思しき方にゆっくり教える奥さん。左指の薬指に綺麗な結婚指輪がはめられた手でゆっくり折り紙を教えてらっしゃった。
飾らない笑顔、照れながらも優しく奥さんの教えでゆっくり折るご主人の表情は柔らかくてみてる人たちの心をほっこりさせる。箸袋で可愛らしくも立派な箸置きが完成して私は心の底からすごいと感嘆する。
折り紙を今の子たちは折れるのかな…
今の私は折り鶴以外に折れるもの、何種類あるだろうか…
伝えていけるだろうか。私たちの次の世代に。この国が持っていた美しい文化を…
ありがとう。
こちらこそ。どういたしまして。
ありがとう。って言葉を最近聞けなくなってしまった。いつからこうなってしまったのか。
気が付いた時は手遅れで、でもそこにかすかでも光があるのならわたしたちはお互い優しさと平和の証に手を繋ぎあって輪をつくって生きていけるはず。そして希望や夢を描けるはず。
自分を信じてみよう。諦めないで。わたしも自分を信じ抜いて生きていくから、この文章を読んでくれているあなたもずっと自分を信じて決して諦めないでしまわないで。きっとわたしたちの願いは信じていくことで実現できる。
Seeing is believing. 百聞は一見に如かず。
だけど
Believing is seeing. 信じれば実現する。
最近のわたしは自分はどのような人間になっていくのか本気でわからない時があるし、そして時々科学者である自分自身、科学的に説明しがたい事象に遭遇する度に正直な話自分が怖い…という感情を抱いてしまうのも事実である。
私は何処へ行くのだろう…その先には何があるのだろうか…
難しく考えないように昔から自由奔放に生きているが自分自身不思議でたまらないのは事実でここに記録として残しておきたい。
昔、父方の祖父母の眠る墓がある和歌山県の世界遺産である高野山にある四国八十八箇所の最後の修験道且最高峰の奥の院で起きたことだ。先ほどまでそこまでいた私と妹が忽然と消えたらしい。父や母が大声で私の名前を呼びながら探しても探しても見つからなかった私と妹は奥の院の一番神聖な場所である地下の場所できゃっきゃ遊びはしゃぎまわっていたそうで、その私たちをみた父は開いた口も塞がらず怒る気持ちなんてさらさら湧かなかったと今でもいう。
その時のことは私の記憶には全くないが、その話を聞いた時思い浮かんだのは『神隠しにあった』という非科学的な言葉だった。まったくもって信じられない話だが、会うたびに何度も首を傾げながら鮮明な記憶を語り「ほんとに覚えてないの?」と何度も問う父を見聞きしてる私自身もそんな過去があったなんて不思議でたまらない。なのでいつも父と私二人で摩訶不思議だなぁと首を傾げている。
ほんとわたしって泣き虫ね。
ひとって、いつ死ぬかわからない。だからね、私はこれからも毎日の日々を丁寧に精一杯生き続けていく…
—『「峠は歴史風景の追想の道」であり「思考の場」である』
今は亡き日本の偉大なる民俗学者≪恩師≫ 柳田国夫氏より
いただいたサポートはクリエイターの活動費として使わせていただきます。

