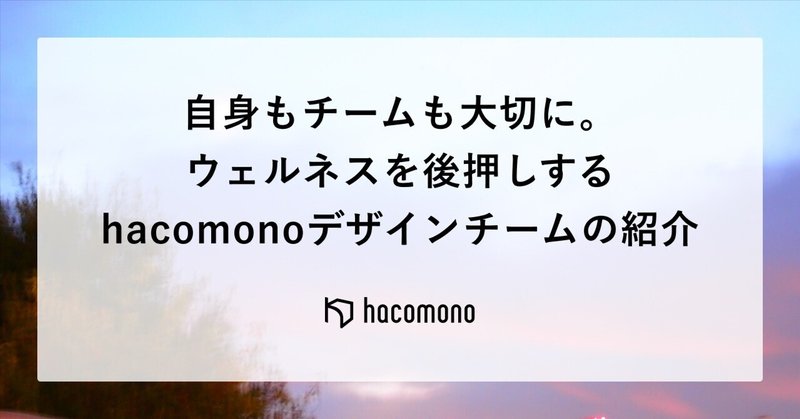
自身もチームも大切に。ウェルネスを後押しするhacomonoデザインチームの紹介
こんにちは、hacomonoでプロダクトデザイナーとして働くSakuと申します!
2023年6月に12年勤めた株式会社MIXIを退職し、7月より株式会社hacomonoに入社しました。
今回は、hacomonoを選んだ理由と、半年経って感じるhacomonoやデザインチームの実状についてご紹介したいと思います。
転職理由
前職ではプロダクトデザイナーとして、SNSミクシィや家族アルバムみてねの新機能・新規事業の開発企画・デザインなどを行っていました。チームもプロダクトも未だに大好きですし、社内で部署異動は何度か経験したとはいえ、環境を変える機会がないまま早10年以上…。子育てと仕事を両立する中で、外から学ぶ機会も減ってきて、「このやり方でいいの?」「他のデザイナーや組織はどうやってるの?」と考えるようになったのが今回の転職の理由になります。
hacomonoを選んだ理由

身の回りの人の生活を良くできる
hacomonoを選んだ理由としては、toCサービスを長年作ってきたので、BtoBtoC型のプロダクトでtoC寄りの体験を想像しやすかった点が大きいです。
実際、ピラティスやパーソナルジムの普及は進んでおり、hacomonoを使ったジムに通っている方が身の回りにたくさんいます。身近な人が使っていることを想像できるので、新しい業界といってもとっつきやすく、好奇心を持って取り組めるように感じました。
組織ブランディングに魅力を感じた
二点目はhacomonoの組織ブランディングに惹かれました。転職活動の中で出会った組織はどこもユニークで明快なミッションやパーパスを掲げていてそれぞれ素晴らしいのですが、hacomonoの「ウェルネス産業を、新次元へ」という心身ともに充実した生活を後押しするメッセージに共感したことと、採用プロセスの中でも掲げているバリューを体現していて、ブランディングの浸透を感じました。前職の後半でブランディングにも携わっていたのもあり、特に魅力的に感じました。
弊社のバリューは目標を立てる際にも明快で活用しやすく、先日もデザインチームのレビュー体制を見直す際に、基本的な指針となりました。
hacomonoのバリュー(コアシンキング/+チャレンジ/ラストマンシップ/オープン&フェアネス/ウィズカスタマー)については下記をお読みください。
フルリモート・フルフレックス
もう一つあげるとすると、フルリモート・フルフレックスの働きやすさです。 リモート勤務によって仕事と子育ては大幅に両立しやすくなりました。私は二人の子どもがいますが、上の子が小学生になったからといって楽になるわけではなく、逆にまともに学童や習い事にも行ってくれずまだまだ手がかかる、そして長期休暇があったり、ある日誰かが突然体調を崩したり…、いざというときに家にいると親子共に安心できます。ときには、鍵を忘れた近所の子を預かったりすることも。 また、今回の転職を機に、長年時短勤務だった雇用形態をフルタイム勤務に変更することができました。
hacomonoは子育て中の社員も多く、ライフワークバランスを維持しながら働くことができます。また、フルリモートであっても、イベントや顧客訪問などでチームメンバーと会う機会は十分にあり、メンバー同士の仲も良いです。
働き方やチームの雰囲気については、他メンバーの記事もぜひ読んでみてください。
デザインチームについて
もともと新規事業などのチームの立ち上げ期に関わることが多かったので、安定した組織よりも、自分たちで作り上げる楽しさのほうを求めるところはありました。多少の火事場は覚悟していましたが、当然良い点もギャップもありました。
hacomonoの良いところ
フィットネス産業の現場の声が面白い
hacomonoはフィットネス業界特化型のサービスなので、顧客との距離がとても近いです。大規模施設・小規模施設ごとの運営の工夫や業界のトレンドなど、サービス開発だけでなく、日々の生活にも活かせるノウハウの宝庫で、UXデザイナーとしては聞いているだけでわくわくします。感化されてジョギングを始めたり、毎日の食事に気を使ったりするようにもなりました。
デザイン組織が新しい
hacomonoはもともとエンジニア中心に開発されてきた経緯があり、デザインチームはここ二年で集まってきた新しいメンバーばかりです。hacomonoを良くしていこうと熱意を持ったメンバーとあれこれ相談しながら、自分たちの力でチーム運営体制やデザイン基盤を整えていくのは、大変ながらもとても楽しく、短期間で視野やスキルも広がったように感じます。
toB画面、toC画面、IoTなど幅広くデザインできる
hacomonoはtoB SaaSのアプリケーションですが、管理画面だけではなく、顧客画面のデザインをする機会も多くあります。また、社内にはIoTチームもあり、PCやスマホ以外のUI設計も体験できます。様々な利用シーンを想像して、飽きることなくプロジェクトに取り組めます。
入ってからわかったギャップ
hacomonoのデザイン基盤が思った以上に整っていないぞ…!
前述した通り、デザイナー不在の期間が長かったため、hacomonoはデザインが行き届いていないところも多く、良く言えば改善する余地が多く残されています。ブランディングやビジョンの根幹部分はしっかりとあるので、それをプロダクトで実現するにはどうすればいいか、日々整理整頓して方針を定めているところです。
組織が細かく分かれており、UXデザインがどう入っていくかは開拓していく必要がある
hacomonoの組織はSaaS系サービスでよく取り入れられている、The Modelを参考にした分業型組織になっています。前職では要件定義やPM的な役割もデザイナーで行うことが多かったのですが、PRD(プロダクト要求仕様書)はPdMがしっかりと書いてくれますし、顧客調査はPMMが担う面が大きいです。toCサービスに比べ顧客要件がずっと複雑なので、各職種の協業あってこそ、顧客に届く機能になっていると感じます。 ただ、私はどちらかというと体験設計の方に強みがあるデザイナーなので、要件がわりと固まっておりてくる中で、PdMとPMMと協業し、どのようにUXデザインプロセスを開発に取り入れていくのか、相談しながら進めているところです。
今後は、PRDとは別でデザイン要件定義書を書くフローを整備したり、ペルソナや顧客環境、デザインルールなど、hacomonoをデザインする上での基本的な情報を参照しやすくして、より安定して品質の高いプロダクトをデザインできるような基盤づくりを進めることができないかなと考えています。
また、質問されることが多いのですが、hacomonoはプロダクトデザイナーとコミュニーケーションデザイナーも組織上分かれています。コミュニーケーションデザインチームがhacomonoらしいデザインを支えてくれていますが、今後はさらにプロダクト側とコミュニーケーションデザイン側の連携を深めて、あらゆるタッチポイントでhacomonoらしいデザインを発信できるように体制を整備していきたいと考えています。
これから何をするのか
今までお話したように、hacomonoデザイナーとしてやるべきことは山積みです。
hacomonoの新機能のデザイン
まずはhacomonoが取り組むべき新プロジェクトのデザインをどんどんやっていきます!
私の入社後初のプロジェクトはイベント機能でした。通常レッスンとは別の期間で開催されるレッスンを運営する機能で、公共施設やスクールのイベントなど、広く用途が想像できる機能です。大きなプロジェクトを一つリリースしたことで、機能や業界理解も進みました。
次の新しいプロジェクトも既に始まっていて今後もリリースされるひとつひとつがお客様が使いやすいものになるようデザインしていきたいです。
デザイン基盤の整備

現行の体験を損なうことなく、より使いやすくより品質の高いものを早くデザインできるように、チーム一丸となってコンポーネントの改善に取り組んでいます!長期的にはデザインシステムを整備していきたいと進めています。最近は体制も整ってきて、改善施策がどんどんリリースされるようになりました。
また、品質が担保できるようレビュー体制の整備やデザインガイドラインなども作っている最中です。
組織の規模に対してデザイナーの数が少なく、課題は日々山積みですが、チームメンバーは熱意があり、かつ、気持ちよく働ける人ばかりです。そして、皆、趣味や子育てなど各自が自分自身を大切にしてウェルネスな生活をできているように思います。
hacomonoはデザイナーを絶賛募集しています。少しでも興味を持っていただければ幸いです。ぜひ気軽にお声がけください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
