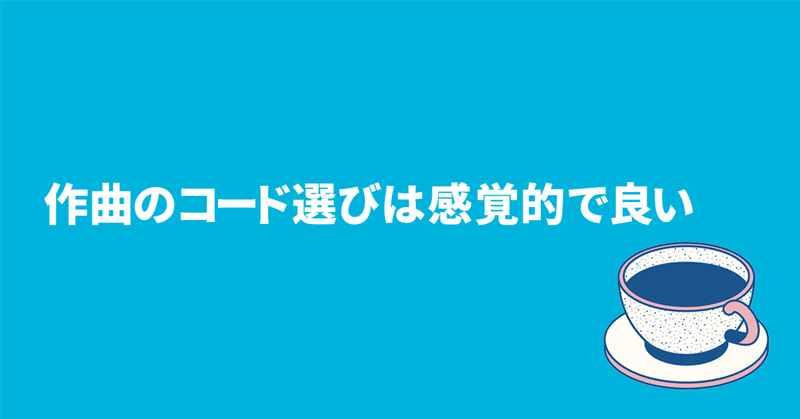
作曲のコード選びはまず感覚的で良いです
作曲のときのコード選びにおいて、
「こんなに適当にコードを選んで大丈夫なのかな…」
「ただあの曲の真似してコードを使ってるだけでいいのかな…」
と不安になることがあるはずですが、私の個人的思いとしてはまずそれで全く問題ないです。
特に作曲に慣れないころは好きな曲をたくさん弾き語って、そこで使われているコード単体やコードの前後関係などをまるごとコピーするように自分の曲に取り入れてみて下さい。
ひとまずそのコードがなぜそこで活用できるかという理論的な裏付けは後回しで、「なんとなくかっこいいから真似して使ってみた」で大丈夫です。
このあたりについて少し詳しく書いてみます。
心地いい響きをそのままコピーする
例えば、いろいろな曲を弾き語りしていると以下のようなコードの流れを頻繁に目にします。
「C→E7→Am」
これは「キー=Cメジャー」の例ですが、ここで扱われている「E7」のコードには独特な響きがあり、その後の「Am」につながって切ない雰囲気を生み出します。
ここで、冒頭で述べたことを踏まえると、作曲するうえでは
「この『E7→Am』がかっこいいから自分の曲でも使ってみよう」
という観点によって、それをそのままコピーするように自分の曲に取り入れれば問題ないです。
【メモ】上記で私は「キー=Cメジャー」と補足を加えていましたが、そのキーの概念すらなくても構わないくらいです。
知識先行だと上手くいかない
実際のところ、ここでの「E7」のコードは体系的な分類では「セカンダリードミナントコード」などと呼ばれるもので、本来のキーの音使い(=Cメジャーダイアトニックコード)に含まれないに特殊なコードとしてコード進行の中でスパイス的な役割を果たします。
そのうえで、例えば作曲の初心者が
「『Cメジャーダイアトニックコード』という概念がある」
「そこに含まれないものとして『セカンダリードミナントコード』に分類されるコードがある」
「その詳細は〇〇…」
「自分の曲にもそのセカンダリードミナントコードを活用してみよう」
というような発想の順序で作曲を進めたとして、果たして音楽的に心地良いものが生まれるのかといわれると、難しいところがあります。
なぜなら、知識を前提としてコードを扱うことでその響きやそこから感じられるイメージなどが後回しになってしまうからです。
結果として音楽は人工的なものになってしまいますが、音楽理論の勉強から作曲に入って上手くいかないケースのほとんどはこれです。
また似たようなケースとして、
「音楽理論を学ぶ」→「知識としてその理論を理解できるけれどそれを実際の曲にどう活用すればいいかわからない」
と悩む初心者の方は多いもので、その原因は同じく「実体験を後回しにしている」というところにあります。
使う→その後に裏付けを知る
コードを扱うことに慣れたり、もっと能動的にいろいろなコードを活用できるようになったり、さらには筋道を立てて自分なりにコードの展開を応用できるようになるために最も望ましいのは
まず使ってみる
その理論的な裏付けを後から知る
という順序を踏むやり方です。
これは、上記で挙げた「E7→Am」のような少し特殊なコードの流れはもちろんのこと、もっと入門的なところにあるものを含めた、あらゆるコード進行に対していえることです。
まずとにかく音楽をたくさん知って、それを自分でも演奏したり響きを体感したあとに初めて理論的な解釈を身につける方が明らかに内容が腑に落ちて、より実用的な知識としてそれらを理解できるようになります。
【メモ】特に作曲初期にこれをやるべきで、土台が固まってさえいれば、例えば中級以降の少し込み入ったコード理論などは知識先行でもそれなりに実用的なものとして扱えるようになっていきます。
私が
「作曲上達のために弾き語りをやりましょう」
といつも述べているのはこのような理由があるからです。
弾き語りをたくさん、いろいろなキーで、いろいろな曲を題材としてやるほどに、ここでお伝えしているような
音楽の基本的なルールとして必ず見かけるコードの展開
その基本を少し外れるような特徴的な響きを持ったコードやコードの展開
が体感としてわかるようになります。
それをもとにして、自分なりの感覚によって自由にコードを扱いながら曲作りを繰り返していれば必然的にコードに対する理解は深まっていきます。
そこに理論的な解釈は必要なく、得たパターンや響きをもとに、「あの曲で使われていたあのコード」という観点でコードを選べばそれで良いです。
ポイントは、上記でも述べたように幅広くいろいろな曲のいろいろなパターンを(弾き語りなどを通して)たくさん知ることです。
変に固く考えて知識から入ろうとしなくて大丈夫です。
真似して作るところから始めて、作曲の熱意優先で楽しんでください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
