
鴇色(ときいろ)の情景~千本桜~
序景

時は昭和二十年八月十五日。帝国臣民にとって最も長い一日の終わり、一人の海軍中尉が道後公園の桜並木の中を岩崎神社へと向かって歩いていた。海軍短剣を大切に携え、全身白の第二種軍装を身に着けた彼女の足取りは決して重くはなく、何か決意を秘めたようなその口元が印象的であった。
(良かった、これなら誰にも知られることはない)
灯火管制で足元が危うい中、彼女は岩崎神社のあまり大きくはない鳥居の隅をくぐると、丁寧に一礼してから手水を取った。そして数段の階段を上ると、ゆっくりとした動作で二礼二拍手一礼を行った。柏手の音も高らかなその所作は海軍中尉にふさわしく、神社の清らかな空間に溶け込んでいた。
彼女は静かに参拝を終えて階段を下りると、向き直って頭を下げ、やがて歌を歌い始めた。それは彼女が海軍兵学校時代、何度歌ってきたかわからない「江田島健児の歌」であった。
「澎湃寄する海原の 大濤砕け散るところ 常盤の松の翠濃き 秀麗の国秋津洲・・・」
彼女は二番まで歌い終わると、愛用の紫色のマフラーを取り出し、自分の膝を縛り始めた。
いよいよである、という時にまた頭の中に本日の正午、頭を垂れながら聴いた玉音放送の言葉が蘇ってくるのを感じた。
(朕カ陸海将兵ノ勇戦朕カ百僚有司ノ励精朕カ一億衆庶ノ奉公各々最善ヲ尽セルニ拘ラス戦局必スシモ好転セズ)
陸海軍も臣民も最善を尽くしたのに事態が好転しなかった、という陛下の詔勅は若干二十歳でしかない彼女のこれからを絶望させるのに十分であった。
また海軍兵学校時代に行動規範としてきた五省の中の、
「不精に亘る勿かりしか」
の言葉が彼女の心を責め立てるのであった。準備を整え、あらためて海軍短剣を彼女が押し戴くと、その目には涙が光っていた。
彼女は震える手で短剣を抜いた。すると彼女に飛び掛かってきたものがあった。
「誉!早まってはいかんぞ。」
手刀も鮮やかに短剣を叩き落としたのは第三四三海軍航空隊司令、源田実大佐であった。
「司令、死なせてください!菅野大尉は未帰還となり、私自身もアクロバット飛行に憧れた若者を何人死地へと追いやってしまったのか・・・この罪は生きて償うことは叶いません!」
「誉!私は明日大分の第五航空艦隊司令部に行って事の次第を確認してくる。軍人たる者は決して感情に基づいて行動してはならない。」
源田が珍しく語気を強めると、誉はがっくりと頭を垂れ、泣き出した。その頭を源田は優しく撫でながら、誉の膝にまだからみついている紫のマフラーをほどいた。
「誉、私だって大村基地で第一報を聴いたときは驚いた。だからまず菅野亡き後の新選組をどうするかをお前に指示してから確認に向かうのだよ。」
「・・・はい。申し訳・・・ございませんでした。」
「誉、お前の報国心、一旦私が預かる。」
誉は驚いて顔を上げた。視線の先には源田のいつもの心優しくも力強い顔があった。源田がうなずく。
誉の目からはまだ涙がこぼれ落ちていたが、表情にはキリリとした涼やかさが戻っていた。
「はい。ありがとうございます。新選組は・・・どうしていればよろしいでしょうか?」
「うむ。ひとまず私が戻るまで屯所で待機。これは新選組だけではなく、他の剣部隊の面々も同じだ。」
「はい。」
誉は泣き止んだ。
「松山は大村と違って錬成部隊だから、待機と言っても訓練飛行は続けられる。人間何もすることがないよりはある方が統率も取りやすいはずだ。」
「はい、そう思います。」
この細やかな伝え方が源田らしいと誉は感じた。
「後は」
源田が一旦言葉を区切った。
「川西誉は第三四三海軍航空隊の貴重な指導的搭乗員、自分を大切にしてほしい。」
誉は深く頷き、すっくと立ち上がった。
「帰ろう。」
「はい。」
道後公園の千本桜の並木道が誉と源田を再び出迎えた。明かりは変わらずなかったが、二人には鴇色に狂い咲く桜の花びらが幻のように頭をよぎった。
「この三千世界を・・・常闇の世にしてはならない。」
源田がぽつりと呟く。誉は並木道の遠く先を見つめながら頷いた。
第一景

源田は誉を伴って隊へと戻った。同隊の中西中尉が駆け寄ってきた。中西中尉は同じ尉官の職にあっても兵学校では誉の一級上の72期生、誉にとっては心優しく、また頼りになる先輩であった。
「中西、心配をかけて済まなかった。」
「申し訳・・・ありませんでした。」
「誉、気持ちは・・・わかるぞ。苦しいが、今は艱難辛苦に共に耐えようではないか。」
中西は苦渋の表情で、絞り出すように呟いた。
「はい。」
誉は頷いた。
源田があらためて中西・誉の二人で新選組を明日からまとめ、戻るまでは努めて通常の訓練を隊員たちに施すよう伝えた。その後源田は早めに休んだが、屯所の司令室内から掩体壕の中の紫電改を中西と誉は静かに見つめていた。
「誉・・・われわれはこれから・・・何をよすがに生きて行けばいいのであろう・・・な。」
中西は天を仰ぎ、嘆息しながら漏らした。
「・・・。」
誉もその答えを自分の中に見出すことはできなかった。
紫電改設計者の川西龍三を父に持ち、海軍兵学校73期生として入学する以前から女性初の戦闘機乗り兼整備士として報国心の象徴のように生きてきた自分。源田とともに源田サーカスと言われたアクロバット飛行に果敢に取り組み、日本中の少年たちを戦闘機に熱狂させた自分。
そしてその縁をきっかけに第三四三海軍航空隊へと召喚され指導的搭乗員として、戦いながらも次世代の戦闘機乗りの育成に携わっていた自分。その全てが今、時代という大きな波によって否定されようとしていた。
「中西中尉・・・まだ源田司令の口から・・・事の次第を聴いていません。」
誉の声はか弱かった。中西はハッとした。彼の問いは誉が今までの自分自身の人生に苦しめられ、折角自決を止めて帰還してきた彼女を再度追い詰めてしまうと気付いたからだ。
「誉、弱気なことを漏らして済まなんだ。結果の出ないことを思い悩んでも仕方がない。われわれももう休もう。」
中西は気持ちを切り替えて誉を促した。しかし、誉はぽつりとつぶやいた。
「紫電改の心臓は・・・誉。そう、私自身・・・。」
紫電改のエンジンの名称は、誉の父龍三が自慢の娘の名をつけたのだと、海軍航空隊に所属する者は皆知っていた。中西は窓の外の紫電改をちらりと見たが、誉の肩に手を置いて力強く否定した。
「誉、お前は人間だ。機械は人間が操る物、取り込まれるな!」
普段穏やかな中西とは思えぬ大声であった。今度は誉がハッとした。自分がまだ死に魅入られているのを感じて、思わず何かを払うようにパンパンと軍装をはたいた。
「休もう、誉。」
中西が誉の目を見て再度伝えた。精も根も尽き果てた、という言葉がぴったりだった。誉は挨拶もそこそこに自室へ帰ると、そのまま深い泥のような眠りに沈んでいった。
翌朝喇叭の音で目を覚ますと、誉は軍装をきちんと解いて寝た自分の習性に驚いた。兵学校の3号生当時、内務で分隊全員の脱ぎ散らかした洗濯物を全て洗い、一部のずれもなく畳んで受け渡していたことをふと思い出した。
第三種軍装に着替えると源田が出立前に朝礼にて訓示の報せがあった。駆け足で向かう。話は昨日と同じであったが、何が起こりうるのかわからないこの混乱した状況においては聴いていて気の引き締まる思いであった。
幸い昨晩何があったのかは隊の皆には知られておらず、源田の訓示も功を奏し新選組は比較的落ち着いていた。また皆が紫電のエースとして尊敬する松場秋夫少尉の講義を三日間に渡って予定していたのも運が良かった。訓示が終わると皆教室へと戻った。
誉が紫電改のエンジンについて説明した後、松場が実践的な操縦法について教える流れであった。講義となると自然と誉は熱が入る。松場も同様であった。何かあっという間に三日間は過ぎ去った。
19日に源田が帰還すると、再び訓示と称して皆が集められた。源田は美しい隊列を見渡すと、真剣な表情で話し始めた。
「去る16日に、大分の第五航空艦隊司令部に行って事の次第を確認してきた。しかし納得のいく回答が得られなかったので、高松宮宣仁親王に直接お会いし、説明を受けて諸君への誠意ある回答を得てきた。」
みなぴくりとした。いかにも源田らしい、と誉と中西は思った。やがて源田は一言一言を振り絞るように、また隊員一人一人の顔を見つめながらこう伝えた。
「陛下の一言、いかんともできぬ。重臣たちがそそのかしたものなら・・・徹底抗戦のつもりだったが、自由もよい、民主もよい、今日から源田は・・・一個人である。もうこうして諸君らと会うこともないだろう。国家再建は容易ではないだろうが・・・頑張ってもらいたい。」
最後のところを源田は力強く伝えた。皆静かに感動していた。
それは終戦以来皆心の中で何度慟哭し、叫び続けたかわからない各自の希死念慮を薄れさせ、「国家再建」という何かまだ良くはわからない道のようなものへと力強く導く訓示であった。
どこからともなく拍手が沸き起こった。それはこれから何をよすがに生きていけばいいのかわからずに彷徨いかけていた若者たちの感謝の念であった。
誉もまた、源田が預かると言っていた「報国心」が新しい、力強い形に姿を変えて手のひらの中に戻ってきたのを感じて涙が出た。
(われわれの肩に、源田司令は新しいものを託された)
自然に皆源田の近くに駆け寄っていた。日焼けした顔に浮かぶ力強い微笑みは一際優しく、穏やかであった。こうして第三四三海軍航空隊で命を永らえた者たちは「戦後」への第一歩を揃って踏み出すことができた。
第二景
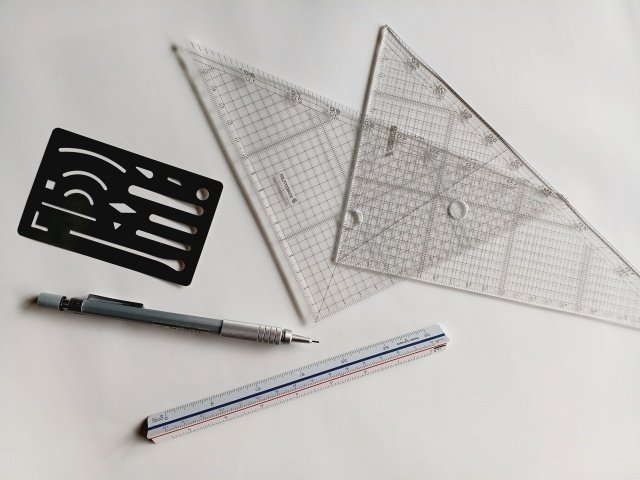
やがて残務整理も区切りがつき、誉も海軍を解員となって実家のある神戸市須磨区へと帰還してみると、国営軍需工場だった川西航空機の工場はGHQに接収され解散を命じられていた。戦闘機の開発技術も接収され、さらに父龍三は公職追放処分を受けていた。川西家の財産は全てなくなり、また戦争を扇動したとして誉自身も世間の厳しい視線に晒されることとなった。
しかし誉はくじけなかった。兵学校時代の得意科目であった物理の教員資格を取り、母校の神戸女学院で教えるようになったのである。誉は二十歳そこそこながら、海軍で教官をしていたため指導が丁寧でわかりやすいと評判になった。
誉は国家再建のためには、女子教育に力を注がねばと何か信念のようなものが自分に芽生えてきているのを感じていた。それは神戸女学院、海軍兵学校で当時の一流の教育を受けたにもかかわらず、女性としての見た目の華やかさから戦争鼓舞の道具へと自らなっていったことへの反省から来るものであった。
誉はただ夢中で働いた。その姿を見た父は公職追放が解かれると昭和24年には早くも会社を設立し、来るべき航空機製造の解禁に向けてさまざまな試みを開始した。
誉は幼いころ川西航空機の設計室を遊び場にして育ったのを想い出し、ふらりと父の新会社の設計室へと足を向けた。そこには父の大好きな航空機の図面が多数掲示されていた。目をやると操縦士として、往年の情熱が自分にふつふつと蘇ってくるのを感じる。誉は思わず目を背けた。
(いけない。私は・・・一人でも多くの女生徒に理系の学問の楽しさを知ってもらわねばならぬのだから)
戦後の新しい学制の中で神戸女学院の生徒の優秀さは勢いを増し、誉の理想の理系大学への進学率へは後少し、というところまで来ていた。
ただ父の生き生きとした姿を見るたびに、何か心に引っかかるものがあるのが自分でも不思議であった。そんな気持ちを抱えたある日、それは突然やってきた。父龍三、62才での死であった。
昭和30年、会社もまだ立ち上げたばかりで社内をまとめるため、誉に社長職を継いでほしいと言ってくる役員も出てくるほどであった。父の愛した会社のためと誉は迷う気持ちもあったが、その申し出はきっぱりと断った。
理由は「経験がないから」というあっさりしたものであった。誉はもう二度と実務の伴わぬ操り人形のような象徴の役割をしたくなかったのである。
一方で父の死をきっかけに、別の想いもまた芽生えてきていた。自分は本当に後進の育成のみに力を注げばいいのか――――――という疑問である。思えば新会社の設計室に足を向けた時の情熱はこれが正体だったようにも感じる。誉はその感情に確信を持ちたくなった。
父の葬式と四十九日を無事終わらせたころ、誉はふとあの設計室にもう一度行ってみたくなった。父の荷物が残っていないかの確認と称して誉は設計室へと向かった。胸が高鳴る。ドアを開けると、設計室の父の机には紫電改の模型とともに、見覚えのある古びた三角スケールが置いてあった。
そして父の机の先に掲示してあったのは紫電改の「誉」あの川西航空機製作のエンジンの図面の再現であった。図面には父の実印が押されてあり、生前父がどうしても再現したくて書き残したものだと誉にはすぐ理解できた。
誉はそれを見た時雷に打たれたように自分の本当にしたいこと、湧き出る情熱を感じ取っていた。(もう一度、空に戻りたい。今度は何かのためではなく、自分自身のために)
設計室からの帰り道、鴇色の桜の花びらが一枚誉の足元に落ちてきた。誉がその花びらを拾い上げると道後公園から戻る道の千本桜が不意に想起された。
(そう、狂い咲いた、と言われようとも・・・)
誉の目には赤く染まる空とともに、細く飛行機雲のように明日への道筋が映り始めていた。
第三景

昭和30年3月、神戸女学院の理系への進学数は折よく誉の目標数へと達した。それを見てからの誉の動きは早かった。昭和28年に源田が航空自衛隊に入隊していたのを小耳に挟んでいた誉は、久しぶりに会ってほしいと手紙を書いたのである。
戦後も何かと旧海軍での部下たちを気にかけていた源田はこの手紙を見て喜んだ。誉はしっかりしているとはいえ、父亡き後のことはさすがに心にかかっていたからである。
誉はすぐに上京した。待ち合わせ場所は銀座千疋屋のフルーツパーラーであった。誉はいかにも部下のことを思いやる源田らしい、と微笑ましく思った。誉が待っていると源田は海軍時の習慣通り、待ち合わせの5分前にきっかりやってきた。
「おお誉!元気でやっていたか。大人になったな。」
子供のように頭をたくさん撫でられて誉は嬉しかったが、さすがに少し恥ずかしくなった。「源田司令、お久しぶりです。」
頭を下げてから着席すると、源田はニコニコと笑って話しかけた。
「誉・・・お前そんなに背丈が小さかったか?何だかかわいらしいなあ。」
「し・・・司令!からかわないでください。軍装ではないからでしょう。」
「そうだそうだ、あの詰襟を無理やり着ていたんだものなぁ。」
源田がしげしげと誉の洋服を眺める。
「花模様のワンピース・・・ね。」
「もう司令!今日は真面目なお話で参りました!」
「相変わらず誉はからかいがいがあるな。ほら、何でも好きなものを注文しなさい。イチゴのショートケーキ?それともフルーツポンチ?」
誉は源田のこういう所が大好きであった。素直にイチゴのショートケーキを注文する。
「で、今は神戸女学院で物理の先生をしているってね。」
「はい。おかげさまで理系への進学率も各段に上がり、良い結果を残すことができました。」
「誉は教官としても若いころから手慣れていたからな。女子教育は戦後の新たな力になっている。いい仕事を選んだと思う。」
「しかし・・・父が亡くなり、最後に紫電改の『誉』の図面を書き残していったのを見て、私はまた・・・」
「また?」
「空に戻りたくなりました!」
誉が思い切り良く伝えると、源田の顔が思わず綻んだ。
「誉!その気になってくれたか。何とタイミングのいい・・・奇跡のようだ。実は4月から私は航空自衛隊航空団司令の内示を受けている。お前がもし入隊したい気持ちがあるのなら、こんなに嬉しいことはない。どうだ、航空自衛隊で今度は平和のために、もうひと暴れするか?」
誉はその言葉を聴いてポロポロと涙をこぼしていた。誰よりも信頼する源田とまた空に戻れるだけでも嬉しいのに、今度は平和のためにもうひと暴れ・・・という言葉が何よりも今の誉の心には響いていた。
「泣き虫は変わらんなあ・・・。ほら、涙を拭いて、ケーキ食べなさい。」
苦笑いして源田がハンカチを差し出した。誉は押し戴いて涙を拭きながらあわててケーキを頬張ったため、今度は口の周りにクリームがついてしまった。今度はナプキンを差し出す。
「しょうがないやつだなぁ・・・」
「はい、すみません・・・嬉しくて・・・」
「ケーキもうまいもんな。」
「はい。おいしいです。」
源田が吹き出す。誉も笑顔に戻り、今度こそは自分の本当に歩きたい道を歩く、と固い決意を胸に秘めていた。
それからの誉の行動は早かった。神戸女学院に辞表を提出し、源田が誉を航空団に推薦して採用が決まるとすぐに浜松基地へと向かった。すると源田からすぐに「一日も早くジェット機の操縦資格を取得しろ」という第一命が下った。源田自身も一緒に取得するという。誉は海軍兵学校の受験時のごとく猛勉強した。しかし座学はともかく、問題は飛行訓練と感じていた。
久しぶりに浜松基地で教官とともに練習機のコックピットに乗り込む。
(ようやく、戻ってきた)
計器類の音、風防、10年前は常に身の周りにあった物だが何か新鮮に感じる。
そんな心とはうらはらに空の人にさえなれば誉の操縦技術は華やかそのものであった。得意の宙返りをすると、雲も空も拍手して出迎えているかのようであった。
高度を臆さず上げてゆくと、ふと背面を垂直に駆け上がっていく黄色のストライプ模様の紫電改を幻のように見た気がした。それは終戦直前の昭和20年8月1日に「帰還セズ」との報を受けた海軍一の撃墜王であり、新選組隊長の菅野直、その人の機であった。
(菅野・・・大尉!)
一緒に出撃すると、必ず指を2本額に当てて隣を風のように駆け抜けていった菅野。新選組に誉が召喚された当初は女に何ができる、源田サーカスと戦いは違うと罵声を浴びせたものの、誉の操縦の腕を認めてからは誰よりも信頼してくれた菅野。彼が時を超え、誉に語りかけてくる。
(誉、何も迷うな。お前の居場所は・・・ここだ!)
最後に菅野の笑顔が見えた気がした。誉は再び大きく宙返りした。それは空に散った彼への哀悼の意と、今度は平和の象徴として空に弧を描く自分自身への決意であった。
「素晴らしい!全くブランクなどなかったかのようだ!」
教官の感動する声で誉は我に返った。誉は菅野が自分のブランクへの無意識な恐れを取り除いてくれたと感じた。基地に帰還すると源田が一足先に到着していた。拍手しながら駆け寄ってくる。
「誉!さすがだ。10年間操縦桿を握っていなかったとは・・・信じられない。源田サーカスの川西誉、此処に在り、だ。」
「司令・・・ありがとうございます。」
誉は一旦呼吸を整えた後、思い切って切りだした。
「司令、空で・・・菅野大尉と・・・お会いできたような気がします。」
源田の表情が急に切なくなった。
「・・・そうか。菅野と、な。」
(オヤジ)
誉と源田には、菅野の声が聞こえたような気がした。源田は下を向いて洟をすすると、誉の肩を叩いた。
「誉、われわれはこれからだぞ!」
「はい!」
誉は拳を作ってみせた。浜松基地に広がる美しい黄昏の光のように、誉の心は晴れ晴れとしていた。
第四景

源田と誉はジェット機の操縦資格を手にすると、早速航空自衛隊のパイロット育成に取り掛かった。すると資格者は増加したが機体の事故損耗率がやや高い。戦時中のような物資不足ではもはやなく、高度経済成長に突入した中で軍隊の時のような意識を保つのは難しいかと思われたが、源田は誉とともに巡回して事故の怖さを操縦士に根気良く講義するようになった。
源田が海軍時代の訓練では飛行機を9台も壊し、いずれも欲を出し過ぎた操作からの事故と反省している話や誉が整備士も兼務していた事から事故機を元通りにするために苦労した話などをすると若い操縦士たちも少しずつ耳を傾けてくれるようになり、やがて安全意識も向上していった。二人はいかにも戦後の航空隊らしい取組みができたと喜び合った。
そして運命の昭和34年12月12日、二人は埼玉県のジョンソン基地で行われた米軍サンダーバーズの日本公演を初めて見たのであった。これはサンダーバーズ初の極東ツアーで、使用されたのはF-100Cという世界初の実用超音速戦闘機であった。
二人の中に当時の日本中の少年少女たちを憧れの的にした「源田サーカス」への想いが一瞬にして蘇った。その時の二人の表情はまるで珍しいおもちゃでも得たいたずらっ子のようであった。
「誉・・・!」
空から視線を降ろし、源田が呼びかける。誉は源田の意志が手に取るようにわかった。
「はい、やります!」
その答えにはさすがに源田も苦笑した。
「気が早いな、お前は。」
公演が終わると源田ははやる心を抑えきれぬ様子で誉を司令室へと促した。源田は黒板に大きく
「航空自衛隊アクロバットチーム設立」
と書いた。
水面下では以前からこの動きがあったものの、反対意見も根強いため一旦チームが試験的に発足したものの解散状態にあることまでは誉も知っていた。しかし、源田が今日の公演を見て自分がこの件に介入する決意を固めたのを誉は感じていた。
「アクロバット飛行はこれから航空自衛隊が将来に渡って国民から愛されるため、また隊員たちの士気向上のためにも必ず役に立つ。」
「はい!」
「俺は今からお前と二人で、飛行チームの安全をまず担保する。そのためには訓練を公的なものとし、事故があった場合殉職扱になるよう制度を改革する必要がある、ということだ。その後誉、お前はチームの要となるのだ。」
「はい!ありがとうございます。」
「そして忘れるな、このチームは平和の象徴だ。戦争の愚かさを誰よりも知っている我々がやらねばならぬ仕事なのだ。」
「はいっ!」
誉は身が引き締まる想いであった。
その顔を見ると源田はとぼけてこう言った。
「俺もそろそろ退官だし、少しはやることを残してやらんとな。」
言われてはたと気が付いた。源田もいつのまにか齢50を越えていたのである。誉は源田の退官までに新しいチームの飛行を成功させてみせる、と心に誓った。
次の日からの二人の動きは早かった。源田は関係各所に働きかけ、あっという間に訓練と制度改革の口約束を取り付けた。誉は源田が直接命じた稲田淳美三佐以外の4人のメンバーを選び、源田を含む総勢7人のチームを編成した。
仮のチーム名を浜松基地近くの川から「天竜」とし、サンダーバーズのメンバーが行っている課目構成に従い訓練を開始した。誉は稲田と比べて経験年数も力量も高かったが、誉をリーダーとするとまだ男性社会の論理が根強い航空自衛隊では風当たりが強くなりすぎる。これを源田が鑑みて稲田をリーダーとしたのを誉は理解していたので徹底して稲田を立てた。
稲田がコールサインをひっくり返して思いついたチームの正式名称「ブルーインパルス」も率先して良い名前と賛成した。稲田は源田サーカスの一員であり、海軍の華としても活躍した誉と一緒に飛行するというのは引け目を感じると周囲に漏らしていたこともあったが、誉の優しい心遣いでその気持ちは消えていった。
チームの結束も技術も高まってきた昭和35年3月4日、16課目のアクロバット飛行を浜松で第1航空団司令と空幕防衛部長宛に披露することになった。源田は飛行前、6人全員の手を握りしめて
「よろしく頼む」
と力強く見送った。
誉は源田のためにも今日の課目は全て成功させてみせる、と心に誓っていた。誉は第二編隊長機である5号機に乗り込み、ソロでバーティカルクライムロールを担当することになっていた。これは急上昇を得意とした菅野大尉に捧げる課目として、誉自らが選んだものだった。
6機は次々と飛び立つ。軍での戦闘ではないのに、また別の戦いがある、と誉は感じていた。――――――-ブルーインパルスを正式に発足させるために。
演目はチェンジオーバーターンから始まった。基地に突入した瞬間縦列が美しく傘型に変換した。決まった!見守る源田が思わずガッツポーズを取る。そのまま他機がサンライズを決めている間、誉は単機でバーティカルクライムロールの準備に取り掛かった。
(菅野大尉、どうか私を見守っていてください)
思わず操縦桿を握る手に力が籠る。サンライズが終わった瞬間、誉は急上昇を開始した。
(誉!いいぞ!)
菅野大尉の声が聞こえたような気がした。
その声に励まされるように、誉は空をぐんぐんと駆け上っていった。回転を開始する。錐揉みしながらの急上昇は気持ちがいい。菅野大尉が紫電改の風防の中からこちらを見て親指を立てているような気がした。しかしその幻に浸る間もなく、次々と課目が誉の前を過ぎ去ってゆく。
ラストはローリング・コンバット・ピッチ。4機のタイミングが見事に合った。誉は源田サーカスを初めて成功させた日よりももっと嬉しいと思った。基地に帰還すると源田が駆け寄ってきた。
「誉!」
「司令!」
思わず抱き合ってしまった。稲田も他のメンバーたちも感情が昂ったのか皆泣き出した。隊員たちが落ち着くと、第1航空団司令と空幕防衛部長が二人ともニッコリ笑いながら
「合格!」
と申し渡した。
誉は源田の退官前に間に合った、と思うと膝から崩れ落ちてしまった。稲田が肩を貸し、7人全員が笑いあう。ここにブルーインパルスの正式発足が決定したのである。
第五景

誉はその後稲田とともに技術向上に努め、源田が財界人や議員団を呼んで行う展示飛行にも積極的に参加していた。ブルーインパルスとしての特別塗装機やスモークなども装備され、源田サーカス時代とはまた違う楽しみが誉の心を満たしていた。
そんなある日、誉は航空幕僚長となった源田の司令室へと呼び出された。ドアノックして声をかける。
「川西誉、参りました。」
「誉か、入って良し。」
いつもの源田の優しい顔がそこにはあった。しかし夕日を背にしたせいか、何かいつもと違う雰囲気を誉は感じ取っていた。
「司令、御用件は何でしょうか?」
「うん。俺もあと退官まで一年となったからな、参議院議員選挙に立候補することにしたよ。」
「えっ!」
誉にはあまりに唐突な話であった。源田の口から今まで政界へ行きたいなどという想いは聴いたこともなかった。真意を理解しかねて、誉は首を傾げた。
「司令・・・司令がいなくなってしまったら、ブルーインパルスは・・・どうなってしまうのでしょうか?」
「ん?ブルーインパルスは稲田と誉に任せておけば盤石だ。老兵はただ消え去るのみ、を地で行きたかったがまだお役目が俺にはあるようだからな。」「司令!私はまだ・・・」
「そのような、とは言わせないぞ誉。お前を源田サーカス、第三四三海軍航空隊、ブルーインパルスで常に副長としてきたのは甘やかすためではない。あくまで海軍や航空自衛隊という男社会の上でお前が生きやすくするための方便だ。何度となく伝えてきたのを忘れたか。副官としての役割を果たしていても、お前の力量は常にリーダーとしてのものだ、と。」
「そんな・・・」
誉は納得がいかなかった。退官まで源田にはどうしても一緒にいてほしい、という想いの方が強かったためであった。すると源田はふと微笑んだ。誉は不思議に感じた。
「今は納得がいかなくてもいい。いずれわかる。誉、ブルーインパルスはこれからだ。」
源田は誉の肩を叩き、言葉を続けた。
「百戦錬磨のお前にできないことなど何もない。自信を持て。」
「・・・はい。」
誉は源田が科学的理由なしには行動を起こさぬ人物であるのを思い出した。今はその想いを計り知ることができなくとも、とにかく源田を信じようと思った。いつのまにか夕日は沈み、青藍の空がはるばると広がっていた。
次の日に源田が定年を前にして退官するという話は早々とブルーインパルスに伝えられた。稲田は源田の話に何か含みがあるのを誉と同様に感じ取っていたようだが、チームの中には源田がブルーインパルスを見捨てたのだと曲解するものもあった。
誉はそれを悲しく思い、何とか誤解を解こうとしたが源田はもはやそのような噂にはびくともせず淡々と日々を過ごしていたため如何ともし難かった。
やがて源田は退官し、参議院議員選挙に立候補した。第三四三海軍航空隊の隊員たちが喜んで選挙応援に駆け付けるのを見て誉も応援に行きたかったが、なぜか源田は誉には訓練に集中せよと強く断ってきた。誉は不可解な気持ちではあったが、やはり源田を信じて指示に従った。
無事源田が当選してもその指示は変わらなかった。誉は寂しく感じたが、今やブルーインパルスを稲田とともに盛り上げていくのは自分しかいない。誉は再び訓練と新たな課目習得に集中する日々を過ごしていた。
第六景

源田が退官して半年後の昭和38年7月、ブルーインパルスに朗報がもたらされた。東京オリンピック組織委員会 より1964年10月10日の東京オリンピック開会式における祝賀飛行の要請があったのである。この報せを聴くと最初は隊員全員ぽかんとしてしまった。
もちろん自衛隊としてオリンピックへの協力体制にあるのは皆知っていたが、ブルーインパルスがここまで重要な役を担うとは思っていなかったからである。さらに少し経つと正式に「開会式にて五輪のスモークを描け」というオーダーが入った。しかも原案はブルーインパルスで作成せよ、ということであった。
皆ここまで来てようやくこの話は源田の置き土産なのではないかと感づき始めた。稲田と誉で確認してみるとどうやらそれは本当で、源田はブルーインパルスで五輪を描く構想を置いていっただけではなく、議員になってからも方々にブルーインパルスのための働きかけを行っていたとのことであった。
隊員たちは源田の深い愛情に再び心酔し、早速皆で原案作りに取り組んだ。カラースモークを青・黄・黒・緑・赤の五色用意し、高度や円の大きさに至るまで細かくミーティングを重ねた。しかし実際に飛行訓練を行ってみると、誉の担当する黒だけどうしてもうまく発色しない。
誉は自分の整備士としてのプライドにかけてこの問題を解決してやると思った。訓練後も居残りして原因を追究する。するとスモーク成分のスピンドルオイルと染料の比重が黒は多色と比べてより大きいため、撹拌を直前まで続けなければならないことがわかった。
誉はこのことがわかった瞬間思わず大声で
「わかったぞ~~~~!」
と声を張り上げたため整備士どころか稲田まで駆け付けた。
「隊長!わかった!わかりました!」
誉が染料で真っ黒になった顔を涙でびしょびしょにしながら報告する。
稲田も整備士たちもこれには思わずもらい泣きした。誉の手には父龍三の遺品の三角スケールが握られ、机の上の紙は計算式だらけであった。誉は最後の力を振り絞って整備士たちに
「撹拌機を・・・」
と伝えるとそのまま倒れてしまった。
医務室へとすぐに運ばれたが睡眠不足と過労によるものと診断されたので皆ほっと胸を撫でおろした。この一件は整備士たちのやる気を奮い立たせた。早速撹拌を続けられるよう撹拌機に改造を施し、後はブルーインパルス次第で五輪は描ける、というところまで持って来られたのは何とオリンピック開会式の10日前であった。
復帰した誉を交えて何度も訓練を行ったが、なかなか美しい五輪を描けない。あっという間に10月9日となった。その日は土砂降りの雨で、翌日の予報も雨だったため隊員たちは開会式が中止となるものと思い込み、残念パーティーと称して誉以外は新橋で飲んでいた。
すると翌日は抜けるような快晴であった。稲田も含めた二日酔いの面々が蒼い顔をして入間基地へと滑り込んでくる。
「誉済まない・・・酒が抜けない・・・」
「副長、申し訳ありません・・・」
誉は隊員たちの詫びを微笑んで聴きながら、稲田に代わって号令をかけた。
「気を付け~~~!」
皆はっとした。
「皆してしまったことは仕方がない。ブルーインパルス、練習では一度も五輪は描けなかった。しかし、今の諸君は酒を飲み、心も体もリラックスした良い状態だ。いっそこのようなままよ、の精神で本番に臨んだ方が良い結果が出る、と私は信じる。皆できることは精一杯やったのだ。いざ本番!行くぞ!」
誉は日頃から稲田を立てており、今まで一度も皆に訓示を与えるといったことはなかった。しかしこの言葉は本当の意味で隊員たちを奮い立たせるものだった。
(これが・・・川西誉のリーダーとしての力量・・・)
稲田は源田が漏らす誉についての評価を覚えていた。
しかし稲田に見せる誉の顔はあくまで副長としてのものだったので、正直その言葉が本当かどうかはわかっていなかった。しかしこの土壇場での力強さ、仲間を信じる心に稲田は心底感服していた。
「よし!行くぞ!」
午後二時半、ブルーインパルスは入間基地を飛び立った。整備士たちが皆並んで見送ってくれた。湘南海岸で待機する。誉はふと源田と最後に話し合った日の言葉を想い出していた。
(百戦錬磨のお前に、できないことなど何もない。自信を持て)
一瞬目を閉じて、言葉を反芻する。
(源田司令、菅野大尉・・・そして・・・お父さん!)
稲田の号令でブルーインパルスは国立競技場へと突入した。それからわずか30秒後、青・黄・黒・緑・赤の美しい五輪が上空へと描かれた。会心の出来であった。
「成功だ!」
稲田の弾む声が無線で伝わる。誰からともなく歓喜の声が挙がった。誉はコックピット内で溢れる涙を止めることができなかった。
(ブルーインパルスは・・・平和の象徴)
自分が戦時中に日本中の少年たちを熱狂させ、戦争へと駆り立てて行った罪が今ようやく全世界に向けて洗い流されたような気がした。都内上空にスモークを引いて「凱旋」しながら誉は夢のような時を過ごしていた。
(もう、心残りはない)
海軍兵学校、源田サーカス、第三四三海軍航空隊、ブルーインパルス・・・自分の飛行機乗りとして、整備士として、そしてブルーインパルスの副長としてやりたいことは全て叶えた。
人生の日々の中で今日が最高の一日だ、と誉は感じていた。
(川西誉・・・心から幸せです。それでは・・・これにて)
誉は無線を切り、急に隊列を離れた。隊員たちが驚いているのもつかの間、誉の機はあっという間に海へと向かった。
(千本桜は・・・美しく、散りゆくのみ)
散り際にひときわ濃い鴇色に華やぐその花を想い起こしながら、誉の機はぐんぐんと高度を上げ、遥か空の彼方へと吸い込まれていった。
あなたをもっと稼げるライターへと進化させたいので、サポートをしていただけませんか?
