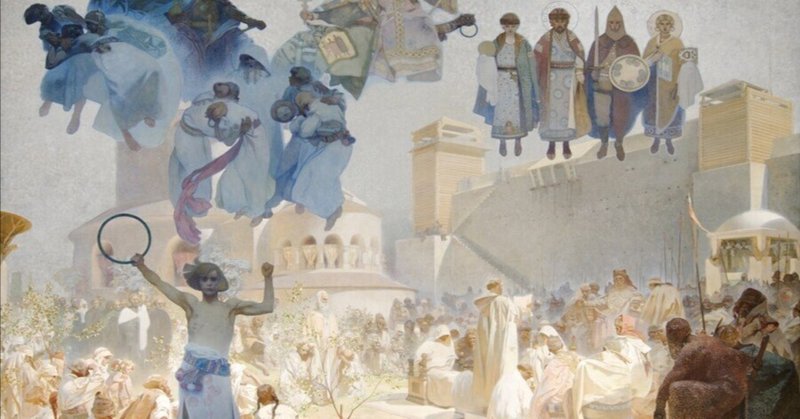
189. わたしと「名著」 【フリーペーパー】
これは去年発行された、NHKの番組「100分de名著」の、歴代番組講師陣が「名著が名著たる所以」について語った書き下ろしのエッセイ集です。
実際に書店で見掛けられた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
見開き1ページずつのエッセイですが考えさせられる話も多く、なかなかためになりました。
様々な”名著”を扱っている「100分de名著」ですから、その講師陣のジャンルも様々。エッセイの切り口も様々です。13名のエッセイの中から、わたしが特になるほど! と思った言葉をいくつかご紹介しますね。
・斎藤洋平(マルクス思想)
難解な古典を読むためには手引きが必要である。そもそもこれほど仕事に忙しくて、さまざまな娯楽に溢れている現代社会で、マルクスやヘーゲルの原著をみんなが読む必要はどこにもない。でも、私は研究者として、その面白さや大切さを少しでも伝えたい。逆に、そうした努力を哲学研究者は十分にやってこなかったのではないかという反省の念さえある。
文学でもそれ以外の書物でも、本以外の映画などでも、”名作””古典”と呼ばれるもののほとんどに触れてきていないことは、わたしのコンプレックスです。
教養として読みたいし、どんなことが書かれているのかも気になる。でもどうしても後回しにしてしまう……という怠惰な自分を甘やかしたまま日々を過ごしてきてしまった。
でもこの一説にはそういうわたしの恥ずかしさを許容してくれる優しさがあるとともに、分かりやすく解説して自分の好きなものを知ってもらいたい、という著者のオタク気質が現れていて、何だか親近感が湧いたのでした。
目の前に山と積まれた、まだその世界に踏み入れていないけれど面白いかもしれないものたち。
とっかかりがあるのは非常にありがたいですし、せっかくとっかかりを作ってくれているのだから、それを足がかりに今度こそ名作の世界へ飛び込みたいものです。
・河合隼雄(臨床心理学)
名著と言われるものは、長い時間を経ても残ってきただけの価値がある。(中略)
名著は一つの世界を持っていて、それを本当に知ることは世界全体を知ることにつながる。世界はいくら多くの情報を集めてもわからない。
本の数だけ世界がある。
その本が”名著”と呼ばれ長く人々に読み継がれてきたのなら、普遍的な何かを持っていると言うこと。
普遍的な何かは世界の真理の一片を表していて、本を理解することは即ち世界の一端を理解することだ。
そういうことかなと解釈しました。
世界は、心は存在するのか、死んだらどこへ行くのか、など身近な疑問でも分からないことだらけです。本は疑問の全てに答えてくれるわけではないけれど、新しい知識を授けてくれたり、読むことで世界の捉え方が変わったりもします。
読書は世界を知り向き合うための、一つの手段。そういう上質な読書をしていきたいと思いました。
・西研(哲学)
人類の精神の発展が描かれるのだが、その内実は、人は他者や社会にどんな態度をとればよいか、の試行錯誤の歴史
(ヘーゲル「精神の現象学」について)
人間は一人では生きられないから、他者との関係性がとても重要ですよね。
言われてみれば、人間が日頃考えていることの半分以上は”他者とどう関係していくか”な気がしますし(社会的な日常を送っている人であれば)、他者との関わりを考えるからこそ対外的に思考が発展していくような気がします。
誰しも周りの人全員と良好な関係なんて築けないし、先人たちがどんな試行錯誤をしてきたのかを知るのは自分の振る舞い方を考える上でも参考になりそうです。
先程の斎藤洋平さんの言葉のところでも少し触れたように、ヘーゲル気になるけど難しそう…と思ってきましたが、この言葉で俄然読みたくなってきました。
・武田砂鉄(ライター)
どんな本でも付箋を用意してあちこちに貼りながら読んでいる。本棚を眺め、久しぶりに引っこ抜いた本にも付箋がついている。フレーズが刺さったのかもしれないし、論理展開に頷いたのかもしれない。付箋をつけた箇所を開いてみると、その半数近くで、つけた意味が読み取れない。このフレーズ、そんなに響かないし、論理展開だって平凡だ。でも、その時は、間違いなくその箇所に心が動いたのだ。
これはもう共感しかないです。
わたしは本に付箋は貼らない派ですが、今度noteに書いたり日記に記しておこうと思って書き留めていたページを、いざ読み返してみると何でそのページを選んだのか全く分からない……そんなことは日常茶飯事です。
メモした時と読み返したところでは”わたし”は別の”わたし”になっているのだから、その精神性が理解できなくても致し方のないところ。
逆に最初は何とも思っていなかった言葉に心動かされることもあります。
ああそういうことって皆あることなんだな、と嬉しい気持ちになりました。
・岸見一郎(哲学)
速読は名著には馴染まない。
なるほど滋味深いのが名著です。
さーっと目で追っていく速読では味わいきれないのは当たり前です。
時短や効率のもてはやされることも多い時代ですが、長い時を渡ってきた本に敬意を持って、じっくり向き合いたいものです。
名のある方、普段専門的な研究をされている方などが執筆されていますが、平易な文章でとても読みやすかったです。
あなたも何か心に響く言葉や考え方に出会えるかもしれません。
先日、池袋のジュンク堂ではまだ配布されていたので、お見掛けの際はぜひ手に取ってみてくださいね。
最後まで読んで頂きありがとうございます。サポートは本代や映画代の足しにさせて頂きます。気に入って頂けましたらよろしくお願いします◎
