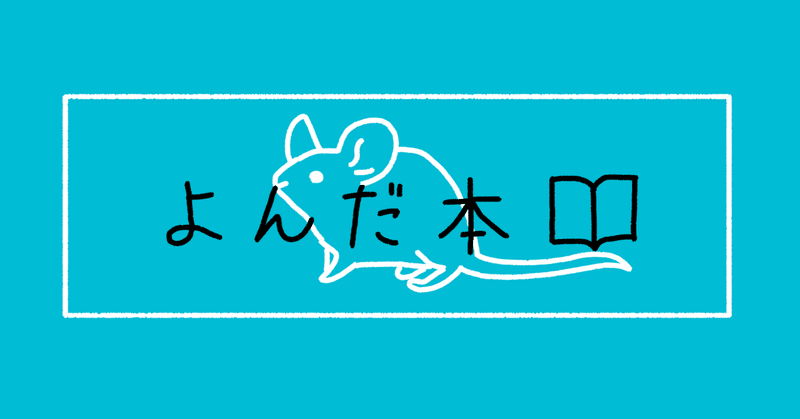
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』を読んだ
私は働いている。日々の生活のため、本を買うため、家に生活費を入れるため、日常の潤いのために、働いている。もはやそれらが何のためにあるのかわからないまま、働いている。あくせく働いている。日々の生活を続ける意味は? 働かず毎日だらだらと過ごしてもいいのでは? 働かなければ日常の潤いも必要なくなるのでは? そう考え始めると人生を終わらせるしかなくなるのでその辺りにして、「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」問題である。
本を読む人々が必ずぶつかる疑問だが、この新書の筆者はどう結論を導き出したのだろう。
読んでいくと、産業革命以降の日本の読書文化の概要がわかりやすくまとめられている。忙しく働いた工業関連の人々は農業従事者よりもかなり長く働いていたり、武士の「立身」と商人の「出世」、二つの言葉が当時合流して武士も商人もない「立身出世」という言葉になったり、勉強さえすれば立身出世できると説かれたシンプルな人生観だったり、そういう初期の考え方から流れていき、人々は忙しい中でも本を読むようになり、最終的には電車の中で文庫本を読みふけるサラリーマン像となる。
私はこの本を読んでいて、円本ブームで見栄えのいい全集を買った大正時代の人々や、自分に重ね合わせて司馬遼太郎を読みふけった昭和のサラリーマン、本を読むことを勉強とした昭和初期以前の人々など、案外現代の日本人と同じで、昔の人もそんなに本を読むのは好きではなかったのでは?と感じた。見栄や立身出世、自信を高めるための読書というのは、本が好きでやる読書とは違うような気がする。
円本を買った世代の子供世代が円本を読みふけったりするのは好きで読んでいるのだろうなと思えるし、その世代が読書の習慣を身に着けたのだろうけれど、本当に本が好きだから読む人というのは、昔から人口的にもかなり少数派なのかもしれない。
結局は、娯楽がないから本が読まれていただけでは……。
とはいえ、本は様々な読まれ方をするものである。私のように好きだから読むことこそが本当の読書と言っていては何も進まないし話が捗らない。
結局、皆が本を読まなくなったのは「長時間労働で疲れているから」だという結論に近いようだ。筆者は自己実現が昔と比べて仕事外ではなく仕事になってしまった現代のことや、新自由主義社会の社会構造にも触れる。でも、結局は働きすぎて仕事や生活が頭の中を占めていて心に余裕がないというのが結論に見える。疲れているし忙しいから手っ取り早く情報がほしいのに、本には情報だけでなくノイズが多すぎるということらしい。
働きすぎか……。確かに私も働き始めてから本を読めないし小説も書けない。読みたい気持ちばかりで気が焦って、積読は二百五十冊を超える。小説は構想ばかりが溜まっていき、書けない間に社会的に合わないし自分の精神レベルにも合わないものになっていく。働くことは、真に文化的な生活から離れることのように思う。ローマ人のような生活を望むが、それは奴隷あっての生活であり、今となっては倫理的に問題があるし(とはいえローマでの奴隷の暮らしは我々が奴隷という言葉から想像しがちなものよりずっとまともなもののようである)、我々の社会にあるAIやロボットはそれとは少し違う働きをしているようだ。
筆者は、「半身社会」を説くが、それは短時間労働で余裕をもって過ごせる文化的な社会のことだ。とても理想的だが、今の社会からはまだまだ遠い世界のようにも感じる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
