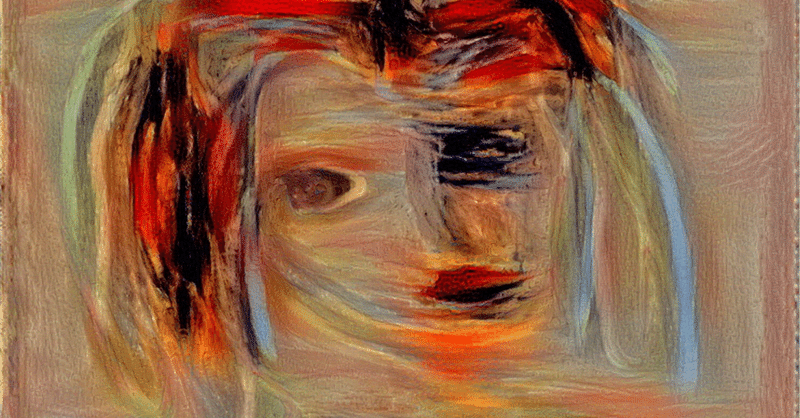
小説:初恋×初恋(その14)
第十一章 四十五階
「次に久望子に会ったのは、それから一年後だった。僕は細々と連絡を取っていた。話す内容はたいしたものではなかった。何処にでもある世間話だ。久望子は生活の拠点を海外から日本に移した。景気が下火となり、海外に投資する日本企業や個人投資家が激減したせいだ。久望子は段々と活躍の場を失いつつあった。でも当時の僕はその事について詳しく知らなかった。自分の生活が手一杯で、久望子の立場にまで心配が及ばなかった。だから仕事を辞めて地元に帰る事にしたと久望子から聞いた時も、会う機会が増えると思っただけだった。それからしばらくして久望子は本当に地元に帰ってしまった。そしてアパートを借りて一人暮らしを始めた。仕事はしていないようだった。彼女のこれまでの年収からすれば、つつましい暮らしをすれば何年間か食べて行けるだけの貯蓄はあったはずだ。実家が近くにあり、久望子の両親が頻繁に行き来し始めた。電話すると、たまに母親が電話に出たりした。僕は高校生みたいにどぎまぎして、慌てて偽名を使い、間違い電話のふりをして電話を切った。そんな折、僕は一人で帰省することにした。妻は僕の実家に帰りたがらなかったし、何より久望子が僕に会いたいと言ったからだ。僕は一人で車を運転して実家に向かった。今日、僕らが通ってきたのと同じ道を使って」そう言い終わると相川さんは私を見た。
「その事と今日のドライブコースは関係があるの?」と私は聞いた。相川さんは私の手の下にあった手を引いて自分の膝の上に置いた。私の手だけがテーブルの上で置き去りにされた。冷たく硬質な感触が私の掌に伝わった。急に孤独になった気がした。世界の端に一人ぼっちで置き去りにされたような寂しさ。相川さんは小さく微笑むと、今度は私の手の上に相川さんの手を重ねた。
「君の人生を巻き込んで申し訳ないと思っている。でも明日で終わる。もう少しの辛抱だ」と言った。
「これは私が決断した事よ。一晩、考える時間を与えてもらった。そして選んで来たの。こうすることが私にも必要だと感じたから。確かにお金も魅力だったけど、それ以上の何かがあったの。だから来たの。気にしないで」と私は言った。相川さんは私の手を離し再び私の手を一人にして話し始めた。
「僕は横浜で彼女と手を繋いで以来、心のどこかで再び、久望子を女として求めるようになっていた。普段は生活に忙殺されていても、ふと首をもたげるんだ。そしてそれ以上に、彼女の中にある特別な何かを求めていた。僕だけが理解出来る、彼女から発する特別な何か。それを再び久望子に会って確かめたかった。もしも彼女の中に僕の為の特別な場所があるのなら、それを求めたかった。そうする事がどういう結果をもたらすのか解っていた。僕がその何かを見つけてそれを求めた時に何を失うのかも。
僕は彼女のアパートの近くまで車で迎えに行った。彼女の指定した場所はすぐにわかった。午前十時。約束の時間よりも早くその場所に着いた。その道の先に彼女の住むアパートがあった。でもあえて、そこには向かわなかった。この場所を指定したという事は彼女なりの配慮なり事情があるのだろうと思った。何より彼女の両親と鉢合わせは避けたかった。遠くに彼女の姿が見えた。久望子は僕を確認すると小走りになった。濃密な時間が始まろうとしていた。
久しぶりに見る久望子は美しかった。彼女の美しさに魅かれて好きになったけど、その時は眩しいほど美しかった。そしてその眩しさの理由がその時には解らないでいた。僕は久望子に言われるまま車を運転した。どうやら彼女には目的地があるらしかった。僕達は海岸線を南に向かって走った。そしてここに来た。このホテルに。今から時間をさかのぼれば、このホテルの一階のロビーに僕達が居るはずだ。まだ幾分若い僕達が」
相川さんはそう言い終わると自分の頬を手でなぞった。若さと時間の流れを確かめるみたいに。でも本当に相川さんの心は過去をさかのぼり、一階のロビーに行ってしまったのかもしれないと思った。
「彼女が一階のラウンジで何を注文したのか思い出せない。久望子がコーヒー党なのか紅茶党なのか、僕は知らない。そういったものは生活の中にあるものだ。僕には彼女との歴史は長くても生活は無かった。一日一緒に居ても、一晩過ごした事はなかった。彼女の中にあるさりげない部分を僕は何も知らなかった。国交のない国の白地図みたいにぽっかりと空いていた。彼女が何を注文したのか思い出せない理由はそういう事だけど、でもそれはとても重要な事だったと思う。僕は長い間彼女と向き合っては来たけど、彼女が何者で何を考えて生きていたのか、何を大切にしていたのか、そういう事が抜け落ちていたんだ。
久望子は僕に突然、来月ここで結婚をするの、と言った。沈黙が続いた。彼女は僕の言葉を待っているようだった。久望子のマスカラは紫に塗られていた。その色が彼女の美しさを手伝っていたのかもしれない。でもそれだけではなかった。彼女は女になっていた。僕の知らない場所で、僕の知らない時間に。ある瞬間、彼女は決断し、そうなったんだ。それで?と僕は言った。それ以上、僕は言葉を持たなかった。こういう時に何と言えばいいのか、何と言うべきなのか、わからなかった。でも次は久望子の番だった。たった一言でも、投げるべきボールは返した。それがどんなに間抜けな台詞でも。
相川君には、ちゃんと伝えておきたかったの、と久望子は言った。僕の事を相川君と呼ぶのは、久望子だけだった。妻は僕を下の名前で呼んでいたし、同僚は皆、相川さんだった。上司でさえ僕の事を相川さんと呼んだ。相川君と言うその響きが僕は好きだった。それは彼女だけに許された特別な称号みたいに聞こえた。僕はその時、そんなどうでも良い事を考えていた。でも事態は深刻だった。水の中は安全だけど、いつまでも息は続かなかった。いつから?と僕は聞いた。久望子は順を追って話し始めた。両親に見合いを勧められていた事。それをずっと断り続けていたこと。不景気になり会社に居づらくなった事。地元に帰ろうと考える様になった事。実際に見合いをした時の事。最初は乗り気ではなく、随分しつこく誘われた事。でも、と久望子は言った。そのうちね、良い人なのかなと思えるようになったの。私がどんなにつれなくしても、次の日にはまた誘ってくるの。私の為に頑張ってくれるの。倒れても倒れても。そのうちね、もっと頑張って、思っている自分が居たの。ちゃんと私を見てって思った。本当の私を、と彼女は言った。僕は、鼻で笑いたかった。そんなの理由にならない。久望子を見たら、久望子の美しさを見たら、大抵の男はそうなる。何も特別な事ではないんだ、と僕は久望子に言いたかった。でも言わなかった。もう何を言っても遅いと感じたんだ。もう手遅れで、次の段階に進んでいるんだと。歩未の時と同じように。そしてそれはその通りだった。久望子は彼を受け入れた自分を説明し続けた。でもそんなことはどうだって良かった。記憶には残らなかったし、残すつもりもなかった。久望子が他の男と結婚をする。誰かのものになる。その理由を聞くのは結果のわかった試合の途中経過を細かく聞くようなものだ。何の興味もない。もちろん僕は黙って聞いていた。聞いているふりをしていた。その間僕は何を考えていたんだろう?不思議と嫉妬心は沸かなかった。彼女を奪われた悔しさも感じなかった。ただ僕が思ったのは彼女が幸せになれるのだろうかという事だった。久望子が話し終わると僕はその男の年齢と職業を聞いた。一回り年上で医者だった。僕は納得した。彼女を幸せにするべき男だと思った。敵わないとか、そんな気持ちではなかった。ただその時僕を支配したのは、どうしようもなく深い諦めだったんだ。
久望子は一通り話すと、ホッとしたようだった。今まで黙っていたことを僕に詫びた。僕は首を横に振った。他に話すべき言葉が見当たらなかった。ラウンジを出ると、僕達は同じフロアにある土産物屋をみて回った。宮崎の民芸品や小物が置いてあった。観光客相手のホテルにありがちな空間だ。久望子は、地鶏のコーナーで立ち止まり、何品かを手に取り、レジに向かった。そして思い出したように振り返り、彼が好物なのよと言った。たまに泊りに来るの。その時の為に、と。僕はその台詞を聞いて、改めて実感した。彼女が他の男のものになった事を」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
