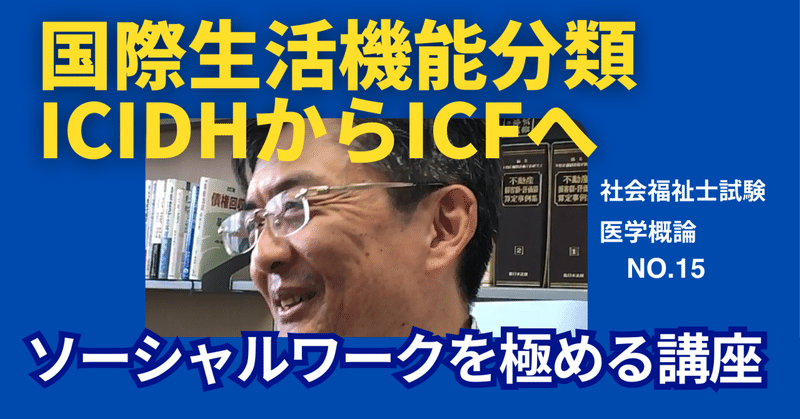
医学概論NO.15 ソーシャルワークを極める講座 国際生活機能分類(ICF)の基本的考え方と概要
今回の内容は、YouTubeで視聴できます。
今回のテーマは、本試験において、大頻出事項です。
1.国際障害分類(ICIDH)から国際生活機能分類(ICF)への変遷
(1)国際障害分類(ICIDH)
国際障害分類(ICIDH)の前の段階から説明します。
国際障害分類が示される前は、定義だけが示されていました。
すなわち、1975年(昭和50年)に国際連合で採択された「障害者の権利に関する宣言」において、障害者の定義が示されました。
定義としては、「先天的か否かにかかわらず、身体的ないし精神的な能力における損傷の結果として、通常の個人的生活と社会的生活の両方かもしくは一方の必要を満たすことが、自分自身で完全にまたは部分的にできない者」としていました。
そして、国連は、この障害者の定義を示した上で、諸権利が、障害の種類や程度にかかわりがないこと、さらに、障害者も他の人々と同じ基本的権利をもっていること、を明記しました。
次に、WHOが、1980年に、国際障害分類(ICIDH International Classification of Impairments、Disabilities and Handicaps クラシフィケーションは分類で、インペアメンツは、機能・形態障害を言います。また、ディスアビリティーズは、能力障害のことです。さらに、ハンディキャップは、社会的不利という意味になります。)を発表しております。
これは、障害の構造モデル概念をはじめて体系的に整理したものになります。
要するに、障害に関する国際的な障害分類を発表し、これを用いることになったわけです。
ここにあるWHOというのは、世界保健機関のことです。
WHOは、国際連合の専門機関の一つになります。
WHOは、人間の健康を基本的人権の一つと捉えて、その達成を目的として設立された機関になります。
このICIDHは、これまたWHOが1980年に発表した「国際疾病分類(ICD) これは、世界中の疾病、傷害および死因の統計分類になります。」の補助として発表されたものになります。
そして、ICIDHは、病気やその他の健康状態を病因論的な枠組みに立って分類したものになります。いわゆる「医学モデル」による分類です。
ここにいう病因論とは、すべての疾病(病気)には原因があり、疾病の原因になるものを病因と言って、この病因を究明していくという理論を言います。
第27回第2問の選択肢
国際生活機能分類 (ICF) の基本的考え方と概要に関する問題で、「ICFは、 病気やその他の健康状態を病因論的な枠組みに立って分類したものである。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、誤りです。
選択肢には、病因論的な枠組みとありますが、ここにいう病因論というは、すべての疾病(病気)には原因があり、疾病の原因になるものを病因と言って、この病因を究明する学問を病因論と言います。そして、WHOによって、この病因論に立って分類したされたものが、国際障害分類(ICIDH)になります。
国際障害分類(ICIDH)の障害の構造モデルは、3階層(3つのレベル)からなっています。

まず、一次的障害として、人は病気や事故に遭うと機能障害を起こします。これは、生物学的・医学的レベルで捉えた障害になります。
例えば、手が動かない。足が動かない。
二次的障害として、機能障害を起こすと、実際の活動が制限され、能力障害を起こします。
これは、個人の生活レベルで捉えた障害になります。
例えば、鉛筆を持って字が書けない。歩けない。
三次的障害として、能力障害を起こすと、偏見、差別を受けるなどにより社会的能力が果たせなくなるため、社会的不利(ハンディキャップ)に陥ります。これは、社会的レベルで捉えた障害になります。
例えば、能力障害で偏見や差別を受けて、やりがいを見つけることができず、不幸になるとか。
DISEASE or DISORDER(疾患・変調)
↓
IMPAIRMENT(機能・形態障害)
↓
DISABILITY(能力障害)
↓
HANDICAP(社会的不利)
このように、病気(疾患・変調)から社会的不利に至る過程を直線的にとらえたものになります。
第28回第3問の選択肢
国際生活機能分類 (ICF) に関する問題で、「障害を機能障害、 能力障害、 社会的不利に分類したものである。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、誤りです。
障害を機能障害、 能力障害、 社会的不利に分類したものは、ICFではなく、ICIDHになります。
ICFでは、 用語を中立的なものに変更し、生活機能全体を「心身機能・構造」、 「活動」、 「参加」というような用語を用いて、ICIDHのように、機能障害、能力障害、社会的不利のようなネガティブな用語を用いるのをやめ、中立的に変更しています。
第27回第2問の選択肢
国際生活機能分類 (ICF) の基本的考え方と概要に関する問題で、「機能障害とは、 個人が何らかの生活・人生場面にかかわるときに経験する難しさのことである。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、誤りです。
機能障害というのは、ICFではなく、ICIDHに出てくる障害分類の一つになります。そして、機能障害とは、一次的障害として、人は病気や事故に遭うと機能障害を起こすという生物学的・医学的レベルで捉えた障害になります。
選択肢に出てくる「個人が何らかの生活・人生場面にかかわるときに経験する難しさ」は、ICFに出てくる構成要素の一つである参加の制約の定義になります。
(2)ICIDHに対する批判
ICIDHに対する批判としては、まず、病気から社会的不利に至る過程を直線的にとらえたことの欠陥が挙げられます。
つまり、「疾患・変調」、「機能障害」を過大視し、それによって「活動」も「参加」も決まってしまうかのように考えることの欠点です。
例えば、二人の障害者がいたとして、その機能障害が同一のレベルであっても、環境(その人が生活する国や地域の福祉施策の水準、街づくり、交通機関、建物、居住環境等)によって2人の能力障害(歩けないなど)は異なるではないか。
また、能力障害を起こすと、必ず社会的不利になるのか?それは本当ですか?そうでない人が多数いるのも事実ではないですか?
例えば、個人因子として、もともとお金持ちの家に生まれた人は、偏見とか、差別も受けにくく社会的不利にならないということもあります。
また、ICIDHに対する批判の2つ目としては、障害者の抱える問題の解決を障害者個人に求めていることから、障害者と社会環境面との関連を無視しているのではないか。
さらに、ICIDHに対する批判の3つ目としては、もっと違う要素があるのではないか?
例えば、背景因子としての環境因子や個人因子があるのではないかと。
(3)ICFの採択
このような批判を受けて、WHOでは、2001年にICF(International Classification of Functioning、 Disabilty and Health : 以下、ICFという。 人間の生活機能と障害状態と健康の国際分類 )という国際生活機能分類を採択しました。
その内容は、「その人が暮らしている社会がどういう社会か。」を重視します。
環境として、例えば、目が見えず杖をついている障害者がいたとして、このような障害者に対して、「邪魔だ、どけ!」という社会なのか、それとも、視覚障害者に対し、「こちらですよ。」などと言って、手を差し伸べてくれる社会なのか。
ICFは、このような環境を重視します。
国際生活機能分類 ICF

ICFでは、ICIDHのような基準の中に、環境因子と個人因子を入れました。
従来のように障害になれば社会的不利になるという一方通行的な考え方ではなくなっています。このような視点で社会福祉を考えていく必要があると宣言したわけです。
そして、この宣言の背景には、ノーマライゼーションの思想(つまり、「障害をもつ人も、持たない人も、地域の中で生きる社会こそ当たり前の社会である」という思想)。それから、エンパワメント(本来持っている潜在能力を引き出すという思想)の影響がありました。
第28回第3問の選択肢
国際生活機能分類 (ICF) に関する問題で、「ICFは、世界保健機関 (WHO) により採択され、国際的に用いられている。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、正しいです。
2.ICFの内容
ICIDHモデルでは、その中に「環境的要素が含まれていないために個人の中で完結している」とか、「構成要素間の関連が十分でない」等の批判がありました。
そこで、ICIDHモデルからの脱却を図るべく、ICFモデルでは、「社会モデル(障害を個人の特性ではなく、主として社会によって作られた問題とみなすというモデル)」、「生活モデル(クライエントを治療の対象とするのではなく、環境との交互作用関係のなかに生きる生活主体者として捉え、援助者は個人と環境との接触面に介入するという点に特徴があるモデルです。)」として、人間の生活機能の低下というものを環境も含めた広い視野でとらえようとしたわけです。
ICFの障害モデルの構成内容は、この図の通りです。

人間の生活機能と障害について、「心身機能・身体構造」「活動」「参加」という3つの次元の構成要素(枠組み)で体系化します。そして、それらは、「環境因子」と「個人因子」という背景因子によって相互に変化し合い、日々の健康状態によっても「活動」が変化するというものになります。
そして、ICFの分類のもとでの障害というのは、「心身機能・身体構造」「活動」「参加」の裏返しで、「機能障害、活動の制約、参加の制約」を指すことになります。
なので、「機能障害、活動の制約、参加の制約」のそれぞれの部分において、環境因子などを考慮して、ノーマライゼーション社会、つまり「障害をもつ人も、持たない人も、地域の中で生きる社会こそ当たり前の社会である」という考え方の社会を作っていこうではないか、というものになります。
ICFの優れているところは、障害という問題を旧来の「医学モデル」で考えて、個人に帰結するのではなく、障害者を取り巻く環境がいかにあるのか、その社会のあり様(ありよう)が重要であることを示してくれたということです。
要するに、ICFには、「障害」を決して否定的なものではなく、ポジティブに捉えようとする21世紀版の熱き人間観が込められているわけです。
そして、今や、その社会の考え方がいかにあるのかによって障害は軽減できるんだ、という「社会モデル」の考え方が、現在の国内外における障害の捉え方の基本になったわけです。
では、ICFの構成要素や背景因子等の定義を確認しておきます。

まず、「健康状態」とは、疾病や体の変調、怪我、妊娠、高齢、ストレスなど様々なものを含む広い概念になります。生活機能低下を起こす原因のひとつとして「健康状態」があるということです。
これは、ICIDHでは疾患・外傷に限られていたのとは異なり、ICFではそれらに加えて妊娠・加齢・ストレス状態その他いろいろなものを含む広い概念となっています。妊娠や加齢は「異常」ではなく、妊娠はむしろ喜ばしいことでありますが、これらは「生活機能」にいろいろな問題を起こしうるので、健康状態に含めるわけです。このことからも、ICFが、障害のある人などの特定の人々にのみ関係する分類なのではなく、「すべての人に関する分類」になったことが理解できると思います。
それから、生活機能の一つである「心身機能・身体構造」は、心身の働きのことです。
つまり、心身機能とは、例えば、手足の動き、精神の働き、視覚・聴覚、内臓の働きなど。
また、身体構造とは、手足の一部、心臓の一部(弁など)などの、体の部分のことを指します。
また、生活機能の一つである「活動」とは、課題や行為の個人による遂行のこと。つまり、行動を指します。
これは、あらゆる生活行為を含むものであります。
調理・掃除などの家事行為・職業上の行為・余暇活動(趣味やスポーツなど)に必要な行為・趣味・社会生活上必要な行為がすべて含まれます。
また、生活機能の一つである「参加」とは、生活・人生場面への関わりのことです。
つまり、家庭や社会に関与し、そこで役割を果たすことです。
なお、機能障害がなくとも、活動・参加は制約されうるという点も押さえておいてください。
例えば、精神疾患があった者がいたとして、その者は、既に精神疾患から回復し、機能障害はない。しかし、周囲の偏見(環境因子)によって就職できない、つまり、参加制約が生じているとか。
そして、これらの「活動」と「参加」は、能力レベルと実行状況レベルの2つで評価されます。
ここでの能力レベルの評価とは、ある課題や行為を遂行する個人の能力を表すものになります。要するに、「能力的に」できる行動や参加になります。
また、実行状況の評価とは、個人が日常生活のなかで特別な努力なしに行っている活動や参加です。
要するに、実際にしている行動や参加を表します。
例えば、あるADL(日常生活動作)が、リハビリテ-ションの訓練時にはできるけれども、自宅の実生活では実行していないということが結構あります。このような状態は、本来は能力的にはできるはずなのに、クライエントの意欲がないために、結果として、「できない」と扱われることが多かったりします。しかし、本当にそれでよいのか。
実は、ADLには、「できるADL」、即ち、評価・訓練時の能力と、「しているADL」、すなわち、実生活で実行している状況、この2つのレベルがあるんだと。むしろこの2つにくい違いがあって当然ではないかとも言えます。
この差の原因として考えられる要因には、いろいろとあると思いますが、大事なのは、クライエントの生活を重視する考え方をする場合には、能力的に「できるADL」よりも、実際に「しているADL」を重視すべきこと、これが大事になります。
念のため、「できるADL」と「しているADL」の差を生む諸条件にも触れておきます。
まず、環境条件です。
模擬的な訓練場面ではやりやすいんだけれども、実際の生活の場である自宅・社会では物的・人的な様々な障害が多いということです。
また、クライエントの心理的要素というのもあると思います。
すなわち、自立欲求と依存欲求とのバランスの問題です。
以上のような事情で、「活動」と「参加」は、能力と実行状況との2つで評価されることになります。
それから、背景因子である環境因子や個人因子にも触れておきます。
環境因子とは、人々が生活し、人生を送っている物的な環境や社会的環境、人々の社会的な態度による環境を構成する因子を指します。
例えば、物的な環境の例としては、点字ブロックがあるかとか。
そして、環境因子は、促進因子と阻害因子で評価されます。
促進因子とは、個々の人の生活機能の発揮を促すものを言います。
阻害因子とは、個々の人の生活機能の発揮を阻害するものを言います。
一方、個人因子は、その人の個性のことになります。
ここに個性とは、年齢、性別、民族、生活歴、価値観、ライフスタイル、興味、関心などが含まれます。
第25回第4問の選択肢
国際生活機能分類 (ICF) に関する問題で、「ICFは、健常者も障害者も区別なく、個別性はあっても「健康状態」という一つの概念のもとにとらえられているという考え方をしている。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、その通りです。
ICFは、「障害」の反対概念としての「生活機能」に着目した分類になりますが、「障害」の分類ではなく、生きることそのものである全体的な「健康状態」を把握しようとしています。ですから、ICFは、障害者だけに関するものではなく、全ての人に関する分類だということになります。要するに、ICFは、ICIDHとは異なり、人間の生活機能を「心身機能・身体構造」、「活動」、「参加」の3つに分類したものになります。そして、これらが障害された状態は、それぞれ「機能障害」、「活動制限」、「参加制限」になります。
第35回問題2
国際生活機能分類(ICF)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 対象は障害のある人に限定されている。
2 「社会的不利」はICFの構成要素の一つである。
3 「活動」とは、生活・人生場面への関りのことである。
4 仕事上の仲間は「環境因子」の一つである。
5 その人の住居は「個人因子」の一つである。
解説
選択肢1は、誤りです。
ICFの対象は、障害者はもとより、全国民を対象としています。生活機能上の問題は誰にでも起りうるものだからです。ICFは、全国民の保健・医療・福祉サービス、社会システムや技術のあり方の方向性を示したものになります。要するに、ICFは、健常者も障害者も区別なく、「健康状態」(健康状態とは、疾病や体の変調、怪我、妊娠、高齢、ストレスなど様々なものを含む広い概念になります。)という一つの概念のもとにとらえ、生活機能の分類をするという考え方をしています。例えば、障害者ではなくても、健常者で風邪をひいたりしただけでも、その方は健康が脅かされているわけです。その場合には、活動制限や参加制限があったりするわけです。ですから、ICFは、障害者だけではなく、健常者もその対象にしているわけです。よって、障害者に限られるとする選択肢は誤りになります。
同じような問題が、第28回第3問でも出題されています。
選択肢2は、誤りです。
社会的不利は、ICIDHの構成要素の1つになります。
選択肢3は、誤りです。
生活・人生場面への関りは、参加です。
活動とは、個人によって課題や行為を遂行することです。
選択肢4は、正しいです。
環境因子は、生活するうえでの物理的・社会的な環境を指します。仲間は環境因子に該当します。
選択肢5は、誤りです。
その人の住居は、環境因子です。
個人因子は、現在までの経験や教育など個人によるものをいいます。
第36回問題2
事例を読んで、国際生活機能分類(ICF)のモデルに基づく記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。
[事例]
Aさん(78 歳、男性)は脳梗塞を発症し左片麻痺(かたまひ)となった。 室内は手すりを伝って歩いている。外出時は車いすが必要で、近隣に住む長女が車いすを押して買物に出かけている。週1回のデイサービスでのレクリエーションに参加するのを楽しみにしている。
1 年齢、性別は「心身機能」に分類される。
2 左片麻痺は「個人因子」に分類される。
3 手すりに伝って歩くことは「活動」に分類される。
4 近隣に長女が住んでいるのは 「参加」に分類される。
5 デイサービスの利用は「環境因子」に分類される。
解説

選択肢1は、✖
年齢・性別は、個人因子に該当します。
選択肢2は、✖
左片麻痺は、機能障害に該当します。機能障害の典型例は、麻痺です。
選択肢3は、〇
歩くことは、生活機能の活動に該当します。
選択肢4は、✖
家族の存在は、環境因子に該当します。
選択肢5は、✖
デイサービスの利用は、デイサービスをやっている施設でサービスを受けるという生活場面の関わりである参加に該当します。
第31回第3問の選択肢
ICFに関する問題で、「生活機能とは、心身機能、身体構造及び活動の三つから構成される。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、誤りです。
生活機能は、ICFの中心概念になりますが、生活機能を「心身機能・身体構造」「活動」「参加」という3つの次元の構成要素(枠組み)で体系化しています。なお、ここで、選択肢のように、心身機能と身体構造を2つとカウントすると、活動、参加で、4つで構成されていることになります。
いずれにせよ、この選択肢では、参加が入っていませんので、誤りになります。
第28回第3問の選択肢
国際生活機能分類(ICF)に関する問題で、「健康状況とは、 課題や行為の個人による遂行のことである。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、誤りです。
健康状況というのは、ICFでいう、「健康状態」のことであると思いますが、健康状態とは、疾病や体の変調、怪我、妊娠、高齢、ストレスなど様々なものを含む広い概念になります。選択肢に出てくる、課題や行為の個人による遂行は、ICFでいう、「活動」を意味します。よって、この選択肢は誤りになります。
第27回第2問の選択肢
国際生活機能分類 (ICF) の基本的考え方と概要に関する問題で、「参加とは、 生活・人生場面へのかかわりのことである。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、正しいです。
第31回第3問の選択肢
国際生活機能分類 (ICF) に関する問題で、「活動は、能力と実行状況で評価される。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、正しいです。
活動は、能力と実行状況に分けて評価されます。
モデル図の真ん中の活動の部分を見て、確認してください。
第31回第3問の選択肢
国際生活機能分類 (ICF)に関する問題で、「個人因子には、促進因子と阻害因子がある。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、誤りです。
個人因子ではなく、環境因子です。
モデル図の左下の部分を見て確認してください。
これを見ると、環境因子のところに、促進因子と阻害因子が記載されています。
環境因子は、促進因子と阻害因子で評価されます。ここでいう促進因子とは、個々の人の生活機能の発揮を促すものを言い、阻害因子は、個々の人の生活機能の発揮を阻害するものを言います。
第31回第3問の選択肢
国際生活機能分類 (ICF)に関する問題で、「活動とは、生活や人生場面への関りのことである。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、誤りです。
活動とは、課題や行為の個人による遂行を指します。
生活や人生場面への関わりは、参加と定義されています。
第31回第3問の選択肢
国際生活機能分類 (ICF)に関する問題で、「参加制約とは、個人が活動を行うときに生じる難しさのことである。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、誤りです。
個人が活動を行うときに生じる難しさのことを活動制限と言います。
参加制約とは、個人が何らかの生活・人生場面に関わるときに経験する難しさを指します。
第27回第2問の選択肢
国際生活機能分類 (ICF) の基本的考え方と概要に関する問題で、「生活機能と障害の構成要素は、 環境因子と個人因子である。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、誤りです。
ICFにおける、生活機能と障害の構成要素は、「心身機能・身体構造」「活動」「参加」という3つの次元のものになります。モデル図の中段の赤線で囲った部分を見て、確認してください。
「環境因子」「個人因子」は背景因子を構成するという位置付けになります。
第27回第2問の選択肢
国際生活機能分類 (ICF) の基本的考え方と概要に関する問題で、「背景因子の構成要素は、 心身機能と身体構造、 活動と参加である。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、誤りです。
ICFでは、背景因子の構成要素は、環境因子と個人因子になります。よって、この選択肢は誤りになります。
介護福祉士試験第25回第87問の選択肢
「片麻痺のある人のICFにおける活動制限としては、トイレに行けないがその一例である。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、正しいです。
活動というのは、課題や行為の個人による遂行のことです。
第28回第57問の事例問題
事例
「Eさん (49歳、 男性) は、 脳性麻痺で足が不自由なため、 車いすを利用している。25年暮らした障害者支援施設を退所し1年がたつ。本日、 どうしても必要な買物があるが、支援の調整が間に合わない。その場での支援が得られることを期待して、一人で出掛けた。店まで来たが、階段の前で動けずにいる。」
この事例を読んで、 「支援なしで外出できることが、国際生活機能分類 (ICF)の「参加制約」に該当する」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、誤りです。
ICFにいう「参加」とは、生活・人生場面への関わりのことになります。そして、選択肢にある「支援なしで外出できること」というのは、生活・人生場面への関わりではなくて、行為の個人による遂行に該当します。これは、「活動」に該当します。よって、この選択肢は誤りになります。
参加制約に該当する例としては、店で買物ができないこと、つまり、店での買い物という生活場面に参加できないといったこと等があります。
精神保健福祉士試験の第27回第73問の選択肢
精神障害の特性に関する問題で、「様々な場面への活動や参加は、健康状態の向上へと導くことになる。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、正しいです。
ICFの構成モデルの図を見て頂ければ、活動や参加が健康状態と繋がっていることが理解できます。
3.ICFの特徴
ICFの特徴としては、3つあります。
①ICIDHでは、機能不全、能力低下、社会的不利という否定的な印象を与える用語を用いたのに対し、ICFでは、それぞれに対応する言葉として、心身機能・身体構造、活動、参加という中立的な言葉を用いています。
ICFは、ICIDHのようにマイナス面ばかりに注目しない、中立的な立場から生活そのものについて考える視点に立っているという特徴があります。
②新たな構成要素として「環境因子」と「個人因子」が加わった点に特徴があります。
これらにより、ある人の生活のしにくさの原因をその人の中にある従来の機能不全や能力低下だけに求めるのではなく、外的な環境や、障害に由来しないその人の特徴等との関連も視野に入れて捉えることができるようになります。
③ICIDHモデルが病気から始まって、機能不全、能力低下、社会的不利までの一方通行的な因果関係になっているのに対し、ICFモデルでは、双方向の矢印を用い、それぞれの構成要素が互いに影響し合って存在していることを表しています。

以上のように、ICFは、マイナスとしての障害の現象だけを切り取って見てしまうICIDHモデルから脱却して、まずは通常の人間の生活機能の低下を環境も含めて見ていこうとする考え方がその根底にあります。
4.具体例
ここで、具体例を挙げて説明しておきます。
健康状態としては、糖尿病を発症しました。その影響で網膜症を併発しました。そして、その後、失明しました。
心身機能としては、視覚器官の機能不全により読み書きや歩行が困難になった。
環境因子としては、点字やパソコンの活用ができる環境にある。
活動としては、読み書きは可能となる。また、白杖などの補助具の活用や盲導犬の利用により、歩行は可能となる。
要するに、環境の改善により、そもそも活動の制限をなくす、または制限を軽減することが可能となります。
参加としては、職場環境の改善や同僚による適切な支援により、失職という参加制約をなくす、または軽減することが可能となります。
こういうことになります。
これに対し、例えば、目が見えず杖をついている障害者に対して、「邪魔だ、どけ!」という社会であった場合、環境因子としては最悪です。
活動は制限され、参加も制限されてしまうわけです。
もう一つ、例を挙げておきます。
例えば、健康状態としては、脳卒中になった。心身機能としては、脳卒中の影響で、右片麻痺になった。この心身機能の低下により、機能障害があり、それによって歩行困難や仕事上の行為の困難(活動制限)が生じて、復職が困難という参加制約となるというケースがあったりします。
しかし、問題解決策として、たとえ麻痺の回復が不十分でも、実際の生活の場や通勤ルートでの歩行訓練、仕事上の行為の訓練などの「活動」への働きかけ、また、その際の杖・装具の活用という環境因子によって、活動の向上を図ることができ、復職が可能となる、つまり参加向上するということがあります。
この例を見ても言えるのは、歩行やその他の行為が困難になった直接の理由は麻痺などの「心身機能」の低下ですが、それを直接治さなくても、どうにかなるということです。
つまり、「歩く」という「活動」そのものへの働きかけ(歩く練習など)、そして、杖・装具という「環境因子」の活用による「活動」向上への働きかけが、効果的であったりするということなんです。
以上、見てきたように、社会環境等が、いかに大事なのかが分かります。
この大事な社会環境等も基準に入れたのが、ICFだということです。
第34回第2問
事例を読んで、国際生活機能分類(ICF)のモデルに基づく記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Aさん(40歳)は、脳性麻痺(まひ)のため、歩行訓練をしながら外出時は杖(つえ)を使用していた。しかし麻痺が進行し、電動車いすを使用するようになり、電車での通勤が困難となった。その後、駅の階段に車いす用の昇降機が設置され、電車での通勤が可能となった。
1 疾患としての脳性麻痺は、「個人因子」に分類される。
2 電動車いす使用は、「心身機能・身体構造」に分類される。
3 杖歩行が困難となった状態は、「活動制限」と表現される。
4 電車通勤が困難となった状態は、「能力障害」と表現される。
5 歩行訓練は、「環境因子」に分類される。
解説
選択肢1は、誤りです。
疾患としての脳性麻痺は、身体の働きに関することなので、「心身機能・身体構造」の機能障害に含まれます。
選択肢2は、誤りです。
電動車いす使用は「環境因子」に分類されます。
選択肢3は、正しいです。
選択肢4は、誤りです。
電車通勤が困難となった状態は、「環境因子」により「活動制限」が引き起こされています。
選択肢5は、誤りです。
歩行訓練は「活動」に分類されます。
第32回第4問
事例を読んで、国際生活機能分類(ICF)に基づいて分類する場合、正しいものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Aさん(50歳、男性)は、脳出血により片麻痺(まひ)を残したが、リハビリテーションによって杖(つえ)と下肢装具を用いた自立歩行を獲得し、復職を達成した。混雑時の通勤の負担と、思うようにならない気分の落ち込みから仕事を休みがちとなったが、職場より出勤時間の調整が図られ、仕事を再開するに至った。
1 片麻痺は、「活動」に分類される。
2 歩行は、「心身機能・身体構造」に分類される。
3 歩行に用いた杖と下肢装具は、「個人因子」に分類される。
4 気分の落ち込みは、「活動」に分類される。
5 出勤時間調整の職場の配慮は、「環境因子」に分類される。
解説
選択肢1は、誤りです。
片麻痺は身体の働きに関することなので、「心身機能・身体構造」の機能障害に含まれます。
選択肢2は、誤りです。
歩行は、自身の生活するのに欠かせない行動に関することなので、「活動」に分類されます。
選択肢3は、誤りです。
杖と下肢装具などの福祉用具は、生活を送るのに必要な物的環境による促進的な影響力なので、「環境因子」です。
選択肢4は、誤りです。
気分の落ち込みは、心理的な機能の低下なので、「心身機能・身体構造」になります。
選択肢5は、正しいです。
出勤時間調整の職場の配慮は、社会的環境や人々の社会的態度なので「環境因子」に分類されます。
5.ICFの活用によって期待できること
ICFを用いることによって、健康に関する状況、健康に影響する因子を深く理解することができます。
また、保健・医療・福祉等の従事者、それから、障害や疾病を持った人、それからその家族が、障害や疾病の状態についての共通理解を持つことが可能となります。
つまり、ICFは、「生きることの全体像を示す共通言語」であり、保健・医療・福祉等の従事者、それから、障害や疾病を持った人、それからその家族の共通理解を持つことに大変有効なわけです。
例えば、もし専門家と患者・家族の間に「共通言語」がなかったとしたら、「話が通じない」ことになりがちで、そのための誤解や不信が起こりがちです。このようなことにならないために、ICFの活用が有用なわけです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
