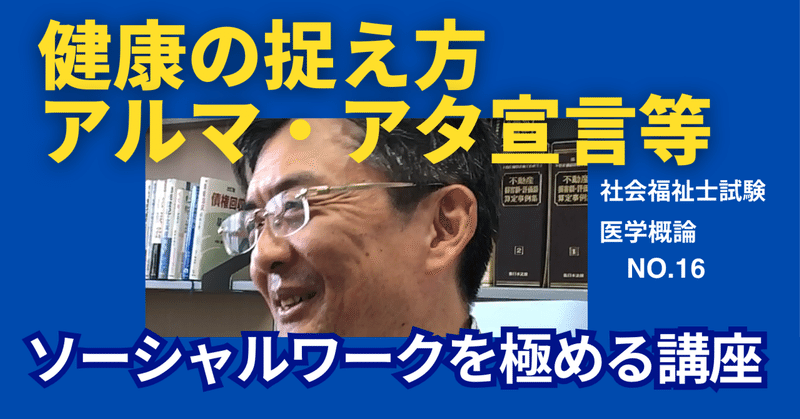
ソーシャルワークを極める講座 健康の捉え方
今回の内容は、YouTubeで視聴できます。
健康の捉え方については、近年、本試験でそこそこ出題されています。
1 健康の概念
みなさん、健康は大事ですよね。健康を害すると、日頃の生活がブルーになります。本当に不快です。そこで、健康は大事だと言われているわけですが、ここでは、WHOの健康概念を見ていきます。
まず健康の捉え方として有名なのは、1948年のWHO憲章の健康の概念になります。
20世紀前半ごろまでは、健康とは、疾病や死の反対側に位置する状態をいう。つまり、主として身体的に良好な状態であると捉えられていました。
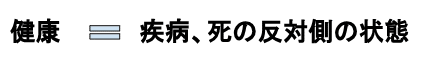
要するに、疾病でなければ、健康である。死の状態でなければ、健康である、ということ
これに対し、1948年のWHO憲章では、「健康とは、身体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。」と定義されています。
つまり、健康とは、単に病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることであると言っています。
要するに、「健康」=「病気ではない」という単純なことではないと認識されるようになりました。
肉体的だけではなく、精神的にもよい状態で、また、社会人として満足な日常生活を営んでいるという社会的にも満たされている状態、これが健康だとWHO憲章では言っています。

身体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態となると、上の図の身体・精神・社会の全てが重なっている赤色の部分の状態が、健康ということになります。このような図で見てみると、健康というのはかなり小さな領域の状態であることが分かると思います。健康状態を維持するのはいかに難しいかが分かると思います。
なお、1998年の第101回WHO執行理事会において、新しい健康の定義が検討されました。
これは、健康の定義に「spiritual(霊的)とdynamic(動的)」を加えたらどうかという提案でした。
「健康とは身体的・精神的・霊的・社会的に完全に良好な動的状態であり、たんに病気あるいは虚弱でないことではない。」
この点、賛否両論があったようです。
このような流れの中で、第52回世界保健機関総会(WHO総会)の議案とすることが決定され、WHO総会で審議しました。
この審議の中では、医療と宗教の混同という問題が指摘されました。それを踏まえて、必ずしも「spiritual(霊的)とdynamic(動的)」を健康の定義に追加する必要がないということになり、結局、採択が見送られたということがありました。
ですから、スピリチュアルやダイナミックは提案があったというだけで、決まったわけではないという点を押さえておいて下さい。
私見としては、霊的、つまり、宗教を健康の定義に入れると、無宗教の人は、「あなたは、健康ではない」ということにもなりかねないので、健康の定義に宗教を入れるのは、やはり抵抗があります。
第26回第3問の選択肢
健康に関する問題で、「WHO憲章では、 「健康とは、 身体的、 精神的、 社会的、 そしてスピリチュアルに完全に良好な状態をいう」と定義された。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、誤りです。
WHO憲章では、「健康とは、肉体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。」と定義されています。スピリチュアル(霊的)という文言を健康の定義に入れようという議論はありましたが、結局見送られ、現在でも含まれていません。
第30回第3問の選択肢
世界保健機関( WHO )の活動に関する問題で、「WHO憲章前文の中で、健康とは、身体的・精神的・社会的・政治的に良好な状態であると定義した。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、誤りです。
WHO憲章の健康の概念ですが、「健康とは、肉体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。」と定義されています。「政治的に」という部分はありません。
2.健康づくり運動の流れ
今から確認していくのは、健康づくり運動の流れになります。
要するに、健康というものは、みんなでいろいろな運動をしていかないとなかなか達成できないということです。
(1)アルマ・アタ宣言
まず、1978年、アルマ・アタ宣言がありました。
これは、当時のソビエト連邦のカザフ共和国の首都アルマ・アタで開催されたWHOの国際会議の宣言になります。
アルマ・アタ宣言は、プライマリ・ヘルス・ケア(PHC)の大切さを明確に示した最初の国際宣言です。
ここでいうプライマリとは、「基礎的な」という意味になります。
ヘルス・ケアは、「健康改善」という意味になります。
アルマ・アタ宣言につきましては、試験の中身を見てみると、全10条からなる宣言の中身を丸暗記するくらいのことが求められています。ですから、皆さんも、各自で宣言の各文言をしっかりと確認しておいてください。
では、ここでは、エッセンスだけを紹介しておきます。
アルマ・アタ宣言のテーマ(目標)は、「2000年までにはすべての人々に健康を」になります。
アルマ・アタ宣言は、政府に対し、国民の健康に対する責任を負わせる内容の宣言をしていて、「プライマリ・ヘルス・ケア」という公衆衛生戦略を提唱したものになります。
そして、アルマ・アタ宣言は、「健康であること」を基本的な人権として認めます。
そして、健康への住民の主体的参加の促進を強調しています。
要するに、他人任せでは健康にはなれないというわけです。
それ以外には、その地域で受け入れ可能な手法で、かつ、普遍的・総合的・継続的な方法で保健医療活動を行うことを強調しています。
要するに、アルマ・アタ宣言では、地域住民が自ら参加して、包括的、継続的で、身近な保健・医療サービスを組織的に提供することを目指していく。このような内容のプライマリ・ヘルス・ケアが提唱されたわけです。
ここでは、「住民の参加」という点がキーワードになります。参加なくして健康なしという感じでしょうか。
例えば、プライマリ・ヘルス・ケア活動の例としてよく挙げられるのが、長野県佐久総合病院での活動があります。
佐久総合病院では、「農民とともに」というスローガンを掲げて、農民固有の健康問題を直視して、農民のための医療と保健にこだわり、病院職員が町村へ直接赴き、住民の健診事業を実施したり、職員による演劇を通じた健康教育や病院を一般市民に開放した病院祭りなどをして、地域住民に参加してもらい、保健・医療サービスを組織的に提供していこうとする試みがあります。
そして、プライマリ・ヘルス・ケアの理念は、一次医療(プライマリ・ケア=家庭医的な診療所による医療)による治療だけではなく、一次予防(罹患率の減少を目指すこと)を含む健康改善(ヘルスケア)を行うという考えになります。
また、アルマ・アタ宣言は、先進国と開発途上国間における人々の健康状態の不平等について言及し、この不平等は、政治的、社会的、経済的に容認できないものであるとしています。要するに、健康格差の解消を目指すということです。
それから、アルマ・アタ宣言では、プライマリ・ヘルス・ケアは、地域、国家、その他の利用可能な資源を最大限利用した活動だとも言っています。
アルマ・アタ宣言が、プライマリ・ヘルス・ケアを提唱したということの覚え方
「アルマ・アタラシイからまずはプライマリ(基礎的な)・ヘルス・ケア(健康改善)でしょ!」
アルマ・アタ ・・・ プライマリ・ヘルス・ケア
アが三つで覚えるのもOK
第30回第3問の選択肢
世界保健機関( WHO )の活動に関する問題で、「アルマ・アタ宣言では、プライマリヘルスケアの重要性が示された。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、正しいです。
「アルマ・アタラシイからまずはプライマリ(基礎的な)・ヘルスケア(健康改善)でしょ!」これを何度も声に出して覚えて下さい。
アルマ・アタ ・・・ プライマリ・ヘルス・ケア
アが三つで覚えるのもOK
第26回第3問の選択肢
健康に関する問題で、「プライマリ・ヘルスケアの理念は、 一次医療(プライマリケア)による治療で健康を改善すべきという考えである。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、誤りです。
プライマリケアというのは、公衆衛生戦略です。つまり、住民に最も身近な地域での健康づくりの取組み、また住民にとって最も重要で根本的な健康づくりの取り組みを指します。このプライマリケアは、地域において医療活動、予防活動、健康増進の積極的展開を図ることで結果的に病気が重くなったりすることを防止するという側面を強く持っています。
プライマリ・ヘルスケアは、WHOのアルマ・アタ宣言で初めて定義づけられたもので、アルマ・アタ宣言のテーマは、「2000年までにはすべての人々に健康を」でした。そして、アルマ・アタ宣言は、健康になる権利は基本的人権だとして、健康になる権利は誰にでもあるということを宣言しています。そして、プライマリ・ヘルスケアの理念は、一次医療(プライマリ・ケア)による治療だけではなく、一次予防(罹患率の減少を目指すこと)を含む健康改善(ヘルスケア)を行うものだという考えになります。よって、この選択肢は、プライマリ・ヘルスケアの理念が一次医療(プライマリケア)による治療だけで健康を改善すべきとしており、一次予防(罹患率の減少を目指すこと)を含む健康改善(ヘルスケア)を行うものだという部分が抜けていますので、誤りになります。
第31回第4問の選択肢
「健康に関する問題で、一次予防とは、疾病の悪化を予防することである。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、誤りです。
疾病の悪化を予防することは、三次予防になりますよね。一次予防の目的は、罹患率の低下、つまり、健康増進と発病の予防になります。ちなみに、二次予防は、疾病の早期発見と早期治療を指します。
まとめると、予防には、
一次(健康増進・・健康相談、健康教育 特異的予防・・予防接種)
二次(早期発見・・健康診断 早期治療・・適切な治療)
三次(悪化防止、リハビリ)
があります。
第32回第5問の選択肢
1978年にWHOが採択したアルマ・アタ宣言に関する問題で、「先進国と開発途上国間における人々の健康状態の不平等について言及している。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、正しいです。
アルマ・アタ宣言第2条では、「人々の健康に関してとりわけ先進国と発展途上国の間に存在する大きな不公平は国内での不公平と同様に政治的、社会的、経済的に容認できないものである。それ故全ての国に共通の関心事である。」とあります。要するに、健康格差の解消を目指すということです。
第32回第5問の選択肢
1978年にWHOが採択したアルマ・アタ宣言に関する問題で、「政府の責任についての言及はない。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、誤りです。
アルマ・アタ宣言第5条では、「政府は国民の健康に責任を負っているが、これは適切な保健及び社会政策の保証があってはじめて実現される。・・・(略)」として、政府の責任に言及しています。国民の健康を守るのは、国家戦略だということです。
第32回第5問の選択肢
1978年にWHOが採択したアルマ・アタ宣言に関する問題で、「自己決定権についての言及はない。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、誤りです。
アルマ・アタ宣言第6条では、「プライマリー・ヘルス・ケア(PHC)とは、実践的で、科学的に有効で、社会に受容されうる手段と技術に基づいた、欠くことのできないヘルスケアのことである。これは、自助と自己決定の精神に則り、地域社会または国家が開発の程度に応じて負担可能な費用の範囲で、地域社会の全ての個人や家族の全面的な参加があって、はじめて彼(女)らが広く享受できうるものとなる。」とされています。よって、自己決定権についての言及がないとする選択肢は誤りになります。
第32回第5問の選択肢
1978年にWHOが採択したアルマ・アタ宣言に関する問題で、「保健ニーズに対応する第一義的責任は、専門職個人にあると言及している。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、誤りです。
アルマ・アタ宣言第7条の7番目には、「地域や後方支援レベルにおいても、保健医療チームとして働くために、また地域社会が求める保健ニーズに応えるために、社会的にも技術的にも適格に訓練された保健ワーカー、すなわち、医師、看護婦、助産婦、補助要員、可能であれば地域ワーカーや、必要によっては伝統治療師たちの力を必要とする。」とあります。
このように、保健ニーズに応えるため、医療・保健の専門職の力を必要すると書いてあります。しかし、特に責任については書かれていません。よって、この選択肢は誤りになります。
保健ニーズに対応する第一義的責任は、当事者になります。第4条では、「人々は皆、自分自身の健康管理の計画や実現に、個人または集団として自らの保健医療の立案と実施に参加する権利と義務を有する」と規定されてます。
ちなみに、オタワ憲章では、専門家や社会団体、保健医療従事者には、人々の健康の発展のために、社会の中での利害関係を調整する重要な責務があるとされています。
第32回第5問の選択肢
1978年にWHOが採択したアルマ・アタ宣言に関する問題で、「地域、国家、その他の利用可能な資源の活用についての言及はない。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、誤りです。
アルマ・アタ宣言第7条の5番目では、「プライマリ・ヘルス・ケアは、地域、国家、その他の利用可能な資源を最大限利用し、地域社会と地域住民が最大限の自助努力を行い、PHCの計画、組織化、実施、管理に参加することが重要であり、これを推進する。そして、この目標のために、適切な教育を通じて地域住民がこれに参加する能力を開発する。」とあります。アルマ・アタ宣言は、地域、国家、その他の利用可能な資源の活用について言及をしていますので、この選択肢は誤りになります。
(2)オタワ憲章
1978年のアルマ・アタ宣言から約10年後の1986年には、WHOのオタワ憲章が提唱されています。
1986年のオタワ憲章の覚え方
オタワにて、トヨタ86をプロモーション
オタワ憲章は、カナダの首都オタワで開催された時の憲章になります。
オタワ憲章では、プライマリ・ヘルス・ケアの理念を基礎とし、それをさらに発展させて、いわゆるヘルスプロモーション(HP)について提唱しています。
ここでのプロモーションとは、「高めること」という意味になります。
プロモーションという言葉ですが、皆さんも、例えば、アイドルをプロモーションしていくとかで聞いたことがあると思いますが、売り出していって、価値を高めていくということです。
では、どうしてヘルスプロモーションが提唱されることになったのか。
先進国では、生活習慣病や加齢による老人性退行疾患が増加し、そのための対応としては、事後対応としてのヘルス・ケアだけではもはや太刀打ちできないわけです。
生活習慣病や加齢による老人性退行疾患の増加に有効な対応をするには、一次予防(罹患率の減少を目指すこと)を含む健康改善(ヘルスケア)を行う必要があります。そのために、アルマ・アタ宣言で、プライマリ・ヘルス・ケアという公衆衛生戦略を提唱しました。
オタワ憲章では、プライマリ・ヘルス・ケアの理念を基礎とし、それをさらに発展させて、いわゆるヘルスプロモーション(HP)について提唱しているわけです。
つまり、社会全体としてライフ・スタイル全般をより健康へと志向させて、また事前対応も重要であって、そのため、その実施には個人とそれを取り巻く環境の双方の健康度(ヘルス度)を高める(プロモーション)ことまで踏み込んだ対策が是非とも必要となる。このようなことで、オタワ憲章では、ヘルスプロモーションが提唱されるようになったわけです。
ヘルスプロモーションとは、住民が自己の健康をコントロールし、改善できるようにする過程(プロセス)と定義される健康づくりのための施策・戦略です。
自らの健康を成立させるために最も重要なことを自分でコントロールができないと、本来持っている能力を十分に発揮することができなくなるということで、ヘルスプロモーション(健康増進)が提唱されています。
健康になるためには、健康を成立させるために最も重要なことについて、医者の言いなりになって単にまな板の鯉的に参加するだけではなくて、ちゃんと自分で医療の情報を集め、そのうえで、医療の内容を理解し、自分のことを決めて、自分でコントロールする必要があるということです。
このヘルスプロモーションは、健康へのより積極的な接近という考え方に立脚しています。
ちなみにプライマリ・ヘルス・ケアは、元来、疾病治療や疾病予防というように疾病を回避するヘルス・プロテクションの概念と関連するものと言えます。ですから、プライマリ・ヘルス・ケアが進化したものが、ヘルスプロモーションと言って良いでしょう。
以上のように、オタワ憲章では、「ヘルスプロモーション」という新しい公衆衛生戦略が提唱されたわけですが、主として工業化諸国を対象にして、疾病予防から健康増進に主眼(目標)を置いて諸活動がなされています。
具体的には、「ヘルスプロモーション」の目的として、「すべての人々があらゆる生活舞台。つまり、労働、学習、余暇、そして愛の場で、健康を享受することのできる公正な社会の創造」というものがあって、そのために健康を支援する環境づくりが不可欠であると提唱されていいます。
そして、「ヘルスプロモーション」の特徴としては、「プライマリ・ヘルス・ケア」がどちらかといえば、開発途上国をターゲットにした公衆衛生戦略であったのに対して、ヘルスプロモーションは先進国をターゲットにしたものであったという点に特徴があります。

第23回第4問の選択肢
「オタワ憲章では、地域住民が参加して包括的、継続的で、身近な保健・医療サービスを組織的に提供することを目指すプライマリ・ヘルスケアが提唱された。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、誤りです。
オタワ憲章では、ヘルスプロモーションが提唱されました。ヘルスプロモーションとは、住民が自己の健康をコントロールし、改善できるようにする過程(プロセス)と定義される健康づくりのための施策・戦略になります。選択肢の内容は、アルマ・アタ宣言の内容です。
第31回第4問の選択肢
健康に関する問題で、「WHOが提唱したヘルスプロモーションは、ヘルシンキ宣言において定義された。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、誤りです。
オタワ憲章にて、いわゆるヘルスプロモーションについて提唱されました。ちなみにヘルシンキ宣言とは、世界医師会(WMA)により、1964年に、フィンランドのヘルシンキにおいて、「人間を対象とする医学研究の倫理的原則」を示したものになります。これは、第二次世界大戦中のナチス・ドイツにおける非倫理的な人体実験を受けての医学研究における人体実験に対する倫理規範になります。
ヘルシンキ宣言は、「インフォームド・コンセント」という用語が導入されたことでも有名で、人を対象とした医学研究における重要な指針になります。
第23回第4問の選択肢
「アルマ・アタ宣言では、人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善することができるようにするヘルスプロモーションが強調された。」との内容の正誤が問われています。
この選択肢は、誤りです。
アルマ・アタ宣言では、健康というものが、人間の基本的権利であるとし、総合的な保健医療活動のあり方がプライマリ・ヘルス・ケアとして提唱されています。選択肢のように、人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善することができるようにするプロセスであるとするヘルスプロモーションが強調されたのは、1986年のオタワ憲章になります。
1986年のオタワ憲章の覚え方
オタワにて、トヨタ86をプロモーション
(3)ヘルスプロモーションと健康都市プロジェクト
1986年には、WHOのオタワ憲章が提唱され、ヘルスプロモーションが強調されました。
そして、その翌年の1987年に、健康都市プロジェクト(ヘルシーシティープロジェクト)というものがスタートしました。
世界的に人口の都市集中による生活環境の激変があって、それによって、人々の健康が大きく影響されるという問題の重要性が認識されてきました。
すなわち、これまでの健康は、個人の責任によると考えられてきました。個人の責任で健康を維持していくものだと。
しかし、都市に住む住民の健康を考えたとき、その都市の水や空気、安全な食べ物の確保、居住環境、都市の整備、教育など、個人の努力だけではどうにもならない要因が複雑に絡み合って影響しています。
例えば、「最近、ちょっと体重が増えてお腹が出てきたな」と感じて、「いよいよダイエットをしよう。家の周りを散歩でもしようかな」と考えたとき、皆さんなら、どんなところでウォーキングをしたいと思いますか?
都会は便利なのは良いけれど、近くの道路には車が激しく往来して、排気ガスが充満している。マンションや高層ビルがたくさん立ち並んでいて、散歩をしようとすると、そのビル群の間のコンクリートの道を黙々と歩いていくしかない。これでは、気持ち的にも身体にもあまり良いことではないと思います。できれば、緑が多く、景色が良くて、緑のにおいがするような空気の澄んだ道を歩きたいし、また、汗をかいた後は、安全な水を飲みながら、静かにくつろげる場所でゆったりしたり、周りの人たちと楽しくお話をしたりしたいですよね。このように、「健康」というものは、食事とか運動のような「個人の健康づくり」だけでなく、「人を取り巻く環境づくり」についても、大切なわけです。ですから、子ども・高齢者・病者・障がい者・低所得者・失業者等、健康被害の不利益を受けやすい人々を含め、都市に生活する人々の身体的、精神的、社会的健康水準を高めるためには、みんなで、都市のいろいろな条件を整える必要があります。
そこで、WHOによって、このような認識のもとで、保健・医療とは無縁であった活動領域の人々にも健康の問題に深く関わってもらい、都市住民の健康を確保するための仕組みを構築しようという取り組みが必要だということで、健康都市プロジェクトというものが、1987年から展開され始めています。
健康都市の考え方というのはどういうものか。
都市に住む我々の健康は、都市の構造や都市の機能、あるいは都市の環境、都市の条件というようなものによって、その都市住民の健康水準はずいぶん違ったものになると。なので、健康を「個人の問題」としてのみ捉えるのではなく、また、従来のように保健・医療だけで個人の健康維持・増進を図るのではなく、それ以外に、地域社会や都市のあらゆる分野を視野に入れた取組みにより、「都市そのものを健康に」することで、そこに住む人々の健康で豊かな暮らしづくりを推進していこうというものです。
WHOは、健康都市(Healthy City)を「都市の物的・社会的環境の改善を行い、そこに住む人々が互いに助け合い、生活のあらゆる局面で自身の最高の状態を達成するために、都市にある様々な資源を幅広く活用し、つねに発展させていく都市」としています。
この健康都市プロジェクトは、WHO(世界保健機関)が現在強力に推進しているプロジェクトになります。
3.その他の概念
次に、覚えておいて貰いたい用語に触れます。
(1)客観的健康と主観的健康感
いずれも、健康を評価するための評価指標です。
客観的健康とは、健診や検査によって客観的に判定した健康状態を言います。
主観的健康感とは、個人が自分の健康をどのように感じているのかということです。これについては、様々な質問票が開発されています。
では、健康を評価するために、主観的健康感という評価指標が用いられるようになったのはどのような経緯があるのか。
1948年に、WHOにより健康概念が提案されました。すなわち、健康とは、「病気や虚弱ではないばかりではなく、肉体的にも精神的にも社会的にも良好状態である」。
そして、客観的健康という評価指標では、このような健康概念を反映することが困難になってくるわけです。このような状況を反映し、1950年代後半より新しい視点から健康を評価するための「主観的健康感」による評価指標が米国を中心に用いられるようになってきました。
(2)首尾一貫感覚(しゅびいっかんかんかく)
首尾一貫感覚は、SOCを指します。
sense of coherence センス・オブ・コヒーレンス
「Coherence」には「首尾一貫」のほか「統一性、全体感」という訳もあり、文字通りの意味は「自分の生きている世界が首尾一貫しているという感覚を持っていること」となります。
この首尾一貫感覚ですが、ストレスに柔軟に対応できる能力を指します。
首尾一貫感覚。なんか小難しい単語です。いきなり「首尾一貫感覚」といわれても、ほとんどの人はピンとこないかもしれません。
ここにいう「首尾一環感覚」は、別名「ストレス対処力」とも呼ばれ、文字どおり「ストレス」に対処するためのヒントになる考え方になります。
首尾一貫感覚は、1970年代に、ユダヤ系アメリカ人の医療社会学者であるアーロン・アントノフスキー博士により提唱された考え方です。
アーロン博士は、ある女性たちに関心を持ちました。
すなわち、第2次世界大戦中にユダヤ人強制収容所に入れられた経験や厳しい難民生活を経験したにもかかわらず、更年期になっても良好な健康状態を維持している女性たちに興味を持ちました。
そこで、彼女たちを対象として、「彼女たちは、なぜ挫折せずに生き抜くことができたのか。」 アーロン博士は、そこに着目をしたわけです。
アーロン博士は、そうした健康的で明るい女性たちに共通する考え方や特性を分析して、それを「首尾一貫感覚」と名づけました。
この首尾一貫感覚の考え方は、日本では2000年頃から非常に広まりました。
それでは、この首尾一貫感覚の内容を確認しておきます。
自己に対してだけでなく、環境や生活の中で起こりうる物事をどのように捉えるかという志向性であり、それらが首尾一貫しているという確信の感覚になります。つまり、生活の中の出来事には何らかの意味があり、把握可能で適切に処理可能であるという確信であり、これは、3つの要素からなっています。
すなわち、有意味感、把握可能感、処理可能感の3つです。
①有意味感とは、仕事や日々の生活、すべての物事に意味ややりがいを感じるということです。
要するに、仮に逆境に遭遇しても、どんなことにも意味があるという感覚です。
②把握可能感は、自分の置かれている状況、自分の置かれるであろう状況がわかるということです。つまり、 先を見通しながら、今の現状を見る。「だいたいわかった」という感覚です。
③処理可能感は、なんとかなる、なんとかやっていける、自分は大丈夫という感覚になります。
例えば、家族がいる、友人がいる、資金がある、知恵がある、その他いろいろな事情があるので、自分は大丈夫と考えるとかです。
このような首尾一貫感覚を身につけると、さまざまな困難やストレスに直面しても、腑に落ちるので、それに対処していけるようになります。
仮に、あなたが、何らかの機会に、過剰なストレスに苛まれている状態の方に関わるようなことがあったときには、この3つの感覚が低くなってしまっているのだなと考えて、首尾一貫感覚が高まるようなアドバイスをしてみると良いと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
