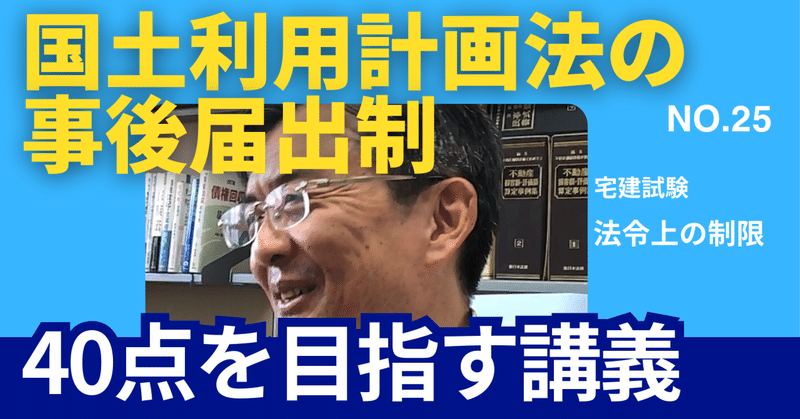
40点を目指す講義NO.25 国土利用計画法の事後届出制
今回の内容は、YouTubeで視聴できます。
1.事後届出制の内容
一定の面積以上の土地について、土地売買等の契約を締結した場合、原則として、権利取得者(例えば、買主など)は、契約を締結した日から2週間以内に、一定の事項(土地の利用目的、取引価格など)を窓口である市町村長を経由して都道府県知事(政令指定都市ではその長)宛てに届け出なければなりません(国土利用計画法第23条)。
この届出の目的は、当該届出の内容が、その地域内の土地利用の方針にきちんとマッチしているかを確認することになります。
事後届出制においては、権利取得者だけが届出をする必要があります。これは、事後届出制が利用目的の規制に重点があるためです。なので、土地を取得し、利用する側の権利取得者が届けるという形になります。
なお、ここで注意なのは、事前届出制の場合は、両当事者(例えば、売買契約であれば売主と買主)が届出をする必要があります。ここは、事前届出制と事後届出制の大きな違いの1つになります。
(1)対象区域
事後届出制の対象区域は、注視区域・監視区域・規制区域を除いた、全国の区域になります。

(2)届出対象面積
土地取引をする場合、すべての取引に事後届出が必要となるわけではありません。届出が必要となるのは、一定の面積の土地取引になります。
というのは、一定の規模以上の土地取引を規制しておけば十分だからです。
事後届出制の届出対象面積

覚え方
2*5=10
*1 市街化区域以外の都市計画区域内とは
都市計画法において、日本の国土は大きく3つに分けられます。


上記届出対象面積に該当するか否かは、誰を基準に判断するのか。
届出をするのは、権利取得者であり、権利取得者を基準に判断します。
では、このような場合はどうでしょうか。
共有者が持分を売却するとき
それぞれの持分相当の面積で、面積要件を判断することになります。
(3)事後届出が必要な「土地売買等の契約」とは
事後届出が必要な「土地売買等の契約」は、3つの要件をすべて満たす必要があります。
(A)権利性、(B)対価性、(C)契約性
➡ 土地に関する権利を、対価を得て、移転・設定する契約
届出・許可を必要とする土地取引(土地売買等の契約)

*1 土地に関する権利とは、土地の所有権、地上権、賃借権、また、それらの権利の取得を目的とする権利(例えば、売買の予約をしたときの予約完結権等)を言います。
具体的に説明します。
例えば、売買契約は、該当する例に入っています。
では、3つの要件を検討します。
売買契約は、所有権という土地に関する権利の移転なので、権利性があります。
また、売買代金と土地の所有権の譲渡という対価性もあります。
さらに、売買契約は契約なので、契約性もあります。ということで、売買契約は、事後届出の対象となる取引に該当します。
では、土地についての代物弁済契約については、どうでしょうか。
代物弁済とは、当事者の合意によって、債務者が負担している給付に代えて、他の給付をすることによりその債務を消滅させることを言います。
例えば、Aから1000万円を借りているBが、金銭での返済の代わりに1000万円の価値のある土地をAに譲渡するという合意をすることにより、Bの借金が消滅するのが、代物弁済です。
この代物弁済契約について、3つの要件を検討します。
権利性はどうか。
代物弁済契約は、所有権という土地に関する権利の移転なので、権利性があります。
また、1000万円の貸付金に対し、土地の所有権を譲渡するという対価性もあります。
さらに、代物弁済契約は契約なので、契約性もあります。ということで、代物弁済契約は、事後届出の対象となる取引に該当します。
では、もっと難しくなりますが、権利金など一時金の授受のある地上権・賃借権の設定はどうか。
では、3つの要件を検討します。
権利金の授受のある地上権や賃借権の設定は、地上権や賃借権という土地に関する権利の設定なので、権利性があります。
また、権利金(権利設定に対する費用)と土地の地上権や賃借権の設定という対価性もあります。
さらに、権利金など一時金の授受のある地上権・賃借権の設定は契約なので、契約性もあります。
ということで、権利金など一時金の授受のある地上権・賃借権の設定は、事後届出の対象となる取引に該当します。
なお、権利金などの一時金の授受のない地上権・賃借権の設定は、地上権や賃借権という土地に関する権利の設定契約なので、権利性や契約性はあります。しかし、権利金という権利設定に対する費用がなく、対価性がありません。
ちなみに、地代や賃料は、使用に対する費用なので、土地の地上権や賃借権の設定との間に対価性はありません。
ということで、権利金などの一時金の授受のない地上権・賃借権の設定は、事後届出の対象となる取引には該当しません。
*2 抵当権の設定、質権の設定は、土地に関する権利を移転・設定するものではなく、「土地売買等の契約」に該当しません。
というのは、抵当権や質権の設定をしても、土地の所有権は債務者のままで、債務者から債権者に移転しないからです。
これに対し、譲渡担保は、実質は担保ですが、法律上は譲渡の形を取っているものです。なので、譲渡担保は、土地に関する権利を移転するものとなって、「土地売買等の契約」に該当します。
*3 信託契約は、委託者が所有する財産を受託者に移転し、信託目的(所定の目的)に従い、受託者に本財産の管理や処分をさせる契約をいいます。この信託契約には、対価性がなく、土地売買等の契約に該当しません。
*4 予約完結権の行使について
予約とは、将来において契約を締結するということを事前に当事者同士で合意することを言います。この予約契約については、例えば、売買契約の予約や代物弁済契約の予約は、権利性、対価性、契約性の要件を満たします。なので、この段階では、事後届出が必要です。
それから、このような予約においては、当事者の一方が予約完結権を持つのが一般的です。
予約完結権を持つ者が契約を行なう旨の意思を表示をすれば、相手方の承諾を待つまでもなく、契約が自動的に成立します。つまり、予約完結権は、形成権の行使であって、予約を本契約へと強制的に移行させる権利になります。
形成権の行使は、完結権を有する者が一方的に「完結します」と言えば、それだけで売買契約が締結されたことと同じ効果が発生します。要するに、そこには、当事者間の合意はなく、契約性がありません。なので、この段階では、事後届出が不要です。
(4)一団の土地の取引の場合
①市街化区域内に所在するX地及びY地を取得する場合

市街化区域内の土地取引の場合、面積が、2000㎡以上(「以上」は、対象となる数字を含む)であれば、届出が必要となります。

AとC間、あるいはBとC間の取引のみであれば、それぞれ1000㎡の売買になるので、2000㎡以上ではなく、届出は不要です。
しかし、Cが、隣り合っているX地とY地を購入して、両土地に跨ってマンションを建築しようと考えている場合であれば、一団の土地の取引とみなされ、この場合には、2000㎡以上となります。
そして、事後届出制の場合、権利取得者が届け出るので、その届出対象面積に達するか否かは、権利取得者であるCを基準に判断することになります。そうすると、本件土地取引は、市街化区域の届出対象面積に達することになります。
一団の土地の取引とみなされる場合とは
①土地が隣り合っていること(物理的一体)
②両地に跨るマンションの建築等という計画的にも一体
この①と②、つまり、物理的・計画的一体性がある場合を指します。
なお、物理的・計画的一体性があれば、契約が時間的にずれていても、一団の土地の取引とみなされます。
では、AとC間の取引が、贈与契約であった場合はどうか?

贈与契約には、対価性がないので、BとC間の取引だけを考えればよいことになります。そうすると、市街化区域の届出対象面積に達することにはなりません。この場合には、届出は不要です。
(5)届け出る者
権利取得者になります。
当事者ではありません。
(6)届出すべき主な事項

(7)届出不要となる場合
事後届出が不要となる主な場合は、以下の通りです。
①民事調停法による調停・民事訴訟法による和解に基づく場合
②農地法第3条第1項の農業委員会の許可を受けることを要する場合
③滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売の場合
④非常災害に際し必要な応急措置を講ずるために行われる場合
⑤当事者の一方又は双方が国又は地方公共団体等である場合
②について
届出が不要となる理由は、農地法第3条第1項の農業委員会の許可を受けるような場合は、農地が譲渡されても農地のまま利用される場合、つまり農地転用はないので、土地の利用目的についてチェックを受ける必要がないからです。
これに対し、農地法第5条の農業委員会の許可を受けるような場合は、農地の権利移動だけでなく、農地転用もその内容に含まれてくるので、事後届出が必要となります。
農地法第3条と第5条の整理

⑤について
⑤の場合に届出が不要なのは、取引を行うのが公的機関だから問題はないという趣旨です。
(8)違反行為に対する措置
事後届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合、つまり、届出義務違反の場合には、土地の取引はどうなるのか?
届出制は、緩やかな規制なので、契約自体は有効です。
届出義務違反の場合には、届出義務を負う権利取得者に対しては、罰則があります。
ちなみに、変更勧告に従わなくても罰則はありません。
2.事後届出制の手続
事後届出制の手続のフローチャートを見てください。

都道府県知事の審査について
都道府県知事(指定都市においては指定都市の長、以下同じ)は、以下のア、イの場合には、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした権利取得者に対し、その届出に係る土地の利用目的のみ(対価の額は勧告対象外)について、必要な変更(商業施設として利用とあるが、宅地として利用にしてくださいとか)をすべきことを勧告(注意なので、勧告を受けた方には従う義務まではない)することができます。
ア 当該取引が、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合しないこと
イ 当該取引に係る土地を含む周辺の地域の土地利用を図るために著しい支障があると認めるとき
★注意!
事後届出においては、土地の利用目的だけでなく、対価の額についても、知事に届け出る必要があります(国土利用計画法第23条第1項第5号、第6号)。
しかし、審査や勧告・助言の対象となるのは、利用目的だけであって、「対価の額」について審査や勧告・助言することはできません(国土利用計画法第24条第1項)。
勧告の時期について
都道府県知事は、権利取得者からの届出があった日から起算して3週間以内に勧告をする必要があります。ですから、3週間経過しても勧告がなければ勧告はないと考えればよいということになります。
但し、調査の必要、勧告のできない合理的理由があるとき(例えば、大震災があったとか)は、3週間の範囲で延長することができます。
その場合、届出者に延長期間及び理由を通知することになっています。
対応②の変更勧告について
勧告に関する事後措置として、変更勧告と措置の報告があります。
変更勧告がなされた場合、権利取得者の対応としては、勧告に従うか、勧告に従わないかの二択になります。
権利取得者が勧告に従った場合
都道府県知事は、勧告に従って当該土地の利用目的が変更された場合、必要があると認めるときは、土地に関する権利の処分(例えば、売却)についてのあっせん等の措置を講じるよう努めなければならないことになっています(国土利用計画法第27条)。ここは、努力義務になります。
例えば、商業施設として土地を利用する目的であったところ、都道府県知事の勧告で、宅地として利用してください、と言われた場合、権利取得者としては、当該土地を持っていても仕方がないわけです。そこで、都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該土地の売却のあっせん等の措置を講じるように努力するということです。具体的には、都道府県知事が、ホームページを利用して、「当該土地の購入者を求む!」と掲載したら、努力したということになります。
権利取得者としては、勧告に従わなければ、公表されるし、逆に、勧告に従っても、都道府県知事が、ホームページを利用して、「当該土地の購入者を求む!」と掲載する程度のことなので、当該土地の購入者が出てこない場合には、大変困惑した状態になります。
権利取得者は、都道府県知事に対して、買取請求を求めたいところではありますが、これは認められていません。
ちなみに、規制区域(許可制)内の土地の権利者は、許可の申請をして不許可処分を受けた場合は、都道府県知事に対し、当該土地に関する権利の買取請求ができます(国土利用計画法第19条)。
変更勧告がなされた場合
都道府県知事は、必要があると認めるときは、勧告に基づいて講じた措置について報告をさせることができます。これが、措置の報告になります。
権利取得者が勧告に従わない場合、都道府県知事は、その旨及び勧告内容を公表することができます。できるのであって、義務ではありません(国土利用計画法第26条)。公表の仕方としては、ホームページに掲載するとか。
この場合、罰則はありません。
対応③の助言について
都道府県知事は、届出をした権利取得者に対し、届出に係る土地の利用目的について、必要な助言(アドバイス)をすることができます。
例えば、助言として、商業施設として利用するとあるが、宅地として利用した方がよいのではないですかとか。
なお、対価の額は、助言の対象ではありません。
また、助言制度は、事後届出のみにあって、事前届出には助言制度はありません。
平成19年問題17
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者であるAとBが、市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行う必要はない。
2 宅地建物取引業者であるCとDが、都市計画区域外の2haの土地について、Dを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Dは事後届出を行わなければならない。
3 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合には、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
4 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者は、その契約の締結後、1週間以内であれば市町村長を経由して、1週間を超えた場合には直接、都道府県知事に事後届出を行わなければならない。
解説
選択肢1は、誤りです。
市街化調整区域内では、5000㎡以上の土地売買等が国土利用計画法の事後届出対象面積になります。

Bは、6000㎡の土地を売買によって取得しています。ですから、事後届出をしなければなりません(国土利用計画法第23条第2項第1号ロ)。
なお、業者間取引であることは、国土利用計画法の届出の要否には無関係です。
選択肢2は、正しいです。
都市計画区域外では、10000㎡(1ha)以上の土地売買等が国土利用計画法の事後届出対象面積です。
Dは、2haの土地を売買によって取得しています。ですから、事後届出をしなければなりません(国土利用計画法第23条第2項第1号ハ)。
選択肢3は、誤りです。
事後届出を怠った場合には、罰金に処せられます(国土利用計画法第47条第1号)。
また、事後届出を行わなかった場合に、都道府県知事から届出を行うよう勧告されることはありません。勧告は、あくまで、事後届出をした場合に、その利用目的に対してなされるものです。
選択肢4は、誤りです。
事後届出をする場合、権利取得者は、当該契約の締結後、2週間以内に、当該土地が所在する市町村長を経由して、都道府県知事に届け出ることになります(国土利用計画法第23条第1項)。
選択肢のように、「1週間を超えた場合には、直接都道府県知事に事後届出」をするとの規定は存在しません。
平成20年問題17
国土利用計画法第23条に基づく都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
2 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
3 個人Dが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Eが購入する契約を締結した場合、Eは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
4 個人Fが所有する都市計画区域外の30,000㎡の土地について、その子Gが相続した場合、Gは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
解説
選択肢1は、誤りです。
市街化区域内では、2000㎡以上の土地取引については、事後届出が必要です(国土利用計画法第23条第2項第1号イ)。
選択肢のB社が取得した土地は、面積1500㎡です。2000㎡以上ではないので、事後届出は、不要です。
選択肢2は、誤りです。
市街化調整区域内の12000㎡の土地を購入する場合、国等以外が売主であれば、事後届出が要求されます(国土利用計画法第23条第2項第1号ロ)。
しかし、当事者の一方または双方が国等(国、地方公共団体など)である場合、例外扱いとなり、事後届出は不要になります(国土利用計画法第23条第2項第3号)。
選択肢では、売主が甲市(地方公共団体)です。ですから、事後届出を行う必要はありません。
選択肢4は、誤りです。
都市計画区域外で、事後届出の対象となる土地の面積は、10000㎡以上です(国土利用計画法第23条第2項第1号ハ)。選択肢で取引されている土地の面積は30,000㎡ですから、届出対象面積の点では、事後届出が必要になります。
しかし、事後届出の対象となるのは、「土地売買等の契約」になります(国土利用計画法第23条第1項)。そして、「土地売買等の契約」とは、①土地に関する権利の移転・設定であって、②対価を得て行われ、③契約である場合(予約を含む)のことをいいます(国土利用計画法第14条第1項)。
選択肢のように、相続による土地の取得は、③の「契約」である場合ではありません。そのため、「土地売買等の契約」に該当せず、事後届出の必要はありません。
平成21年問題15
国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者Aが都市計画区域外の10,000㎡の土地を時効取得した場合、Aは、その日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
2 宅地建物取引業者Bが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合、Bがその助言に従わないときは、当該知事は、その旨及び助言の内容を公表しなければならない。
3 宅地建物取引業者Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが購入する旨の予約をした場合、Dは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
4 宅地建物取引業者Eが所有する都市計画区域外の13,000㎡の土地について、4,000㎡を宅地建物取引業者Fに、9,000㎡を宅地建物取引業者Gに売却する契約を締結した場合、F及びGはそれぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
解説
選択肢1は、誤りです。
都市計画区域外で、事後届出の対象となる土地の面積は、10000㎡以上です。選択肢で取引されている土地の面積は、10000㎡ですから、届出対象面積だけを見れば、事後届出が必要な場合です。
しかし、事後届出の対象となるのは、「土地売買等の契約」になります(国土利用計画法第23条第1項)。そして、「土地売買等の契約」とは、①土地に関する権利の移転・設定であって、②対価を得て行われ、③契約である場合(予約を含む)のことをいいます(国土利用計画法第14条第1項)。
選択肢のように、時効取得による土地の取得は、③「契約」ではありません。そのため「土地売買等の契約」に該当せず、事後届出の必要はありません。
選択肢2は、誤りです。
都道府県知事の助言に従わなかった場合、それを公表できるとする規定はありません。
都道府県知事が公表ができるのは、勧告を受けた者が、その勧告に従わないときです(国土利用計画法第26条)。
選択肢3は、正しいです。
「土地売買等の契約」の中には、予約も含まれます(国土利用計画法第23条第1項、第14条第1項)。
そして、市街化調整区域においては、5000㎡以上の土地取引につき、事後届出が要求されます(国土利用計画法第23条第2項第1項ロ)。
選択肢のように、市街化調整区域内の6000㎡の土地について購入予約をした場合には、事後届出が必要です。この場合、届出期間の「2週間」も、予約の日から起算します。
選択肢4は、誤りです。
事後届出が必要な「一団の土地」に該当するかどうかは、あくまでも取得者側を基準に考えます。選択肢で言うと、譲渡人Eではなく、譲受人であるFとGを基準に届出の要否を判断します。
都市計画区域外で事後届出の対象となるのは、その面積が10000㎡以上の場合です(国土利用計画法第23条第2項第1号ハ)。
選択肢では、FもGも取得した土地の面積が10000㎡未満です。よって、事後届出の必要はありません。
平成22年問題15
国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。
2 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Cは、甲県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。
3 乙市が所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地と丙市が所有する市街化区域内の2,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが購入する契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
4 事後届出に係る土地の利用目的について、丁県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Eが勧告に従わなかった場合、丁県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。
解説
選択肢1は、誤りです。
市街化区域において、5000㎡の土地を売却する場合、事後届出の対象となります。
このとき、事後届出の義務を負うのは、権利取得者である買主Bになります(国土利用計画法第23条第1項)。このBは、届出義務を履行しなかった場合、そのことを理由に、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(国土利用計画法第47条第1号)。
一方、売主Aには、そもそも届出の義務がありません。よって、刑罰を受けることもありません。
選択肢では、「A及びB」に刑罰の可能性があるとしているので、誤りです。
選択肢2は、誤りです。
知事の勧告に対し、勧告を受けた者が土地の利用目的を変更したとしても、知事には、土地に関する権利の処分についてあっせんその他の措置を講ずる努力義務があるに過ぎません(国土利用計画法第27条)。
選択肢は、「権利を買い取るべきことを請求することができる」とありますが、この点が誤りです。
ちなみに、規制区域(許可制)内の土地の権利者は、許可の申請をして不許可処分を受けた場合は、都道府県知事に対し、当該土地に関する権利の買取請求ができます(国土利用計画法第19条)。
選択肢4は、誤りです。
都道府県知事は、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨と勧告の内容を公表することができます(国土利用計画法第26条)。
この点ですが、あくまで、「公表することができる」だけであって、公表の義務はありません。
平成24年問題15
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利の移転の対価が金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は、当該対価を時価を基準として金銭に見積った額に換算して、届出書に記載しなければならない。
2 市街化調整区域においてAが所有する面積4,000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
3 C及びDが、E市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、C及びDは、それぞれ事後届出を行わなければならない。
4 Fが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、FとGとの間で締結した場合、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Gは事後届出を行わなければならない。
解説
選択肢4は、誤りです。
「停止条件付の売買契約」も、事後届出の必要な「土地売買等の契約」に含まれます(国土利用計画法第23条第1項、第14条第1項)。
選択肢では、市街化区域内で、2500㎡の土地を売買により取得する場合です。ですから、市街化区域では、2000㎡以上の土地の売買であれば、事後届出が必要です(国土利用計画法第23条第2項イ)。
そして、事後届出の期限は、「契約を締結した日から起算して2週間以内」です(国土利用計画法第23条第1項)。選択肢では、「停止条件が成就した日」を起算日とする点が誤りです。
令和2年12月問題22
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
1 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
2 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
3 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。
4 個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。
解説
選択肢1は、誤りです。
事後届出においては、土地の利用目的だけでなく、対価の額についても、知事に届け出る必要があります(国土利用計画法第23条第1項第5号、第6号)。
しかし、審査や勧告・助言の対象となるのは、利用目的だけであって、「対価の額」について勧告することはできません(国土利用計画法第24条第1項)。よって、選択肢の「対価の額」についても勧告することができるとする部分は誤りです。
利用目的を変更するように勧告されたにもかかわらず、この勧告に従わない場合、知事は、その旨と勧告の内容を公表することができるという部分(国土利用計画法第26条)は、その通りです。
選択肢2は、誤りです。
都道府県知事による勧告は、権利取得者の事後届出に対して、土地の利用目的を変更するよう促すためのものです(国土利用計画法第24条第1項)。ということは、勧告は、事後届出がされていることが前提になります。選択肢では、「事後届出を行わなかった場合」に勧告を行うとありますが、これはできません。
この場合には、勧告ではなく、罰則の対象になります(国土利用計画法第47条第1号)。
選択肢4は、正しいです。
まず届出を必要とする土地取引(土地売買等の契約)に該当するか、について検討します。
土地に関する地上権や賃借権を設定する契約は、権利金などの対価を支払う場合には、「土地売買等の契約」に該当します(国土利用計画法第23条第1項、第14条第1項、令第5条)。
そして、面積要件について検討すると、都市計画区域外で事後届出の対象となるのは、その面積が10000㎡以上の場合になります(国土利用計画法第23条第2項第1号ハ)。選択肢の土地は、11000㎡です。ですから、事後届出の必要があります。
平成23年問題15
国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、法第23条に規定する都道府県知事への届出をいう。
1 都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講じなければならない。
2 都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。
3 Aが、市街化区域において、2,500平方メートルの工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500平方メートルをB社から購入し、残りの1,000平方メートルはC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。
4 Dが所有する市街化調整区域内の土地5,000平方メートルとEが所有する都市計画区域外の土地12,000平方メートルを交換した場合、D及びEは事後届出を行う必要はない。
解説
選択肢1は、誤りです。
都道府県知事は、勧告に従って当該土地の利用目的が変更された場合、必要があると認めるときは、土地に関する権利の処分についてのあっせん等の措置を講じるよう努めなければならないです(国土利用計画法第27条)。ここは、努力義務になります。
選択肢3は、正しいです。
国土利用計画法の事後届出が必要な場合は、①土地に関する権利の対価の授受を伴って、②移転・設定する契約を締結した場合で、かつ、③買主の取得した土地の面積の合計が届出対象面積を満たす場合になります。
この点、市街化区域内の土地の場合の届出対象面積は、合計して2000㎡以上になります。
ただし、選択肢のように、C社から取得した1000㎡の土地が贈与により取得したものである場合、①の対価の授受がありません。そのため、この取引については、届出面積に含みません。したがって、B社から売買契約により取得した1500㎡のみで判断されます。そうすると、届出対象面積である2000㎡以上に達していないので、事後届出は不要となります。
選択肢4は、誤りです。
交換は、対価性があり、土地売買等の契約に該当します。
そして、事前届出は、当事者(売主または買主)のどちらか一方の土地の面積の合計が届出対象面積を満たす場合には届出が必要になります。
市街化調整区域では、5000㎡以上で届出が必要になり、また、都市計画区域外では、10000㎡以上で届出が必要です(国土利用計画法第23条第1項、第2項第1号ロ・ハ)。

選択肢では、Dが所有する市街化調整区域内の土地は、5000㎡なので、5000㎡以上に該当します。また、Eが所有する都市計画区域外の土地12000㎡は、10000㎡以上に該当します。したがって、いずれも届出対象面積に達しており、D及びEは届出が必要です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
