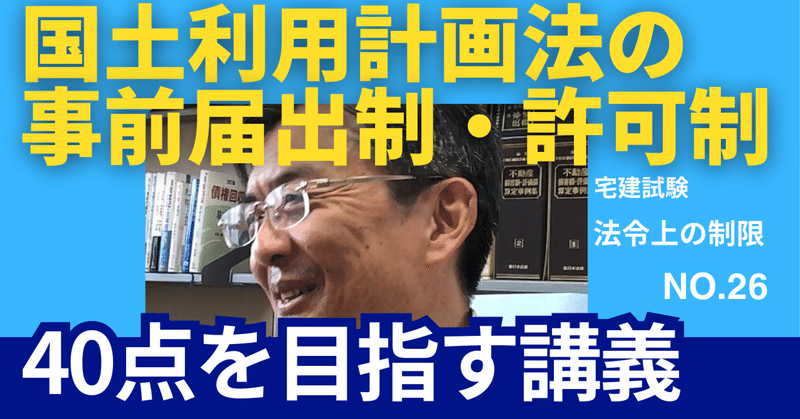
40点を目指す講義NO.26 国土利用計画法の事前届出制・許可制
今回の内容は、YouTubeで視聴できます。
1.事前届出制
(1)事前届出制の制度趣旨と区域指定等

事前届出制の制度趣旨は、投機的取引による値上がりを防止することです。
投機とは、将来の価格変動を予想して、現在の価格との差額を利得する目的で行われる売買行為のことをいいます。
事前届出制の対象区域は、注視区域と監視区域になります。
注視区域や監視区域では、適正な土地利用の他、土地の値段を抑制しようという目的がプラスされた区域になります。
注視区域と監視区域の相違点と共通点
注視区域と監視区域の各土地において土地売買等の契約をしようとする場合、契約の両当事者は、事前に、一定事項を都道府県知事(指定都市においては指定都市の長。以下同じ)に届け出なければならないことになっています(国土利用計画法第27条の4、第27条の7)。
事前届出を必要とする「土地売買等の契約」は、3つの要件をすべて満たす必要があります。
これは、事後届出を必要とする場合と同じ概念です。
(A)権利性、(B)対価性、(C)契約性
➡ 土地に関する権利を、対価を得て、移転・設定する契約
届出・許可を必要とする土地取引(土地売買等の契約)

注視区域・監視区域の指定手続について
①都道府県知事は、あらかじめ土地利用審査会および関係市町村長の意見を聴いて区域を指定し、公告することになります(国土利用計画法第27条の6第2項、第3項、第12条第3項)。
②この指定は、5年以内の期間を定めて行うことになります。
③都道府県知事は、指定期間が満了するとき、指定の事由がなくなっていないと認めるときは、再度、区域の指定を行うことができます。
(2)届出対象面積・届出内容等
①注視区域・監視区域の届出対象面積

注視区域の場合は、事後届出制と同じ面積になっています。
2*5=10 で覚えたところになります。
監視区域の場合は、注視区域の届出面積よりも小規模な土地取引についても事前の届出を求めるために、都道府県知事が規則で定める広さとされています。これは、小規模な土地取引であっても、地価上昇の抑制が必要な場合があるからです。
例えば、空港予定地である小笠原村が監視区域になっています。
東京都知事は、東京都の規則で、届出面積を500㎡以上と定めています。
一団の土地の扱いについて
事前届出制の場合は、届出者は契約の両当事者になることから、当事者双方が基準となって、届出対象面積の要件を検討することになります。
注視区域の場合

この図の場合であれば、契約当事者であるAは、2000㎡の土地の売買契約をしているので、事前届出の必要があります。これに対し、契約当事者であるBとCは、それぞれ1000㎡の土地の売買契約ということで、2000㎡以上ではないので、事前届出の必要はありません。
②注視区域・監視区域の届出内容等

届出後に当事者・予定対価の額・利用目的等に変更が生じた場合は、改めて届出が必要となります。
ただし、減額(値段を下げる)だけの場合は、地価を抑制するという観点からは特に問題はなく、再度の届出は必要ありません。
例外的に届出不要となる場合
以下の通りです。ここの部分は、事後届出制と同じです。
①民事調停法による調停・民事訴訟法による和解に基づく場合
②農地法第3条第1項の農業委員会の許可を受けることを要する場合
③滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売の場合
④非常災害に際し必要な応急措置を講ずるために行われる場合
⑤当事者の一方又は双方が国又は地方公共団体等である場合
(3)事前届出制の手続
事前届出制の手続きのフローチャートを見てください。

変更勧告の例としては、対価の値段が高すぎるので下げなさい等
①届出の効果
届出者は、その届出をした日から起算して、6週間を経過するまでの間は、売買等の契約をしてはならないことになっています。
但し、6週間を経過するまでに不勧告等の通知を受けた場合は、チェックが済んでいるので、契約を締結することができます。
②勧告の要件(審査基準)
注視区域と監視区域に共通する主な審査基準は、以下の通りです。
予定価格の額に関する審査基準
➡予定対価の額が、公示価格を基準として算定した価格に照らして著しく適性を欠くか否か
土地利用の目的に関する審査基準
➡土地利用の目的が、土地利用基本計画等に適合しているか否か
➡周辺の自然環境の保全上明らかに不適切である場合か否か
監視区域に特有の審査基準
監視区域については、土地の値段を抑える必要性がさらに高いため、特例として、特有の審査基準があります。
予定価格の額に関する審査基準
➡短期間での転売によって「投機的土地取引」(土地転がし)とみなされる場合か否か。
③勧告に関する事後措置
届出た者が、都道府県知事の勧告に従う場合、都道府県知事は、必要であれば、権利の処分について、あっせん等の措置を講じる努力義務があります。
届出た者が、都道府県知事の勧告に従わない場合、都道府県知事は、勧告内容を公表することができます。
勧告に従わない場合に罰則はありません。
また、勧告に従わないで締結された契約の効力自体は、有効です。
(4)違反行為に対する措置
以下の場合には、罰則があります。
・事前届出をしないで契約をした。
・虚偽の届出をした。
・審査期間中に契約をした。
・報告義務違反または虚偽の報告をした。
なお、違反行為があっても、契約自体は、有効です。
(5)事後届出制と事前届出制の比較

2.許可制

規制区域内で、一定の土地取引を行う当事者は、一定の手続きを経て、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
(1)規制区域として指定されるエリア
規制区域は、都道府県知事が指定しますが、規制区域に指定されるのはどのような区域か?
注視区域や監視区域での事前届出制の規制では、地価の高騰が抑制できないような区域になります。
具体的には、土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、または行われるおそれがある区域になります。
投機的取引とは、利益を得るために売買・転売をするような取引を指します。
要するに、土地を安く買って、その土地を高く売るという取引です。
都道府県知事は、規制区域を指定する場合には、その旨並びにその区域及び期間を公告しなければなりません(国土利用計画法第12条第3項)。
この公告をしたときは、その公告の日から起算して2週間以内に、関係市町村長の意見を付して規制区域の指定が相当であることについて土地利用審査会の確認を求めなければなりません(国土利用計画法第12条第6項)。
都道府県知事は、規制区域の指定について、土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告するとともに、国土交通大臣に報告しなければなりません。
都道府県知事によってなされた規制区域の指定は、土地利用審査会の確認をうけられなかった旨の公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失います(国土利用計画法第12条第9項)。
規制区域においては、注視区域や監視区域の場合よりも、区域の指定について、厳しい扱いが規定されていますが、これは、規制区域においては、国民の自由をより強く規制する許可制が採用されているためです。
ちなみに、現在、規制区域に指定されているところはありません。
平成23年問題15
国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、法第23条に規定する都道府県知事への届出をいう。
1 都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講じなければならない。
2 都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。
3 Aが、市街化区域において、2,500平方メートルの工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500平方メートルをB社から購入し、残りの1,000平方メートルはC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。
4 Dが所有する市街化調整区域内の土地5,000平方メートルとEが所有する都市計画区域外の土地12,000平方メートルを交換した場合、D及びEは事後届出を行う必要はない。
解説
選択肢2は、誤りです。
監視区域については、選択肢のような規定はありません。
規制区域とのひっかけ問題です。
都道府県知事は、規制区域を指定する場合には、その旨並びにその区域及び期間を公告しなければなりません(国土利用計画法第12条第3項)。
この公告をしたときは、その公告の日から起算して2週間以内に、関係市町村長の意見を付して規制区域の指定が相当であることについて土地利用審査会の確認を求めなければなりません(国土利用計画法第12条第6項)。
都道府県知事は、規制区域の指定について、土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければなりません。
都道府県知事によってなされた規制区域の指定は、土地利用審査会の確認をうけられなかった旨の公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失います(国土利用計画法第12条第9項)。
規制区域においては、注視区域や監視区域の場合よりも、区域の指定について、厳しい扱いが規定されていますが、これは、規制区域においては、国民の自由をより強く規制する許可制が採用されているためです。
(2)届出制と異なる点
①面積について
規制区域においては、面積にかかわらず、許可を受けることが必要となります。
というのは、地価高騰を防止する必要性が高いからです。
②許可が必要な土地取引について
許可が必要な土地取引については、「土地売買等の契約」です。
ここの部分は、届出が必要な土地取引の場合と同じです。
しかし、異なる部分があります。
取引の当事者の一方または双方が、国・地方公共団体等である場合は、都道府県知事との協議の成立をもって許可があったものとみなされます。
③許可申請後の変更について
許可申請後、予定の対価の額や土地利用目的を変更しようというときは、改めて許可申請が必要となります。
ただし、予定の対価の額については、減額する場合は許可申請は不要です。
④契約の効力等
許可を受けなかった契約の効力は、無効です。
許可を受けないで契約をすると、罰則があります。
許可申請に対し、不許可処分を受けた場合、契約当事者は、2つの手段を選択することになります。
・都道府県知事に対し、買取請求ができます。
・土地利用審査会に対し、不服申し立てである審査請求ができます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
