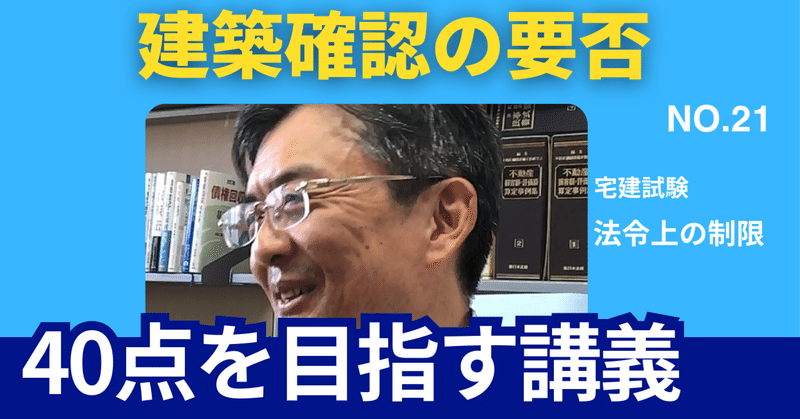
40点を目指す講義NO.21 建築基準法を守らせるための制度(建築確認)
今回の内容は、YouTubeで視聴できます。
1.建築確認の仕組み
建築確認の仕組みを説明します。
一定の建築物を建てる工事をする前に、建築主事という建築専門の役人が建物や地盤が建築基準法や各市町村の条例などに適合しているかを確認して、この確認でパスしたものだけが工事に着手できるということにして、違反建築を未然に防止するための仕組みが、建築確認制度になります。
具体的には、これまで学習してきた、建ぺい率や容積率、北側斜線制限などが守られているかなどが確認されます。
建築確認を申し込むことを「建築確認申請」と呼び、その際に提出する書類を「建築確認申請書」といいます。
建築主は、建築主事に建築確認申請書を提出します。
そして、建築業者などの工事施工者は、確認済みであることが分かる標識を、工事現場の見やすい場所に設置しなければなりません(建築基準法第89条)。
なお、建築確認申請は、設計事務所や施工会社が申請者(建築主)の代理者として行います。
建築確認については、基本的には自治体の建築主事が行います(建築基準法第6条)。
ただ、自治体から指定を受けている民間の指定確認検査機関の確認が建築主事の確認とみなされる制度も設けられています(建築基準法第6条の2)。
建築確認制度の学習上のポイントは、主に2つになります。
・どのような場合に建築確認が必要なのか。
・建築確認の手続の流れ
2.建築確認の要否(建築基準法第6条)
建築確認を必要とする建築物か否かを見極めるためには、以下の表を理解する必要があります。
なお、令和4年6月17日公布の建築基準法改正に伴う建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直しについては、令和7年4月からの施行を予定しています。
ここでは、施行前の内容で説明します。
建築確認の要否の判断に当たっての着眼点には、3つあります。
・その場所(区域)
➡建築確認が必要な場所か
・その建築物の種類・規模(大きさ)
➡建築確認が必要な建物か
・行為の種類
➡建築確認が必要な工事か
この着眼点を基にした表が以下のものになります。

*注1 増築・改築・移転については、増築・改築・移転に係る部分の床面積の合計が、10㎡以内であれば、建築確認は不要(つまり、10㎡までは不要)で、10㎡超であれば、建築確認が必要となります(つまり、10㎡を少しでも超えれば必要)。
しかし、防火地域又は準防火地域の場合は、10㎡以内であっても確認が必要となります。
というのは、防火地域内又は準防火地域内では、たとえわずかな増築等であっても、いい加減な工事が行われれば、火事が発生した際には人命にかかわるからです。逆に言うと、防火地域又は準防火地域以外で、火災に対してそれほど気を遣う必要がない区域であれば、10㎡以内の小規模な増築・改築・移転であれば、あえて建築確認は必要ないとしているということです。
*注2 都市計画区域等とは、都市計画区域・準都市計画区域、もしくは準景観地区内、または都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部もしくは一部について指定する区域内のことを言います。
なお、都市計画区域・準都市計画区域、もしくは準景観地区内については、それぞれ対象から除かれる部分があります。
都市計画区域・・・都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域
準都市計画区域・・都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域
準景観地区・・・・市町村長が指定する区域
この都市計画区域等においては、全国の区域であれば、新築、増築・改築・移転の際に建築確認が不要な建築物(AからC以外の建物、つまり小さな建築物)であっても、特別扱いとなり、建築確認が必要になります。
但し、大規模修繕や模様替えについては、建築確認が不要です。ここは、要注意です。
また、繰り返しになりますが、防火地域、準防火地域以外で建築物を増築・改築・移転する場合には、その床面積が、10㎡以内であれば建築確認は不要です。
*注3 用途変更とは、建築物の用途を変更して、出来上がるものが特殊建築物の場合を言います。
特殊建築物とは、劇場、映画館、集会場、ホテル、下宿、共同住宅、倉庫、自動車車庫といった不特定多数の方が利用する用途に供する建築物で床面積が200㎡を超える建築物をいいます。いわゆる「とっけん」です。
例えば、事務所は特殊建築物ではありません。しかし、事務所の用途に供していた建築物をホテル(特殊建築物)に変更する場合には、変更に係る工事に着手する前に建築確認申請が必要となります。
もっとも、政令で指定する類似の用途相互間の用途変更の場合は、建築確認が不要となっています(建築基準法第87条第1項)。
というのは、類似の用途相互間の用途変更の場合(建築基準法施行令第137条の18)には、変更前後の建築物が同じような構造なので、あまり大がかりな工事にならないからです。
類似の用途の例(建築基準法施行令第137条の18)
一 劇場、映画館、演芸場
二 公会堂、集会場
三 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
四 ホテル、旅館 👈注意 共同住宅は類似ではない
五 下宿、寄宿舎
六 博物館、美術館、図書館
七 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
八 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
九 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
十 待合、料理店
十一 映画スタジオ、テレビスタジオ
ただし、用途地域によっては類似の用途間の変更であっても確認申請が必要となります。ここは細かいので割愛します。
B・Cについて
B・Cは、区域としては、全国どこでもの区域で、大規模建築物になります。
一般的に大きな建築物は、建築基準法をきちっと守ってもらう必要性がより高いということで、建築確認を受けるべき、となります。
大規模建築物には、2種類あります。
木造か、木造以外(鉄筋造など)の建築物です。
では、木造よりも木造以外の建築物の方が規模の小さなものから、事前の確認を受けることになっています。これはどうしてか?

これは、仮に木造以外の鉄筋造の建築物が建築基準法に違反していることが発覚した場合、鉄骨造は頑丈なので、違反部分を改築するのが難しいからです。
そこで、木造以外の建築物は、木造に比べてより規模の小さいものから、事前の確認を受けてもらう必要が高くなるということになります。
大規模建築物に該当するための基準ですが、A・B・Cを並べてみて、面積については、基本の面積は、200㎡で、木造だけが、500㎡であると覚えておいてください。
Aについて
Aは、区域としては、全国どこでもの区域で、用途に供する床面積の合計が200㎡を超える場合に、建築確認が必要です。
要するに、特殊建築物で、かつ、大きなものを指しています。
特殊建築物とは、劇場、映画館、集会場、ホテル、下宿、共同住宅、倉庫、自動車車庫といった不特定多数の方が利用する用途に供する建築物で床面積が200㎡を超える建築物をいいます。
一定の規模の不特定多数の方が利用する用途に供する建築物については、ちゃんとした物を建ててもらわないと、万が一の時に、被害者数が多くなるので、全国どこでも、用途に供する床面積の合計が200㎡を超える場合には、建築確認が必要になるとしています。
*事務所は多数の方が利用する可能性はありますが、特殊建築物ではありません。というのは、事務所は、不特定の方が利用する用途に供する建築物ではないからです。
Dについて
Dは、区域としては、都市計画区域等で、建築物の規模(小さな建築物でも)を問わず、建築確認が必要です。
以上のまとめ(確認の要否を問われる問題を解く際のコツ)
その行為が、都市計画区域・準都市計画区域等の区域内で行われる場合
かを確認する。
Yesの場合は、
新築であるなら、建築物の規模に関係なく、建築確認が必要
増築・改築・移転であるなら、その行為が、さらに、防火地域・準防火地域内で行われる場合かを確認する。
Yesの場合は、
その部分の床面積の合計数にかかわらず、建築確認が必要
Noの場合は、
その部分の床面積の合計が10㎡を超える場合は、建築確認が必要
ちなみに、区域が全国で、一定の特殊建築物、大規模建築物の場合の増築・改築・移転については、その部分の床面積の合計が10㎡を超える場合になると、建築確認が必要となります。10㎡以内であれば、建築確認は不要です。
平成19年問題21
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確認を受けなければならない。
2 居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにするため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
3 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、すべて耐火建築物としなければならない。
4 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
解説
選択肢1は、正しいです。
共同住宅は、特殊建築物に該当します。特殊建築物で、床面積の合計が200㎡を超えるものの大規模修繕を行う場合は、あらかじめ建築確認を受けなければなりません(建築基準法第6条第1項第1号)。

平成11年問題20
建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 木造3階建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。
2 鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。
3 自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300㎡)にしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。
4 文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物の大規模の修繕をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。
解説
選択肢1は、正しいです。
選択肢の建築物は、木造3階建てとあるので、大規模建築物に該当します。
したがって、その建築に際しては、建築確認が必要です(建築基準法第6条第1項第2号)。

選択肢2は、正しいです。
選択肢の建築物は、鉄筋コンクリート造、延べ面積が300㎡とあって、200㎡を超えるので、大規模建築物に該当します。したがって、その建築に際しては、建築確認が必要です(建築基準法第6条第1項第3号)。
選択肢3は、誤りです。
共同住宅は、特殊建築物に該当します(建築基準法第6条第1項第1号)。自己居住用の建築物を共同住宅という特殊建築物に用途変更し、その床面積が200㎡を超える場合は、建築確認を受ける必要があります(建築基準法第87条第1項)。
同じような問題が、平成22年問題18でも出題されています。
選択肢4は、正しいです。
文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物については、建築基準法は適用されません(建築基準法第第3条第1号)。ということで、建築確認を受ける必要もないということになります。
平成27年問題17
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。
2 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
3 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
4 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
解説
選択肢1は、正しいです。
防火地域及び準防火地域外において建築物を改築しようとする場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認を受ける必要はありません(建築基準法第6条第2項)。
選択肢2は、正しいです。
都市計画区域又は準都市計画区域外の建物については、大規模建築物に該当する場合には、建築確認の対象となります。
大規模建築物のうち、木造の建築物については、

選択肢の木造建築物は、木造3階建てですから、大規模建築物に該当します。したがって、新築にあたり、建築確認を受ける必要があります。
選択肢3は、誤りです。
事務所をホテルに用途変更する場合、ホテルは、特殊建築物に該当するので、その用途に供する床面積(500㎡)が、基準の200㎡を超えていますから、建築確認を受ける必要があります(建築基準法第87条第1項、第6条第1項第1号)。

選択肢4は、正しいです。
映画館は、特殊建築物に該当します。そして、その用途に供する床面積は300㎡であり、基準の200㎡を超えています。したがって、改築にあたっては、建築確認が必要です(建築基準法第6条第1項第1号)。
平成22年問題18
3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。
2 用途が事務所である当該建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、建築確認を受ける必要はない。
3 当該建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。
4 用途が共同住宅である当該建築物の工事を行う場合において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えたときは、中間検査を受ける必要がある。
解説
選択肢1は、誤りです。
選択肢の建築物は、区域としては、都市計画区域外に建築されます。
都市計画区域や準都市計画区域外の建築物の場合、大規模建築物に該当する場合には、建築確認の対象となります。
大規模建築物は、以下の建築物です(建築基準法第6条第1項第2号、第3号)。

選択肢の木造建築物は、木造3階建てで延べ面積600㎡ですから、上記基準からすると、大規模建築物に該当します。したがって、新築の際に、建築確認を受ける必要があります。
平成21年問題18
建築基準法に関する次のアからエまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。
イ 防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100㎡以内であるときは、建築確認は不要である。
ウ 都道府県知事は、建築主から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から1月以内にその結果を記載した通知書を建築主に交付しなければならない。
エ 指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
一つ
二つ
三つ
四つ
解説
アについては、誤りです。
建築する場所が準都市計画区域内とあるので、一般の建築物に該当します。この場合に新築する場合には、建築物の規模を問わず建築確認が必要です(建築基準法第6条第1項第4号)。
例外的に建築確認が不要となるのは、①防火・準防火地域外で、②10㎡以内の増築・改築・移転の場合に限られます(建築基準法第6条第2項)。

イについては、誤りです。
一般建築物について、建築確認が不要となるのは、①防火・準防火地域外で、②10㎡以内の増築・改築・移転に限られます(建築基準法第6条第2項)。
選択肢の建築物は、区域としては、防火地域内にあることから、①を満たしていません。したがって、その増築には、面積によらず建築確認が必要となります。
平成16年問題21
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 準防火地域内においては、延べ面積が1,200㎡の建築物は耐火建築物等としなければならない。
2 木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。
3 特定行政庁は、仮設店舗について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、一定の場合を除き、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。
4 居室を有する建築物は、住宅等の特定の用途に供する場合に限って、その居室内においてホルムアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。
解説
選択肢2は、誤りです。
建築確認が必要になるのは、以下のケースです(建築基準法第6条第1項)。

選択肢の建築物の場所は、都市計画区域等ではない区域になります。そして、木造3階建て、高さ15mになるので、木造の大規模建築物に該当します。この場合、大規模修繕に当たっては、建築確認を受ける必要があります。
平成10年問題20
建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築主事等の確認を受けなければならない。
2 建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内のものであれば、建築主事等の確認の申請が必要となることはない。
3 建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築主事等の確認を受けなければならないことがある。
4 建築主事等は、事務所である建築物について確認をする場合、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければならない。
解説
選択肢1は、正しいです。
階数3以上あるので、大規模建築物に該当します。よって、新築の場合には、建築確認は必要です。

選択肢2は、誤りです。
10㎡以内の建築物の改築でも、防火地域・準防火地域内であれば、建築主事等の確認が必要となります。
選択肢3は、正しいです。
建築物の修繕については、大規模の修繕になれば、一定規模以上の建築物について、建築主事等の確認が必要となります。

平成29年問題18
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
2 長屋の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。
3 下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
4 ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
解説
選択肢4は、誤りです。
共同住宅は特殊建築物に該当します。しかし、類似の用途変更の場合は、規模に関係なく、建築確認不要です。では、ホテルから共同住宅への用途変更の場合は、類似の用途変更になるのか。この点は、類似の用途変更にはなりません。
以上より、共同住宅は特殊建築物に該当しますので、その床面積の合計が200㎡を超える場合は建築確認が必要になります。そして、選択肢の共同住宅では、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡とあり、200㎡を超えるので、選択肢のケースでは、建築確認が必要となります。
平成2年問題21
建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100㎡のときでも、建築主事の確認を受けなければならない。
2 延べ面積が200㎡の下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合、建築主事の確認を受ける必要はない。
3 都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)において、延べ面積が10㎡の倉庫を新築する場合、建築主事の確認を受けなければならない。
4 延べ面積が150㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建であれば、建築主事の確認を受ける必要はない。
解説
選択肢1は、正しいです。
木造の建築物の建築確認の要件は以下の表の通りです。

但し、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築・改築・移転しようとする場合で、その増築・改築・移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、建築確認は不要とされています。従って、選択肢の建物の改築に係る部分の床面積が100㎡のときは、10㎡以内ではないので、建築確認が必要となります。
選択肢2は、正しいです。
下宿から寄宿舎への用途変更は、類似の用途変更に該当するため、建築確認は不要です。
下宿とは、一定期間の契約で部屋を間借りさせる建物を指します。
寄宿舎とは、1つの建築物に複数人が同居し、共用の便所・台所・浴室などが1ヵ所〜数ヵ所に設けられる居住施設を指します。
選択肢3は、正しいです。
都市計画区域内において、建築物を新築する場合は、その用途、規模を問わず、建築確認が必要です。
選択肢4は、正しいです。
自動車車庫は、特殊建築物に該当します。
特殊建築物は、200㎡を超える場合、建築確認が必要となります。従って、選択肢の建物は、延べ面積が150㎡になるので、一定の特殊建築物には該当せず、建築確認は不要です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
