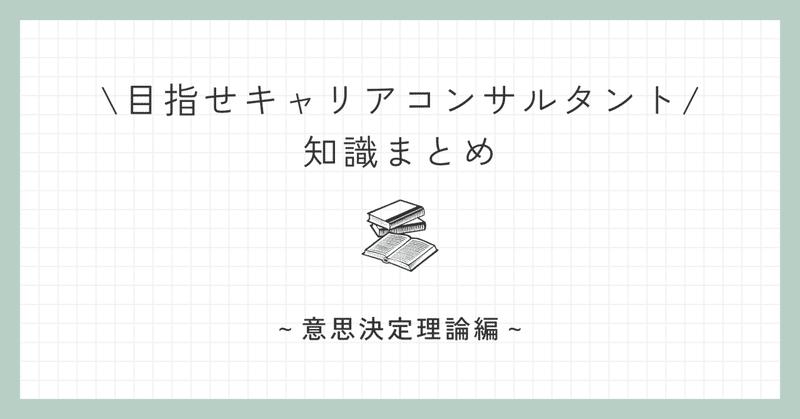
\目指せキャリアコンサルタント/ 知識まとめ~意思決定理論編~
こんばんは。Machiです。
キャリアコンサルタント資格試験に向けて、定期的に知識をアウトプットしていくこの連載。
今回は「意思決定理論」編!。
気になる分野をさくっと復習できるように文字数少なめにします◎
この記事がみなさんのお役に立てれば嬉しいです。
一緒にキャリアコンサルタント試験までがんばっていきましょう!
🙇お願い🙇
筆者が調べてまとめているものです。
もし修正点等ございましたら、他の読者のみなさんの学びにもなりますので、コメントいただけますと大変ありがたいです。
今日のお題:意思決定理論
キャリア形成で重要なポイントである意思決定理論。
意思決定理論で重要な登場人物はこの5人(6人)です。
ティードマン&オハラ:キャリア意思決定理論 8段階
ジェラット:連続的意思決定プロセス 3段階、積極的不確実性
ヒルトン:認知的不協和理論
クランボルツ:意思決定モデル 7段階、計画された偶発性
ディンクレッジ:意思決定の8スタイル
数字が出てきたのと、間違えそうな単語がたくさん出てきましたね……
この後、整理していきます。
方策実行の6ステップ

登場人物の整理をする前に、方策を実行するためのステップを整理します。
大事なポイントは<主体はクライアント>だということ。
意思決定を行うのはキャリアコンサルタントではなく、あくまでクライアントなので、誘導しないようにすること。
ティードマン&オハラ
ティードマン&オハラはキャリア意思決定理論を8段階×2フェーズで表現しています。

ジェラット
ジェラットの意思決定理論は「連続的意思決定プロセス」。

積極的不確実性
意思決定の中に「不確実性」を積極的に利用していこうとする考え方。
未来を予測することはできないため、客観的で合理的な戦略だけではなく、主観的・直観的な戦略も必要ということ。
不確実な時代なので、柔軟に対応していくことが大事をいうことですね。
ヒルトン
心理学の考え方を用いて意思決定理論を展開したのがヒルトン。
「眠い」のに「夜更かししたい」ときってありますよね。
心の中で、矛盾が起きている状態が認知的不協和です。

クランボルツ
職業選択は、過去の出来事と将来の出来事をむずびつけて意思決定していくことだと唱えるのがクランボルツ。
その意思決定プロセスに影響を与えるのが次の4つです。
①遺伝的特性・特別な能力
性差、民族、身体条件、性格、知能など
②環境条件や出来事
自分ではコントロールできない社会・経済・政治的な環境や出来事
③学習経験
道具的学習経験:自分が直接やってみて得られた学習経験
連合的学習経験:他人を観察して得られた学習経験
④課題接近(解決)スキル
問題解決能力、課題への取り組み方
クランボルツが唱える意思決定モデルは7段階。

そして、クランボルツといえば、「計画された偶発性」理論!
(この理論、好きなんですよね……)
偶然の出来事をいかにチャンスにするか。
「偶然を活かしていきましょう!」という理論です。
偶然をキャリアに活かしていくために意識していくべき5つのスキルがあります。

この理論が好きすぎて、記事を書きまして……
なんとコンペに採用していただきました。
よろしければ、お読みください。
ディンクレッジ
最後にディンクレッジ。意思決定のスタイルを8つに分類しました。
前提として、次の7つの行動を意思決定のプロセスとしています。
①決定内容の明確化
②情報収集
③選択肢の明確化
④根拠の評価
⑤選択肢の最終決定
⑥行動
⑦決定と結果の振り返り
・・・①に戻る
この行動をやるのかやらないのか等でスタイルを分けています。

(わたしは延期型の気がします……)
まとめ
今回は意思決定理論をまとめました。
改めて、ポイントです。
ティードマン&オハラ:キャリア意思決定理論 8段階
ジェラット:意思決定の3段階、積極的不確実性
ヒルトン:認知的不協和理論
クランボルツ:意思決定モデル 7段階、計画された偶発性
ディンクレッジ:意思決定の8スタイル
お読みいただきありがとうございました!
よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!
