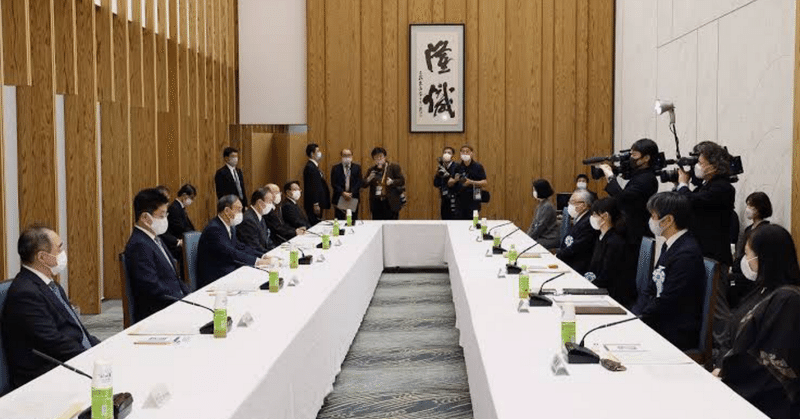
レジュメだけでは不十分だった──4月8日の有識者ヒアリング「レジュメ+議事録」を読む 4(令和3年5月1日、土曜日)
前回の続きです。(画像は官邸HPから拝借しました)
4月8日のヒアリングの中身について、ひと通り検証してきました。4番手の新田均氏までは資料はレジュメだけでしたが、その後、議事録が公開されましたので、5番手の八木秀次氏についてはレジュメと議事録の両方から点検することができました。
議事録を読んで、当然ながら、レジュメのみによる検証では不十分なことが分かりましたので、4方のヒアリングについて、あらためて中身を吟味することにします。〈https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/taii_tokurei/dai2/gijiroku.pdf〉
▽6 ふたたび岩井克己氏──なぜ男系の絶えない制度を考えないのか
岩井氏のレジュメではもっぱら戦後のみの「象徴」天皇論が展開されているように見えました。しかし一方で、歴史的立場から解き起こそうとする和辻哲郎の『国民統合の象徴』を引用しているところには論理的一貫性の無さが感じられることを前回は指摘しました。
あらためて議事録を読んで分かるのは、岩井氏の意外な謙虚かつ慎重な姿勢です。皇太子妃(皇后陛下)を長く苦しめるきっかけとなった「懐妊兆候」スクープで知られる岩井氏ですが、加齢によって円熟されたということでしょうか。
「皇室の長い歴史や様々な天皇の足跡を勉強すればするほど、現代の社会環境との間でどう国民的コンセンサスを取るのかは断定し難く、また、断定するのは非常に不遜であるという気持ちになる」などと述べ、「例外なくずっと続いてきた皇位の継承原則は非常に重いもので、できる限り、ぎりぎりまで大切に考えて対処しなければならない」と訴えています。
しかしそれなら、男系の絶えない制度を模索するのが筋ですが、岩井氏はそうはせずに、「万が一危機が決定的な縁(ふち)にまで来たというときに備え」た、「内親王家」なるものの創設を提唱します。「本当に危機が深まったときに、周りに誰も、内親王すらおられないということにならないようにしておくべきではないか」というわけです。
なぜそのように考えるのか、論拠は天皇とは何か、天皇の役割とは何か、ということになります。そして岩井氏は、古代律令でも「禁秘抄」でもなく、やはり戦後憲法を引き出します。
興味深いのは、その岩井氏が憲法の「世襲」が「hereditary」ではなく「dynastic」と英語表現されていることに注目していることです。そのことは私が小嶋和司憲法論を引用し、何度も言及してきたことで、「王朝の支配」の意味のはずですが、岩井氏は少し違います。
つまり、憲法学者の樋口陽一氏や佐藤功氏を引用したうえで、「敗戦の崖っぷちの中で、なぜ天皇は残ることができて、その後も象徴として定着していき、今も安定的に続いているか」というと、「権力関係とは一線を画したソフトな伝統的・文化的側面の、遠い過去からの歴史的な蓄積、厚み、そういうものではないのかな」と自問自答するのです。
要するに、岩井氏は126代続いてきた「祭り主」天皇の「象徴」性ではなく、近代以降の「立憲君主」天皇の変遷を論じているということでしょう。
岩井氏が亀井勝一郎を引用しているのも、皇室の長い歴史から「象徴」の地位を説き起こすのではなくて、「ある意味では象徴天皇の理論付けを一生懸命に行い、国体は崩れたけれども、象徴天皇という体制になったということを言う」と述べて、あたかも牽強付会の理屈であるかのように論じています。
結局のところ、岩井氏は悠久なる皇室自身の天皇観について吟味しようとしません。敗戦後、天皇は「象徴」として生き残ったのではなく、古来、「象徴」であったことに思い及びません。それが「祭り主」であることに気付かないのでしょう。男系男子によって紡がれてきた祈りの重みに思い至らないとすれば、男系の絶えない制度を模索しようとするはずはありません。できる道理がありません。
岩井氏が議論の慎重さを要求していることには大いに共感できますが、それならなぜ古来の男系継承の維持を訴えないのでしょうか。論理的に破綻してませんか。
▽7 ふたたび新田均氏──皇位の本質を見誤っている
2人目の笠原英彦氏、3人目の櫻井よしこ氏については、とくに付け加えるべきことはありません。補足しなければならないのは、4人目の新田均氏です。
新田氏はヒアリングのあと、「皇位継承が男性を基本としてきた理由」と題する「補足説明資料」を提出し、「祭祀の過酷さ」を指摘しています。〈https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/taii_tokurei/dai3/sankou.pdf〉
女性であっても皇統に属していれば皇祖を祀る資格があるが、とくに女性にとっては過酷である。大嘗祭は古来、厳寒の中で行われきた。明治天皇の大嘗祭において、皇后の御拝は風邪のため行われず、大正天皇の大嘗祭においては、妊娠中のため皇后の御拝はなかった。祭祀の厳修は女性には過酷な義務だからだと述べています。
指摘自体に間違いはありませんが、わざわざ「補足説明」すべきことなのかどうか、疑問です。小泉内閣時の皇室典範有識者会議では、「宮中祭祀の代行」について質疑があり、「今は昔より妊娠・出産の負担は軽い」との発言があったと伝えられましたが、まさに宮中祭祀「簡素化」を進めた張本人・入江相政のように宮中三殿にエアコンを取り付けたらどうかという反論がすぐにも飛び出してきそうです。
要するに、本質的でないのです。本質を見誤っているのです。
新田氏の「祭り主」天皇論は、天皇の役割=「皇祖の祭り主」「日本国家の祭り主」とするものでした。その根拠はヒアリングでは示されていませんが、いわゆる神勅であろうことは容易に想像がつきます。「天壌無窮の神勅」「宝鏡奉斎の神勅」「斎庭の稲穂の神勅」が三大神勅と呼ばれています。皇祖神の命に従い、皇祖を祀り、国と民のために祈るというのが新田氏の「祭り主」天皇観であり、その過酷さを強調しているのです。
さすが神道学者の面目躍如たるものがありますが、違うのです。すでに書いたように、天皇は皇祖の「祭り主」だけではありません。皇祖ほか天神地祇を祀り、公正かつ無私なる祭祀を厳修するところにこそ、「過酷さ」はあります。天皇の祭りは「氏」や「家」の私的な祭りではありません。
神勅が天皇の祭祀の根拠なら、天神地祇を祀る必要はありません。祭場は賢所で十分であり、神嘉殿も大嘗宮も不要です。神饌は伊勢神宮のように米だけでいいはずで、粟をあわせ供する必要性はありません。なぜ天皇は皇祖神ほか天神地祇を祀り、米と粟をささげて祈るのか、新田氏は深く追究していないのでしょう。
天皇の祭祀が神勅に基づく稲の祭りなら、畑作民は疎外感を感じ、天皇は国と民をまとめ上げることはできないでしょう。畑作民には畑作の神がいる。スメラミコトは米と粟を献じて、米の神、粟の神に祈るからこそ、スメラミコトなのです。神勅ばかりに注目し、民の側の信仰に目を向けないのは神道学の限界です。
歴史上、女性天皇は存在します。しかし愛する夫があり、妊娠中・子育て中の女性天皇は存在しません。それは女性差別ではなく、新田氏のいう「過酷さ」が理由でもなく、逆に夫や子供への熱い思いを肯定し、女性の特性と価値を十分に認めるがゆえのことではないでしょうか。
新田氏は「補足説明」するとするなら、そのことを指摘すべきだったと思います。まことに残念というほかはありません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

