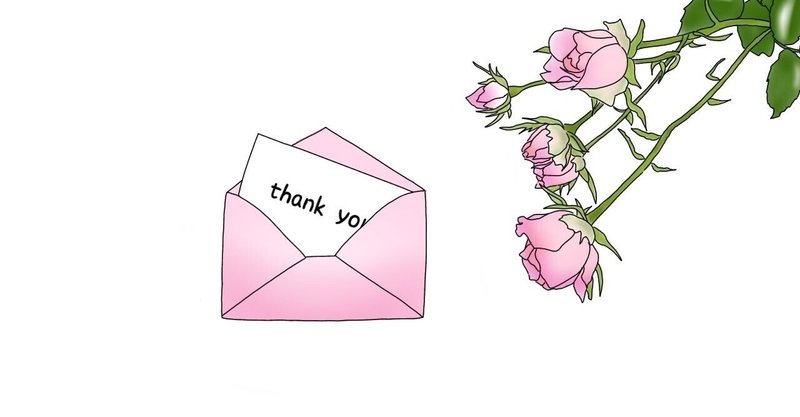
なぜ『手紙』は先を読ませる力があるのか?
あれは、たしか、去年の暮れのこと。友人のお子さんからお手紙をもらいました。そこには、とっても可愛らしい文字が綴られています。動物のキャラクターが描かれた便箋には、きらきらのシールがたくさん貼られてありました。
お手紙をくれたその子は幼稚園生です。それでいて文字を書いている。一生懸命書いている。筆圧が高い。ピンクとか、キイロとか、ミズイロとか、いろいろな色のペンで彩られた文字は、眺めているだけで自然と頬がゆるんでしまう。
ちなみにその子のママさん(友人)からも手紙を頂きました。どちらも同じく嬉しいです。もらったお手紙を何度も何度も繰り返して読んでしまうのは、やはり嬉しいからでしょう。
手紙には読ませる力が備わっている。猫目は手紙というものの魔力に改めて気づかされました。そこで本日は手紙をテーマにお話ししていきたいと思います。
長い手紙も必ず最後まで読んでしまう不思議
小学生時代、猫目はクラスの友人と手紙のやり取りをしていました。そのころに貰った手紙が机の引きの中に眠っているのを思い出して、さっそく掘り出してみて、思わず猫目は感嘆を洩らします。
「長ーーーーーーーーーーーーーーーい」
封筒を開封するとそこには、キャラクラーの書かれた便箋にびっしり鉛筆での文字。それが数枚・・・五枚も・・・ありました。当時の記憶がほんの僅か思い返されます。小学校の教室の匂いも一緒に思い出されたので、猫目はきっと待ちきれなかったのでしょう。自宅ではなく教室で手紙を読んでいたのでしょうね。
それら手紙には起承転結なるものは無く、しかし事情と心情はしっかり書き留めてありました。誰それが好きだとか、誰先生がこうこう、それで私はこんなふうに思っている、お母さんがどうこう、などなど。
支離滅裂と言ったら相手に怒られるかな、と思いますが当時は小学生です。彼女よりもきっと猫目の文章の方が一段と支離滅裂だったに決まっています。猫目は作文が得意だったのですが、どうも手紙となると、うまく書けていません。
猫目が友人に充てた手紙の残骸がなんと他の手紙といっしょに、引き出しの奥に眠っていました。猫目はそれら自分が書いたであろう手紙を読んで、改めて仰天。発狂しそうでした。なんじゃこれ、です。
恥ずかしすぎてお見せすることは出来ませんが、とにかく、まあ、ひどいのなんの。庭に大きな犬(熊?)が出た、とか、電線まで空を飛んだとか。よくもまあ。そこんなことを書けたものです。これではまるでファンタジー作品です。文章をすべて読んだところで、伝えようとしている事柄が一から十までわからない。不明瞭が際立っています。
頭を抱えるどころか、自分の手紙を読み返しているうちに猫目の頭から、恥ずかしさのあまり湯気があがるくらいです。比喩です。顔中が赤らんでいたことは事実です。とにかく意味不明な手紙に困惑しました。
それでも最後まで読んでしまうのはなぜでしょうか? 一体全体、手紙と言うものは、どうしてこんなにも人に読ませる力があるでしょう?
ひとつの結論としては自分に向けられて書かれたものからでしょう。自分自身に向けられた文章ならば人は、どれほど長い文章でも読む、ということでしょう。そこには人間の本質的な問題が関係しています。
これは誰しも自分のことに一番興味があるという心理からきているものです。つまり手紙というものは、そもそも自分に向けられて書かれた文章です。そうなると俄然興味が湧いてきます。最後まで目を通さないわけにはいかなくなります。「読まなくては」でなく「読みたい」と心が動きます。
この原理の発生により、悪口の全文を読んでしまうのでしょう。猫目は悪口を最後まで読む必要性は無いと思っています。ですが読んでしまうのが人間の心理です。気にしなくなる、のには時間が掛かります。習慣にしてしまうのが最もですが、それまでは悪戦苦闘です。
猫目も学生の頃はそういう悪口の書き込まれた文章(ブログ等)は全文隈なく読んでいました。時間の浪費です。改善を求められていない、本質の無い、罵詈雑言、悪口ばかりの文章は即刻捨てましょう。消去しましょう。
手紙を書くことは何よりも頭を使う
SNSでエッセイを書く、記事を書く、ブログを書く、それらは全てどうしても相手を忘れてしまいがちです。意識的に相手を脳に彷彿させる必要があります。日記ともなれば相手は自然に未来の自分となるはずです。
一方で手紙というのは、相手ありきではじめて成立するものです。つまり相手を想定していない手紙は、それは作品であり、手紙という目的の遂行には沿いません。
真っ向から相手(実在する個人)のことを想いながら書く。容易なことではありません。むしろ猫目は手紙こそが頭を使う最高潮の文章であると思っています。
久しぶりに手紙を書こうものなら、その難しさときたら・・・もちろん慣れていないという事もあるのでしょう。構成うんぬんの前に相手の気持ちを汲み取るのが難しい。そして正確に伝わる文章でなくては相手は勘違いをしてしまう・・・それら思考は容易に猫目のペンを止めます。
何枚も書き直す手紙
なんと猫目は一日費やしても手紙を書き終えることが出来ませんでした。驚愕の事実です。たった便箋一枚です。これには猫目も狼狽の色を隠しきれず、日を跨いでも、なおうまく書ける気がしませんでした。おかしい。絶対におかしい。
とにかく手紙を書くのは頭を使います。おかげで滅多に食べない飴玉をガリガリ噛み砕きながら、ううと低く唸りをあげております。なぜこんなに頭を使うのか。それは相手が明確だから。
改めて猫目は、文章を書くときに相手(読者)のイメージを明確にすることの必然性を感じました。
手紙を綴るように小説を綴る
よく海外の小説などでは、表紙のあたり目次前などに『親愛なる〇〇・〇〇へ贈る』という一文を発見します。相手(読者)の人物像がはっきり据えられているのですね。
大勢の人を対象とし書くのでは、その内容はブレてしまいます。一定の人物に絞った上で執筆をすることの大切さ、それを猫目は手紙から改めて学びました。
間書体に学ぶ
さて。現在『芥川竜之介 書簡集/石割透 編』を拝読しています。率直に面白いですね。飽きずに読んでしまう。やはり手紙の力は偉大です。とくに相手によって筆の具合が変わるところがすごく、いい。なんだか告白文を読んでしまっているみたいで・・・いろいろとどきどきします。
芥川竜之介の場合だと、とくに『塚本文子』と『夏目先漱石』へ贈る手紙は引き込まれるように読んでしまう。次の書簡集は夏目漱石で決まりです。読みたい書籍がたくさんあります。自分は読むのが遅いのでたいへんです。
なんだか今日は、ひどくカタコトな文章な気がします。なぜでしょう。最近文章がうまく綴れていない気がしてなりません。しかし焦ってはいけませんね。焦りは禁物です。焦っても良いことがあまりない。
それでは
ながーい文章を読んでくださったあなたさま。きょうも心から感謝しております。いつもいつも読んでくださり嬉しい限りです。ありがとうございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
