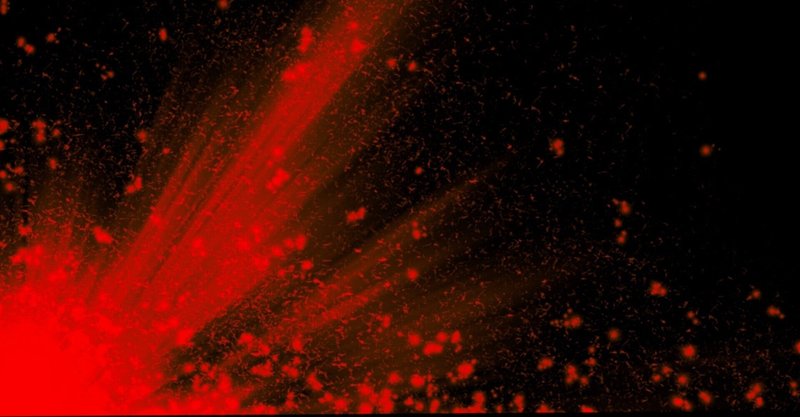
物語のタネ その九『吸血鬼尾神高志の場合#26』
「ハロウィンね」
「ハロウィン⁈」
ドラキュラ会長の言葉に皆一斉に声を揃えて反応した。
会長はちょっと顎を突き出しながら自慢げ?にぐるりと僕たちを見回した。
「そう、ハロウィン。街に沢山のゾンビがいても不思議じゃない唯一の日よ」
「確かに」
尾神さんがトマトジュースのストローを咥えながら頷く。
「となると、中々手強いですね」
村田さんが眉間に皺を寄せた。
「最近のハロウィンコスプレはレベルが高いですから、街の中のゾンビ、どれが本物か見分けがつかないかもしれません」
「確かに、去年のハロウィンの時、六本木のお店もハロウィンナイトで。そこの女の子でメイク勉強している娘がいてね。超気合入れてゾンビメイクして来たのよ。もう、本物より本物っぽいっていうね。正直、あれはちょっと引いたな。俺の好みとしては、ちょっとだけでいいんだよね、やっぱり可愛くないとさ、ゾンビも。俺としては、目の下がちょっと青くて頬のあたりにハート型の傷がある、なんてのがいいな。な!勇利」
「な!って、知りませんよ。それ、ゾンビの話じゃなくて尾神さんのキャバ嬢の好みの話じゃないですか」
「とにかく、昨今のハロウィン事情を考えると、ゾンビたちが行動を起こすにはもってこいの状況であるということは確かですね」
ハールマンさんが話を軌道修正。
「そうね。とにかく、ヴァンパイアの名にかけて全力で阻止するわよ」
「会長、どんな策で行きましょうか」
尾神さんがグイッと前のめりになって聞く。
「とにかく世界中のうちの社員たちをここ東京に集めましょう。そして、ゾンビに噛まれた人がいたらすぐに血を吸い取るのよ」
「ゾンビに噛まれたと思ったら次はヴァンパイアにですか。忙しいですね、その人」
「仕方ないじゃない。ハロウィンだし、モンスターフルコースを堪能して貰いましょうよ」
「ハロウィン、本来そういう日じゃないですけど」
「さっきキャバクラのハロウィンパーティを熱く語っていたアンタが何言ってんのよ」
「あ、ま、スミマセン」
チューとトマトジュースを飲む尾神さん。
「しかし、会長、それだとイタチごっこになるだけですよね」
ハールマンさんは冷静だ。
「そうね、ハールマン、アンタの言う通り。ゾンビの血を吸い出しているだけでは根本的な解決にはならないわ」
「親玉のボーイを消滅させたら、と言う話もありますが、そのボーイは、多分もう物理的に消滅している可能性が高いですよね」
「多分、既にもうね」
研究室に重い沈黙が流れる。
ゾンビたちが噛んだ人を見つけて血を吸い出す。
どこで誰をゾンビたちが噛むか分からない中、その作業は世界中のヴァンパイアを総動員したとしても、確実に成果を出せるとは言い切れないだろう。
むしろ、難しい・・・。
そして、彼らのコントロールタワーであるボーイの肉体はこの世に存在せず、ゾンビたちの精神世界にその存在を移してしまっている・・・。
どうしたら良いのか?
考えても、何も良い策は思いつかない・・・。
「一つだけ、ボーイを、ゾンビたちを倒す方法はあるわ」
重苦しい空気を破り、ドラキュラ会長が口を開いた。
「会長、それは?」
ハールマンさんと尾神さんが同時に聞いた。
「アタシとボーイの直接対決」
皆の頭の上に“?“が浮かぶ。
「でも、もうボーイは物理的には存在していないんですよね?」
代表してハールマンさん。
「そうよ。だからハッキングするの」
「ハッキング?」
「言ったでしょ、血は最古にして最も基本のネットワークだって」
「ええ」
「だから、そこに侵入するのよ」
「どうやって?」
今度は尾神さん。
ドラキュラ会長は、そんな尾神さんをチラッと見て
「尾神はともかく、ハールマン、アンタ、科学者だから分かるでしょ」
「ウィルスを仕込む・・・」
「そうよ。正解」
「でも、そのウィルスって?」
「アタシの血、よ」
皆の頭の上にさっき以上に“?“が並んでいる。
「皆で100人のゾンビにアタシの血を注入するのよ!」
そう言うと、ドラキュラ会長はニヤリと笑った。
・
・
・
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
