
wellbeingとは何か。続編。
前回の記事では、「wellbeing」という抽象概念の「外観をつかむこと」を目的としていました。そのため、あまり私見は交えずにまとめ記事にしたつもりです。
今回は、「wellbeing」をわたしはどう捉え、どう扱っていくのか?をテーマに書いてみたいと思います。
●wellbeingへのもやもや
前回、wellbeingを理論から眺めたことで、「経済的wellbeingもあれば、心理的wellbeingもあること」、「心理的wellbeingの構成要素は、複数あること」など、先人たちの思考の道筋に触れることができました。言葉の定義は大切にしたいタイプですので、必要なプロセスでもありました。
しかし、その結果、どうだったのか・・・
私は、釈然としませんでした!w
「結局、wellbeingって何なんだ?」というのが、正直な感想でした。読者の方の中にも、もやもやされた人がいたかもしれません。わたしのもやもやの伝播だったら申し訳ないのですが、もやもやしていたのが事実です。
そんなだからこそ、「現実的に、wellbeingをどう扱ったらいいのか?」という次の問いにすぐぶち当たってしまったわけですね。
そこで、ちょっと視野を広げてみました。わたしは、どんな世界をよしとしているんだろう、何に価値を置いていたんだっけ、現代人に何を届けたいんだろう・・・と。
その結果、浮かび上がったのは、「心の豊さ」「自分を知る」「人間性への回帰」という昔から大切にしていたキーワードでした。この変化が多く、スピーディーで、不確かな時代に、「人間が備えておくといいもの、備えておくといいスキル」は、こんなあたりなんではないか?と思っている。そんな原点に戻ってきた。という感じでした。
ならば、「wellbeingから学んだもの」と「自分の大切にしているもの」の共通項を見出せたら、スッキリするかもなと。

●わたしがwellbeingで大切にしたいこと
わたしは、wellbeingを学んだ中で、イギリスの「beyond GDP」という姿勢と「Measuring what matters!!」というスローガンにグッときました!(ちなみに単なる感情論ではなく、それが国の繁栄にどう重要か?などがイギリスでは研究とともによく検討されています。)また、パパート先生の「ネガティブ心理が測れるなら、ポジティブ心理も測れるでしょ?」という発想にもとても共感が持てました。
だから、この4つを大切にwellbeingを扱っていきたい。
①なぜ、wellbeingが大事と思うのか?をはっきりさせること
②こころの見える化をすること
③ポジティブ心理を測ること
④人間性の成長に投資すること
WHYをはっきりさせること。これは、個人にも、コミュニティにも、言えることだと思うのです。自分の人生の目的とか、ありたい姿とか、コミュニティの理念とか、そういったものとwellbingがリンクするならば、その確証の上で、取り組むといい。リンクすると思えないなら、きっとそれはwellbeingに取り組むべきタイミングはない、ということなのではないでしょうか。
そして、測ることのインパクト。②と③はセットみたいなものですが、もっと「こころ」が扱いやすくなったらいいなと思っています。言語化する、数値化するという努力をしないと、扱われないままになってしまう。それこそ、労働時間も、有休消化率も、血圧も、体重も、数値であるから、注目されるし、管理もできるんだろうと思うのです。
また、「質問」というものはとてもパワフルです。問うことによって、相手はその視点を知り、考えます。ですから、「ストレスチェック」のように、ネガティブな側面を聞く質問票だけをやることは望ましいとは思えません。「ポジティブな側面」に光を当てること。色んなポジティブに「あえて気づく」をしていけると良いと考えています。そのために、何か1つ尺度を選んで、測ることから始めてみるのがいいと思っています。
最後に、「人間性の成長、心の成長」という視点です。ここには、「レジリエンスを高める」「教養をつける」「心理的柔軟性を高める」「他者の成長を支援する」など、色んな解が含まれると思います。個人でも、コミュニティでも、目指したい姿に適したテーマを具体的に選んで、プログラムを設定して、そこに投資をしていけるといいのではないでしょうか。そしてのその成果を測ることです。
●wellbeingやポジティブ心理の注意点
なお、「ポジティブ心理を高める」ことは悪いことではないのですが、ポジティブは良い、ネガティブは悪い、という論理にならないように、注意が必要かと思います。「感情は、経験することでインストールされる」という構成主義的情動理論というものがあります。ネガティブな感情も含め、色んな感情を経験し、認識した人は、心が豊かになり、他者の色んな感情をも想像することができるといいます。さらに、ネガティブ感情を抱えた「ありのままの自分を知る」、ネガティブ感情を「消すのではなく、うまく付き合う」というアプローチで心を育んでいくことも重要です。
以上のように、何となくですが、わたしの脳内にあるもの、大切にしているものと、wellbeingとの重なりを考えてみました。
このように「こころ」についてゆっくり考える時間というもの自体に、意味があるような気もしております。
今月もあと数日。みなさまに笑顔がありますように。
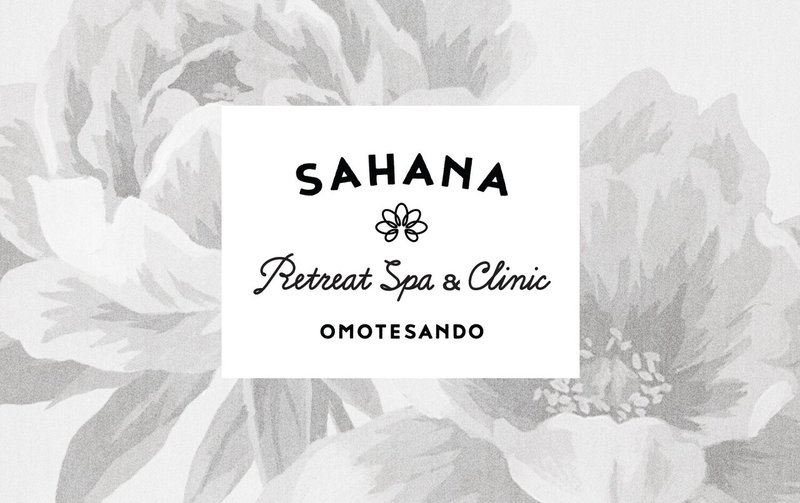
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
