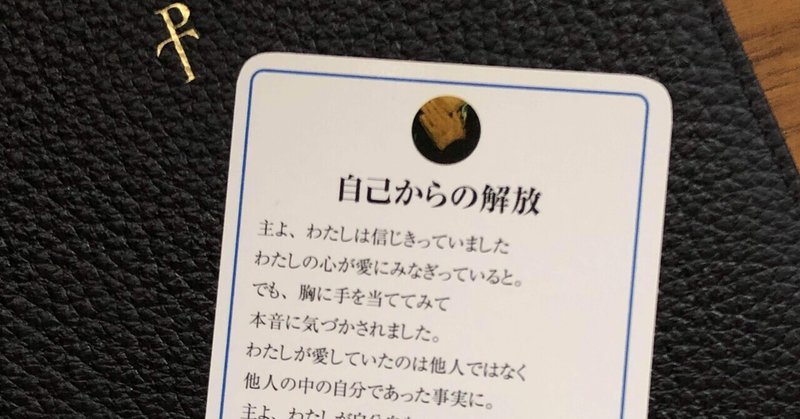
「この自由を得させるために」 ─ ガラテヤの信徒への手紙 ─
「この自由を得させるために」 ─ ガラテヤの信徒への手紙 ─
2006年7月15,16日 第10回妙高聖書講習会
第1講 パウロの伝えた福音
─ 主イエスのピスティスによる義
1.はじめに
(1-1)私たちの不幸
15わたしたちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。16けれども、人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、わたしたちもキリスト・イエスを信じました。これは、律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら、律法の実行によっては、だれ一人として義とされないからです。17もしわたしたちが、キリストによって義とされるように努めながら、自分自身も罪人であるなら、キリストは罪に仕える者ということになるのでしょうか。決してそうではない。18もし自分で打ち壊したものを再び建てるとすれば、わたしは自分が違犯者であると証明することになります。19わたしは神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。わたしは、キリストと共に十字架につけられています。20生きているのは、もはやわたしではありません。キリストがわたしの内に生きておられるのです。わたしが今、肉において生きているのは、わたしを愛し、わたしのために身を献げられた神の子に対する信仰によるものです。21わたしは、神の恵みを無にはしません。もし、人が律法のお陰で義とされるとすれば、それこそ、キリストの死は無意味になってしまいます。
第一講を始めさせていただきます。
今日は何をお話させていただくかと申しますと、ただ今、皆様と拝読したこの「ガラテヤの信徒への手紙」2章1節から21節は、新約聖書の中心、いや聖書全体のへそと言ってもよい箇所です。
皆様もよくご存知と思いますが、この新共同訳では、パウロの真意を正しく表現していないのではないか、否、むしろ根本的に違っているのではないか、という問題提起をさせていただこうかと思います。どう違っているのか、皆様とご一緒に「ガラテヤの信徒への手紙」を通して考えたいと思います。
先ほど皆様とご一緒に歌っていただいた讃美歌の461番「主われを愛す」から次のような思いを抱かされました。まず、この讃美歌の歌詞を見てみましょう。
主われを愛す、
主は強ければ、
われ弱くとも
恐れはあらじ。
わが主イエス、わが主イエス。
わが主イエス、われをあいす。
子どもでもわかる平易な言葉で、福音の何たるかを表現したすばらしい歌詞ですが、実は、この曲の英語の歌詞はちょっと違っています。
Jesus loves me! this I know,
For the Bible tells me so;
little ones to Him belong,
They are weak, but He is strong,
Yes, Jesus loves me! (repeat)
訳してみますと、
イエス様がわたしを愛してくださっている
そんなことはわかってるよ
聖書がそう教えてくれるから。
最初の部分は日本語の歌詞と同じですが、次の「聖書がそう教えてくれるから」という部分が日本語の歌詞には欠落しています。欧米の子供たちはこのように歌って、聖書の重みを幼い頃から植え付けられているのでしょう。私も最初にこの英語の歌詞を見たときに、まさにこれこそ「キリスト教」だなと思いました。
皆様は、少なくとも聖書に興味を持っておられるか、またはよく読んでおられる方々だと思いますが、私たちクリスチャンでさえ、「聖書がそう教えてくれるから」と幼子のように純朴に読めなくなりました。
私たち現代人は近代化に伴い、聖書すら相対化してしまいました。聖書の権威は否定され、歴史文書として、文学作品としてあるいは倫理、宗教の研究の対象となりました。
もちろん聖書は、信仰の対象として崇め奉るものも、聖書無謬主義のように絶対化すべきものではありません。相対化されたことは良いことです。
しかし、もはや伝統的な聖書の読み方はできなくなり、どう読んだいいのか分からなくなりました。
それだけでなく、聖書を通して、主が私たちを「愛してくださっている」ことが、心底実感できなくなってしまったのではないでしょうか。単純明快に「知ってるよ」と言い切る幼子のような姿が、今の私たちにはほとんど見られなくなりました。それは私たちの不幸ではないでしょうか。
また、聖書を通して、イエス様に出会っているのでしょうか? 「お前を愛しているよ」という主の御声を聞いているのだろうかという問いを、懐いていただけたらと思います。
様々な社会問題など不正と不信が満ちあふれる今、私たちは半ば諦めつつも魂のどこかでピスティス(真実)溢れる世界に強い憧れを懐いています。それは、パウロが生きた紀元1世紀のローマ帝国でも同じだったと思います。不信と不安渦巻く世の中で、救いを求めてあがいていたガラテヤの人たちに、初めて伝えられた主イエスの〈福音〉とは一体何だったのか。パウロの生の声を伝える手紙を通して、ご一緒に尋ね求めてみたいと思います。
(1-2)「あなた」とは誰? “You raise me up”の紹介
まずは心安らぐ曲をお聴きいただけばと思います。
「You raise me up(ユー・レイズ・ミー・アップ)」です。歌詞を御覧下さい。
You raise me up
作詞:Brendan Graham
When I am down and, oh my soul, so weary
When troubles come and my heart burdened be
Then, I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up......To more than I can be(*)
?2001 Universal Music Norway/Acorn Music, Ireland
訳してみますと、次のようになります。
落ち込んで、魂がすっかり疲れ果てているとき
困難に見舞われ 心がそれに打ちのめされているとき
そんなときはただ黙して、じっと静かに待っていよう
あなたが来て 私の傍らでしばし佇んでくれるまで
あなたが私を奮い立たせてくれるから、
私は高い山の頂にも立てる
あなたが私を奮い立たせ、
怒濤逆巻く海すら歩ける
私は強い、あなたに担われたとき
あなたに奮い立たされ……
私は、自分以上の自分でいられる
(試訳:横江)
この曲を聴いて、人間を超える存在、神のような存在を感じ、挫折した自分を支え導いてくれているという感想を述べる方もいらっしゃいます。
ここで言われる「you(あなた)」とは誰のことでしょうか?
それは、友達かもしれません。両親や兄弟、家族の場合もあるでしょう。また、先生や上司、同僚かもしれません。
が、私は究極的には主イエスであり、神様ではないかと思います。
ギリシア語で「聖霊」は「パラクレートス」と言いますが、その意味は、傍らに立って私の代わりに語ってくれる人(弁護してくれる人)という意味です。まさにこの「you」はパラクレートスではないでしょうか。
また、この歌詞は人生の真実を言い表しています。
「you」は、ずっと一緒にいてくれるのではなく、困窮で打ちのめされているとき、ふっとやって来て、しばし一緒に佇んでくれる、というのです。だけどそれが私を奮い立たせてくれる。神様のなさる業もそうだと思います。
パウロは「わたしは弱いときにこそ強いからです」(Ⅱコリ12.10)と言いました。まさにパウロは主イエスに担われたときに強かったのです。そのことを今日、ご一緒に学んでみたいと思います。
では早速曲を聴いてください。
You raise me up
〔『ケルティック・ウーマン(Celtic Woman)』
(東芝EMI, TOCP-67890)〕
今お聞きいただいたCDの演奏者は「ケルティック・ウーマン」というグループです。この曲は2005年のノーベル平和賞受賞パーティでも歌われたそうで、この歌が出来たのは2002年ですから、現代の讃美歌だと言ってもよいかと思います。
この「ケルティック」というのは「ケルト人の」という意味です。
実は、これが本日学ぶ、ガラテヤと関係があるのです。
③ガラテヤとは
ケルト人は紀元前1200─700年に中部ヨーロッパに渡来したケルト語を使う民族で、しばし栄えましたが、ゲルマン民族の圧迫を受け、フランス、スペイン、イギリスなどヨーロッパ周辺へ、さらには小アジア半島、現在のトルコにまで移住しました。
その後フランスのケルト人はカエサルによって支配されました。ローマ人はケルト人のことを「ガリア人」、その国を「ガラティア」と呼んだそうです。
ケルト人は自然崇拝の多神教で、ドルイドという神官が司る宗教を信奉し、独自の原語、文化を有し、後にキリスト教が入ってからも独特のキリスト教文化を形成したことで有名です。
その文化遺産は主にアイルランドを中心として現代まで伝えられています。アイルランド出身の「ケルティック・ウーマン」にもその伝統が引き継がれているとのことです。
一方、東に移住したケルト人は次のような歴史を辿りました。
B.C.278年 約2万人が小アジア中央部の高原地帯
(現在のトルコの首都アンキュラ付近)に定住
B.C.189年 ローマに征服され、自治州ガラテヤに
B.C. 25年 小アジアの南部フリュギア、ピシディア、ルカオニア、イサウリアがガラテヤ州に併合
パウロの時代では、小アジア中央部と南部諸州を「ガラテヤ」と呼ばれていたようです。
第一講ではパウロの時代に「何があったのか」「パウロは何を伝えようとしたのか」を、第二講では、その現代的な意義を学びたいと思います。
2.定説に疑問? (パウロの生涯を再現するために)
従来の定説に対する疑問
まず最初に、「定説に疑問」という仰々しい題を掲げました。
先に、ローマ書の講義で、人が救われる根拠は「主イエスのピスティスによる」という福音の奥義を学びました。
しかしその後、キリスト教の長い歴史の中で、この福音のメッセージがだんだん覆われて、違うものになっていきました。
それは福音がいわゆる「宗教」になって行った過程だと言えます。
私たちは伝統的な宗教としての「キリスト教」を伝え聞いてきました。小さい頃から先生や先輩たちから教わったことがしっかり刻まれ、私たち自身の〈定説〉になっています。伝統的な解釈や諸先生、諸先輩の教えを無批判に受け継いで「定説」として固定化して読んでしまっているのではないでしょうか。
しかし、率直に聖書に向かってみると、これまでの〈定説〉では説明がつかないことが多々あることに気付きます。
パウロの生涯についても当てはまりましょう。
パウロの手紙と、彼の生涯を描いた「使徒言行録」の間では大きな開きがあります。
従来の定説の根拠は主に「使徒言行録」の記述によっています。しかし、「使徒言行録」は紀元90年代、つまりパウロが生きていた時より少なくとも40年後に書かれたものなのです。
紀元一世紀では、おそらく実際に生前のパウロに会った人たちの口伝や、著者(伝統的にルカと言われています)の手許に集められた資料などを元に書かれたと思います。また著者は、自身が置かれた当時の状況に合わせ、様々な意図、たとえばキリスト教会はひとつにまとまったものとして内外に示したいという意図などが伺えます。それらに沿うように本来の史実を取捨選択したことも当然予想されます。
それに比べ、パウロの書簡、特にパウロの真性の書簡(ガラテヤ、Ⅰテサロニケ、Ⅰ・Ⅱコリント、フィリピ、フィレモン、ローマの7書簡)は、40年後に書かれた「使徒言行録」とは違って、パウロの生の声が残されています。
今日学びます、「ガラテヤの信徒への手紙」(ガラテヤ書)にはパウロの半生というか、回心前から回心を経てガラテヤの信徒たちと出会うまでのことが、パウロ自身の言葉で書かれています。
それらは「使徒言行録」にほとんど欠落しているか、ないしは触れていても、視点の異なる解釈がなされています。ですから、パウロの真性の手紙を一次資料としてパウロの生涯を再現すると、これまでの「定説」とは異なるパウロの歩みが再現されるのではないかと思います。
《定説と重要な相違点》
まず、最初に指摘せねばならないことは、私たちが教わってきた初代キリスト教の歴史、主イエスの公生涯である「イエス運動」と、弟子たちである「クリスティアノス(キリスト者)(使11.26)の働きは、何か歴史の主役のように見なされていますが、当時の歴史の主流からみれば、それらは見向きもされない脇役以下の存在に過ぎませんでした。
ローマ、ユダヤ当局はもとより、大衆にとっても、数多くある宗教の中の一つ、それもユダヤ教という特殊な宗教の分派運動に過ぎません。ましてやそのキリスト教の中で、パウロたちはさらに傍流中の傍流だったのです。
実は後でお話しますが、パウロはキリスト教の主流から追いやられて、やむなく独立伝道をしたというのが真相のようです。
それは「使徒言行録」に描かれ、「定説」として教えられてきた大使徒パウロの生涯とはずいぶん異なる歩みだと言えましょう。パウロの手紙を克明にそのまま読み、そこから浮かび上がる彼の生涯を再現するとそうなのです。その中でも、特に三つの重要な相違点を取り上げておきます。
①三度の伝道旅行
まず、伝統的にパウロは三回の伝道旅行をしたと言われてきました。その内、第二次、第三次の根拠になっているのは「使徒言行録」の18章21─23節です。
パウロは……エフェソから船出した。カイサリアに到着して、教会に挨拶するためにエルサレムへ上り、アンティオキアに下った。パウロはしばらくここで過ごした後、また旅に出て、ガラテヤやフリギアの地方を巡回し、すべての弟子たちを力づけた。
この箇所は「使徒言行録」の著者の意図的な加筆ではないかと私は思います。
つまり、マケドニア、アカイア地方での伝道の拠点作りをひとまず終え、いわゆる「第二次伝道旅行」の結果報告を、エルサレム本山とアンティオキア母教会にしたという意図が伺えます。
実際は、18章19節から19章1節に接続し、コリントでメドがついたパウロ一行は次の伝道の拠点をアジア州の都エフェソと定め、そこで精力的に伝道したというのが実情ではないかと私は想像します。
また、この「使徒言行録」の記述が事実だったとしても、その後に書かれたパウロの真性の手紙からは、エルサレム本山とアンティオキア教会から具体的な援助を受けた形跡は伺えません。
つまり、定説ではシリアのアンティオキア教会を母教会とする伝道旅行となっていますが、アンティオキア教会でのペトロやバルナバと衝突してからはアンティオキア教会の支援のもとでというより、パウロと同労者たちが独力で伝道活動をなし、アジア、マケドニア、アカイアなどエーゲ海沿岸地域の主要都市にエクレシアを形成していったと推察する方が史実に近いように思います。
ただし、パウロはエルサレム使徒会議での約束、エルサレムの貧しい聖徒たちを援助するために、誤解と誹謗されながらも献金を集め、また文字通り命がけで届けたのでした。
表1では、パウロの真性の書簡から推理される伝道活動と定説による伝道旅行を比較しました。
第一次から第三次伝道旅行と一般に呼ばれている内容を、パウロの真性の手紙から得られる情報を下に推理した結果と比較しました。
表2では、パウロの残した真性の書簡から推理される伝道された地域とエクレシアが形成された都市を一覧表にまとめました。
表1 定説とパウロ書簡からの推理の比較
定説による伝道旅行(使徒言行録) 真性パウロ書簡からの推理
第一次(13.8〜14.28) バルナバと伝道(キプロス、南ガリラヤ地方)
第二次(15.40〜18.22) 独立伝道(南ガリラヤ→マケドニア→アカイア→エフェソ)
第三次(18.23〜21.16) 独立伝道(エフェソを中心とした環エーゲ海地域伝道)
表2 パウロの伝道地域と書簡(真性のパウロ書簡により推測)
伝道地域 教会形成された都市名 関係するパウロの真性書簡名
南ガリラヤ イコニオン、リストラ、デルベ等 「ガラテヤ書」
マケドニア フィリピ、テサロニケ、ベレア等 「テサロニケ書」「フィリピ書」
アカイア コリント、ケンクレアイ等 「Ⅰ・Ⅱコリント書」
アジアほか エフェソ、コロサイ、ラオデキア、ヒエラポリス等 「フィレモン書」ほか
②ガラテヤ教会の所在地は?
次に、この「ガラテヤの信徒への手紙」の宛先に関する定説です。従来「北ガラテヤ説」と「南ガラテヤ説」があり、論議されてきましたが、「北ガラテヤ説」が定説とされてきました。その根拠も「使徒言行録」の短い記述が上げられてきました。また、「ガラテヤ書」が晩年の「ローマ書」と内容的に近似することから、執筆年代も第三次伝道旅行末期と推定されることも根拠とされてきました。「使徒言行録」の根拠となっている箇所は次の二箇所です。
いわゆる「第二次伝道旅行」の途上で、小アジアを縦断するようにシリア・キリキア地方からトロアスを経てマケドニアに向かうという旅程の記述の中で、「フリギア・ガラテヤ地方を通って」(16. 6)とあります。
また、「第三次伝道旅行」でアンティオキア教会からエフェソへの途上を「ガラテヤやフリギア地方を次々に巡回し」(18.23)と記述しています。これらが首都アンキュラを中心とした「北ガラテヤ」にパウロが伝道し、そこがこの手紙の宛先とする説の聖書的根拠となっています。
しかし、この二箇所は①と同様に、「使徒言行録」の著者による繋ぎの文章ではないかと類推されます。
また、真性のパウロ書簡群には「北ガラテヤ」にエクレシアが存在したことを明示する具体的な記述は認められません。
これに対して「南ガラテヤ説」に立ってみると、パウロの有力な弟子であるテモテが南ガラテヤのリストラの出身であること、「ガラテヤ書」では、「バルナバ」の名前が読み手側には当然承知であることを前提で使用されていること(バルナバは第一次伝道旅行でパウロと同行し、南ガラテヤ地方を伝道した)、他のパウロの真性の手紙には見られない点として、アンティオキアでのペトロ・バルナバとの衝突の直後の切迫した内容が書かれていることから、記述年代がアンティオキア事件直後の49年から50年とすると、「第二次伝道旅行」の出立直後で、その時点では未知の「北ガラテヤ地方」というより、先に伝道で訪れた実績のある「南ガラテヤ」と見なす方が妥当だと思います。
最初に申しましたように、パウロの生の声に率直に耳をかたむけるためにも、一次資料であるパウロの真性の書簡を中心に読んでみたいとおもいます。
3.パウロの驚き
(3-1)「ガラテヤ書」の意義
〈ガラテヤの信徒への手紙〉
この書簡は、パウロが主イエスの福音を真っ向から証した彼の生の声が残されています。
歴史的にも第一級の一次資料です。
しばしば「自由」の書、宗教改革の原点ともなった書とも言われ、中でもルターはこの書を「我が妻」と呼んで尊んだと言われています。その意味でも、近代社会の基本的、普遍的概念である〈自由〉形成の歴史を語る上で、避けて通れない書です。
にもかかわらず、近代化し、先の敗戦を経て「自由」を国の基本(憲法)とする我が国では、この自由の真意がほとんど顧みられず、むしろ誤った自由理解が氾濫しています。戦後60年を経て今や、人格や社会を崩壊させる危機的状況におかれています。どうしてでしょう。内村鑑三は「解放」という文で次のように述べています。
解放もまた近代人絶叫の一である。彼らは社会的伝習より、軍国的偏見より、宗教的拘束よりの解放を叫びつつある。彼らのある者はヱホバの神よりの解放をさえ叫んで憚らない。……
まことに罪はすべての束縛の中に最も重きものにして、すべての束縛の因(もと)である。しかれども近代人はこの事を解せず彼らは罪よりの解放を要求しない。ゆえに彼らは解放を叫ぶに関せず依然として旧(もと)の奴隷である。彼らは民主主義、社会主義、労働組合によりてすべての拘束より自己を解放したりと信じつつあるもなお依然として前(さき)の奴隷である。
神はその子イエスキリストにありてすべて彼を信ずる者を罪の束縛より解放し給うた。真正の自由はここにある。解放がここに始まらずしてその忽焉(こつえん)として浮雲のごとくに消え去るは知るべきのみである。
(1920年、内村鑑三『勝利の生涯』下、264ページ)
〈真の自由〉とは、〈罪〉からの解放であり、主イエスの福音はまさにそれそのものです。
しかし、私たちは〈罪〉が何かすらわからないため、福音が罪からの解放(つまり〈自由〉)であることもわからないのです。ですから私たちにとって大切なことは、私たちが捕らわれている〈罪〉の悪魔的実体を暴き、そこからの解放である〈主イエスの福音〉を証言することです。
正にそれを中心命題にしたのが「ガラテヤ書」です。ここに「ガラテヤ書」を学ぶ今日的意義があります。
(3-2)パウロの驚愕
では、「ガラテヤ書」を読んでみましょう。まず冒頭(1.1-10)から衝撃的な発言に出会います。
人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストと、キリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされたパウロ、ならびに、わたしと一緒にいる兄弟一同から、ガラテヤ地方の諸教会へ。……
キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなたがたがこんなにも早く離れて、ほかの福音に乗り換えようとしていることに、わたしはあきれ果てています。ほかの福音といっても、もう一つ別の福音があるわけではなく、ある人々があなたがたを惑わし、キリストの福音を覆そうとしているにすぎないのです。しかし、たとえわたしたち自身であれ、天使であれ、わたしたちがあなたがたに告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするならば、呪われるがよい。わたしたちが前にも言っておいたように、今また、わたしは繰り返して言います。あなたがたが受けたものに反する福音を告げ知らせる者がいれば、呪われるがよい。
「わたしはあきれ果てています」は、タウマゾーで「(腰を抜かすくらい)びっくりする」の意味です。驚いて言葉もない、信じられない、と言っています。
「呪われるがよい」はギリシア語で「アナテマ・エストー」と言います。これは「アナテマ」が神の奉納物を意味し、神に奉納して復讐をゆだねること。転じて「呪うこと」を意味するようになったそうです(新約聖書ではここの他にはⅠコリ16.22で使用)。パウロはここで「呪われよ」と二回もくり返しています。
これはパウロにとって引くに引けない重大な問題であることと、もはや議論では説得できない乖離すら感じる厳しさ示唆されます。パウロはこのようにしばしば論敵との激しい対決を迫られていました。パウロの伝道の歩みは闘いの生涯でもありました。
「ガラテヤ書」の中の直接的な論敵批判の例をあげると次のようなものあります。
「あなたがたをかき乱す者たちは、いっそのこと自ら去勢してしまえばよい」(ガラ5.12)。
「肉において人からよく思われたがっている者たち(ガラ6.11)」、「物分かりの悪いガラテヤの人たち(ガラ3.1,3)」などです。
他の書簡で見られる激しい非難の言葉の例としては、「あの犬ども(フィリピ3.2)」、「偽使徒、ずる賢い働き手(Ⅱコリ11.13)、「キリストの使徒を装っている」「サタンでさえ光の天使を装う」(Ⅱコリ11.13-14)、「盲人の案内者、闇の中にいる者の光、無知な者の導き手、未熟な者の教師(ローマ2.20、論敵を皮肉った言葉)」、「外見上のユダヤ人(ローマ2.23)」など枚挙に暇ありません。
では、なぜパウロはこんなに激しい言葉を使わざるを得なかったのでしょうか。それは論敵の影響がかなり深刻に及んでいたからでしょう。まさに福音の本質を巡るもので、パウロの伝えた福音から離れそうになっていました。
キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなたがたがこんなにも早く離れて、ほかの福音に乗り換えようとしていることに、私はあきれ果てています。(1.6-9)
あなたがたは、よく走っていました。それなのに、いったい誰が邪魔をして真理に従わないようにさせたのですか。(5.7)
それは「隷属状態」に復帰することを意味します(4.8-11)。
ところで、あなたがたはかつて、神を知らずに、もともと神でない神々に奴隷として仕えていました。しかし、今は神を知っている、いや、むしろ神から知られているのに、なぜ、あの無力で頼りにならない支配する諸霊の下に逆戻りし、もう一度改めて奴隷として仕えようとしているのですか。あなたがたは、いろいろな日、月、時節、年などを守っています。あなたがたのために苦労したのは、無駄になったのではなかったかと、あなたがたのことが心配です。
パウロの伝えた福音は、「〈罪〉の隷属からの解放」つまり〈自由〉であったのに、彼らは再び「奴隷の軛」(5.1)に再びつながれようとしていたのです。具体的には彼らは救いの保証として割礼を受けようとしていました。
もし割礼を受けるなら、あなたがたにとってキリストは何の役にも立たない方になります。……律法によって義とされようとするなら、あなたがたはだれであろうと、キリストとは縁ゆかりもない者となれ、いただいた望みも失います。(5.2-6)
肉において人からよく思われたがっている者たちが、ただキリストの十字架のゆえに迫害されたくないばかりに、あなたがたに無理やり割礼を受けさせようとしています。……あなたがたの肉について誇りたいために、あなたがたにも割礼を望んでいます。(6.12-13)
この問題は、パウロが伝える福音の真価が問われる抜き差しならぬものを含んでいました。
つまり福音の奥義に直結する問題であったのです。
だから、パウロは「アナテマ・エストー」と激しい言葉を吐いてまで叱責せねばならなかったのです。それは福音を曲げる行為でした。
何がどう曲げられているのか、それが重要です。パウロはこれに続いて自分自身の歩みを述べています。自分のことを振り返ることによって、彼が受けた福音がどういうものかを伝えようとしたわけです。自分がどのように神様に導かれ、恵みを受けてきたかをありのままに語るのが、本当の証しでしょう。パウロもそうでした。誰かからこう教わったからとか、何々先生がこう言っているから、ではないのです。自らの体験から語るのです。それが何であるかを学ぶためには、パウロの歩みを彼自身の言葉によって振り返る必要があります。そのために、パウロの真性の書簡をもとに、特に福音とは何かと絡め、彼の生涯の一部を学んで見たいと思います。
4.パウロの生涯(一次資料を中心に再現)
(4-1)回心前のパウロ
ガラテヤ書にはパウロ自身の言葉で、自分の半生が語られています。まず回心前の彼の生き様です。
あなたがたは、わたしがかつてユダヤ教徒としてどのようにふるまっていたかを聞いています。わたしは、徹底的に神の教会を迫害し、滅ぼそうとしていました。14また、先祖からの伝承を守るのに人一倍熱心で、同胞の間では同じ年ごろの多くの者よりもユダヤ教に徹しようとしていました。(1.13-14)
「フィリピの信徒への手紙」3章5─6節にも同じような表白がなされています。
わたしは生まれて八日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤミン族の出身で、ヘブライ人の中なヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心の点では教会の迫害者、律法の義については非のうちどころのない者でした。
パウロス、ローマ式ではPaulus(パウルス))はおそらく家系名(cognomen)で、「小さい」という意味だそうです。もしかしたら、パウロは自分の名に、神の前に低く小さな存在という福音的意義を自覚していたかも知れません。
「使徒言行録」によると彼のヘブライ名は「サウル」とありますが、パウロは手紙の中で一度も「サウル」と自称していません。ベニヤミン族出身ですので、彼の両親が初代イスラエル王「サウロ」にあやかって命名した可能性はあります。
ただ、「使徒言行録」の著者ルカが、パウロを良きユダヤ人として登場させるときに「サウロ」を使用し、また13章9節以降からは「パウロ」と呼び異邦人伝道者として描くという意図的手法とみることもできるそうです。
彼はキリキア州のタルソスに生まれ、ユダヤ人として厳格に育てられ、青年期にはエルサレムに上ってファリサイ派に属していたようです。職業は家業でもあったテント職人(革加工、布細工など)でした。
(4-2)パウロの回心《紀元32−25年頃》(ガラ1.15−16)
しかし、わたしを母の胎内にあるときから選び分け、恵みによって召し出してくださった神が、御心のままに、御子をわたしに示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされたとき、わたしは、すぐ血肉に相談するようなことはせず、17また、エルサレムに上って、わたしより先に使徒として召された人たちのもとに行くこともせず、アラビアに退いて、そこから再びダマスコに戻ったのでした。
ここがいわゆるパウロの回心の部分です。「使徒言行録」には三度(9.1-19, 22.6-16, 26.12-18)も詳細な記述がありますが、パウロ自身による一次資料には、この箇所も含めて以下の数カ所に僅かに触れられるだけで、詳細な記述は一切ありません(ルカの記事の種は、パウロ自身に遡る伝承かもしれませんが)。同様の消息を他の手紙にも認めています。
わたしたちの主イエスを見たではないか。(Ⅰコリ9.1)
そして、最後に、月足らずで生まれたようなわたしにも現れました。(Ⅰコリ15.8)
わたしの主イエス・キリストを知ることのあまりのすばらしさに、今では他の一切を損失とみなしています。キリストゆえに、わたしはすべてを失いましたが、それらを塵あくたとみなしています。(フィリピ3.8)
わたしは、キリストとその復活の力を知り、その苦しみにあずかって、その死の姿にあやかりながら(原語「シュンモルフェー」=共にモルフェーを同じくされて)、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。」(フィリピ3.10,11)
これらのパウロ自身の証言から、パウロの回心は復活された主イエスの顕現だったと言えましょう。
実は、「回心」というのは、「過去の罪の意志や生活を悔い改めて神の正しい信仰へ心を向けること」(広辞苑)とあるように自覚的に為されるものを指しますが、パウロの場合は思いも掛けず、正に想定外に、復活の主イエスの顕現に遭遇したのでした。
主イエスの教えの何たるかも知らないまま、否むしろ主イエスの教えは異端だと受け止めていました。
ですから、彼は教えを聞いて入信したのではないのです。自ら厳しく求道し、信仰告白してクリスチャンになったのではありませんでした。
むしろ、ユダヤ教徒として誰よりも熱心に、律法に忠実であろうとして、当時異端視されていたクリスチャンの迫害に狂奔していました。
その途上で、パウロがまったく予想だにしない形で〈復活の主〉の顕現を受けたのでした。それまでユダヤ教の優等生だったパウロの生き方そのものが完全に否定された出来事でした。まさに打ちのめされた〈=死んだ〉瞬間でもありました。ですから、むしろ信じ得なかったのに、信じる者とされたというか、強引に引き寄せられたとでも言えましょう。彼はそれを「啓示によって示された」と表現しています。
《パウロに啓示された福音とは》
この時の体験がパウロの原点でしょう。
主イエスによって完膚無きまでに打ちのめされたのです。それまでの自分が完全に葬られました。まさに茫然自失、生きる指針を見失ったのでした。
その消息は「使徒言行録」での物語にある程度投影していると思われます。パウロは人の手を借りてダマスコに連れて行かれ、三日間「目が見えず、食べも飲みもしなかった」ようです。
それにも拘わらずこの挫折ともいえる体験は、主にあって新しく創造され、新たな出立の時でもあったのです。
これはいわゆる「回心」ではありません。
パウロはまったく無自覚で、想定外の出来事だったからです。
しかし、それこそ何にも代え難い〈福音〉であるという消息を、パウロはこの後、生涯を通して何とかして説き明かそうと苦労しました。
彼が残した書簡はまさにその結晶であり、それは遺作ともなった『ローマの信徒への手紙』に結実したのでした。
彼は、この後すぐに、「その福音を異邦人に告げ知らせるようにされた」とあり、異邦人伝道の召命を賜ったようです。
その時に「わたしは、すぐ血肉に相談するようなことはせず、また、エルサレムに上って、わたしより先に使徒として召された人たちのもとに行くこともせず、アラビアに退いて、そこから再びダマスコに戻ったのでした」とあります。
ここも非常に重要なポイントです。
彼は、主イエスの召命を、弟子たちを通してでもなく、ましてや血縁でもなく、まったく想定外に賜ったのでした。
もちろんこのことは、血縁や師弟関係を重んじる人々には躓きとなったことでしょう。事実、ガラテヤの信徒たちを惑わした勢力は、そういうものを重視した人々でした。しかし、パウロは、自分が使徒として召された権威は、復活の主イエスからの直接の啓示であったという事実をありのままに述べるしか仕方ありませんでした。
(4-3)クリスチャンとして歩み始める(ガラ1.18−23)
それから三年後、ケファと知り合いになろうとしてエルサレムに上り、十五日間彼のもとに滞在しましたが、ほかの使徒にはだれにも会わず、ただ主の兄弟ヤコブにだけ会いました。わたしがこのように書いていることは、神の御前で断言しますが、うそをついているのではありません。その後、わたしはシリアおよびキリキアの地方へ行きました。キリストに結ばれているユダヤの諸教会の人々とは、顔見知りではありませんでした。ただ彼らは、「かつて我々を迫害した者が、あの当時滅ぼそうとしていた信仰を、今は福音として告げ知らせている」と聞いて、わたしのことで神をほめたたえておりました。
おそらく主の顕現に接してから三年後、彼はペトロを訪ねてエルサレムに上りました。そこでペトロと、当時のエルサレム教会の指導者であった主の兄弟ヤコブと面会したようです。ここでパウロは先輩たちより、キリスト信仰の基本を確認したと思われます。最初期の信仰告白定型(「ケリュグマ」と言われています)をペトロたちから直接学んだのかも知れません。これはパウロ自身の信仰告白でもありました。彼はⅠコリント15章3-5節に「最も大切なこと」(原意は「まず最初に(伝え聞いたこと)」)として引用しているものがそれに当たるようです。
キリストが聖書に書いてあるとおりわたしたちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また、聖書に書いてあるとおり三日目に復活したこと、ケファに現れ、その後十二人に現れたことです。
このケリュグマは、ヤコブを中心としたエルサレム本山、ペトロなど十二使徒群、アンティオキア教会を中心としたヘレニスト信徒、パウロの仲間たちとほぼ全キリスト者に共通するものでした。ガラテヤ書の冒頭にも、このケリュグマが引用されています。
キリストは、わたしたちの神であり父である方の御心に従い、この悪の世からわたしたちを救い出そうとして、ご自身をわたしたちの罪のために献げてくださったのです。(ガラ1.4)
但しこのケリュグマでは、主イエスが私たちの「罪のために死んだ」と訳されるように、文法でいえばアオリスト形つまり過去に一回きりの出来事を言い表しているのに対して、パウロはガラテヤ書2章1節、3章1節等では、現在完了形、つまり過去から継続している出来事、訳すなら「十字架につけられ給ひしままなる」(文語訳)という独特な表現をしています。
このパウロの独特の言い方については後述しますが、非常に重要な内容を含んでいます。
このケリュグマのように、初代クリスチャンたちがユダヤ教徒は異なる独自の信仰告白や教義を形成しつつありました。
ケリュグマはその一端を表していますが、同様にキリストへの讃美歌も生まれつつありました。その代表例がフィリピ書2章6-11節です。
キリストは、神の身分でありながら、神と等しい者であることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、僕の身分(モルフェー)になり、人間と同じ者になりました。人間の姿(スケーマ)で現れ、へりくだって、死に至るまで従順でした。…
(4-4)アンティオキア教会を中心とした伝道
21その後、わたしはシリアおよびキリキアの地方へ行きました。
おそらく、この部分に「使徒言行録」の第一次伝道旅行を含む前後の記述部分に相当するのではないかと思われます。(ただし「使徒言行録」ではシリア、キリキア地方だけでなく、キプロス、南ガラテヤ地方にまで足を運んでいます。)
それによると、エルサレムから故郷のタルソスに戻っていたパウロをバルナバが呼び寄せて、アンティオキア教会で有力な伝道者として登用したようです。
当初は、かつて迫害者として恐れていたパウロが、今はキリストに捉えられた者として福音伝道に邁進しているとして、彼らの間でも評判になったことでしょう。
彼の確信に満ちた説き明かしは、多くの人、特にゲール(異邦人からユダヤ教に改宗した人たち)や異邦人に広く受け入れられたことでしょう。アンティオキア教会は派遣伝道を行えるだけに成長していったようです。
その後第一次伝道旅行としてバルナバの故郷でもあるキプロス島へ行き、さらにはキプロス島で知遇を得た地方総督セルギウス・パウルスの紹介などから、当初予定していなかった小アジアの南部地域であるパンフィリア、ピシディア、南ガラテヤ地方への伝道に赴いたようだです。(「使徒言行録」13.4-14.28)
(4-5)パウロとガラテヤの人々との出会い
南ガラテヤ説を採るとすると、この第一次伝道旅行がガラテヤ地方への伝道となります。
まずベルゲに行き、ピシディアのアンティオキアを経て、南ガラテヤの町々へ(イコニオン、リストラ、デルベ)という旅程でした。「使徒言行録」によれば大変過酷な旅だったようです。
それぞれの町でまずユダヤ人シナゴーグで伝道を始めました。賛同者も得たようですが、強い反撥も当初からありました。リストラでは投石によるリンチに遭い、パウロは瀕死の状態から奇跡的に回復したようです。
にもかかわらず更にデルベまで行き、狙われているのを覚悟で来た道を戻り、誕生間もない各地のエクレシアを励ましつつ帰りました。この内、リストラはテモテの出身地で、ガラテヤ書の宛先がこの南ガラテヤではないかとの推測に一つの有力な根拠を与えてくれます。
①福音以前のガラテヤの人々(4.8-10)
では、主イエスの福音に出会う前のガラテヤの人々はどうだったのでしょう。
ところで、あなたがたはかつて、神を知らずに、もともと神でない神々に奴隷として仕えていました。しかし、今は神を知っている、いや、むしろ神から知られているのに、なぜ、あの無力で頼りにならない支配する諸霊の下に逆戻りし、もう一度改めて奴隷として仕えようとしているのですか。あなたがたは、いろいろな日、月、時節、年などを守っています。
同様にわたしたちも、未成年であったときは、世を支配する諸霊に奴隷として仕えていました。(4.3)
「諸霊」「ストイケイア」とは「ストイケイオン」の複数形で、意味は「基礎、要素、天体、もろもろの霊力、諸霊」と訳されます。英語ではelementsです。
新約聖書中パウロ文書に4回(ガラ4.3,9、コロ2.8,20)、Ⅱペトロ書に2回(3.10,12)、ヘブライ書に1回(5.12)出てきます。「一つの序列に属するもの、構成単位、あるものの基礎、宇宙の元素(地、水、気、火)」などを指し、当時は、宇宙の諸元素(ストイケイア)を特別な日や月や時節に関連させ祀ったそうです。
これは何も2,000年前の人たちだけの問題ではないでしょう。
私たち現代人にも様々な「ストイケイア」があり、それらに隷属しているのではないでしょうか。ストイケイアを〈人の行動を律する考え方やイメージ〉のようなものとすれば、それは、生き方、信条、思想、宗教、慣習、しがらみ、占い、風水などが挙げられます。それぞれ蓄積された経験が根拠(裏付け)となったものとも言えましょう。
こうしたものが逆に私たちをがんじがらめに縛り、私たちはかえって生きにくさを抱えています。
救いとはこの呪縛からの解放でもあります。この解放の喜びを、人は潜在的に魂の奥底から慕い喘ぎ求めているのではないでしょうか。ガラテヤの人々もきっとそうだったに違いありません。
②衝撃的な福音との出会い
4章13−15節にガラテヤの人々がパウロと出会ったときのことが回想されています。
知ってのとおり、この前わたしは、体が弱くなったことがきっかけで、あなたがたに福音を告げ知らせました。そして、わたしの身には、あなたがたにとって試練ともなるようなことがあったのに、さげすんだり、忌み嫌ったりせず、かえって、わたしを神の使いであるかのように、また、キリスト・イエスででもあるかのように、受け入れてくれました。あなたがたが味わった幸福は、いったいどこへ行ってしまったのか。あなたがたのために証言しますが、あなたがたは、できることなら、自分の目をえぐり出してもわたしに与えようとしたのです。
「使徒言行録」の記述も参考に想像すると、ユダヤ主義者や、彼らにそそのかされた町の有力者たちによって、パウロたちは激しい迫害を受けていたにも拘わらず、ガラテヤの人々はパウロたちとその証言を受け入れたというのです。
また、パウロ自身が何らかの理由で、神々しさとはほど遠い、見るに堪えない身体的状況を呈していたようです。
病に倒れた見知らぬ旅人は人々の関心の的になるのでしょうか。にも拘わらず、彼らはそんなパウロを全身全霊で支えたのでした。
「できることなら、自分の目をえぐり出してもわたしに与えようとした」とあります。それが何を意味するのは分かりませんが、とにかく、そんなパウロであっても彼が伝えた福音故に、彼らをそうまでさせたのでした。彼はまた、その時のことを「あれほどのことを体験した」(3.4)と懐古していますし、さらに「あなたがたが味わった幸福」と表現しています。パウロの伝えた福音が劇的に人々の人生観を変えたことは確かでした。では、パウロの伝えた福音とはいったい何だったのでしょうか? これについては後ほどまたお話したいと思います。
(4-6)エルサレム使徒会議(2.1−10、48年ごろ)
いわゆる「エルサレム使徒会議」と呼ばれている、初代キリスト教会において大変重要な会議について述べられています。
「使徒言行録」では15章1−29節ですが、こことは非常に重要な相違点があります。おそらくパウロの伝える会議の内容の方がより史実に近いと思われますが、「使徒言行録」には著者ルカを取りまく90年代のキリスト教界の状況が色濃く反映しているように思えます。事実、2世紀以降のキリスト教界は、「使徒言行録」に記載されているような、いわゆる「ノアの律法」と呼ばれている禁令が広く定着していきました。
私たちは、誕生間もないキリスト教会は一枚岩のように受け止めがちですが、実はそうではなかったようです。少なくともいくつかの派閥がありました。
まず、主イエスの弟ヤコブを中心とした「エルサレム本山」とも呼ばれるグループがあります。彼らは、義父の譬えでいえば、「ユダヤ教の殻をお尻につけたままのヒヨコ」でしょうか。イエスはユダヤ教を原点に戻す預言者であり教師(ラビ)、またローマの支配から解放する王(メシア)として受け止めていました。リーダーは主イエスの血族から選ばれ、当初は弟のヤコブでした。ですから、律法や割礼の遵守を徹底し、日常凡てを神に献げ、神殿礼拝を厳格に守っていました。「ユダヤ主義者」とも呼ばれています。このグループは、主イエスの弟ヤコブが62年に殉死した後、彼の従兄弟クレオパの子シメオンをリーダーに立てましたが、紀元66年の第一次ユダヤ戦争によるエルサレム陥落にともないペレヤに逃げた後は、しだいに本山としての影響力を失い、伝説では数代続いたイエスの血縁が途絶えたことで消滅したと言われています。思想的には「ヤコブの手紙」や「マタイによる福音書」などに影響を及ぼし、古代キリスト教界に足跡を残していきました。
次に、十二弟子たちの流れを汲むグループです。これはペトロやヨハネなどがリーダーとなり、それぞれ特徴あるグループを形成していったようです。ペトロと呼ばれたシモンは使徒の筆頭として、ユダヤ主義者のみならずヘレニストにも幅広く支持されたようで、「ケファ」、つまりペトロ(岩)という綽名が暗示するように、古代カソリックの象徴的存在になっていきました。シリアを中心にアジア、アカイア、ローマにも足跡を残しています。「マルコによる福音書」、「マタイによる福音書」、「ペトロの手紙」などにその影響が認められます。
一方、使徒ヨハネも独自の神秘的思想をもとに独特のグループを形成していったようです。おそらくシリア近辺で発展し、後にはエフェソなどアジアにも展開したようです。「ヨハネ福音書」や「ヨハネ書簡」がそのグループによるものと考えられます。
これらに対してギリシア語を日常的に使っていたディアスポラ出身のグループ(ヘレニスト)がありました。
彼らはユダヤ主義者たちと違って、ユダヤ教のワクを超えていました。
中でもステパナは激しい神殿批判を展開し殉死しました(使徒6−7章)。
実は、主イエスが闘った強大な勢力の一つが神殿宗教でした。その闘いを受け継いだのがステパナだったのです。
ヘレニストたちは、ローマ帝国各地に居住し、コスモポリタン的な交流の中に生活していたことから、ユダヤ教の民族主義的、国粋主義的傾向にとらわれることなく、ユダヤの神殿宗教のワクを遙かに超えた主イエスの福音の広さ、深さに惹かれていったようです。もちろん彼らは主イエスと同じようにユダヤ人宗教家たちから迫害されました。彼らヘレニストたちは、かなり早い時期にエルサレムを追われ、ローマ帝国各地へ散っていったようです。そのため、ダマスコやシリアのアンティオキアに、彼らが中心となったエクレシアが発展していきました。パウロも当初は、このアンティオキア教会に属していました。
アンティオキア教会では、こうしたヘレニストだけではなく、ユダヤ主義者や、異邦人の改宗者、さらには異邦人などが混在していたようです。中でもユダヤ主義者たちとヘレニストたちの間で、特に異邦人伝道について見解の相違が目立つようになったことでしょう。ユダヤ主義者たちにとっては律法の遵守を最優先とするため、異邦人はまず改宗者(「ゲール」という)となることが必要だと主張したようです。これに対して主イエスの福音はそのような改宗(割礼を受け律法を守る)ことを救いの必須条件としないと主張し対立していったようです。こうした背景からエルサレムでの話し合いが持たれたようです。
その後十四年たってから、わたしはバルナバと一緒にエルサレムに再び上りました。その際、テトスも連れて行きました。エルサレムに上ったのは、啓示によるものでした。わたしは、自分が異邦人に宣べ伝えている福音について、人々に、とりわけ、おもだった人たちには個人的に話して、自分は無駄に走っているのではないか、あるいは走ったのではないかと意見を求めました。しかし、わたしと同行したテトスでさえ、ギリシア人であったのに、割礼を受けることを強制されませんでした。潜り込んで来た偽の兄弟たちがいたのに、強制されなかったのです。彼らは、わたしたちを奴隷にしようとして、わたしたちがキリスト・イエスによって得ている自由を付けねらい、こっそり入り込んで来たのでした。福音の真理が、あなたがたのもとにいつもとどまっているように、わたしたちは、片ときもそのような者たちに屈服して譲歩するようなことはしませんでした。……実際、そのおもだった人たちは、わたしにどんな義務も負わせませんでした。7それどころか、彼らは、ペトロには割礼を受けた人々に対する福音が任されたように、わたしには割礼を受けていない人々に対する福音が任されていることを知りました。……また、彼らはわたしに与えられた恵みを認め、ヤコブとケファとヨハネ、つまり柱と目されるおもだった人たちは、わたしとバルナバに一致のしるしとして右手を差し出しました。それで、わたしたちは異邦人へ、彼らは割礼を受けた人々のところに行くことになったのです。……
パウロの伝えた福音は、割礼を受けていない異邦人キリスト者であるテトスという生きた事実を通して実証されました。テトスから醸し出されたキリストの香りの前に、対立者たちも黙したことでしょう。しかし、逆にユダヤ主義者の根深い拒絶を誘発したことも、この後の経過から伺えます。両者の一致を阻むものが歴然としてありました。それはまさに私たちの罪でもあります。パウロの伝えた福音はまさにそこに立ち向かったのでした。
(4-7)ペトロ、バルナバとの衝突(2.11-14、49年ごろ?)
いわゆる「アンティオキア事件」です。エルサレム使徒会議で一応の一致を見たわけですが、現実には根本的に解決されたわけではありませんでした。「ガラテヤ書」に述べられた内容はパウロサイドの見解であり、「使徒言行録」に残された内容はユダヤ主義者たちの意見も採り入れた妥協策を、最初の教会史の正式記録として残したかったのかもしれません。おそらく、ユダヤ主義者たちはパウロたちの異邦人伝道を過小評価し、この時点ではさほど大きな問題とは思っていなかったのではないかと想像されます。そのため、「ガラテヤ書」に見られるような結論を許可したのでしょう。しかし、現実には異邦人クリスチャンがどんどん増えていきました。そして、彼らが恐れていたことが現実化していったのではないでしょうか。それで、エルサレム本山は、各地のエクレシアに人を派遣し、実態を調査し始めたようです。パウロたちがいたアンティオキア教会にもエルサレム本山から派遣されてきました。たまたまペトロもアンティオキアに来ていました。
さて、ケファがアンティオキアに来たとき、非難すべきところがあったので、わたしは面と向かって反対しました。なぜなら、ケファは、ヤコブのもとからある人々が来るまでは、異邦人と一緒に食事をしていたのに、彼らがやって来ると、割礼を受けている者たちを恐れてしり込みし、身を引こうとしだしたからです。そして、ほかのユダヤ人も、ケファと一緒にこのような心にもないことを行い、バルナバさえも彼らの見せかけの行いに引きずり込まれてしまいました。しかし、わたしは、彼らが福音の真理にのっとってまっすぐ歩いていないのを見たとき、皆の前でケファに向かってこう言いました。「あなたはユダヤ人でありながら、ユダヤ人らしい生き方をしないで、異邦人のように生活しているのに、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強要するのですか。
「ケファ」というのはペトロのことです。「彼ら」とはペトロやバルナバを指します。
それまで同志であった彼らに対して、パウロにとっては福音の本質に関わる、譲れない、妥協できない問題が起きました。具体的には、エルサレム本山からやってきたユダヤ主義者に配慮して、ペトロやバルナバさえもが律法に従い、異邦人クリスチャンに対して「異邦人」として一線を画し向き合ったようです。例えば、それまでは自由に一緒に摂っていた食事も、ユダヤ律法の厳格な食事規定に従って、異邦人クリスチャンたちと区別したのです。食事を一緒にするというのは、彼らにとっては非常に重要な問題でした。
これは後に聖餐式として重要なサクラメントになることからも分かります。もし、私たちが彼ら厳格なユダヤ人たちと一緒に食事をとろうとすれば、おそらく耐えられないのではないでしょうか。
ペトロは当初異邦人と一緒に食事をしていたそうですから、もしかしたら律法の食物規定に反する物も食べていたかも知れません。これについては「使徒言行録」10章にその片鱗が伺えます。しかし、ユダヤ主義者たちが来たら、それを止めてしまったのです。ペトロは彼なりにエルサレム本山の意向を尊ぶと共に、ユダヤ人やユダヤ主義者の躓きにならないように配慮したのかも知れません。
しかしそれは、パウロにとって許しがたいことでした。なぜなら、この行為を正当化し根拠付け促した「律法」、何々をしてはならない、何々を食べてはならないという律法こそ、パウロ自身がキリスト教徒を迫害し抹殺しようと血眼になっていた信念の元であり、彼自身の生き甲斐として堅く守ってきたものだったからです。
しかし、それが根本的に間違いだったことを、復活の主イエスの顕現に触れ示されたのでした。この律法とは何かというのは、ユダヤ人でない私たちにはいまいちピンときませんが、この点については次講でご一緒に考えたいと思います。
私たちにとって律法、私たちの中にも、ユダヤ人のいわゆるトーラー(律法)とは違う「律法」(「ノモス」)があると思うからです。その律法とは何か、それは簡単に申しますと、他者を裁くもとになるもの、他者を断罪する根拠になるものと言ってもいいかもしれません。パウロはこれを「律法の呪い」とまで言っています。
この「律法の呪い」から解放されるのが福音だ、というのがパウロの結論なのです。その呪いから私たちを解放するものは何か、それが「主イエスのピスティス」だとパウロは主張しています。これが本日のお話の中心ですので、後ほど詳しくお話しします。
この後のパウロがどうしたかについて「ガラテヤ書」に述べられていません。
ですからおそらくこの手紙は、この事件の直後に書かれたことが示唆されます。パウロはこの衝突を機に、アンティオキア教会と袂を分かち、独立伝道へと旅立ちます。
出立してさほど経たないうちに、おそらく故郷のキリキア辺りで、すでに第一次伝道旅行で福音の種を蒔いた南ガラテヤ諸教会にも、ユダヤ主義者たちの影響が及んでいることを知ったパウロは、南ガラテヤを目指す途上でこの書簡を認めた可能性が高いと思われます。とすれば、現在手にするパウロの真性の書簡の中で最も古い、つまり新約聖書中最も古い文書となります。
この衝突がきっかけとなり、パウロはアンティオキア教会を離れて、独立伝道に旅立ち、故郷のタルソスを経て、キリキア門を通り、第一次伝道旅行で訪れたデルベからリストラに入りました。
ここで、この後彼の右腕ともなる愛弟子テモテを同行させています。そしてイコニオンを経て皇帝街道に沿ってアジア州(おそらく州都エフェソか)を目指したようですが、何らかの理由で阻まれ(「使徒言行録」では北部のビティニア州を目指したことになっていますが)北上し、フリギアからミシアを経てトロアスにたどり着いたようです。
そこでビジョンを受けエーゲ海を渡り、当時のヨーロッパの東の入口であるマケドニア州に上陸しました。このままエグナティオ街道を西進すれば帝都ローマにたどり着きますので、おそらくパウロは当初からローマを目指していたのかもしれません。しかし、この時はフィリピ、テサロニケを経てアカイア州に至り最後はコリントにたどり着きそこでしばらく伝道することになりました。
「使徒言行録」には、このパウロの分離については、第一次伝道旅行で、小アジア南部へ伝道しようとした矢先にパウロたちから離れてアンティオキアに帰ってしまったマルコを、この度の伝道旅行に同行させるかどうかで「意見が激しく衝突し」(15.39)たからとあり、ペトロ、バルナバとの対立は伏せられています。パウロはエルサレム教会から派遣されていたシラスと共に「兄弟達から主の恵みにゆだねられて、出発した」と述べ、あくまでもアンティオキア教会を母教会とし、エルサレム本山のお目付を同行したというスタンスをとっています。ここにも教会内の統一性を重視した著者ルカの意図が見受けられます。
5.パウロの伝えた福音とは(2章15‐21節)
ペトロ・バルナバとの衝突事件とガラテヤの信徒たちが直面していた問題は同根でした。パウロにとってそれは福音の本質を巡る抜き差しならぬものだったのです。つまり、〈救いの根拠〉に直結する問題でした。おそらく、この点についてはペトロやバルナバとは重さのはかり方が異なっていたようです。少なくとも彼らには、パウロのような「律法の呪い」という認識はなかったと思われます。だからパウロは使徒生命を賭けて、たとえ母教会と袂を分かつことになろうとも、この問題に真っ向から挑まねばなりませんでした。では、パウロがそうまでして伝えようとした福音の中心的使信とは一体何だったのでしょうか。
それが、冒頭にお読みいただいたガラテヤ書2章15−21節に表明されています。しかし、現在の共同訳を始め伝統的な訳において、果たしてパウロの真意を的確に伝えているのだろうか、という疑問を抱かざるを得なくなりました。以下は、私なりに示されたものですので、間違っているかも知れません。批判的に検証していただければ幸いです。
《中心的使信》2章15−21節
《キリスト・イエスのピスティスによる「義」(=救い)》
まず、新共同訳では次のように訳されています。
15わたしたちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。16けれども人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって(*1)義とされると知って、わたしたちもキリスト・イエスを信じました。これは、律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって(*2)義としていただくためでした。
「わたしたちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません」は、パウロの常套手段というか、論敵の主張をまず引用して「がしかし、何々」と自説を展開します。ですからここは、「わたしたちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません」とあなたたちは主張するが、人は律法の実行ではなく、……と続けるとよくわかります。
「義とされる」とは、日本的な〈正義〉という意味から想像されるような正しい人となるというような意味ではなく、簡単に言えば「神と正しい関係にあること」を指します。神様の御前にあって後ろめたさがなく、平安に包まれた状態です。したがって、この反対の不義とは、神様から離れていること、神に背を向けていること、後ろめたい思いを引きずっていることを指します。
「信仰」と訳された単語は原語では「ピスティス」と言います。この「ピスティス」というのは大変重要な言葉です。
確かにこの動詞形のピステウオーは「信じる」と訳されるように、ピスティスには「信仰」という意味もあります。しかし、〈ピスティス〉は、本来、「真実」、「まこと」、「信頼」という意味なのです。
これはヘブライ語の「エムナー」という言葉に遡るもので、簡単に言えば約束を守るという意味です。
ユダヤ人にとって「真実」(エムナー)というのは、約束を守ることです。つまり、神様が人間に対して与えて下さった「祝福するよ」という約束を、神様が守り通すこと、それが〈エムナー=ピスティス〉なのです。
次に、上記聖句のアンダーラインの部分を検討してみます。実はここが非常に重要な部分です。
新共同訳で「イエス・キリストへの信仰」と訳されている箇所は、直訳すると「イエス・キリストのピスティス」となります。「イエス・キリストの」という所有格なのです。
ピスティスの動詞形ピステウオー「〜を信じる」の一般的な用例を見ますと、前置詞を使わない場合は基本的に与格(〜に)を用いるのが普通です。パウロもこの16節では「主イエスに(対し)信じる」と与格で使っています。
これらに対してパウロはこの箇所では属格(〜の)を使用しています。つまり単純に率直に訳せば、「主イエスのピスティス」となります。確かに所有格でも、「何々への」と訳す語法があり多くの神学者は「への信仰」を支持してきましたし今もそうですが、一部の学者は「の」と訳すことを主張しています。最近では哲学者の清水哲郎氏が「の」の立場で論文を発表されています。
このように、素直に訳せば「の」となるべきところを「への」と訳してきたところに、何か深い問題を感じるようになりました。
それは、、救いの根拠は、私たちの不確かな信仰や確固たる信念・信心ではなく、〈主イエスのピスティスにある〉という主張を受け止めたからです。
この視点から聖書を読み直すと、今まで「への信仰」と訳され、読んでいた聖句がまったく別の輝きを発してきました。従来「イエス・キリストへの信仰」と訳されてきた箇所で、上記のように「イエス・キリストのピィスティス」と解釈できる代表例を以下にあげます。いずれもパウロが救いの根拠を示す重要な箇所ですので、お手元の聖書でご確認下さい。なお( )書きに、参考として私訳を記しました。
①ガラテヤ2章16節(二回)
②ガラテヤ 2章20節
わたしが今、肉において生きているのは、わたしを愛し、わたしのために身を献げられた神の子に対する信仰(原文では「神の子のピスティスにおいて〔エン=in〕」)によるものです。
③ガラテヤ3章22節
しかし、聖書はすべてのものを罪の支配下に閉じ込めたのです。それは、神の約束が、イエス。キリストへの信仰(原文「イエス・キリストのピスティスから〔エク=from〕」)によって、信じる人々に与えられるようになるためでした。
④ローマ3章22,節
イエス・キリストのピスティスにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。
⑤ローマ3章26節イエスのピスティスによって義とされる。
⑥フィリピ3章9節キリストのピスティスによる義
もちろん、学者の間でも議論されていますし、「キリストへの信仰」と結論される場合の方が圧倒的に多いですが、しかし、パウロはローマ5章19節では、「一人の従順によって多くの人が正しい者とされるのです」とあり、この「一人」つまり主イエスによって、多くの人が義とされると主張しています。
また体験的に救い(義とされる)の根拠は私たちの「信仰」にあるのではなく神様の側にある、とする方がパウロの真意ではないかと私は思えてなりません。
私は「キリストのピスティス」の立場からガラテヤ書2章15、16節を試訳してみました。
人は律法を実行することによってではなく、ただイエス・キリストのピスティスを通して(によって)義とされると知り、私たちもキリスト・イエスを信じました。律法の実行ではなく、キリストのピスティスから(によって)義としていただくために。
ここで私たちがよく間違えることがあります。
それは〈信仰〉というと〈信心〉つまり、信じる心と混同してしまうことです。「信心」に相当するギリシア語は「トレースケイア」や「エウセベイア」でピスティスと区別されています。
私たち日本人は、「信仰」と言うとき、どちらかと言えば「ピスティス」というよりも、「信心」の意味合いが強く、それでこの部分も「イエス・キリストを信心することによって〔救われる〕」という意味合いに受け止めがちではないでしょうか。
あのルターが「信仰のみ」と言ったときも、私たち日本人は「信心のみ」と受け止めてきたのではないかと思うのです。
そして、それはおそらく浄土真宗の影響があるからではないかと思います。「弥陀の本願」に委ねて救われるという〈信心〉です。それがこの「キリストへの信仰」に投影されているように思います。
しかし、私自身の体験から、自分の信仰、信心が救いの根拠であり得るはずがありません。こんなあやふやで、いい加減な信心が救いの根拠ならば、私たちはとうてい救われません。まさに「ああ、我悩める人かな」、「ああ、惨めだ、自分は永久に救われない」と嘆くばかりです。
しかし、パウロはそうじゃない、というのです。
救いの根拠は「主イエスのピスティス」であって、主イエスを通して示される、神様がご自身の約束を守り通すという〈ピスティス〉、主イエスを通して示された神様のピスティスなのだと証するのです。
これがここの主旨ではないでしょうか。
そこで、皆さんにぜひやっていただきたいことがあります。このガラテヤ書の「信仰」と訳されているところを、「ピスティス」と変えて読んで見てください。その「ピスティス」は私たちの「信仰」ではなく、「主イエスのピスティス」という意味で読んでみてください。
おそらく今までとは全く違った印象を受けられると思います。
主イエスを通して顕された神様のピスティスこそが、私たちを救う(義とする)ための根拠なのだということを、パウロは繰り返し繰り返し主張しているのがわかります。
今日、ぜひご紹介したいお話があります。
ガラテヤの人たちがパウロによって主イエスの福音に出会ったとき、喜びに溢れ、感激した彼らの声がガラテヤ書にも記されています。
どうやらその時パウロはひどい病気を患っていたようです。おそらく眼病だったのでしょう。その姿はとても神々しい立派な教師ではなく、見るに堪えないようなみすぼらしいものだったようです。
にもかかわらず、彼が伝えた福音を聞いて、自分の目玉をくりぬいて差しだそうとしたほどパウロの伝えた福音を歓迎したのです。感涙を流し、感謝に溢れたのです。その時の感激、感謝、讃美、それはどこにいったのか、と後にパウロは彼らを叱責しています。
福音と出会うとはどういうことかな、と想像します。皆様もそれぞれ福音との出会いを経験されたことでしょうし、これからも繰り返し、繰り返し様々な事件などを通して出会っていくことでしょう。
しかし福音と出会う感激といっても、なかなかピンと来ない方もいらっしゃると思います。自分自身の体験を語ればよいのですが、今日はある人の体験談を代わりにご紹介させていただきます。
私の学生時代に、わずか11ヶ月という短い期間お交わりを頂いた野村伊都子さんという女性がいます。
ご存知の方もおられると思いますが、彼女は若くして結核を患い、腎臓摘出など計七回の大手術をされ、人生の大半を闘病に明け暮れました。
その中で主イエスの福音に触れ、諸先生の導きを頂き、「祈の友」という結核療養をするキリスト者の群れにも連なっておられました。
彼女は晩年、期せずして私たちの住む町に来られ、私たちも思いがけずお交わりを頂きました。私たち若者をとても大切にして下さり、何かあればいつもお招きくださいました。
ある時は病床の友を訪ね、ある時は福音に生きる人の現場に連れて行って下さり、信仰の訓練をさせていただきました。
その彼女の遺著が『流れのほとりに』です。
その中に、「涙」という一文があります。これは彼女が入院中のエピソードです。お読みします。
「涙」
野村伊都子著『流れのほとりに』(聖燈社刊)98-102ページ
もうどれくらい時間がたったろう。うぶ毛のような若葉がきらきらして、丸い日射しが地面にゆれ、何やら小虫がいそがしそうにあちこちしていたのに、いつの間にか黄昏が迫って窓辺の空気がひえびえとしているのも気づかず、私はぼーっと外をみつめていた。
私にとってこの窓辺の時間は、長い緊張のときだった。その日の窓辺は、〈若葉が素敵、青葉が何てすばらしいんだろう〉と眺めるには、神経に余裕がなさすぎた。
彼女と同室になって一週間。私の目は窓辺で外に向かっているが、神経は背中じゅうを目にして彼女の動静をうかがっているのだ。
彼女は七十を過ぎた〝昔の娘さん〟で、乳ガンで入院してきた。もう素人目にも判別できる手遅れ症状で、首にもむくむくとコブがみえている。おそらく乳ガンだけではないのであろう。血尿も出ているし、ひどい便秘もある。それなのに、このおばあさんはいつもニコニコして決して苦痛にゆがんだ顔をみせないのだ。医者にも看護婦にも、そして私にも、面と向かえばいつもニコニコして柔和であり、ねても起きてもかたちをくずすことをしない。
あるとき、私が病室に戻ってくると、彼女は洗面所の水でタオルを搾ってそっと胸のあたりを冷やしているのに出くわした。ハッとして見た鏡に写る彼女の顔の、何という痛々しさ。おもわずかけよって手をかしたが、彼女はとんでもないところをみられてしもうた、といわんばかりに、いつもの笑顔でベッドに横になるのだった。そのときだ。私は彼女の痛みがどんなに激しいものであるか、そしてそれをただじっとガマンしつづけることが、いつか身についた生き方となった過去の厳しい歩みの一端を、うちのめされたようにうかがい知らされたのは。
だから、おばあさん! 私が窓辺によって若葉のみどりにみほれている間だけでも、どうか笑顔をやめて苦痛に顔をゆがめて頂戴。痛い、苦しい、とありのままにおもいっきりうめきを吐露して頂戴! 私がこうして外の小虫と遊んでいる間だけでも。
窓辺によって私はあれこれ思いみた。〈おばあさん、一体この笑顔はどこから?これはあなたのカクレミノ? それとも、絶望の果てのあきらめ? いや、苦しみから救われることより、絶望を妨げることを望むものに与えられた知恵? 特質?〉
彼女は十五人もの子供を生んだ。自身は生みの親の顔も知らず他家にやられ、十五歳のとき結婚。そして次々に子供を生みつづけ、やがて若くして寡婦になり、働いて働いて働き通して、人生の終わりに近くガンという病魔におそわれた。しかし彼女にとって、この病魔は決して決定的な悲劇ではなかった。彼女にとって悲しいことは、息子三人が戦死したことだった。そして更に悲しいことは、この戦死した息子の遺族年金が、残った子らの合い争う原因になったことだった。彼女をひきとろうとするものはその金を目当てにし、金からはずれたものは「金が目当てだ」といって母親をひきとった者をあしざまに言いふらした。
だから、母親が入院しても、おたがい腹をさぐり合うだけで、親身に世話をするものはいなかった。それでも彼女はぐち一つ言わず、おろかなことを一度も口にしなかった。「貧しすぎて、みんなに人間らしい思いをようさせなんだからなあ」と詫びては、すっかり裸にされておっぽり出される母親だった。そして、〝もう二度と戦争だけは起きませんように〟これが彼女の唯一のたしかな祈りであった。
彼女は湖北、即ち琵琶湖の北の貧村の出だった。湖北は哀しい。侘びしさを通りこしてかなしいところだ。彼女の話をききながら、「侘びしい断崖へ音もたてずに打ちよせる波」と誰かが書いていた湖北の淋しさを思いおこした。
湖へ山が切りたって落ちそうなところに、まるで貝殻がひっついているように立つ家。どこに一体田畠があるというのか。カイコが唯一の生業だった。ところが、桑畑は遠い山の端のその端にあって、負い籠を背負うての桑つみも一日がかり……。その最中に産気づいて一目散にかけ帰ったが間に合わず、土間で生んでしまった児もあるという。
ひもじゅうて、児らが泣いて、下にみえる暗い湖をみつめたときもあったろうに──。貧しい傾斜地は哀しい。が、「すべりおちてははいあがるんじゃ、はいあがるんじゃ、そう自分に言いきかして働きました」と、小柄な体をベッドにちょこんと座して、淡々と柔和な顔を語って聞かせてくれるとき、十五人もの児を生み育てた女の強さに目をみはった。
「なんで私なんかに一人だった育てる力がありましょう。私は生ましてもろうただけです。子供は神様よりのさずかりもの。そう思うても、日々の生活におわれて、さずかりものらしうあつかうことにこと欠いて……。だから今さらどんなに責められても、罰をあたえられても、当たり前やと思うとります」
私は彼女の話をききながら、「長血をわずらう女」(マルコ5・25、ルカ8・43)の信仰を思い出した。彼女はこれまでいかに苦しんできたかを長々とのべたてようとはしなかった。おのが身を恥じていた彼女は、出来ればただイエスの御衣の裾にそっと手をふれさせてほしと決心した。彼女の信仰は、癒されるにはただそれだけで充分だったのだ。
長い苦しみの中にあるものにとって、心身の疼きはその年月の長さに決して比例しない。むしろ幾層倍加することを私は知っている。そうした中にあって、一層心貧しく柔和であれば、「幸福なるかな、天国はあなたのものだ」とのお言葉をかけていただくのにふさわしいといえよう。
「おばあさん、聖書にはこう書いてあります。『こころの貧しい人たちは、さいわいである。天国は彼らのものである。悲しんでいる人たちは、さいわいである、彼らは慰められるであろう』……」
私はマタイ伝五章を読んだ。彼女はきょとんとして微笑んでいた。自分にはおよそ縁がないことだといわんばかりに──。しかしその微笑みの陰に、長い人生をひとりで戦ってきたものの悲しみと孤独が秘められていた。そのことを本当に知っていてくださるお方は全能の主おひとりである。その片鱗はベッドに隣りする私にもひしひしと迫りくるものを覚えるのだった。
ある夕、突然彼女は言った。
「聖書とやらを、読んでほしい」
私はヨハネ伝11章のラザロの復活のところを読んだ。そして35節、
「イエスは涙を流された」
といったとき、彼女は突如、うううっと吠えるような声を出した。慟哭(どうこく)だった。号泣だった。
「神様の御子が涙を流してくださった」
このことは彼女にとって、肺腑に沁みる慰めであり、かつて覚えたことのない感動であったのだ。人間として生まれてはじめて味わう真実であり、愛の言葉だったのだ。
「神様の御子が……、神様の御子が……」
彼女はありがたい、ありがたい、といって泣き伏した。
それより数日後、彼女は尿毒症を併発して一夜にして逝った。やすらかな最期だった。
「神様の御子が、私のために十字架にかかって死んでくださった。もったいない。もったいない」とうわごとをいいつづけての召天だった。
どんなときにも自分のことで泣かなかった彼女も、最後に、主の御涙にありがたいもったいないと、号泣して天翔(あまがけ)ったのだ。本当に、彼女はすばらしい〝昔の娘さん〟だった。あんまり見事だったので、私はしばし夢をみているようだった。
若葉の季節になると、このおばあさんのことをいつも思い出す。そして、神様のなさることに瞳をきらきらと輝かさずにおれないのだ。
以上、引用。
一昨年、ノーベル平和賞を受賞したマータイさんが来日して、日本語の「もったいない」が、彼女の提唱する4R〔消費削減(リデュース)、再使用(リユース)、資源再利用(リサイクル)、修理(リペア)〕を象徴する言葉であるとして話題になりましたが、湖北のおばあさんが言った「もったいない」と少々意味が違いますね。
自分には過分だ、私には十分すぎるという意味の「もったいない」です。
こういう意味の「もったいない」の気持ちを持てる魂、心貧しき魂が、今私たちに求められているのではと私は思います。
そういう時に、聖書はたった一言であっても、この湖北のおばあさんのように、その人の魂を捉え、イエス様と出会うことができるのだと思います。
〈主イエスのピスティス〉という問題は学問的な議論となると本当に難しいのですが、私たちの「主イエスへの信仰」によって義とされる(救われる)のではないということを、私は確実にそうだと受け止めざるを得ません。
ぜひ、聖書をもう一度、〈主イエスのピスティス〉という観点で読み直してみてください。
新しい発見があると思います。
そして、この湖北のおばあさんのように、聖書の御言葉に打たれ、聖書によって、主イエスが私たちを愛して下さっていることを私は知っているよ、というあの讃美歌を心から歌える人に造りかえていただきたいと思います。
第二講義
前講の最後の結論で、私たちの救い、つまり義とされるのは私たちの〈信仰〔信心〕〉ではなく、〈主イエスのピスティス〉による、と学びました。
義とされるというのは、神様と正しい関係になることを言い、何のやましいこともなく、神様の下で安らぐ状態を指します。
私たち自身罪だとは思っていなくとも、神様の前に、丁度赤ちゃんのように委ねきって安らぐようにいられない、つまり自分で何とか取り繕おうとあがいているとしたら、それは義とされていない、救われていないわけです。
その義とされる、つまり救われる根拠は、私たちの信心、信念、信仰にあるのではなく、神様の側から、主イエスを通して示された真実、ピスティスなのです。
ピスティスとなかなか発音しにくいですが、残念ながら的確な訳語がありません。
丁度キリスト教の「愛」は、「アガペー」ですが、これを「愛」と訳すと誤解を生じるのと同じです。今の日本には「愛」は氾濫していますが、それはけっして「アガペー」ではありません。その本質は、むしろ仏教用語で言う「渇愛」(自己中心的な愛着)ではないかと思います。ですから本来なら「愛」と訳さずに「アガペー」のままの方が良いのかも知れません。
それと同じように、このピスティスも、訳語としては「まこと」とか「真実」とか「信頼」「信仰」となりますが、その本来の意味は、神様が一旦なされた祝福の約束を守り通して下さる、という「エムナー」ということなのです。
少なくとも「信心」的な意味あいが強い日本語の「信仰」と訳してしまうと、本来の〈ピスティス〉の意味から遠いように思えます。
ガラテヤ書で「信仰」となっている部分を「ピスティス」と読み替えるという提案をさせていただきましたが、どなたか試みられたでしょうか。
一つ、演習をいたしましょう。ガラテヤ書の3章1節から14節を,「信仰」を「ピスティス」に読み替えてみます。皆様も考えながら御覧下さい。
1ああ、物分かりの悪いガラテヤの人たち、だれがあなたがたを惑わしたのか。
「まどわす」というのは、「魔法にかける」という意味です。「誰があなたがたを催眠術にかけたのか」というようないみです。
目の前に、イエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。
ここも訳ではうまく表現できないのですが、原文は「十字架につけられた」という過去に一回起きた過去形ではなくて、今もそれが続いている「十字架につけられつつある」という意味も含めた現在完了形なのです。文語訳の聖書ではここを、「十字架につけられ給ひしままなる」と忠実に訳されています。
十字架につけられた主イエスが、今も私たちの目の前につけられたままである、という言い方なのです。
2あなたがたに一つだけ確かめたい。あなたがたが“霊”(聖霊)を受けたのは、律法を行ったからですか。それとも、福音を聞いて信じたからですか。
「福音を聞いて信じたからですか」も、原文を見ると違っています。直訳すると「そのピスティスを聞いたからですか」です。
3あなたがたは、それほど物分かりが悪く、“霊”によって始めたのに、肉によって仕上げようとするのですか。4あれほどのことを体験したのは、無駄だったのですか。無駄であったはずはないでしょうに……。5あなたがたに“霊”を授け、また、あなたがたの間で奇跡を行われる方は、あなたがたが律法を行ったから、そうなさるのでしょうか。それとも、あなたがたが福音を聞いて信じたからですか。6それは、「アブラハムは神を信じた。それは彼の義と認められた」と言われているとおりです。
7だから、(主イエスの)ピスティスによって生きる人々こそ、アブラハムの子であるとわきまえなさい。8聖書は、神が異邦人を(主イエスの)ピスティスによって義となさることを見越して、「あなたのゆえに異邦人は皆祝福される」という福音をアブラハムに予告しました。9それで、(主イエスの)ピスティスによって生きる人々は、信仰の人(ピストス=真実な人)アブラハムと共に祝福されています。
「信仰の人アブラハム」は、原文はピストス(pistovV)で「真実な人」という意味です。ピスティスと語源が同じです。
10律法の実行に頼る者はだれでも、呪われています。「律法の書に書かれているすべての事を絶えず守らない者は皆、呪われている」と書いてあるからです。11律法によってはだれも神の御前で義とされないことは、明らかです。なぜなら、「正しい者はピスティスによって生きる」からです。12律法は、ピスティスをよりどころとしていません。「律法の定めを果たす者は、その定めによって生きる」のです。
12節は「律法はピスティスからではなく、そうではなくて、『律法の定めを……』と続きます。原文は一つの文章です。
13キリストは、わたしたちのために呪いとなって、わたしたちを律法の呪いから贖い出してくださいました。
第二講のテーマはここから取りました。
「律法の呪いからの解放」です。主イエスは私たちを縛り付けている「律法の呪いから贖い出して」くださった、つまり解放して下さった、それがキリスト者の自由ですが、それをお話したいと思います。
「木にかけられた者は皆呪われている」と書いてあるからです。14それは、アブラハムに与えられた祝福が、キリスト・イエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また、わたしたちが、約束された“霊”を(主イエスの)ピスティスによって受けるためでした。
「ピスティスによって」というのは、直訳すると「ピスティスを通して」です。主イエスのピスティスを通して約束された聖霊を賜るのだ、と言っています。私たちの信仰によって聖霊を賜るのではないのです。主のピスティスによって賜るのです。
このようにこれまで「信仰」と訳され読んできたところを、「主イエスのピスティス」ないしは「ピスティス」と読み替えてみると、まったく異なる語りかけが聞こえてきます。
救いの根拠は、私たちの信仰ではなく神様の側にあるのです。
もちろんだからといって、私たちが「信じる」という態度が必要ないかといえば、そうではありません。主イエスのピスティスに触れたものは、自ずと主イエスを信じる者(信頼し委ねる者)とされます。主のピスティスに対する応答として信仰が生じますが、
しかし、その応答として生まれたピスティス(信仰)が救いの根拠ではないのです。保障ではないのです。
救いの保障は神様の側にあって私たちの側にはないというのが、徹底したパウロの主張だと私は思います。
律法を守ることなど救いの根拠が人間の側にあるという主張に対し、徹底的にパウロは闘ったのでしたが、それをパウロは〈律法〉という言葉で表現しました。この〈律法〉という誤解を生じ易い言葉を敢えて使ったために、ユダヤ教徒はもとより同じキリスト教徒からも生涯理解されず、受けなくて良い迫害を受け続けました。
また、彼が造った教会内でもパウロの真意が中々伝わらず、混乱を招いていたのでした。しかし、このことが非常に重要なことで、救いの根拠を人間の側に持つために起きているのが、この世の中の凡ての混乱だと言っても過言ではありません。
それがある意味サタンの策略であると言えましょう。この世に聖国を来らせるのを妨げるために、人を欺くサタンの戦略ではないかと私は思います。
もう一箇所、見てみましょう。5章5、6節です。
5わたしたちは、義とされた者の希望が実現することを、“霊”により、(主イエスの)ピスティスに基づいて切に待ち望んでいるのです。6キリスト・イエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。
6節は殆どの訳がこの新共同訳とほぼ同じですが、これによると、「割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切」とあり、私たちの「信仰」、それも「愛の実践を伴う信仰」が大切だという道徳的教訓になっています。つまり、マザー・テレサのような愛の実践となって現れる「信仰」が大切だ、ということになります。
だとすれば、マザーのように無条件に他者を愛せない私の信仰では到底、救いはかないません。その信仰が救いの根拠だとすれば、絶望的です。
しかし、そうではないのです。主イエスのピスティスという視点からこの原文を直訳すると全く別の訳ができるのです。
「アガペーを通して威力を発揮する(主イエスの)ピスティスが一番大切だ」となります。
割礼の有無が問題ではなく、アガペーつまり愛としてその実力を発揮してくる(主イエスの)〈ピスティス〉が最も大切だと言っているのです。
ですから、人間の側の〈信仰〉として解釈して訳するのと、〈主イエスのピスティス〉として訳するのでは、天地の差があります。割礼の有無ではない、主イエスのピスティスこそ最も大切だとパウロは主張しているのではないでしょうか。
但し前講でも申しましたように、これは全くの私見です。間違っているかも知れません。多くの神学者、聖書学者は新共同訳の立場を取っていますし、ほとんどすべての教派もそうでしょうから、むしろ私が異端なのかも知れません。あくまでもこれは、諸先達を通して学んだ福音の見方を元に、もう一度聖書を原文に戻り読み直して示されたことと、自らの体験に重ね合わせて自ずと導かれた私の信仰告白として受け止めていただければと思います。パウロはそう言っていると思わざるを得ないのです。
間違っているかも知れません。皆様ご自身でこの問題を検証して頂き、批判、ご助言いただければと思います。
なぜ、「イエス・キリストのピスティス」が「イエス・キリストへの信仰」と解釈され訳されてきたのか、またそれによってどんな問題があるのか、ということです。
実は、ここを「主イエスへの信仰」と解釈することにより、この人間の側の「信仰」の内容、質が重要な問題となってきました。
パウロの後の世代の人たちは、「では、どういう信仰が正しく、どういう信仰はだめか」というので議論を始め、それが延々2,000年間も続き今日に至っていると言えましょう。この問題でキリスト教各派は相争い、時には殺戮し合ってきました。信仰の〈質〉を問うたためです。
実は、その〈信仰〉をこういうものだと主張するためにできたのが、〈宗教〉 なのです。
宗教の三点セットというのがあります。
まず、「教義」つまり教えです。二番目に「サクラメント」儀式です。三番目に「制度教会」、宗教を維持するための組織です。この「教義・サクラメント・制度教会」の三つが揃うと「宗教」になるのです。
実はこの三点セットを有したものが、キリスト教も含め世の大半の宗教といわれるものです。その宗教と宗教が相争っているのです。どういう「信仰」が正しいのかその〈質〉を問うていくと、自ずとこの三点セットが生み出さざるをえなくなるのです。キリスト教の歴史は、誕生まもなくからすでにその議論が始まり、様々な信仰告白信条が生み出されてきました。それらに基づいて、ローマ・カソリックやギリシア正教が成立しました。それはまた後でお話します。
キリストの福音を「宗教化」するということは、主イエスを偶像化するとまでは申しませんが、偶像のように崇め奉る対象とするわけです。拝む対象とするのです。これは確かに宗教です。
しかし、主イエスの福音は拝むものでしょうか。
「拝め」と主はおっしゃったのでしょうか。
宗教化したキリスト教と、本来の福音は根本的に違うのではないでしょうか。似て非なるものです。
結局は主イエスを偶像化しています。偶像というのは旧約聖書にもありますように、人間が担ぐものです。
神様は人間に担がれるような軽々しい方、小さな方では決してありません。我々の思いを遙かに超えた方でしょう。人間の限界ある言語で表現した教義などで捉えきれる存在ではあり得ません。それなのに、人間の想像できるちっぽけなものに納めようとするのです。
「群盲象を撫でる」という諺があります。
目の見えない人が、それぞれ大きな象を撫でて、例えば足を撫でた人は「象というのは柱のようなものだ」と言い、鼻を撫でた人は「蛇のようだ」と言うように、それぞれ自分が体験した範囲内で把握したものこそが真理だと言い張れば、実際の象そのものを誰一人正確に理解することはできません。それと同様ではないでしょうか。
神様を、主イエスを、教義やサクラメントや制度教会という人間の生みだした小さな枠内に留めそのように見てしまえば、それは本来の姿ではとうていあり得ません。
主イエスは、私たちのちっぽけな思いを遙かに超えて、宏大で深遠な方でしょう。私たち人間の常識を突ききって歴史に介入され、そのピスティスゆえに私たちを愛して下さる方だと聖書は伝えてくれています。
福音の「宗教化」とは、その主イエスのピスティスと愛を人間の思いで小さく狭めてしまうことと言えるのではないでしょうか。
人間が福音を〈宗教〉にしてしまうのです。
神様のダイナミックな業を人間は捉えきれなくて、人間のために神様がなされた業であるにも拘わらず、そうではなくむしろ神を冒するものとして断罪したのが、あの主イエスの十字架でした。
主は私たちに神の愛をもたらすためにこの世に来られたのに、何と人間は、それこそイエスは神でない、神を冒瀆するものだと断罪して十字架につけたのでした。それと同じことなのです。主イエスを信仰の対象として崇め奉るということは、人間が知り把握できるものとして、主イエスを決定してしまうことなのです。私たちの理解できる枠内に収めてしまうことなのです。そうではないのです。福音はもっと宏大で、人間の手中に収まるようなものではありません。パウロはそのことを伝えようとしたのではないでしょうか。なぜなら、彼の体験自体が全く彼の思いも及ばぬ形で、圧倒的な恵みとして臨んだからです。こういうことが皆様にも人生の大小の様々な事件や体験を通して臨んでいましょう。そして、それらを通して主イエスの福音を身を以て受け止められたと思います。
それでは、人類はこの主イエスの福音をこれまで2,000年間どのように受け止めてきたのかを、おおざっぱに眺めてみたいと思います。
まず、主イエスですが、公生涯はたった三年間だったと言われています。その間に何をされたかと言うと先ず、神の支配の到来宣言をされました。「神の国は近づいた」。そして、主イエスの〈ピスティス〉を貫いたために、時の権力者、宗教家、そして大衆によって十字架につけられました。そして、死んで葬られ、三日目に復活されました。
主イエスの抵抗勢力は、まず神殿宗教の担い手であった祭司・律法学者たち、次に、大衆に律法の覚醒運動を展開し、平信徒指導者を自認していたファリサイ派の人たちです。両者に共通していた認識は、「ナザレから良いものがでようか」という疑いであり、また主イエスが自らを神の子としたり、神殿を冒涜したとして告発しました。
主イエスの弟子たちは、十字架の死によって挫折しました。しかし、復活の主の顕現により彼らも再び立ち上がったのです。そして、主イエスの福音とは何かを、聖書(今日の旧約聖書)にその答えを求めました。そこで見出したのが、「自分たちの罪のために死んで下さった」という難しい言葉で言えば「刑罰代受」として受け止めたのでした。イザヤ書53章の苦難の僕は、まさに主イエスのことだという信仰告白です。
また、主イエスは、ローマ帝国の支配からイスラエルを解放する王だという認識もありました。当時のユダヤ教はファリサイ派運動により民衆レベルでも信仰の覚醒が広がっていましたが、弟子たちには、それもまだ不完全で、もっと徹底して神に立ち帰らねばならないというスタンスに立ったようです。主の弟ヤコブなどはユダヤ人らからも尊敬されていました。ですから初期のキリスト教はユダヤ教の覚醒運動の一つ、ユダヤ教の一派(しばしば「ナザレ派」とも呼ばれていますが)というとらえ方もされています。
非常にラディカルで、ファリサイ派よりも律法の根本に迫る生き方をめざしていたとも言えます。当然、彼らの抵抗勢力は、主イエスと同じく既存の宗教の枠に収まっていた宗教人たち、つまり祭司、律法学者、ファリサイ派などになります。また、主イエスを隷属から解放する「王」として主張したことから、時の為政者、サンヘドリンなどユダヤ当局やローマ当局からも睨まれたことでしょう。事実、十二使徒の一人でヨハネの兄弟ヤコブはそのために捉えられ惨殺されたようです。また、ヘレニストたちは、主イエスの神殿批判を受け継ぎました。ステパナはそのために殉教したのです。この時、彼はこのリンチに立ち会っていましたが、パウロは後にこのヘレニストに近い立場に身を置いていました。
パウロは更にラディカルに福音を主張したのでした。神殿とか制度・形式ではなく、彼らの根本であり、一部のキリスト者がもっと徹底せよとしていた「律法」からの解放こそ〈福音〉だと主張したのです。ですから、これはある意味でユダヤ教の全否定と見なされるでしょう。それはまた、ユダヤ教の分派と見なされていた初代キリスト教徒たちからも危険視されたのでした。だからパウロはみんなから嫌われ、抹殺されようしていたわけです。
そのパウロの福音というのは、救いの根拠は神様の側のピスティスで、私たちが救われるのはこの神様の恩寵、恩恵のみによるのだというものでした。人間は全くの受け身です。これは文字通り福音、喜びの知らせです。しかし、これを聞いた異邦人の中には、誤解が生じました。もしパウロのいう通りならば、「我々は救われて完全な者(テレイオス)、完成された者になっている。もう自由なのだ。だから、何をしてもいいじゃないか。どんな悪いことをしても許されるのだから何でもやろう」と主張する人たちがパウロの教えを聞いた中から出てきたのです。ユダヤ人たちはこのことをつまり無規律、容認された放縦を恐れていました。
また、初代のエルサレム本山などキリスト教主流の人たちがなぜパウロの活動を牽制したのかといえば、パウロの主張の論理的帰結としてこういうことが容易に想像できたからです。事実そういう人たちが出てきたわけですから、パウロの教えを危険視し排除しようとしたことは十分理解できます。
パウロはこういう「完全な者」(テレイオス)を自認する者たちとも闘わざるをえませんでした。パウロは、いわゆる「ユダヤ主義者」や彼らに象徴される「原理主義的」な人たち(今回は「割礼主義者(カタトメース)」と呼ばれています)と、自分たちはすでに救われて「完全な者」(テレイオス)になっていると自認している人たちの狭間におかれ、両面での闘いに追われていたのでした。前者は、救われて解放されたからもう自由だと言って何をしても良いわけがなく、何らかの縛り(規範)が必要だと主張し、後者は何よりも自由を主張したのでした。
パウロは、自由を標榜する人たちに対して、自由になったと言っているが実は自分の罪の奴隷になっているに過ぎず本当の自由ではない、キリストにある自由はそうではなくキリストのノモス(律法)の下に止まることであり、それはアガペー(愛)のノモス(律法)である。だからキリストの奴隷なのだと反論しています。自由というのは何をしてもよいのではなくて、キリストのアガペー(愛)を溢れさせるための自由なのです。
では、パウロの後、キリスト教界はどうなったかと言いますと、古代から中世ですが、「キリストのピスティス」が「キリストへの信仰」へと変わったために、主イエスは崇め奉る対象にされ、宗教の三点セット、教義、サクラメント、制度教会が様々な議論を経て確立されていきました。その三点セットの微妙な相違から我こそ正統な信仰だと主張し、それぞれの「宗教」を確立していきました。
それが、ギリシア正教やローマ・カソリックです。これは人間の側の「信仰」の解釈を巡る相違です。
その相違で相争うという悲劇が、2,000年に渡って連綿とくり返されてきました。三点セットのほんのわずかな相違でどれほど多くの人が迫害され、犠牲となり、時には殉死してきたか、歴史はその記録であったと言っても過言ではありません。
「教会と国家学会」の会報作成のお手伝いをさせていただきました。その中に、秋山昇先生による「ロシアにおける教会と国家」という論文がありました。1,000年に及ぶロシア正教会の歴史をご紹介されていますが、その大半がこの三点セットの相違による血で血を洗う闘争の歴史であったといえます。
簡単な例をご紹介します。ロシア正教では儀式の時に、右手を使って体の前で十字を切りますが、その際、従来は指二本で切っていたのを、ニーコン総主教が「教会典礼の改革」を発令し、三本で十字を切ることにしました。これに対して、伝統的な典礼を守ろうとした人たちは抵抗し、迫害を受け集団で殉死していくのです。各地で教会に閉じこもり伝統的な讃美歌を歌いつつ焼身自殺をとげたそうです。
迫害した側も、迫害される側も、徹底的に自分たちの〈律法=ノモス〉(この場合は宗教の三点セット)〉を命よりも大切な譲れないものとして、主張が通らなければ敢えて〈死〉を選んだのでした。
こうした歴史はロシアに限らず、キリスト教史全般にずっと付きまとってきましたし、今日もこの冷徹な現実は変わりありません。
宗教化したキリスト教の負の遺産です。
これがパウロの言う「律法の呪い」ではないでしょうか。
律法といえばユダヤ教の十戒から始まるトーラーだから私たちには無関係だと思ったら大間違いで、パウロのいう〈律法〉というのは非常の根源的なもので実は私たちの中にも〈律法〉があるのです。
キリスト教界に歴然としてあったのは、この宗教の三点セットという形で現れた〈律法〉でした。
途中を飛ばしてしまいましたが、宗教改革時代では、ルターが「信仰のみ」と主張しました。
ただこの「信仰のみ」の「信仰」というのは「主イエスのピスティス」ではなかったのです。
なぜルターが「信仰のみ」と主張しカソリックにプロテスト(抗議)せねばならなかったかというと、カソリックは救いの根拠としてこの三点セットをもちろん掲げていました。ですから「教会の外に救いなし」と主張したのですが、それだけでなく、その三点セットを更に拡大し、救われるためには免罪符を購入せよとか、聖遺物を拝めと勧めたからでした。
色々なものを救いの根拠として提示しただけでなく、教義を広げ、様々な戒律を日常の細部に至るまで広げていきました。
ルターは救いを求めて修道院でこれらの戒律を必死で守ろうと努力したのですが、挫折するのです。自分はもう救われないという恐怖の中から、あのローマ書の「信仰のみ」の言葉によって救いの光を賜ったのでした。
「人は戒律を守ることによって義とされるのではなく、信仰によって生きる」という視点が、あの宗教改革となり、三点セットでがんじがらめのキリスト教界を刷新していったのでした。
ただ、このルターのいう「信仰」はまさに「信仰」だったのです。
主イエスのピスティスとは微妙に違っていました。
だからルターによって始まった宗教改革以降において、も「正しい信仰とは何か」という問題が最大の争点でした。
この定義を巡って様々な主張が生まれ、そこから教派が誕生し、その教派間で、これまた血で血を洗う悲惨な争いを展開したわけです。「何が正しい信仰か」を巡る争いだったのです。
それは主イエスの福音では絶対ありません。ルターもまた大きな間違いの根を残してきたのではないでしょうか。
こんな主張は間違っているかも知れませんが、「主イエスのピスティス」という視点から歴史を見直すとこのように見えてくるのです。
三点セットで宗教化した組織では、その三点セットに合わせられない人は排除せざるをえない。またその三点セットそのものが排除の理由となっているため、心情的には他者をも歓迎したいのに、その人がある一線を越えて自分たちと同じ三点セットの枠内におさまらないといけないところがあるのです。そのためにその人は三点セットに則った「信仰告白」をしたり、受洗したりせねばならないのです。
そこには明らかに歴然とした「ライン」(境界)が引かれています。
しかし、そういうラインはすべて、人間の側がつくった「信仰」を巡る定義から引かれたものであって、神様はけっしてそんなラインを必要とされていないのではないでしょうか。
実は宗教改革によって、カソリックが制限していた救いの枠から解放され、各自の主体性による自由に受け止められるようになりました。これが近代精神の根源です。
ですから、人々は自分の信念に従って自由に意見を述べるようになりました。多くの人が、我こそはかくかくしかじかの真理を有する、と主張したのです。
このことは確かに貴いことでしたが、しかし、これが徹底されていくと、それまで「絶対的」であった教会の権威、聖書の権威すら相対化されていったのでした。
そういう自由もあります。信仰を捨てる自由もあるのです。それが突き進んでいくと、「神は死んだ」という現代に至るわけです。
絶対的な権威を見失い、全ては相対的である。それが極端になると、ただ自分だけが良いとなります。ジコチュウです。それは虚栄にすぎません。それは突き詰めると無神論に至り、「何をしても許される」となります。
そしてそれは倫理の崩壊、社会倫理の崩壊へと突き進みます。今の日本に起きている現象は正にこれではないでしょうか。
このままでは日本が滅びるから、これではダメだと言って、何かワクをつくらなければいけない、もっと誇りを持って生きる指針が必要だということで、愛国心や古来の伝統精神や武士道、教育勅語などへ立ち帰れと提唱する人が出て来るのです。
際限のない自由が蔓延ると社会倫理が崩壊するという危機感から、何か指針になるものを強制的にも教育して植え付けなければならないと考える人がでてくるのです。
けれども、そういう人たちも、究極的には自己を誇る、傲慢に陥ってしまうのです。我こそは、世界一、かつての大日本帝国がそうでした。大東亜共栄圏を標榜し我が国こそ盟主と言ってアジア各地に侵略し、多くのアジアの民衆に辛酸を舐めさせたのでした。アジアを救うのだと言いながら、実は略奪し虐待したのでした。その驕り高ぶりです。これも基本的には「我々は正しいから、何をしても許される」となるのです。高ぶりです。今のアメリカもそうではないでしょうか。かつての大日本帝国の教義が「国家神道」でしたが、ブッシュ大統領は「キリスト教原理主義」あるいは「自由、民主主義原理主義」という言葉があるかどうか分かりませんが、そういうものではないでしょうか。
こうした原理主義的な人たちも、また自由を標榜する人たちも、その魂の最も深いところでは、どこかで「不安と恐れ」に取り憑かれているのです。
それは誰にでも訪れる冷徹な「死」への恐怖です。
真の安らぎに浸っていないのです。だから何とかして、自分たちの安心を得たいという強い思いがあって、そのために、ある者は自分の思うが儘にやりたい放題に振る舞い、他方は何かの縛りに自分たちを雁字搦めに縛りつけることで粋がっている、強がっているのではないでしょうか。
この両者で議論しても、何ら積極的な議論は成立しないでしょう。
互いに自己の主張をがなり立てるばかりです。
なぜなら、この恐れと不安に取り憑かれた世界から私たちを真に解放するのは、この両者のいずれでもなくキリストのピスティスによる福音だからです。神様の側からの介入でしか〈義〉は実現しないのです。人間がいろいろあれこれ努力してもできっこないのです。これがパウロのいう福音と〈律法の呪い〉の現実です。自分たちで何とかできる、何とかしようとするのが〈呪い〉なのです。
では、パウロのいう〈律法〉とは何だろうか。これを次に皆さんとご一緒に考えたいと思います。ここからが本来の第二講になります。
「律法の呪い」からの解放
6.律法とは
(6-1)ユダヤ人にとって律法
まず、律法とは何でしょうか。狭義では、イスラエルの民がヤハウェの神より賜った生きる指針で、「トーラー」(旧約聖書=ユダヤ聖書の最初の五書)を指します。ギリシア語で「ノモス」と言い意味は「掟、慣習法、規範、法則」を指します。
ユダヤ人にとって「律法」とはなくてはならぬものです。「律法を守る」ということは、生きることそのものなのです。イコールなのです。彼らの生き甲斐です。
ですから〈律法〉は私たちにとって言えば、生きるための必須条件とでもいいましょうか、「自分達を自分達たらしめるもの」とも言えましょう。旧約聖書に残されたユダヤ人の歴史は、正にこの律法を巡る葛藤でした。律法を守らなかったが故に、祖国滅亡とバビロン捕囚という苦い体験をしました。そこから「律法を守らなかったからこうなった」という激しい悔いが起きました。そして、それは「律法に帰れ」という原点復帰運動となり、さらにそれが律法の〈絶対化〉へと至ったわけです。
(6-2)イスラエルの現状
ユダヤ戦争によってローマ帝国に滅ぼされて以来、ユダヤの民は祖国を失い、帝国各地へと離散していきました。その後、キリスト教が権力を握るとユダヤ人は迫害の対象とされ、「ホロコースト」などという激しい迫害を繰り返し受けてきました。にもかかわらず、彼らのアイデンティティを失うことなく今日に至っています。これは例えば日系移民たちと比較するとよく分かります。ほとんどの日系移民は三世当たりで日本人としてのアイデンティティを喪失し、その国に同化してしまいます。もちろんこれはDNAの問題ではありません。ユダヤ人にとって〈律法〉が如何に生活の指針となり伝統となり、アイデンティティであるかを如実に示しています。
(6-3)紀元1世紀のユダヤ教界
では紀元1世紀のユダヤ社会ではどうだったのでしょうか。
聖書などの記述を参照すると、まず、「ファリサイ派」という人々がいました。青年パウロも当初この派に属していたようです。彼らは庶民レベルで宗教覚醒運動を推進していた人たちでした。彼らは律法を表面だけの儀礼的に遵守するのではなく、根本精神から尊び守ろうとする真摯な宗教運動だったようです。
次に、「エッセネ派」という人たちがいました。彼らは悪の誘惑に溢れている俗世を離れ特殊共同体環境の中で律法の実践を目指していました。バプテスマのヨハネや、主イエスもこの運動から派生したと見る学者もいますが、彼らは閉鎖的、隠遁的な傾向が強く、やがて歴史から消えていきました。
次に、政治的傾向の強い「ゼロータイ」つまり熱心党ですが、彼らは神の支配到来実現に身を挺しており、神以外の支配者への抵抗運動を展開しました。現在の武力テロを推進するイスラム原理主義者たちに共通する生き方かも知れません。
こうした「律法」を巡る様々な生き方が提示されていたにも拘わらず、ローマの属国として、また一辺境の国家として、様々な困難を抱えたユダヤ社会に、新たな宗教覚醒運動が起きました。それが、洗礼者ヨハネと、主イエスの運動です。「ヨハネ教団」とも呼ばれる洗礼者ヨハネの運動は、原始キリスト教会以上に当時は勢力を伸ばした運動だったようです。彼らもまた悔い改めの洗礼を授け、律法の真意からの実践を目指したユダヤ教覚醒運動でした。
主イエスの活動
当時の人々にはナザレ出身のイエスの運動は、律法の本義に立ち帰れ、というファリサイ派的な預言者的覚醒運動に映ったようです。しかし、イエスの妥協の余地のない神殿粛正や宗教家批判、加えて自らを「神の子」とか「イスラエルの王」と自認する発言などから、為政者や宗教家から強烈な反発を受け、神を冒涜する者として宗教裁判で断罪されました。また当局からは政治的クーデターを企てた咎で政治犯として十字架刑に処せられました。
残された弟子たちは、イエス運動に挫折しましたが、その後、復活の主の顕現を賜り、毅然として立ち帰りました。そして、主イエスの十字架と復活の意味を旧約聖書に尋ね求めたのでした。その中で、イザヤ書53章に示された苦難の僕の姿に着目し、十字架による主の犠牲は、「なだめの供え物」であるという「刑罰代受」の信仰が定着しました。
しかし、当時のユダヤ人には、彼らの弟子たちの集団は、あくまでのユダヤ教内の覚醒運動に映ったようです。それを今日ユダヤ教「ナザレ派」と表現する学者がいます。事実、主イエスの兄弟ヤコブを中心としたエルサレム本山は、エルサレム神殿での礼拝と律法の厳格な遵守を身を以て実践する集団だったようです。彼らは、紀元66年のエルサレム神殿崩壊と共に、やがて消滅していきました。
パウロ
パウロは若き日よりファリサイ派であり、熱心党にも近かったようです。ですから、誕生間もないキリスト者たち、中でも神殿批判を先鋭化したヘレニストたちの迫害に熱心でした。「律法の義については非のうちどころのない者」と自認していたと述懐しています(フィリピ3.6)。
その真っ最中に、《復活の主の顕現》に遭ったのです。それは、それまでの彼の生き方そのものが、根本的に倒錯であり、全否定されたことを意味します。彼は完全に打ちのめされたのでした。しかし、それは「死」ではなく新生への一歩でした。まさに目から鱗が落ちるような体験だったのです。そして、彼は主の顕現前の自身の生の根幹であった「律法」の本質に向き合ったのでした。
7.私たちの〈律法〉
(7-1)私たちにとって〈律法〉とは?
ユダヤ人にとっては「生きるために必須要件」であり、「自己肯定感」また、帰属感(アイデンティティー:自己同一性、主体性)、自分や共同体をしっかりと立たせるもの、自己と共同体を他者から守る城壁、他と区別する基準、ともいえましょう。
イエス様やパウロたちの時代における律法とは、旧約聖書のトーラーでした。
では、私たちにとって律法とは何か、上述の生きるための必須要件、自己肯定感、帰属感、アイデンティティを持つためのものというようなことから考えますと、例えば習慣とか風習、伝統、家訓、迷信、占い、家風、社風、これは会社務めをしておられる人は肌身に感じておられると思います。それから、思想、信条、宗教などです。
また、おおよそ「何々主義」と呼ばれるものは殆どがこれに該当するのではないかと思います。(注:主義〔principleの和訳〕広辞苑による定義では、「思想、学説などにおける明確な一つの立場、イズム。または特定の制度、体制または態度。堂々もっている意見、主張」とあります)。
例えば、次のようなものがあります。政治的なものとしては、先の大日本帝国のバックボーンであった皇国思想と国家神道、列強の帝国主義、ナチス・ドイツの反ユダヤ主義、スターリン主義、毛沢東主義などの共産主義など、いずれも征服や弾圧、粛正という悲劇を産み出しました。今日で言えば、北朝鮮の主体(チュチェ)思想もそうかも知れません。民族主義、家族主義もそうでしょう。ナショナリズムは21世紀の今日においても依然、強烈な自己主張の根源です。家族主義というのは、最近韓国のプルム平和園の元敬善先生の出版をお手伝いさせていただきましたが、元先生はこの家族主義が世界平和実現のために克服せねばならない問題だと指摘されています。これは韓国や日本を含む東洋共通の問題かも知れません。
人生の生き方の観点から見れば、現代の「律法」としては、まず経済至上(市場原理主義、利益優先主義)が上げられます。巨大企業が生き残るために、子会社、孫請け、ひ孫受けの下請け零細企業にすさまじいコストカットを強いています。たった半歩でも無駄を省け、との至上命令があります。その効率主義は徹底していて、だからこそ、シェア争いに生きのびてきたと擁護されていますが、今それが品質の低下、技術レベルの低下などの形で揺らいできています。
それから次に幸福至上主義、これは皆さんほとんどすべての人がそうではないでしょうか。若い人たちは言います。「今、自分たちが幸福であればいい」と。
そして、健康至上主義。これも皆さんそうでしょう。健康が何より大事。健康は確かに大切ですが、お会いしてまず「お体どうですか?」と訪ね、健康のことだけが話題になってお別れするのがほとんどではないでしょうか。本当はもっと大切なこと、もっと尋ねなければならないことがあると思います。また、いつも健康に不安を抱え、毎日病院巡りで日がな一日過ごす人も多くいます。次に、科学万能主義、科学で説明できないことはないというものです。効率主義・能力主義などもそうです。
イスラム原理主義やキリスト教原理主義などもそうです。また、日本人の特質として中山治氏が指摘する「情緒原理主義(中山治『無節操な日本人』)」、これは「情緒がすべての中心にあり、それが認知や行動を大きく支配した生き方」とありますが、確かに私たちの行動傾向を言い表しています。それから山本七平氏がかつて指摘した「空気の支配」(山本七平『空気の研究』)、これも「律法」かもしれません。
以上思いつくままに上げましたが、それぞれに「教義」と「サクラメント」と「制度組織」の三点セットに相当するものが自ずと生じています。
共通する特徴は何かといえば、「我こそは、私たちこそは正しい」という強い主張で、さらにその生き方に高い誇りを抱いています。そこには何の疑いも抱いていません。それが当たり前、当然だと思っています。また、そうでなければおかしいという強迫観念すら抱きます。ですから、しばしばテレビなどで討論番組がありますが、ほとんどが自分の主張ばかりを述べるに終わり、議論が成立しないことが多いです。何故かと言えば、本当の意味での真理に対する畏敬の念、謙遜の念がないからです。それぞれが、我こそは最高の真理を持っている信じ切っているからです。
(7-2)〈律法主義〉による混乱と破壊
では、このような「律法」(私たちの当たり前)に支配された社会はどうなるかと言えば、実は今日の日本の現状がそれを示しています。まず、我が国の借金は、 827兆円 (1人当たり648万円)となりました。皆さんこの金額を今すぐに支払えますか? 実はこの金額は既に648万円ではありません。この瞬間にもどんどん金額がつり上がっているのです。あるホームページでは我が国の借金をリアルタイムで表示していますが、その数字はめまぐるしく増加しています。確か三年前にご紹介したときは総額666兆円だったと思います。それから既に200兆円も膨れ上がっています。
何故こんなに借金をしているのでしょうか。実は、これは先ほど申し上げた、私たちの「幸福至上主義」によるのです。今の自分たちの生活が豊かになることを願い、予算を積み上げ、借金をして享受しているのです。私たちが享受するこの便利さ、繁栄は正に、借金という虚構の上に築かれたものなのです。今の幸福のために次の世代にツケをまわしているのです。
一旦火がついた欲望は抑えられません。際限なき欲望の充足という呪縛にはまっているのです。かつて鈴木弼美先生は私たちの結婚式の祝辞で、「経済成長は神の刑罰」とおっしゃられ、当時はびっくりしましたが、確かにそうだと思います。私たちは今、神様が日本を借金地獄という状況に放置されるという「刑罰」を受けているのではないでしょうか。
次に、「負け組」に冷たい社会です。
今年も昨年の統計が発表され、自殺者はまたも3万人を超えました。交通事故死の四倍強です。自殺者というと若者たちの集団自殺などが注目されますが、統計を分析すると、その70%が50代以上の中高年男性なのです。かつては一家の大黒柱と呼ばれた人たち、家族のため、自分のために毎日懸命に働き、就業してからは会社のためが加わり、まもなくリタイアして余生を悠々自適に過ごそうと夢を抱く年代の男性たちが、人生の頂点で挫折して、絶望して自らの命を絶っていくのです。
これが私たちの社会です。いわゆる「負け組」のレッテルが貼られたときにどうならざるを得ないか、思い知らされる数字です。能力主義、成果主義、効率主義という〈律法〉が生んだ切り捨て社会ではないでしょうか。
三番目として、「個」の抹殺が上げられます。
かつて軍人勅諭にこんな言葉がありました。「義ハ山岳ヨリモ重ク死ハ鴻毛ヨリモ軽シト覚悟セヨ」。
しかし、これは戦前戦中の話ではなく、今も私たちを縛っているのではないでしょうか。「義」、大義名分と言ってもいいでしょう。会社のために、社会のために、国家のために、など何々のためにと言う大義に殉じて、私たちは命を削っています。また企業では組織維持の大義名分と利益最優先のために、人間性を奪われています。利益を上げるため経費をカットせねばならず、そのためアルバイト、派遣、外国人労働者などを低賃金で酷使しています。また、パート職でも責任だけ負わされて、殆ど保障もなく、不要になればすぐに解雇される、まさにふっと吹けば飛んでいく「鴻毛」よりも軽いものではないかと思います。以前、義母の本(『風の町で』)を作成しましたが、戦前のある町の風景を写した写真がありました。洪水で橋が流されようとしているのを、村の男衆たちが重しとして橋に乗って橋を守ろうとしていました。まさに、人名より橋が大切という価値観なのです。今の日本にもこの写真と同じような光景が至るところで見られるのではないでしょうか。
四番目に〈律法〉の対立が上げられます。これは「正義」対「正義」の衝突から起きる戦争やテロがまさにそうです。
イラク戦争やアフガニスタン攻撃も然り、イスラエル・パレスチナ紛争もそうです。また、今問題になっている北朝鮮と我が国の問題も、互いに抜き差しならぬ正義対正義という構造がありましょう。
これは何も、国家対国家の問題だけではありません。自他を区別し他者を排除するという形で明らかになるものです。自分を良く思うためには、他者を蔑むわけです。「優越感と劣等感は表裏一体、コインの裏表の関係」なのです。
秋田で起きた連続児童殺人事件の容疑者に関するテレビの報道で驚いたことがあります。それは、容疑者の高校卒業文集で彼女への同級生のメッセージに、まったく聞くに堪えないような言葉が連ねられていたことです。「死ね」とか「帰ってくるな」とか、「何年後には殺人者」とか、そういう言葉が文集に平然と連ねられていました。彼女はそういう状況の中で青春時代を送ってきたようです。同級生たちはどういう思いからそんな言葉が書けたのだろうか。ふざけたと言えばそれまでですが、それだけではないと思います。子供たちの間にあるイジメや排他、無視などにも、この〈律法〉に連なる問題が根深くあると私は思います。
〈律法〉は自分、あるいは自分たちと異なる他者を拒否し、告発します。
パウロはこれを「実に律法は怒りを招く」(ローマ4.15)と表現しています。
正に、今世界中で溢れている〈怒り〉の根源は、それぞれの〈律法〉ではないでしょうか。
山本七平氏はこんなことを言っています。
…『旧約聖書』の筆者が、何をサタンと呼んだか、なぜ神の傍らなる告発者を悪魔と呼んだかが、おぼろげながらわかるように思いました。……人が義を口にするとき、正義の側に立って告発するとき、それがじつは憎悪であって「愛」ではないという恐るべき事実の指摘です。
(山本七平『すらすら読めるイエス伝』講談社+アルファ文庫82ページ)
「サタン」というと、私たちは人間を超えた悪魔的な存在を思い浮かべますが、実はサタンは天使で、義の番人、不義を告発する者です。
キリスト教団体や平和団体でもこれがあります。彼らの主張はもとより正しいのです。しかし、それを主張するとき果たして〈愛〉から発せられた言葉なのだろうかと疑わざるを得ないような、もしかしたらこれは憎悪ではないかと感ぜられる発言がしばしば見られます。
〈正義〉の側に立っているという罠です。平和団体、福祉団体、政党など〈正義〉の側に立つと自認する集団がよく陥る落とし穴です。それは 「自分たちは正しい」と確信するがゆえに、他者を断罪し〈怒る〉つまり、これが自己絶対化の呪縛、呪いです。これが〈罠〉なのです。これについて藤尾正人先生が次のような文章を発表されています。
「アーメンと言えない祈り」
「その日、荻窪栄光教会の一室に集まった5人は、机の正面に森山諭牧師、左右に向き合い酒枝義旗先生と安利淑女史、下座に待晨堂の市川昌宏店主とわたし。1973年春のこと。
それは安利淑著「たといそうでなくても」についての話し合い。安さんは、著書が書店に並ばない理由。続刊しないのはなぜか。2万部も売れたなら著作権料をいただきたい。
酒枝先生の答え。群小出版社の本は本屋に並ばぬ。だから「朝日・書評」をねらった。続刊休止は待晨会堂の数千部を行事のたび移動する会員の苦労休止のため。定価は破格の1200円で利益はない。著作権料代わりに米国へ著書数百部発送済み。
森山牧師は市川さんの発送の苦労を語った。安さんは「そんな苦労は殉教した韓国の聖徒に較べ、ち〜さいことです」。 話し合いは平行線。酒枝先生は別に用意されたお金を渡された。力が抜けた。
森山牧師は「あすはイースター。祈りましよう」。森山、酒枝、市川、わたしと祈った。最後の安さんの祈りにわたしは「アーメン」と言えなかった。
神社参拝を拒否して6年もピョンヤンに入獄した安さんの祈りは「この本の出版を阻むものを呪ってください。その呪われたことをその身にあらわしてください」。以後わたしは、迫害に耐えたなどを、たいしたことと思わなくなった。人間が何をしたかでなく、キリストが何をされたかが大事だ。
「迫害する者のために祝福を祈りなさい。呪ってはなりません」(ローマ12・14)
以上、引用は「藤尾正人(http://d.hatena.ne.jp/shirasagikara/)ブログ2006年5月19日より」
自分たちが絶対的に正しいという立場に立つとき、人間は「律法の呪い」の縛られているのではないでしょうか。
この呪いから解放されなければ、人は本当の自由ではないのです。
例えば最近こんなことがありました。戸田市教育委員会の伊藤良一委員長が、君が代斉唱時に起立しない教員や父兄に対して「はらわたが煮えくり返る」発言し問題視されました。「規律を乱すことは教育の場では許されない」との弁解をされましたが、「はらわたがにえくりかえる」とは、思わず本音の言葉が突いて出たのでしょう。彼はまさに、「律法」に捕らわれた人でしょう。だから、自由に振る舞っている人たちに対して、許せない怒りと反撥を感じたのだろうと思います。今彼のような人がどんどん増えてきています。
しかし、これは人ごとではありません。私たちも実は「律法」に捕らわれた存在ではないでしょうか。普段、夫として、妻として、親として、子供として、上司として部下として、自分の「律法」に捕らわれていないでしょうか。子供への価値観の押しつけなどしばしばあります。先日もある高名な先生が講演中に、「子育てに失敗しまして」と発言されました。おそらく謙遜しておっしゃられたのだろうと思いますが、実は子供の側から見れば、それは軽々しく言われたくないことでしょう。人生の先輩として、自分は成功し信仰も持てたという暗黙の自負が、知らないうちに高みから我が子を見てしまっているのではないか、ふとそう思わされました。
まさにこれらも「律法の呪い」(3.13)ではないでしょうか。
それはまた、迫害に狂奔していたパウロの姿でした。
彼は律法に忠実であればあるほど、命がけになればなるほど、実は主イエスご自身や主にある者を迫害・抹殺するという倒錯のめり込んでいったのでした。それは、実は最も仕えねばならないはずの神様を、自らの「律法」によって拒否したことなのです。それがまったく分かっていなかった。まさに倒錯です。的外れです。聖書は罪を「ハマルティア」(的外れ)と言いますが、まさにその意味でこれが罪なのです。
自分が「律法」に捕らわれているかどうかを簡単に見分ける方法があります。
それは自分だけでなく、他者も客観的に見られるかどうか、さらに言えば、他者の言うことを冷静に聞くことができるかどうかです。
「律法」に捕らわれているときは頭がかっかとして、こういう考えしかないと思いこんでいますから冷静な判断はできません。相手の意見も率直に聞けません。相手がちょっとでも発言しようものなら、すぐに自説を主張してしまいます。子育てのときによくありますね。子供が何か言い訳をしようとすると、すぐにしかり付けてしまいます。そういう時は、自分が「律法」に捕らわれているのです。
それは決して福音ではありませんし、そこからは建設的なものが生まれてきません。これが〈律法の呪い〉に捕らわれているかどうか、よく分かるバロメーターです。
私たちが陥りやすい罠は、自分たちが正しい側、福音を知っている側にいると思い高みに立って他者にアプローチし、裁く側に立ち易いということです。「律法の呪い」に取り憑かれてしまうのです。
パウロが闘ったユダヤ人やユダヤ的キリスト者たちのようになってしまうのです。
8.〈律法の呪い〉からの解放
では、どうしたらこの(律法の呪い)から解放されるのでしょうか。
(8-1)主イエスのまなざし
主イエスはまさに律法に徹した宗教人(ファリサイ派と律法学者)と闘われました。福音書に残された主イエスの激しい非難にそれが現れています。
自分の「律法」に捕らわれている者に対して、たとえば「杯や皿の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちている」(ルカ11.37-52)とか「知識の鍵を取り上げ、自分が入らないばかりか入ろうとする人々おも妨げてきた……」ルカ(11.52)とか、「あなたたちは人に自分の正しさをみせびらかす」(ルカ16.15)と言っています。
これに対して、非難されたファリサイ派や律法学者たちの反応はどうだったでしょうか。「彼らは怒り狂って、イエスを何とかしようと話し合った」(ルカ6.6-11)ようですし、また「激しい敵意を抱」(ルカ11.53)いたとあります。正にパウロの言うように「律法は怒りを招」いたのです。そして、それが主イエスを十字架に釘付けにしたのです。
では、主イエスのまなざしはどこに向けられていたのでしょうか。私はこの問題を考えるとき、いつも福音書のあるエピソードを思い起こします。それは、ルカによる福音書18章にある「ファリサイ派の人と徴税人」(ルカ18.9-14)です。
自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人々に対しても、イエスは次のたとえを話された。「二人の人が祈るために神殿に上った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って、心の中でこのように祈った。『神様、わたしはほかの人たちのように、奪い取る者、不正な者、姦通を犯す者ではなく、また徴税人のような者でもないことを感謝します。わたしは週に二度断食し、全収入の十分の一を献げています。』ところが、徴税人は遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。『神様、罪人のわたしを憐れんでください。』言っておくが、義とされて家に帰ったのは、この人であって、あのファリサイ派の人ではない。だれでも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。」
このファリサイ派の人は「自分は正しい人間(ディカイオイ)だとうぬぼれ(エクスーセヌータス=他を軽んずる)」ていました。そして彼は、当時律法に忠実で正しい生き方を求めていた者たちの祈りを代弁しています。それは、自分は「奪い取る者、不正な者、姦通を犯す者、徴税人のような者でないことを感謝します」というもので、自らが正しい側にあることを神に容認してもらう祈りです。次に、その保障として「週に二度断食し、十分の一税を献げています」とし、神の御前に自己誇示と正統性を主張しています。これは正に神様にとって「高ぶる者」そのものです。
「高ぶる者」の原語は、ヒュプソーン エアウトン=「自分自身を賞賛する」つまり自画自賛です。自惚れ(己惚れ)です。英語で言えば、false pride (自惚れ、高慢)でしょうか。人にはプライドが大切です。それは英語ではtrue pride(自尊心、プライド、誇り)と言いますが、その真逆がfalse pride 自惚れです。
これに対して、「義」とされた徴税人は、「遠くに立って、目を天にあげようともせず、胸を打ちながら、……「神様、罪人のわたしを憐れんでください」と祈りました。彼には自分を誇るようなものは微塵もありません。むしろ、「律法」を犯している罪人だという自覚に打ちのめされていました。聖なる神殿に近づくこともできず、目を高くあげることなど到底できず、己の不甲斐なさに「胸を打ちながら」祈るばかりでした。彼には誇るべき「律法」は微塵もなかったのです。しかし、主イエスのまなざしは、まさしくこうした低くされた人に注がれたのです。その瞬間、彼が義とされていたのでした。
(8-2)パウロの闘い
次に、パウロの「律法」との闘いを見てみましょう。
前講でパウロが「ガラテヤ書」でこの問題と真正面から向き合っていたことを学びました。
彼は、次のように断言します。「律法の実行によっては、だれ一人として義とされないからです」(2.16)。
これは正に、復活の主の顕現に会う前のパウロ自身の生き様でした。
青年時代のパウロは「先祖からの伝承を守るのに人一倍熱心で」同年配の誰よりも「ユダヤ教に徹し」(ガラ1.14))「律法の義については非のうちどころのない者」を自認すらしていたのでした(フィリピ2.6)。ですから律法の何たるかを、彼を責めていたユダヤ教徒やユダヤ主義的キリスト者の誰よりも身を以て痛いほど知っていたのです。おそらく傍目には彼の姿は、彼の自認するとおりだったのでしょう。彼はユダヤ教の、またファリサイ派のホープとして先輩や同僚たちからも期待されていたに違いありません。しかし、彼はその時は気付かなかったでしょうが、実は深い深い罪に捕らわれていました。その実体に盲目になっていたことを後に述懐し、その罪が「貪り」であったことをローマ書7章で告白しています。「ところが、罪は掟(エントレー)によって機会を得、あらゆる種類のむさぼりをわたしの内に起こしました」(ローマ7.8)。
掟はエントレーといい律法(ノモス)の個々の戒めを指します。律法を完璧に守り神に仕えていると自認していても、「貪り」という十戒の第十番目の戒めを犯す自分が魂の奥底に潜んでいたのでした。そんな彼には、真の平安はなかったのです。パウロはこう述懐しています。
律法の実行に頼る者はだれでも、呪われています。「律法の書に書かれているすべての事を絶えず守らない者は皆、呪われている」と書いてあるからです。律法によってはだれも神の御前で義とされないことは、明らかです。(3.11)
だから一層熱心に「ユダヤ教に徹し」ていたのかもしれません。そしてその結果、主の僕たちを抹殺しようとしたわけです。
殺してもよい、むしろ神を冒涜する因子として積極的に排除せねばならないとの思いに駆り立てられていました。青年パウロの頭からは、かっかと怒りが発していたことでしょう。「実に律法は怒りを招く」でした。その怒りの頂点で、復活の主イエスの顕現に出会ったわけです。
キリストは、わたしたちの呪いとなって、わたしたちを律法の呪いから贖い出してくださいました。(3.13)
この「律法の呪い」、自分たちでどうしようもない、がんじがらめの呪縛から解き放ち給うのは、神様の介入以外あり得ません。それが主イエスの十字架による福音です。
人間は元来、自己中心的で己の「腹を神とし」(フィリピ3.19)「自分の腹に仕えてい」ます(ローマ16.18)。この自己中心(ジコチュウ)な自分を「絶対化」し、それを最強にバックアップするものこそ、様々な「ノモス(律法)」ではないでしょうか。
なかでも「律法(トーラー)」は、ユダヤ人にとって絶対者である神から賜ったものでした。それは人間的なノモスとは比較にならない最強の根拠でした。事実、パウロも律法の意義を、ガラテヤ章3章19節から24節において、主イエスのピスティスが現れるまでの「監視役」「養育係」として神聖なものであり、神の恩恵だと見なしています。(括弧内は横江の補足)
「律法とはいったい何か。律法は……違反を明らかにするために付け加えられたもの」(19節)
21それでは、律法は神の約束に反するものなのでしょうか。決してそうではない。万一、人を生かすことができる律法が与えられたとするなら、確かに人は律法によって義とされたでしょう。22しかし、聖書はすべてのものを罪の支配下に閉じ込めたのです。それは、神の約束が、イエス・キリストへの信仰(イエス・キリストのピスティス)によって信じる人々に与えられるようになるためでした。
23信仰(このピスティス)が現れる前には、わたしたちは律法の下で監視され、この信仰(ピスティス)が啓示されるようになるまで閉じ込められていました。こうして律法は、わたしたちをキリストのもとへ導く養育係となったのです。わたしたちが信仰(ピスティス)によって義とされるためです。
しかし、この神聖で神の恩恵たるトーラーも、人間の手中にされたとき、他の人間的な自己絶対化の根拠たる習慣・伝統・宗教・信条・思想・「空気」などとは、比較ならない強力な裏付けとなって、人を怒りの駆り立てていきました。
それは頑強さとなり、また、〈誇り〉が〈傲り〉へとすり替えられていきます。恩恵である〈律法〉が人間の自己絶対化の根拠にすり替えられる、これこそ「律法の呪い」ではないでしょうか。
神でさえも許さない絶対性を手中にするという倒錯、この自己絶対化から解放されるには、もはや死ぬしかありません。パウロはこの消息を次のように伝えています。
わたしは神に生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。わたしは、キリストと共に十字架につけられています(現在完了形「つけられたままです」)。生きているのは、もはやわたしではありません。キリストがわたしの内に生きておられるのです。」(2.19-20)
この十字架によって、世はわたしに対し、わたしは世に対してはりつけにされているのです。(6.14)
主イエスと共に十字架につけられ「死ぬ」ことで、律法の呪いから解放されるというのです。
このことは人間の論理で理解できる消息ではありません。
パウロも、限界ある人間の言葉で説明しにくいこの奥義を、何とかして言葉に言い表そうと試みたことでしょう。その足跡が彼の書簡に認められます。論敵との論争はその意味で非常に有益だったことでしょう。また、エクレシア内で起きた様々な問題を通して、信徒たちには身を以て福音の奥義を得心させたかもしれません。そうした葛藤の末生み出された珠玉の言葉が、彼の書簡として残され、また聖書に編纂されて私たちの手にも届けられているのです。
では、「十字架」とは何でしょうか。
私たちにとって「十字架」につけられて死ぬということはどういうことでしょうか。
これについては正直私もよく分かりません。しかし、わずかな人生体験や、先輩たちの証から、十字架とは人生の〈事実〉、特に人生の様々な苦難、不条理、不幸、悲劇等ではないかと思います。病気や家族の問題、仕事や社会の問題、時には戦争や飢餓など、こうした人生の不幸や悲劇と呼ばれるものに出会ったことのない人は一人もいないでしょう。苦労の差は大なり小なりありましょう。それぞれその人に相応しく、時に応じて、分相応にそうした苦難とも言える十字架を神様はご用意され、私たちは負わされます。
自分の〈律法〉に捕らわれていると、それらは受け入れがたいものです。「律法を守っているのに、私が何をしたというのだ。何故、私は祝福されないのか」。あるいは、「律法を守らなかったからこの悲惨さに遭わされたのか」。もしくは、「こんな不条理はあってはならないものだ」、「自分の基準(ノモス)から言ったらあり得ないのに、何故だ」という訴えに近い疑問をいだくでしょう。不条理と思える事態に、しばしば私たちは直面し困惑します。天災や事故など人災で、朝元気に出かけていった家族や友人に二度と会えないという悲劇もあります。そうした不条理を前に私たちはただ絶望するばかりです。「神も仏もあったものか」と天を呪いたくなることでしょう。これは今回学ぶ「ヨブ記」のテーマでもあります。
その時、自分の〈律法(ノモス)〉にしがみつくか、あるいは「どうにでもなれ」とやけになってしまうかではなく、主イエスと共にその十字架につけられているのです。十字架を甘受するのです。そこへ主イエスのピスティスが突入してくるのです。
どんなに絶望的な状況であっても、私たちの「義」は約束されている、保障されているという平安を賜るのです。
ですから、たとえこのままこの病気で亡くなっても、このまま不慮の事故で死んだとしても、予想外の悲惨さの中におかれても、自分の会社が倒産しても、国家が崩壊しても、主イエスのピスティスは不動だから、私たちの義は約束されているという安心を得るのです。たとえ私たちの外観(スケーマ)がボロボロになっていっても、主にあって私たちの本質(モルフェー)は神様の懐で安らげるという約束です。その喜び、その希望が私たちを義、つまり、神を恨み拒絶するのではなく、赤ちゃんのようにその懐で安らぎ委ねることが許されるのです。
神は真実な方(ピストス)です。あなたがたを耐えられないような試練に遭わせることはなさらず、試練と共に、それに耐えられるよう、逃れる道をも備えていてくださいます。
(Ⅰコリ10.13)
前講でご紹介した湖北のおばあさんは、人生の苦難に耐え、どんなに辛くとも人前では姿勢を崩さずニコニコと静かにしていました。名もなき多くの庶民がそうであるように。しかし、主は伊都子さんを通して語りかけます。「泣いてもいいんだよ、叫んでもいいんだよ」と。そして、いまわの際で読まれた聖書の一句に、湖北のおばあさんはせき止められてきた思いを一気に溢れさせ、声を挙げて泣いたのでした。その涙は何よりも貴い天への献げものでした。ヨブ記の御言葉に通じる「涙」です。
このような時にも、見よ
天にはわたしのために証人があり
高い天には
わたしを弁護してくださる方がある。
わたしのために執り成す方、わたしの友
神を仰いでわたしの目は涙を流す。
(ヨブ記16.19-20節)
私たちには「わたしのために証人」であり、「弁護してくださる方」、「わたしのために執り成す方、わたしの友」である方、ピストスな方がいらっしゃるのです。
それこそ、私たちにとって何にも代え難い喜びではないでしょうか。そ
れも神の御子である主イエスなのです。
まさに「神の御子が、もったいない、もったいない」ではないでしょうか。
十字架を通して、この喜びへの道が開けているのです。まさに「十字架のメド」(針の糸を通す穴)なのです。
今日一日流した涙と心の痛みを
永遠の希望につなごう
ワタシの永遠の希望の糸は
どんなに弱くつても
十字架のメドを通って
天国の生命に結ばれる
(樫葉史美子『十字架のメドを通って』)
内村鑑三は次のように言いました。
人生の目的は神を知るにある。その他にない。金をためるのではない。人にほめられるのではない。哲学と美術とを楽しむのではない。神を知るにある。これが人生の唯一の目的である。この目的を達せずして、人生は全く無意味である。ほんとうの夢である。この目的を幾分なりと達せずして、最も成功せる生涯も失敗である。……(内村鑑三)
この十字架を共に担ってくださる主イエスこそ、神のピスティスをお示し下さった方であり、この主イエスと出会うことが人生の究極の目的ではないでしょうか。
9.福音の自由に生かされて
エゴの克服
今日のあらゆる社会問題は、「自己(エゴ)」を如何に超克するかにかかっています。先の講習会でも紹介させていただきましたオスカル・ロメロの詩をもう一度読みます。
われわれが謙虚になり、
その謙虚さからのみ、
われわれが贖罪者となって、
世界が本当に必要としているような仕方で、
協力し合うことを学ぶことができるためには、
われわれはあまりにも多くの偶像を、
そして何よりもまず自己という偶像を、
打ち倒さねばならない。
─ オスカル・ロメロ ─
(『われらの悲しみを平和への一歩に』(岩波書店)巻頭の詩)
「あまりにも多くの偶像」とは、思想、文化、宗教、そして今日じわじわと、しかし大胆に台頭してきた我が国のナショナリズムなどが入るでしょう。今回の講義で言えば、それらは〈律法〉とも言いかえることができます。
しかし、「そして何よりもまず自己という偶像を」という一節が迫って参ります。
どんなに寛い心を抱こうと志し努力しても、また正しく生きようとしても、否、むしろパウロのように正しく生きようとすればするほど、この「偶像」に呪縛されていきます。
それは頑固さとなって現れ、罪となって噴出します。
まさに「うなじ堅き者」です。
「正しく生きよう」という生き方、まさにここに「律法の呪い」があるのです。
人は自分自身によっては、そこから中々抜け出せません。それこそ、「自分が死ぬ」しかないのです。
まさにそこに、主イエスの十字架の福音の逆説が、鋭く差し込んでくるのです。
パウロはそれを次のように言っています。
目の前に、イエス・キリストが十字架につけられた(現在完了形「十字架につけられてしまったまま」岩波訳、「十字架につけられ給ひしまま」文語訳)姿ではっきり示されたではないか。
キリストは、わたしたちの呪いとなって、わたしたちを律法の呪いから贖い出してくださいました。(3.13)
わたしは神に生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。わたしは、キリストと共に十字架につけられています(現在完了形)。生きているのは、もはやわたしではありません。キリストがわたしの内に生きておられるのです。」(2.19-20)
共に十字架につけられることで、律法の拘束(支配)から解放されるのです。
それは〈律法の呪い〉からの解放であり、これこそ福音の「自由」です。そこでは「自己という誇り」を打ち砕かれてしまいます。これが共に十字架につけられた者の姿でしょう。
そしてその時、私たちの側のあり方に全く無関係に、キリスト・イエスのピスティスによって救い出されている自分を発見するのです。もはや、この世のさまざまな〈律法〉にも、自分自身にも縛られない、自由さ、柔軟さを賜ります。
これが福音による自由なのです。
その時、自分や自分たち、そして他者をも絶対化せず、客観的に冷静に見つめることができるようになります。
この捕らわれない柔軟な魂にこそ、キリストの新しい「いのち」が注ぎ込まれてくるのです。
キリスト・イエスにある「生」
私たちは、その「いのち」を自分で勝ち取るのではなく、生まれながらに賜った「神の約束による相続人」(3.21-29)なのだとパウロは言います。
また、「あなたがたは皆、信仰により、キリスト・イエスに結ばれて神の子なのです」(3.26)とも。ここは原文を直訳すると、「あなたがたは皆、キリスト・イエスにあって(エン=in)、ピスティスを通して(ディア=through)、神の子なのです」となります。
それは、具体的には、「聖霊」を賜ることです。
人間的には思いもよらぬインスピレーションと活力を賜り、困難を切り開き、聖国を前進させるのです。
「あなたがたが、“霊”を受けたのは、律法を行ったからですか。それとも、福音を聞いて信じたからですか」(3.2)。ここも原文では、「エク アコエース ピステオース」で、「ピスティスを聞いたからですか。」と直訳できます。〈主イエスのピスティス〉を聞いたことで喜びを賜り、聖霊をいただいたのです。
また、3章14節では「それは、アブラハムに与えられた祝福が、キリスト・イエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また、わたしたちが、約束された“霊”を信仰によって受けるためでした。」とありますが、ここの「信仰によって受ける」も直訳すると、「ディア テース ピステオース」「その(主イエスの)ピスティスを通して(聖霊を賜る)」となります。
私はあの有名なニーバーのThe serenity Prayer(「冷静を求める祈り」静謐の祈り)は、聖霊を求める祈りではないかと思います。
O God, give us
serenity to accept what cannot be changed,
courage to change what should be changed,
and wisdom to distinguish the one from the other.
神よ、
変えることのできないものはそれを受け入れる冷静さを、
変えることのできるものはそれを変える勇気を、
そして、それがどちらであるか見きわめる知恵を、
与えたまえ。
ラインホールド・ニーバー
この冷静さ(セレニティー)こそ、〈主イエスのピスティス〉によって支えられている者のもつ平安の表れではないでしょうか。
また、パウロは〈主のピスティス〉によって新しく創造された人を「キリストをまとう」とも表現しています。
3章27節には「洗礼を受けてキリストに結ばれたあなたがたは皆、キリストを着ているからです」とありますが、ここの原文を直訳しますと、「キリストへの(エイス=into、〜に向かって、〜を目標として)バプテスマを受けた者は誰でも、キリストをまとった(「エンドゥオー」のアオリスト)からです」となります。ローマ書13章14節には、ずばり「主キリスト・イエスを身にまといなさい」とパウロは勧めています。
この「キリストをまとう」とき、「そこではもはや、ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由な身分の者もなく、男も女もありません。あなたがたは皆、キリスト・イエスにおいて(エン=in)一つだからです。あなたがたは、もしキリストのものだとするなら、とりもなおさず、アブラハムの子孫であり、約束による相続人です。」(3.28-29)
このことを称してパウロは福音の「自由」と言っているのです。
2章4節には「キリスト・イエスによって(原文「キリスト・イエスにあって〔エン=in〕」得ている自由、また5章1節には「この自由を得させるために、キリストはわたしたちを自由の身に(解放)してくださったのです」とあります。「あなたがたは、自由を得るために召し出されたのです」と5章13節に述べています。
まさに、キリストの福音は、「滅びの隷属からの解放」(ローマ8.21)です。
主イエスは私たちの罪のために、今も目の前で「十字架につけられつつ」あるのです。
そして、私たちも共に、様々な苦難や重荷を通してその十字架に主と一緒につけられています。
日々の重荷、隣人、社会の呻きに向き合わされています。
それらは、人間の手中にある〈律法(ノモス)〉では決して克服されません。
しかし、その十字架は、主が共に担ってくださるのです。そして、私たちを「律法の呪い」から解放して下さるのです。
そこに新しい創造という希望があります。この希望によって生かされとき、「互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそ、キリストの律法〈ノモス〉を全うすることになるのです」(ガラ6.2)。
なぜなら、大切なのは、割礼の有無ではなく、キリスト・イエスにあって、アガペーを通して力を発揮するピスティスこそが、益だからです(ガラ5.6、横江訳)。私たちは、この〈主イエスのピスティス〉によって新しい命を賜っているのです。その幸いを感謝しつつ、聖国の前進に共に連ならせていただこうではありませんか。
いのち
こんなに汚い私に
イエス様はいのちを下さった
神様は生きよとおっしゃった
私でない私 私はすでに死んで
イエス様の力と愛が生きている
それでも心のうちに
罪をおぼえ 自己に苦しむのは
イエス様の愛と力が
あまりに強く迫るからだ
イエス様の愛に押しやられつつ
全き生へと前進する
(樫葉史美子『十字架のメドを通って』)
追記、2018年に改訳された日本聖書協会の新しい訳『聖書協会共同訳』では、「キリストへの信仰」が「キリストの真実」と訳されています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
