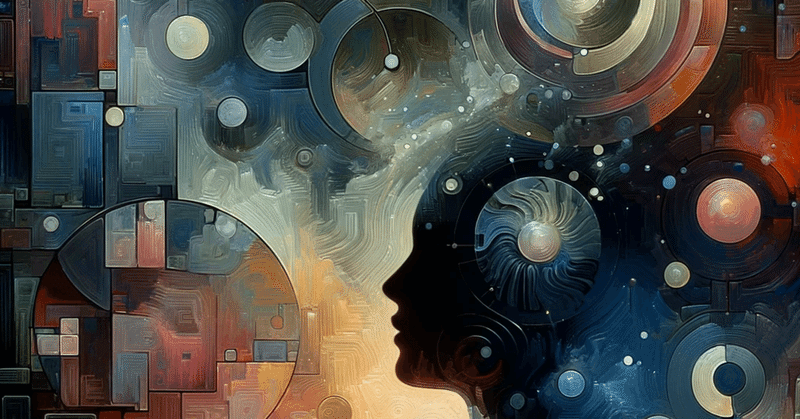
『痛みと悼み』 二
太田さんが、めぐむの背中にそっと手を置く。変死体が見つかった、あなたが唯一の肉親です、事件性はなさそうですが、確認のために警察にきていただけますか、私たちが同行しますので自宅に立ち会ってください、夏の暑い時期だったのでご遺体はかなりひどい状態で、検視が終って荼毘に伏しました、あなたが見つかるのに時間がかかり、恐縮でしたが。電話でそう太田さんから言われたときには、その言葉にも、赤の他人が死んだようで全く動揺がなかった。警察署の6畳ほどの白いコンクリート剥き出しの取調べの部屋の、冷たいスチール机の前で簡単な説明を受けた。事務的だったことが、めぐむには救いだった。警察にとっては、時々ある孤独死の事件。母との日々がこれで完全に遠い過去、記憶のゴミ箱に捨て去さられ完全に忘れ去ることができる、その安堵感で、心は軽くなっていたような気がしていた。そして、かつてのあの自分達の家に向かう。それが、あの部屋を見たときに、一気に過去に引き込まれ、抗いようも無く、めぐむは頭からかつてあの部屋でともに過ごした母の、あのときの内臓が腐敗したような酒と混じる息の匂いを頭から浴びて、嘔吐とともに溺れるように窒息する。

吐いた口から滴るよだれの筋がキレるのをぼんやり見ながら、この部屋を出ていったときのことを思う。その刹那、体の奥に鋭く縦に走る痛みが、めぐむの生きることの配線を切断して、そのとき、生きるのをやめようとぼんやりとしかし揺るぎない不思議な思いで思った。
翌日、雨が降っていた。めぐむは、警察で太田さんから母の遺骨を受け取ると、雨に濡れた服のまま、灯りの切れた部屋の隅で小さく踞って膝を抱え、天井の隅をじっと見続ける。もう、生きることはここで終わりにしようと、生きるための活動を全て止めて。
第2 冷静で賢い母親
雨を感じたあの日から2年、めぐむは生きていた。その間に世の中は大きな感染症が流行り、生きたかったたくさんの人々がその思いを遂げられなかった。逆に、めぐむは、いくつかの偶然と何かの力によって、生かされていた。感染症は、まだ、世の中を静かに人目に触れることなく走り続け、燎原の火が燃え尽きないように世の中の命をスキあらば燃やし続けている。4度目の緊急事態宣言が9月30日まで延長された夏の終わりに、めぐむが乗る白い軽トラの二人乗りの小さな座席に、運転席でハンドルを握る社長と助手席にめぐむが座る。二人とも会社のロゴが胸に入った、ポケットのいっぱい付いたグレーのつなぎの作業着を着ている。めぐむは同じ色のキャップ帽を目深にかぶって助手席から窓の外を見る。今日も、環状8号線は混んでいる。練馬の会社から世田谷の現場に向かうには、あと1時間はかかる。めぐむは、渋滞のなかをゆっくりと進む左右の車線の車をぼんやり眺める。
めぐむがこの特殊清掃の仕事についてから、1年半ほどが経った。あの、生きるのをやめようと思ったときから、めぐむは、自分の人生はオマケの、余生のようなものだと思っている。本当は、あのときにそのままことキレていてもよかった。でも、孤独な母の死を確認した一月ほど後、たまたま心配して新宿区中野にある築年数が分からないほどの古い2階建てアパートを訪れてくれたあの太田さんが、衰弱しためぐむを部屋の中で見つけ−太田さんは、生還しためぐむの奇跡に感嘆するように、そのときの様子を見舞いに訪れた病院のベッドサイドで、横わたるめぐむにため息混じりに言った。立ち上がれないほどの衰弱の中で、近寄るものを斬りつけるようなめぐむの目の光だけが見ていて哀れだったと。でも、そのときにも、見当たらなかったであろう母の遺骨のことは太田さんは一言も触れなかった−慌てて開かれたカーテンから刺す眩しい光と何人もの救急隊員の慌ただしい足音が嵐のように部屋に溢れる中で意識を失い、再び気がついたときは病室の白い天井がぼんやり見えた。
