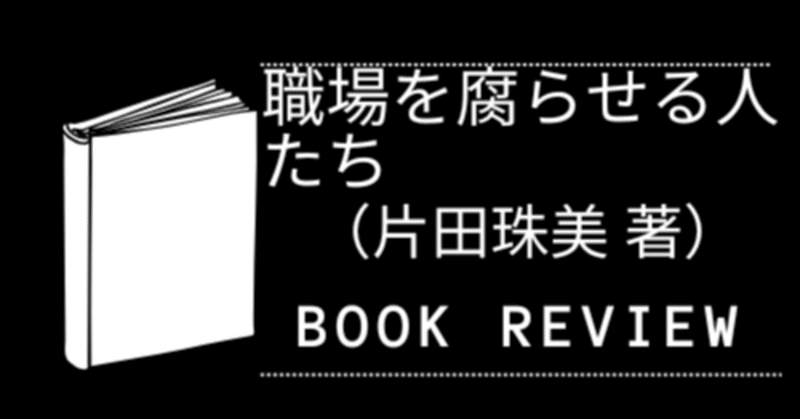
「職場を腐らせる人たち/片田 珠美 著」を読んだ話
北海道在住の鶴木貞男@コンサポ登山社労士です。
北海道小樽市にある「つるき社会保険労務士事務所」で特定社会保険労務士として社労士業務を行っております。
先日、精神科医の片田珠美氏の著作「職場を腐らせる人たち」を読みました。
私は、3月で退職した勤務先で、何人も問題社員というか、どうしてそのような行動をするのかが理解できない方々をみてきました。
そういう方々の周囲にいる人たちがメンタル不調に陥ってしまうケースもありました。
そのような人たちを減らしたい想いがあり、社会保険労務士としてもそのような部分で、関与する会社の力になりたいと思っており、そのための勉強の一環としてこの本を手に取りました。
この本は、著者の精神科医として診てきた患者の最も多い悩みは職場の人間関係に関するもので、だいたい職場を腐らせる人が近くにいる人であるとの経験を踏まえ書かれたものです。
第1章では、15の職場を腐らせる人の例をもとに、その精神構造と思考回路を分析します。「実際にこういう人がいたな」という例がたくさん書かれています。
第2章では、職場を腐らせる人を変えることが難しいのは、その人だけでなく、日本社会の構造にも原因があることについて書かれています。
第3章では、職場を腐らせる人が近くにいる場合、どのように対処すべきかについて解説されています。
最後の対処法は、特効薬的に、すっきりと解決できる方法、これをやれば簡単に職場を腐らせる人の問題を解決できる、というものではなく、多少なりとも痛みを伴うようなものであり、実際に対応するのは非常に大変だと思います。が、書かれている内容はとても現実的なものだと思いました。
根性論を押し付ける、相手を見下す、責任転嫁、足を引っ張る、自己保身、人によって態度を変える……どの職場にも必ずいるかれらはいったい何を考えているのか?
これまで7000人以上を診察してきた著者は、最も多い悩みは職場の人間関係に関するものだという。
理屈が通じない、自覚がない……やっかいすぎる「職場を腐らせる人たち」とはどんな人なのか? 有効な対処法はあるのか? ベストセラー著者が、豊富な臨床例から明かす。
「長年にわたる臨床経験から痛感するのは、職場を腐らせる人が1人でもいると、その影響が職場全体に広がることである。腐ったミカンが箱に1つでも入っていると、他のミカンも腐っていくのと同じ現象だ。
その最大の原因として、精神分析で「攻撃者との同一視」と呼ばれるメカニズムが働くことが挙げられる。これは、自分の胸中に不安や恐怖、怒りや無力感などをかき立てた人物の攻撃を模倣して、屈辱的な体験を乗り越えようとする防衛メカニズムである。
このメカニズムは、さまざまな場面で働く。たとえば、子どもの頃に親から虐待を受け、「あんな親にはなりたくない」と思っていたのに、自分が親になると、自分が受けたのと同様の虐待をわが子に加える。学校でいじめられていた子どもが、自分より弱い相手に対して同様のいじめを繰り返す。こうして虐待やいじめが連鎖していく。
似たようなことは職場でも起こる。上司からパワハラを受けた社員が、昇進したとたん、部下や後輩に対して同様のパワハラを繰り返す。あるいは、お局様から陰湿な嫌がらせを受けた女性社員が、今度は女性の新入社員に同様の嫌がらせをする。
こうしたパワハラや嫌がらせの連鎖を目にするたびに、「自分がされて嫌だったのなら、同じことを他人にしなければいいのに」と私は思う。だが、残念ながら、そういう理屈は通用しないようだ。」ーー「はじめに」より
私が、特にこの本から学んだ点はこんな感じです。
・人は目の前の現実を直視したくないとき、マニック・ディフェンス(躁的防衛)により軽躁状態になることがある。これが「職場を腐らせる人」になる原因となることがある。
・羨望が他人の幸福に我慢ならない怒りなら、嫉妬は自分の幸福を奪われるのではないかという喪失不安である。嫉妬のほうがより陰湿で合理的判断を妨げる。
・悪意はアリストテレスの定義によると、「自分が得をするためではなく、相手が得をしないように他者の願いの邪魔をすること」である。
・一番厄介なのが、ドイツの精神科医が名付けた「ゲミュートローゼ」というタイプで、これは思いやりや同情心、羞恥心や良心のような高等感情が欠如している人を意味し、日本語では「情性欠如者」と訳す。このような人は、罪悪感を覚えることを徹底的に拒否し、反省も後悔もせず、良心がとがめることも一切ない。
#北海道 #社会保険労務士 #社労士 #職場を腐らせる人たち #片田珠美 #問題社員 #読書感想文 #わたしのチャレンジ #私なりのアウトプット
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
