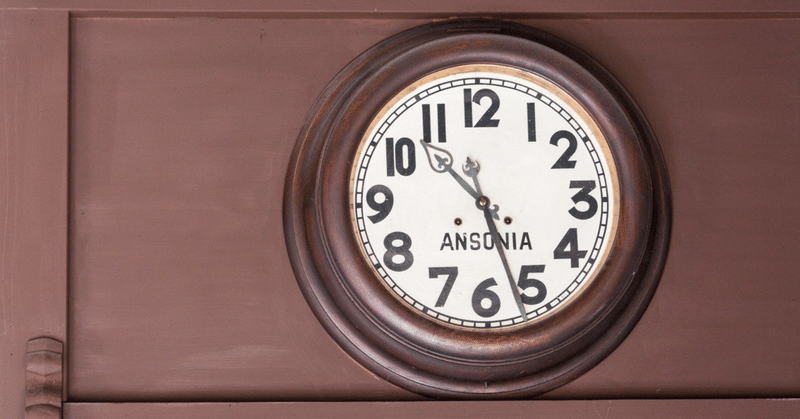
タイムロス ー横浜における幻の教育クラウド提案ー
よくお仕事をご一緒するHさんのnoteに首がもげそうなほど頷いたのでシェア。
noteにかかれていたこと
ChatGPT先生に要約してもらうとこんな感じのことが書かれています。(御本人から異議があった場合は差し替えますw)
未来を100年先まで考えることは重要であり、現代の課題は将来の基盤となるデータやシステムの整備を求めています。
150年も前に作られた戸籍や不動産登記などの仕組みにパッチ当てしてごまかせる時期はいつまでも続かないので、どこかで現代の技術と社会システムに適合させる必要があります。同時に、短期的な課題に追われることなく、遠い将来の社会の変化にも目を向けることが重要です。
100年後の社会は人口減少と高齢化が進み、新たな技術の導入が必須となるでしょう。デジタル化の推進とデータの正確な管理は、未来の社会を支えるための鍵です。
私が、これまでの人間の営みに傷められまくった地球や社会システムをこのまま自分の子どもたちに負わせることはホントーーーに嫌!と思って活動を始めてから早10年以上が経過していますし、生まれてからこれまでを考えても50年100年なんてあっという間だなと感じています。
その「あっという間の時間」に、人々が昔のスパコン並みのスペックを持つ端末を手に持って歩くようになり、海の向こうの人とリアルタイムにやり取りができるようになり、電車や飛行機のチケットや各種予約はオンラインですべてが済むようになり、海外では自動運転車が普通に道を走るようになったりしています。
英国における教育ビッグデータ活用
今日の日経新聞には、イギリスにおける教育ビッグデータ活用の記事がありました。
こちらは有料記事なので、読めない部分のポイントをざっと書くと
英国が学校のデータに注目したのは1990年代後半
国が学校の情報を集約して審査機関による評価を行い、著しく低いと閉鎖勧告をする制度があり、学校は存続のために改善が必須に
20年以上のデータ活用の経験が「脱一律」の考え方に結びつき、教材や課題を個々に合わせられる教育を実現
米アリゾナ州立大学では、在学生17万人分の履修データを使って、留年・中退を減らすための科目選択支援システムを10年かけて整備し、それらを含む取り組みと合わせて卒業率を20%高める
そして最後に、日本における教育データ活用の残念な現状についても書かれていました。
世田谷区では、生徒に配った学習端末の検索履歴を学校側が閲覧し、悩みの把握などに役立てようとしたところ、議会から「個人の内心に関わることで、検閲めいている」と批判があり、区は計画を取りやめた
横浜における幻の教育クラウド提案
実は、私も教育委員会事務局情報教育課に所属していた15年ほど前に「教育クラウドを整備して、ハード整備の効率化をするとともに、児童生徒の学習履歴を小・中と一貫して指導に利用できる環境を作ろう」という提案を教育長にしたことがあります。
結果として、教育長からは賛同を得られたものの、当時の課長に「そんなもんはなんの役にも立たない(笑)」と一蹴されて実現しませんでした。
アリゾナ州立大学ですら、学習データを使った支援システム構築に10年かかっています。
横浜市立小・中学校に所属する児童生徒24万人の学習履歴データが15年間蓄積されていたら、2024年の今現在、それがどれほどの価値を持つことになっていたのだろうと考えると、あの当時、単に想像力がないだけでそれを一蹴した課長はどう責任取ってくれるんだろうと、今でも腹立たしく思います。
今、行政にいる責任職の方々は、自分のつまらないプライドの前に、そうした「未来への責任」を自覚した上で、物事を判断してほしいと願ってやみません。
想像力の欠如は社会の発展を阻む最大の敵
スマホや様々なオンライン手続きなど、知らない人には社会が勝手に便利になったというだけで、その裏で様々な技術に関する標準化や、激しいデファクトスタンダード獲得競争があることには想像も及ばないと思います。
そして、そうした悪気ない想像力の欠如に、技術を支える人たち、それらを正しく活用しようとした人たちがどれだけ辛酸をなめさせられてきたのかも、おそらく永久に想像できないのだろうと思いますし、あまつさえ「デジタルを使えばなんでもちゃちゃっと作れるんでしょ~」というような寝ぼけた言葉を吐く人は、これからもわんさか出てくるだろうと思います。
Hさんのnoteにも書いてあるとおり、デジタルの活用を阻む最大の敵は、未発展の技術ではありません。
そうした未来への想像力を欠いた人達による「デジタルを活用するために必要になる超ーーーー地味なアナログ改善作業への無理解」です。
それが10年100年の遅れに繋がりかねないことを、社会全体はもちろんのこと、個々人も理解する時期かと思います。
