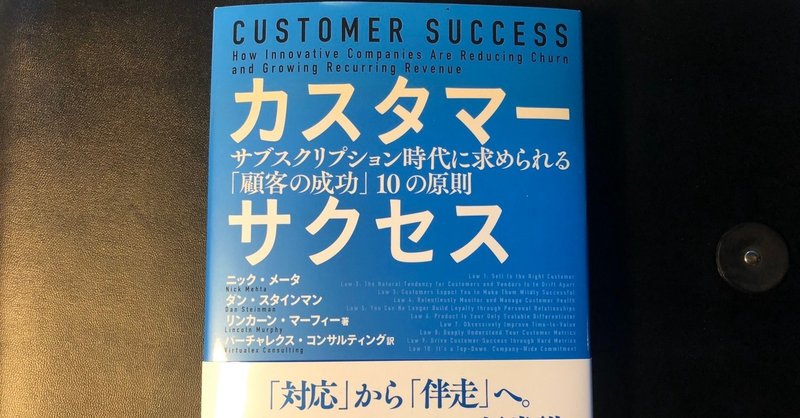
イチ営業パーソンが カスタマーサクセス青本 を読んで感じたこと①
「カスタマーサクセスが重要だ!」と話題になってから随分時間が経った。
職場の勉強会などで断片的な知識としては頭に入れていたものの、体系的に知識として取り入れるという事についてはまだとりかかれていなかった。
ようやくというか、もはや今更になってしまうが、オススメしてもらった『カスタマーサクセス サブスクリプション時代に求められる「顧客の成功」10の原則』を読んで、重要だと感じた点や自分の今の仕事に活かせそうな点についてアウトプットしていきたいと思う。
●:重要だと感じたポイントの要約 (一部引用、一部田村による要約)
★:自分が今の仕事へ活かしたい内容
第1部 第1章
サブスクリプションの津波
カスタマーサクセスの緊急性が急に高まった理由
●顧客ロイヤルティには二種類ある
「心理ロイヤルティ」と「行動ロイヤルティ」だ。
「感情ロイヤルティ」と「理性ロイヤルティ」とも言い換えられる。
●顧客をアドボケートにしたいのならば、大事なのは心理ロイヤルティだ。カスタマーサクセスは、そのために必要な手段である。
●CSの考え方は大事だが、それが会社の利益に莫大な影響をもたらさなければ組織の変革はそう簡単に起こらない。だが、SaaS、サブスクリプションモデルの普及とともに今やカスタマーサクセスは必須事項になっている。
★今自分が扱っているサービスに心理ロイヤルティを抱いている人は、どんな部分をよく思っているのだろうか?考えよう。
第1部 第2章
カスタマーサクセス戦略
新たな組織と従来のビジネスモデルとを比較する
●カスタマーサクセスに期待できる成果は次の三点が挙げられる
「①チャーンの減少と管理」金銭面の損失だけでなく、競合企業に流れるのを防ぐ。
「②既存顧客の契約金額増」
「③カスタマーエクスピリエンスと顧客満足度の向上」顧客が転職先でまた利用してくれるかもしれない、口コミで他者に広げるかもしれないという"二次収益"への期待
●CSは、カスタマーサポートと下記の点において異なる
「財務上、収益ドライバーとしての責任を持っている」
「能動的であり、データや分析結果から働きかける」
「成功重視型であり、収益増加を目指す。コスト削減ではない。」
「先を見越した予測分析が良い結果に繋がる」
「言われてから対応するのではなく、それを先回りできる予測性が重要」
●CS部門は一部署だけで成立するものではないどころか、他部署を駆り立てる権限、リソースをめぐって戦う権限、事業の戦略的決断を下す権限などその全てを与えなければならない。
●CSの理念が全社に浸透していくと他部署はどのように変わるのかを下記にまとめる。
・営業部門
→マーケ/営業の対象が、長期成功が可能な顧客に限定される
→LTVを犠牲にする場合は特に、初回契約自体の重要性が薄くなる
→契約更新への意識が高まる
→潜在顧客に設定される期待が高まる
→OBを確実に行い、ノウハウ移行とアフターサービスの準備が重要になる
→更新やLTVに対しても報奨制度が定められる
・製品部門
→投資利益率(ROI)が評価指標として設定される
→自社製品の実装が容易になる
→機能だけでなく導入しやすさがデザイン基準になる
→機能そのものより顧客を惹きつけることが重要視される
→デモ版の品質よりも性能の方が大切になる
→アップセルを想定し全てを基本パッケージに入れない
→顧客が自立しやすくなる
・サービス部門
→アフターセールス部隊ではなく"プリセールス部隊"であるという認識を
→CSMはお客様への助けが不要になるよう他部署に働きかける必要あり
★どんな顧客が長期的成功を収めているのか、あるいはその顧客の初回契約時点での特徴を語れるようにしておこう。
★営業サイドにくる対応依頼についても、なぜその問い合わせが来たのか、それが不要になるためには何をしてればよかったか?を考えておこう。
第1部 第3章
定期収益型でないビジネスにおけるカスタマーサクセス
●今やサブスクリプションモデルは特定業種のものだけではない。
カスタマーサクセスという理念の中心にあるのは、顧客が常に戻ってくるように、製品から顧客が最大の価値を受け取れるようにすることなのである。この変化の影響を全く受けない事業はない。
●同じCSでも顧客数に応じて「ハイタッチ」「ロータッチ」「テックタッチ」をカテゴリー分けする必要がある
「ハイタッチ」:ベンダーと顧客の間で頻繁なやり取りを行う。適切な接客スキルと頭脳を持っている人材を配置し、顧客に成功をもたらす。
「ロータッチ」:必要最低限の工数に抑えながらもある程度の個別対応を行う。
「テックタッチ」:価値の大きくないロングテールでも収益の上では大きな役割を果たす。様々手法があるが、丁度良いタイミングで、幅広い顧客に合わせた内容を送信できるeメールが非常に強力である。
★今の顧客を上記三分類に分けるとしたら、どうなるか?それぞれにできることは何があるだろうか?考えておこう。
----------------
第1部まとめ
今自分が扱っているサービスについてはnoteでは触れられないため、これより詳細な思考についてはここには書かないけど、考えるべきテーマのヒントについては整理することができたように思う。
これについてしっかり自分の意見を持って、次の第二章に進もうと思う。
第二章はいよいよ本の副題にもあったような「10の原則」について触れられる。基礎は第1章で整理できた。次はいわゆるこの本のメインディッシュなので、楽しみだ〜
次のnoteはこちら。
----------------
恥ずかしながら分からなかった、本に出てきた単語シリーズ
【喫緊】きっきん
さしせまって大切なこと。【緊急】に意味は違いが、一分一秒を迫る【緊急】とは違い、「今すぐに」というニュアンスは無く、「速やかに」というニュアンスがある。
【ビジネスインテリジェンス】略語:BI
企業の各部署がそれぞれに蓄積している膨大なデータを、収集・蓄積・分析・加工し、経営戦略のための意志決定を支援すること。
【ベンダー】
製造元、販売供給元のこと。特に、コンピュータ、ソフトウェア、ネットワーク機器などのIT関連製品の販売業者のことを指すケースが多い。要は、供給側という事。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
