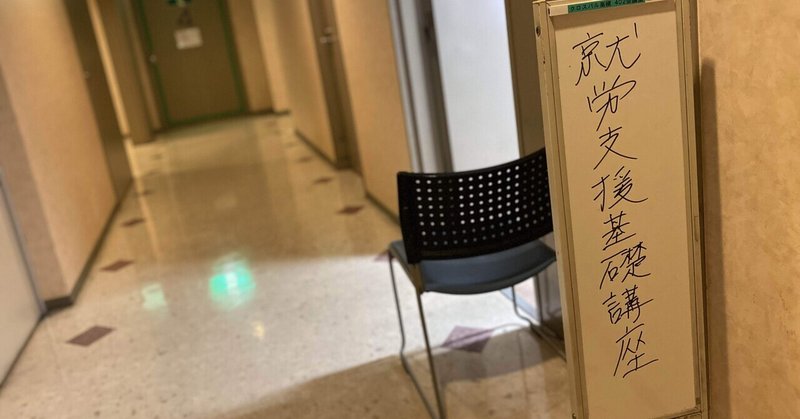
【社内ブログ】講義後にもらった2つの質問
このブログは、毎日書いている職場内(就労移行・自立訓練の事業所2箇所)ブログの中からnoteで公開できるもののみ、シェアさせていただきます。noteの皆さまにとって少しでもご参考になれば嬉しいです。
(10/13職場内ブログ)
おはようございます。
今日は、月1回のコンサルです。
早朝の電車は、程よく混み合っていて、眠そうにしてる人も多いこともあってか、落ち着いた車内は心地よさを感じます。
今日も長丁場なので、しっかり働きたいと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーー
▼講義後にもらった2つの質問
ーーーーーーーーーーーーーーー
さて、昨日は就労支援基礎講座でした。
テーマは、「発達障害の特性理解と就労支援の進め方」ということで、いつものレジュメを使って40分ほど話をしてきました。
講義の後、2つの質問をもらいました。
2つの質問とも、最近ぼんやり思うことでもあったので、タイミングがよかったというか、うまく言語化して回答できなかった気もしますが、改めて考える機会をもらえたのは良い時間でもありました。
こちらでも、2つの質問に対する僕なりの意見を書いておきたいと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーー
▼企業に伝えたいことは何か?
ーーーーーーーーーーーーーーー
今回の講義は、就労支援者向けの研修会でもあったので、参加者の方も支援者の人がほとんどでした。
ただ、企業への営業をしている人もおられたり、企業で長く働いた後に福祉職へ転職された人もおられるようで、「発達障害のことで企業の人に一つだけ伝えたいこととなれば何ですか?」とご質問もらいました。
難しい質問だなぁと思いながら、昨日もケースのことをスタッフの方と話していたことをふと思い出し、中山さんからもいつも言われることを思い出したことも重なって以下のようにお応えさせてもらいました。
「企業が本人に求めること(要求水準)を高く設定しないでほしい」
「障害のある人は、障害のない人に比べて成長のスピードは比較的ゆっくり。長い目で成長を期待してほしい」
製造工場などの企業で働くと、どうしても一人ひとりの生産量を数字で評価されてしまいます。
今の本人は他の従業員と比べると50%の仕事ぶりであるとか、もう少しスピードアップしてほしいとか、数字に置き換えられると結構シビアです。
障害のある人が、障害のない人と同様の生産量を達成できるかはケースバイケースなように思いますが、そこが最大の評価点では障害の有無は関係ないような気もしています。
それよりも、僕らで作った動画2つに出る社長さんたちのように、ご本人の強みが企業の職場環境に良い影響を与えていると話してくださることに僕らは共感したくって、「人柄」「裏表のないところ」「明るくて真面目なところ」を何よりも大事にしてほしい評価ポイントでもあります。
成長のスピードはゆっくりかもしれませんが、それ以外に期待できることもあるわけで、そんなことが企業に少しでもポジティブに伝わったらなぁって思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▼学校を卒業するまでに教えておいてほしいこと
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
就労支援基礎講座は、支援者向けではあるものの、毎年、支援学校の先生も来てくださいます。
昨日も参加してくださっていて、「学校を卒業するまでにやっておいた方がいいこと、身についていた方がよいことってなんですか?」とご質問をもらいました。
ここでも少し悩んだんですが、先日開催した家族ミーティングで作ったレジュメを思い出し、普段のインテークやケース会議などでも感じることは多いなぁと思いながら、以下のように応えさせてもらいました。
「大人になると自分で選んで自分で決めることがとても多くなる、どの会社を選んで受けるとか志望動機はなんですか?と会社に聞かれることも多くなる」
「自己選択と自己決定が身についていると良いのではないか」
「買い物に行ったら何を買うとか、メニューからご飯を好きに選ぶとか、自分で選んで自分で決めれたら親は口出しせずに尊重するぐらいがいいかも」
「まずは、身近なことから自分のことを決める練習をしてほしい」
ちょっと偉そうになってしまいましたが、前にも書いたように「本人抜きの支援」は何も生まれないというか、本人不在で進むケースワークは本人も説得させられる一方なので本人の意思を尊重しているとは言い難いように思います。
親と本人の意見が食い違うことは多々あるかもしれないですが、「本人がどうしたいか」はきちんとアセスメントして、自分の人生を自分なりのやり方で進められるようサポートするのが僕ら支援者の役割期待であるようにも思います。
子どもの時から少しでも、「自分で選んで自分で決めること」ということに慣れておられたら、本人中心で就労支援を進めやすいように思います。
ーーーーーーーーーーーーーー
▼自分たちのやり方を再確認
ーーーーーーーーーーーーーー
支援に答えがないということもあって、研修講師でお話しする機会は「支援の再確認」を自分なりにしている時間でもあるように思います。
人前でお話しする時は、自信を持って話すしかないんですが、話をしている中で「このやり方でいいのかな?」「話してる内容は正しいんだろうか?」と心配になることもあります。
昨日みたいに、質問をもらうのは自分の講義内容に不十分さというか分かりにくさがあっての質問でもあるように思い、受講する人一人ひとりに講義の学び方と理解の仕方に違いはあるものの、質問を受けることで新たな気づきになることも多く、ご質問2つともありがたい内容でした。
これからも、色んな視点で答えのないことと向き合っていきたいですね。
それでは、本日もよろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
