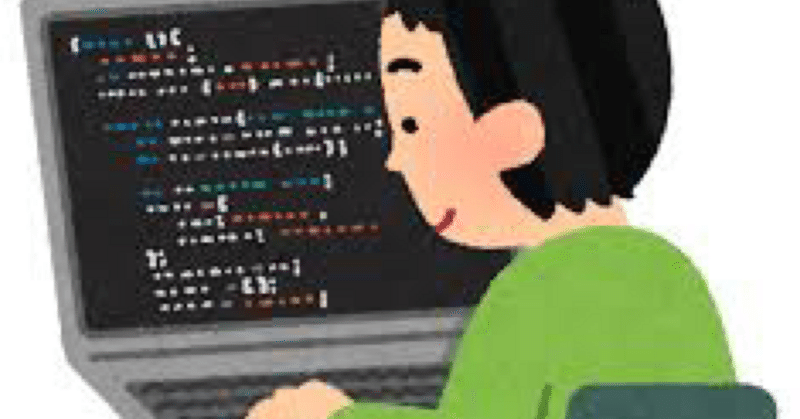
プログラミングを学んで気づくSNSの危険性
旅の話題とは関係ないけど、最近少し考えることがあったのでちょっと独り言。
私は現在デンマークの大学でプログラミングを勉強している。
最近授業で、本屋のホームページを制作するという課題が出た。言語はJavaだ。
具体的には、
一番評価されている本をトップページに表示する
自然科学の本を多く読むユーザーに自然科学系の本を多く表示する
などの機能を追加することが求められる。授業自体はとても面白く、タメになる授業だ。グループワークで現地の学生と交流できるのも楽しい。
それはそうと、この授業を通じて1つ気づいてきたことがある。
それは、私達がインターネットを使用して何かをしている時、それはその設計者の思想の中で踊らされているのと同義なんじゃないか、ということだ。
本屋のホームページを利用している時、同時に私達はホームページの設計者の思惑の中に収まることを余儀なくされる。
これはSNSにも言えることだ。
noteを利用している時、私達はnoteの設計者の思惑の中で記事を読み書きすることを余儀なくされる。
ただ、恐ろしいのが、どこの誰が、どういう意図で、どういうアルゴリズムを実装しているのかが不透明なことが多いという点だ。
SNSを通じた情報統制が行われている国があるのは、もはや周知の事実だろう。
もし仮に、自国の政権を支持するような記事はより多く人目につくように表示され、逆に自国の政権を批判するような記事が人目につかないように表示されるアルゴリズムがnoteに導入されてたら、どうであろうか。
多くのSNSには「いいね」の機能があり、あたかも特定の思想が社会で多数派のように錯覚されることがある。
しかし、考えてみたらこの「いいね」もどういったメカニズムで実装されているのかはわからない。
もちろんユーザーがいいねボタンを押せば増える、という単純な一面もあるだろうが、特定の投稿には「いいね」の数が押されやすいようなアルゴリズムが導入されている可能性も否定できない。
無論、多くの記事においてはそんな情報操作とは無縁だろうし、私の気にしすぎなのかもしれない。
ただ、SNS等におけるバーチャル上の文字や数字に何の恣意も働いていないと言えば、それは嘘だろう。
明らかに、そのプログラムの設計者の恣意の中に私達は生きている。
そこにどういったアルゴリズムが働いているのか。常に疑う視点が重要だ。
プログラミングというのは、基本的には発明のツールだ。
だが、基本的なプログラミングの知識はネット社会の弊害から自分の身を守る盾にもなる。
SNSのアルゴリズムは不透明なことが多い。
バーチャルの文字や数字に踊らされないためには何が必要なのか。
色々考えさせられる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
