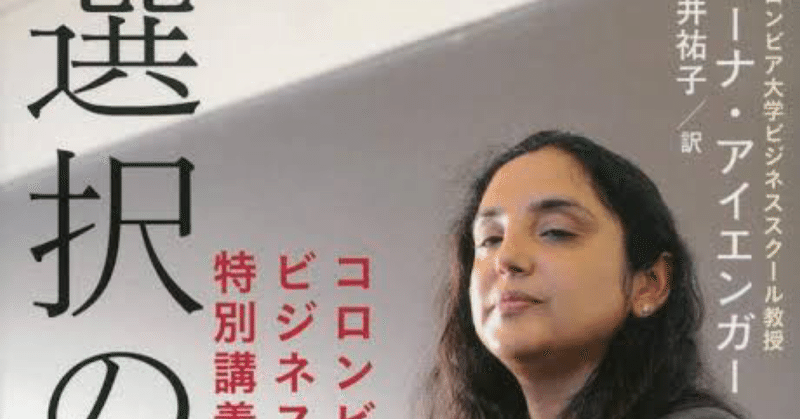
選択肢が増えすぎて難しいーー『選択の科学』
「仕事にやりがいなんて求めてないから、給料と休みがたくさんあればいい」
友人がそんなことを言ってた。うんうんうなずきながら、それもなんだか悲しいことだなと思った。
「仕事行きたくない」という話はよく聞くけれど、「仕事が充実してこの上なく楽しい」という話はそんなに聞かない。「上司の言っていることが昨日とぜんぜん違う」「言われた通りやったのに文句つけられた」こんな言葉は何度耳にしたかわからない。
仕事に満足することはそれだけ難しいのかなと思いつつ、モヤモヤしていた。
最近読んだ『選択の科学』では、選択することには大きな力がある一方で、思い通りに選択することの難しさが示されていた。難しさの種類も様々で、育った環境による影響や心理的なバイアスなど様々である。満足のいく選択をすることは、思っている以上にハードルの高いものだった。
選択できると思えること
そもそも「選択」ができるようになるには前提条件がある。
わたしたちが「選択」と呼んでいるものは、自分自身や、自分の置かれた環境を、自分の力で変える能力のことだ。選択するためには、まず「自分の力で変えられる」という認識を持たなくてはならない。
(シーナ・アイエンガー『選択の科学』p29、文春文庫)
知人が「ガッときたものをグッとつかむ」という表現をしていて。チャンスがきた時には逃さないことだ!と、常々言っている。
選択ができるってそういうことなのかもしれない。「自分の力で変えられる」と思っていれば、選択肢に気付ける。しかし思っていなければ、それが選択肢であることにすら気付かない。
「この仕事に興味ある人いる?」と言われて、「やりたいかやりたくないか」で迷う人と、「どうせ私には無理だから」と思う人がいるように。
「自分の力で変えられる」と思えるためには、ささいなことでも頻繁に選択することが有効らしい。ランチメニュー選ぶことなら、今日からできるかもしれない。
選択肢が多すぎて困る
選択できるという認識を持てたとしても課題は残る。そのうちの1つが、選択肢の数の問題である。『選択の科学』では人間の情報処理能力の限界についても触れられている。
わたしたちは選択を行うとき、今挙げたような多くの処理能力に頼っている。すべての選択肢を認識し、それらを比較して違いを見つけ、自分の下した評価を記憶し、その評価をもとに順位をつける。処理能力の限界のせいで、選択肢の数が増えるにつれて、それぞれの段階がますます手に負えなくなっていくのだ。
(シーナ・アイエンガー『選択の科学』p268-269、文春文庫)
処理可能な選択肢の数は、7±2という説もあるらしい。多いと適切に処理できないと聞いて、連想した記事があった。
連想した一部を引用する。
正しくは、より広がった選択肢から、自分の時間やスキルをどのように投資するかを、より一層考えなければいけない時代が来たのではないだろうか。
(りょかち、『副業ブームの今、大企業を辞めて私があえて専業ライターを選ぶ理由』、https://www.businessinsider.jp/post-239751、(2021年8月28日))
複業の考え方まで広まり、私たちの働き方はより複雑になった。定年まで勤めるためのスキルを伸ばす人もいれば、複数箇所から収入を得られるようにスキルを伸ばす人もいる。
どんな働き方なら自分が最も満足できるのだろう。週5日の時短勤務がいいのか、2つの会社で週3日フルタイム+週2日フルタイムがいいのか。そもそも、何時から何時間働くのが自分に合うのか。
働き方の選択肢が増えているなら、あらゆる形が選べるはずで。でもなんとなく週5日フルタイムで働くことを選んでしまうのは、多すぎる選択肢をなんとなくで減らしたいからかもしれない。その結果、満ち足りない働き方を選んでしまっていると気付かず。
おわりに
私たちの未来は常に変化している。理想の働き方も同様である。
結婚して子供が生まれれば、勤務が調整しやすいと都合がいいかもしれない。子供が中学校に入る前には、フルタイムでたくさん働きたいかもしれない。優先順位は時間の融通から給料が高いことに変わっていくという1つの例だ。
理想の働き方も100人100通りある。未来は不確実だから、一度選んだものをその時の状況に合わせて変えてもいい。
すべてを吟味しきれないほど選択肢がたくさんある世界で、私たちはどんな基準で選択すると満足できるのだろうか。給料が高くて有給がたくさんある仕事ができるようになったら、思い描いているような生活が送れるのだろうか。
考えることをやめることなく、理想に近づくための選択をし続けていきたいと思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
