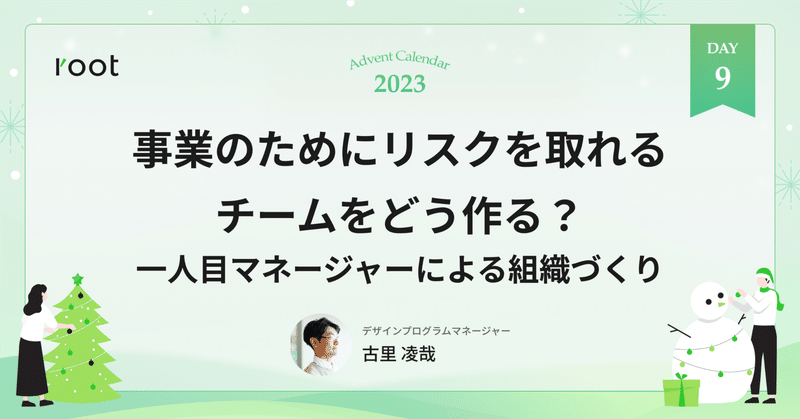
事業のためにリスクを取れるチームをどう作る?一人目マネージャーによる組織づくり
記事を読みにきてくれてありがとうございます。いやーほんとによかった!このタイトルに関心を持って読んでいただけて大変光栄です。rootの古里です。僕はrootのプロダクトデザイナーとして、またデザインプログラムマネージャーとしてクライアント企業の成長に伴走しながらさまざまな支援をしています。この記事はrootの2023アドベントカレンダーの記事です。今回のテーマは「デザイン組織づくりをする一人目マネージャーの困難さと僕のトライ」です。今年はアドカレの順番が3週連続巡ってくるという幸運に恵まれているので、今年の振り返りと来年に向けたトライをどんどん書き綴っていこうと思います!
さて、rootという会社は「Design doing for more - デザインの実践を個から組織・事業へ」というビジョンのもと、デザイン組織化支援も行なっています。「デザイン組織」や「デザイン経営」ってほんとによく使う言葉になりましたよね。一方でその言葉が指し示しているものがなんであるかが曖昧になることって多いなと感じます。この記事の中での使い方について明示しておこうと思います。
事業と経営の必要性から組織が生まれる

まずは「組織」から確かめていきましょう。組織は会社が備える機能や会社の目的を遂行する活動体のうち、複数の人数で構成されているものを指します。会社が事業を回すこと・会社という形を維持する必要性から生じた「機能」が役割を果たすためにあるのが組織だと考えています。なので、デザイン組織は会社が事業や経営にデザインを必要としているときに成立します。デザイナーは「必要性(ニーズ)」を嗅ぎつけるのが得意なので、僕はこういう理解をしてます。
会社が「デザイン」という機能を必要とし始めたのは、歴史的に最近のことです。例えば僕は支援先で広報IR組織がユーザーのプロダクトを開発していますが、広報やIRという活動は会社が創業した時からずっと備えている機能の一つです。デザインと違って広報という機能は多くの会社の場合創業時から必要とされています。最初は創業者が自ら、だんだんとマーケや企画を兼務する形で一人広報担当者から始まり、会社の規模の拡大に応じて組織化・分掌化されていきます。
rootはあえて創業期からデザインという機能は備えておくべきだと考えており、インキュベーションのフェーズのスタートアップにもデザイン支援を継続して行なっています。
デザイン組織は小さな会社組織
樹木全体と葉は相似的な構造をしているのと同じように、会社の内部組織もまた事業的な活動と経営的な活動をもつ構造をしています。

組織の形をメタファーで表現する試みは様々な会社が行なっていますので、それら個別についてはここでは触れません。言いたいことは「会社の内部組織はいずれも最終的な目的として事業の拡大のための必要性から存在している」ということです。デザイン組織もまた然りです。事業活動の中でデザインの実践をのびのびと広げられるために、幹を太く・根を深く大地に張り巡らせるようなことですね。
デザイン組織のリーダーやマネージャーはしばし、デザインタスクや開発タスクの効率化だけを組織の目的と置いてしまいがちです。ですが事業の拡大のために会社内のヒト・モノ・カネ・情報などの経営資源を配置し構成することが経営的活動の目的です。タスクの効率化・ナレッジ化・ワークフローの整備はコストを減らすための一側面だけであり、より積極的に事業貢献のためにできることはまだまだあります。
では具体的にその活動の全体像はどんなものか?これも会社経営になぞらえるとわかりやすいです。まずは経営上のテーマ・会社としての一番大きいオブジェクティブやビジョンを決めるところから始まります。デザイン組織は経営と事業の両面の必要性から成り立つため、その両面から目標を定めます。
デザイン組織を会社組織に喩えてみるとその目標設定に必要な項目が見えてきます。
事業における目標
事業部:主に、社内の事業活動の中で、デザイン活動を通じて価値を生み出す
営業部:デザイン組織の可能性やケイパビリティをより多くの事業活動へ売り込む
技術開発部:デザイナーのスキルを増やし実績を一般化してナレッジを作る
経営における目標
資産管理:過去のナレッジや自社の持つデザインシステムなどの資産を管理する
人事:いいチームのための価値基準や評価軸などの方針を示す。目標設定や評価をする
採用:組織の拡大のためにメンバーを増やす。採用の基準を作る
広報:組織の認知を広める
デザイン組織の運営は、会社経営と似ている
いやはや、やることがたくさんありますね。しかもこれ、組織の立ち上げにあたって全部ゼロから作るんですよ。あなたにはできますか?
デザイン組織が会社組織と似ているということは、つまりデザイン組織の立ち上げは会社の立ち上げと似ているということです。経営からキャリアを始めるデザイナーは少ないです。デザインからデザイナーになった僕は新しい知識を学び直さないといけないなと実感しました。でも運の悪いことに(あるいは運のいいことに)僕は「一人目」マネージャーだったんです。一人目はいつだって先人がないためマネジメントされない。正解も間違いもわからない中で模索することほど苦しいものはないなと思い知りました。

一人目マネージャーにとって経営的活動が未熟な会社は適者生存の世界です。サバンナでファーストペンギンやるぐらいのサバイバル。誰の助けもなく、誰も手をつけたことのない荒野を耕し、自由な生活ができる自分だけの村を作る。かなりハードなミッションです。生き残れないと判断してより整地された先進国に移住することも、フリーランスになって各地の村々を旅するのも生存戦略として正当だと思います。
整地された世界では十分に大きな幹があり、広く根が張られていて、心理的に安全な枝葉でのびのびやれるでしょう。あらゆることがお膳立てされている先進国には大きな魅力があります。
ですが僕はそれを選びません。なぜかというとこれは僕のWillですが、与えられるより与える側・消費する側より作る側・お膳立てをされるよりする側でいたい。(だってデザインしたいから!)
では最初の問いに戻って、あなたには荒地を整える、事業のチャンスにメンバーがいつでも飛び込める組織を作れますか?太い幹と深い根で支えられた、メンバーがリスクを取りやすいチームをつくれますか?

この問いに答えるにあたって「リスクを取れるチーム」というのがどういうものか、解像度が低いのが悩みでした。これは僕自身がリスクを取れる環境にいた経験のなさにも起因していると思います。なぜならずっと事業の世界にいたから。リスクをコントロールするのはいつだって自分個人で、他の誰かに委ねることやリスクについてあえて考えないことなんて、そんなのあり得ないと思っていました。
事業のリスクをどうコントロールする?この懸念点にどう対処する?自分の経験から未来予測を膨らませ不安を潰すことだけに精一杯になって、最悪自分がケツを拭く役目なればいいやと思ってる。チームで向き合うべき・対処すべきリスクを個人レベルでできてると錯覚してしまっている。でももう見えました。限界。個人のレベルでできることに一定の諦めをつけたことが、リスクを取れるチームを作ることに正しく向き合うきっかけになったなと思います。
デザインを個人に留めない・事業に留めないためのトライ
個人のレベルを超えてデザインの持つポテンシャルを解放するには組織でやるべきです。「早くいきたいなら一人で行きなさい、遠くへ行きたいならみんなで行きなさい。」という遠い国の諺にもあるように、組織的な活動にすると、私たちが作っているものの意味や価値の持続性が上がります。人が1つの会社・組織に所属していられる時間はそんなに長くないです。あなたがチームで作ろうとしているものは、あなたが辞めてしまったら、誰かが辞めてしまったら、エンジニアが総入れ替えになったら、POが交代したら、ユーザーに価値を届けられなくなってしまうなんて寂しいなと思いますよね?

もちろん状況に合わせて変化することも大事です。ですが変化するなら常に前向きに変化していきたいものです。その時自分たちにとってどっちが前なのかの定義をしておかないと、間違った変化で事業を縮小させてしまう可能性もあります。デザインの実践を個から組織・事業へ広げていくことが、事業が生み出す価値を最大化し、かつ持続可能な仕組みにしていく方法になると思っています。
とはいえ僕もトライ中の身ゆえに、うまくやる方法は知りません。今の僕は内省を通じて状況を認識することでトライするのみです。適者生存の世界から脱出することなく今でもrootで頑張ってます。頑張ろうと思える理由は2つあります。
一つは結局この世界どこに行っても不確実さに溢れているからという理由です。であるなら確実な基盤は自分で作るしかない。事業側の世界でもがいてきたことはきっと経営的活動を作っていく上でも生きることだろうと考えています。
もう一つは、僕と同様に一人目マネージャーでデザイン組織を立ち上げようとしている・生き残りをかけて開拓しようとしている仲間が必ずいるはずだということ。一人目デザイナーの諸君がキャリアを成長させていくにつれこの組織化の課題に突き当たると思っています。あなたたちはとても優秀なので事業にめっちゃコミットしてどんどん会社が成長させるからです。そしてより一層の事業の拡大のために経営的活動が要求された時、事業的活動と経営的活動の2つの要求を満たせるチームを一人でゼロからつくらないといけなくなる。これに備えてみんなの経験からパターンを見つけ、ナレッジを増やしたいと思っています。
まず手始めに12/14にデザインリーダーを集めて振り返りイベントをやります。好評につき恐縮ですがこの記事を公開した時点で残り1席なので、ご興味ある方ぜひ幸運を引き当ててください。もしかしたら増席するかもしれないので、その時は改めてお知らせします🙏
また、ユートラでカジュアル面談も開いているので、同じ課題を共有し合える仲間と対話できることを期待しています☺️
まずはrootからデザイン組織を作り運営できるよう、この先もひたすら内省とトライの繰り返しのみと考えています。それではまたお会いしましょう!
rootでは共にVision実現できる仲間を探しています!
私たちは、「Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜」をVisionに、事業の成長によりそい、デザインを実践しようとする人々を支え、世界をより良く前進させていくことを目指しています。
共に、クライアントと事業の本質(芯)を見いだしながら、事業本来の価値をユーザーに届け、デザインの根源的な力を個から組織・事業へと広げることで、世界をより良く前進させていきたいという方!
ぜひ一度カジュアルにお話ししませんか?ご連絡お待ちしています!
👇カジュアル面談はこちら
CEO西村とのカジュアル面談をご希望の方はこちらよりエントリーください。
👇root公式Xはこちら
UI/UXデザインやプロダクトデザインに関する知見やお知らせを発信しています。 ぜひ、フォローをお願いします!
https://twitter.com/ic_root
👇rootの採用情報はこちら
Vision・Mission・Valueやカルチャー、はたらいているメンバーの紹介など、充実したコンテンツで採用情報をお届けしますので、ぜひ、ご覧くださいませ!
👇 rootの発信コンテンツ一覧はこちら
rootをより詳しく知ってもらうための発信コンテンツをカテゴリー毎にまとめたページを作成しました。 チェックいただきたいコンテンツや最新情報を集めていますので、こちらもぜひご覧くださいませ!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
