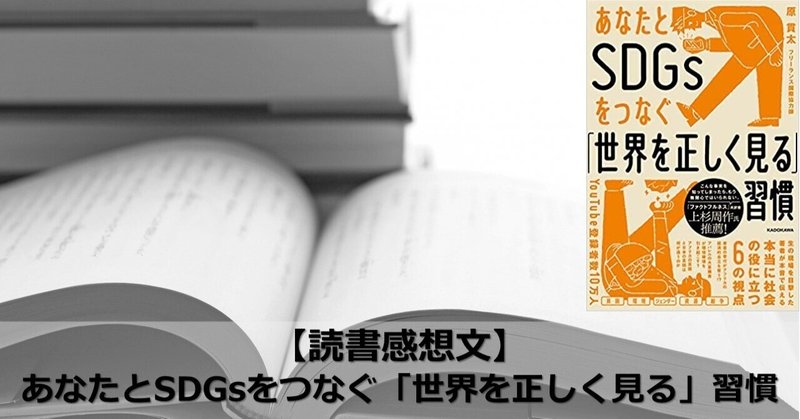
【読書感想文】あなたとSDGsをつなぐ「世界を正しく見る」習慣
こんにちはー!
今日は、原貫太さんの『あなたとSDGsをつなぐ「世界を正しく見る」習慣』の読書感想です。
最近、会社でもメディアでも、急にSDGsって言ってるけど、なんなんだ・・・とりあえず、意味合いは理解したけど、日本はあんまり関係ないんじゃない・・・?えぇ・・・!?学校で子どもも習うの??って言う方に特におすすめの本です。
これは、教科書である
唐突ですが、義務教育は何のためにあると考えますか?
僕は以下の4つの目的があると考えています。
①一般的な教養を身に付けることができる
②同年代 の友人との交流で自身の人格形成の場となる
③自身の能力の可能性を高め、在学中に学び、興味を持ったことを深めていくことで今後の進路を定めることができる
④集団の中で規則を守ったり団体行動の大切さを学び、社会へ出て行くための準備期間という役割
そして、その役割のうち、①と③の教養と学びのために存在している教材に、教科書があります。
定義的には文部科学省が認可した図書としての教材となるのですが、僕は、教科書にはその目的から、以下の条件が必要になると考えています。
①幅広く一般的な教養を身につけることが出来るが、義務教育期間に学べる範囲の広さである
②深く学ぶきっかけとなり得るだけの情報量であるが、義務教育期間に理解できる範囲の深さである
つまり、義務教育期間という限られた時間の中で、幅広く教養や学びとなり、それがより深い探求のきっかけとなる解像度であるということが教科書に求められる条件だと考えています。
さて、前置きがすごく長くなりました。
実は、原貫太さんの『あなたとSDGsをつなぐ「世界を正しく見る」習慣』は、教科書の要素をすべて兼ね備えているのです。
書籍という限られた情報量の中で、幅広く社会問題の気づきや学びとなり、それがより深い探求のきっかけとなる解像度であると言える書籍です。(書籍という限られた情報量というのが口惜しく、おそらくテーマとして書ききれなかった課題もあると思うので続編も期待してしまいます・・・!)
すなわち、『あなたとSDGsをつなぐ「世界を正しく見る」習慣』は社会問題の教科書であると言えるのです。
僕は、教科書のもっとも難しく、重要で素晴らしい部分は、その解像度の設定であると考えています。
嘘ではいけないけど、専門的すぎて意味不明でもいけない・・・子どもが関心を持てるような解像度にするための設定はすごく大変なのではないかと考えています。
同じように『あなたとSDGsをつなぐ「世界を正しく見る」習慣』も、嘘ではいけないけど、専門的過ぎず、分かりやすい解像度にならないといけないいう部分にとてつもなく真摯に向き合っています。
ここからは、僕がこの本の一番すごい部分だと思っている、この解像度について、解説します。
もう、そんなにオススメなら買っちゃうよ!って言う人は、つづきは読まなくていいですw
なぜなら、ここからは、解像度の説明のために、必然的に専門的過ぎる内容になるからですw
(ここから4000字くらいあるので、その体力をこの本を読むことに使ってください!)
この先を読まずに、購入する方はコチラ↓(このリンクから購入しても、何か僕の得になることはございません)
嘘ではいけないけど、専門的過ぎず、分かりやすい解像度
僕の言う、嘘ではいけないけど、専門的過ぎず、分かりやすい解像度を僕の専門領域においてお話します。
この本の6章で、日本の貧困問題について言及されています。
相対的貧困(所得の中央値の半分以下)に該当する方について、掘り下げて解説がされています。(なんと、国民の6~7人に1人が相対的貧困だそうです。知ってました?)
その解説の中で、シングルマザーの非正規雇用の割合が高いという問題に触れられています。非正規雇用の女性については、僕は15年現場にいるプロです。(ごめん・・・!一応プロとさせてください!)
まず、素晴らしく解像度の高いポイントが、
出典がはっきりしていて、しっかりと調べられていること
です。
・・・当たり前じゃねぇか!って思う人も多いかもしれません。
でも、少なくとも労働問題については、全く当たり前とは言えない現実があります。
専門書や専門分野の方が書いていない場合、(どこのインフルエンサーとは言わないけど)どこから出てきたのかよくわからない印象だけの理論でアジテーションしていたり、言葉を間違えて使っている書籍は想像よりも多いです。
例えば、この本では注釈16(237ページ)で、同一労働同一賃金のことを
「同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すもの」
とはっきり説明しています。
↓URLも参考に記載してくれてます。
・・・・素晴らしい!
いや、本当に、「同一労働同一賃金って言ってー、同じ仕事なら同じ賃金って言う方向に進んでますからー(嘘)」って書いてある本やしゃべってるインフルエンサーめっちゃいますから。
本気で嘘ついているのか、調べることもなく字面だけで決めつけているのか分かりませんが、国際協力が主戦場で、アフリカでの支援などを実務とする原貫太さんがこれを調べて、本で紹介するにはどれだけの労力と努力があったでしょうか・・・
素晴らしいと思います。
また、父子家庭についても注釈15で、厚生労働省「ひとり親家庭の現状と支援施策について」↓という出典を明らかにしたうえで、下記の情報を紹介してくれています。

このあたり、しっかりとしたデータに触れないままで進んでいく論説が多いので、ここも素晴らしいと思います。
さて、ここまでは解像度の高い要素です。
一方、専門的ではなく分かりやすく解説し、教科書たるには、解像度の低い部分があります。
そして、それこそが、この本を教科書たらしめているポイントです。
例えば、下記の部分。シングルマザーで非正規雇用の割合が高くなっているのは、出産による退職が理由という解説です。
シングルマザーで非正規雇用の割合が高くなっているのには、やはり出産が大きく関係しています。父子世帯の父親は、離婚前から正規雇用として働いていることが多い傾向にあります。一方、母子世帯の母親は、出産を機に退職を余儀なくされることがあり、結果として専業主婦やパートタイマーになるケースも多いからです。
235ページより
ここで、専業主婦やパートタイマーになるケースも多いと断言を避けます。
それもそのはず。実は父子家庭の解説で出てきた、厚生労働省「ひとり親家庭の現状と支援施策について」という出典元に、下記のデータがあるのです。

こちらの資料では、母子家庭になる前と後の雇用形態が比較できます。
・母子家庭になる前の不就業は23.5%、現在では9.4%であり、14.1ポイント減
・母子家庭になる前の正規は32.1%、現在では44.2%であり、12.1ポイント増
・母子家庭になる前の非正規は57.6%、現在では48.4%であり、9.2ポイント減
母子家庭になった後で、正規雇用は12.1ポイント増えて、非正規雇用は9.2ポイント減っているのです。
つまり、母子家庭になる前は働いていないか、非正規雇用だった方が、正規雇用になっている可能性が高いわけです。
この点を加味すると、シングルマザーに非正規雇用が多いのは、出産のときの離職が原因というのは、少し強引だと思いませんか?
このままでは、僕が原貫太さんを嘘つき呼ばわりしているようになってしまいます・・・
僕は、(言葉の定義が)ふざけたインフルエンサーは嫌いですが、原貫太さんは大好きです。そして、この本は素晴らしい教科書です。
特筆すべきは、シングルマザーに非正規雇用が多いのは、出産のときの離職が原因というのは真実でもあるということです。
↓内閣府の「第1子出産前後の女性の継続就業率」及び 出産・育児と女性の就業状況についてという資料によると、およそ1割の方が、出産・育児を理由に退職しています。
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/top/hyouka/k_45/pdf/s1.pdf
第1子出産前後の女性の継続就業率」及び 出産・育児と女性の就業状況について 平成30年11月 内閣府男女共同参画局

これは、産休育休の取得が増えていくとともに少しずつ改善されて行っているものの、やはり大きな課題といえます。
いわゆるM字カーブ(女性の年齢別の就業率のグラフがMの字になることからそう呼ばれる)も、年々緩やかになってきていますし、下記の通り、配偶者のいる女性の就業率も向上していっています。

それでも、およそ1割の方が、出産・育児を理由に退職しているわけで、それは明らかな問題といえるわけです。
母子家庭になった後で正規雇用になる人が増えるのも、望んで非正規になった人もいるでしょうが、結婚生活の役割分担のために、不本意に非正規雇用になった人がいるからかもしれません。
何を言いたいか。
シングルマザーに非正規雇用が多いのは、出産のときの離職が原因といえるというこの本の主張は真実。
だけど、雇用の仕組みだけではなく、家庭の役割分担や男女の役割へのバイアス、もしかしたら、親権を持つことが多いのが女性という問題(離婚などを機に僕の所属する派遣会社に孫壇に来る方はたくさんいます)などが複雑に絡まり合っていて、出産のときの離職が原因の全てではない。
これだけの資料に当たりながらこれだけ骨太の内容の本を書いている原貫太さんはこの事実を知っているはずです。
それでも、あえて、問題は出産のときの離職が多いとしたのです。
実際、僕の説明をここまで読んでも(筆力の差は目をつぶってください)、分かりにくいですよね?これがずっと続いたら読みたくなくなってしまいます・・・
これが、書籍という限られた情報量の中で、幅広く社会問題の気づきや学びとなり、それがより深い探求のきっかけとなる解像度であると僕が考えたポイントです。
僕に言及できるのは、労働問題くらいですが、この本で扱われている全ての項目で、このように絶妙な解像度になるように苦心しているはずです。
僕は、実際にこの本を読んで、衣服ロスについて、調べてみたいと思いましたし、少なくとも自分の買い物の仕方を考えたいなと思っています。
すなわち、『あなたとSDGsをつなぐ「世界を正しく見る」習慣』は社会問題の教科書であると言えるのです。ですので、これを読んで興味が湧いた部分があれば、どんどんと元データや専門書を読み、学んでいくことが可能です。まさに教科書!!
専門分野の解像度はもっと高い
ここで、補足しておきたいのは、原貫太さんの専門分野である、国際支援についての解説の解像度は圧倒的に高いということです。
これについては、僕が初めて購入した原貫太さんの書籍、『世界を無視しない大人になるために 僕がアフリカで見た「本当の」国際支援』という本を読んでいただければ・・・(昔、購入したとき手書きのメッセージ付きで届いて、嬉しかったなぁ)
国際支援に関わる部分の領域はこちらの本のほうが、体験を濃密に紹介してもらえるのですが、やはりそのバックボーンから、国際支援、とくにアフリカが関係する部分の解説は、実体験を背景にした迫力と説得力で解説されています。
この点は、教科書である要素をぶっちぎっています。僕らの何気ない日常が世界に影響を与えていること、僕らの便利の負担をしている人や国があること、善意の寄付が逆効果であることもあることなどをこれだけのリアリティで伝えてくれる方は、そういないのではないでしょうか。
最後に
長々と書きましたが、僕が言いたいことはこれだけです。
『あなたとSDGsをつなぐ「世界を正しく見る」習慣』は社会問題の教科書である
難しいことや複雑なことを簡単に、かつ正確に伝えることは難しいです。
いや、多様な社会問題に対してという意味であれば、不可能に近いのではないかとさえ思います。
そんな中、書籍という限られた情報量の中で、幅広く社会問題の気づきや学びとなり、それがより深い探求のきっかけとなる解像度になるように、ひたすら真摯に描かれているのが、この書籍です。
どれだけの時間と労力がこの本の背景にあるでしょうか。そして、あえて書かないでシンプルにするのに、どれだけの勇気が必要だったでしょうか。
たった、1400円でこれだけのコストがかかった情報に触れることが出来ることはとても素晴らしいことだと思います。(ありがとうございます!)
『あなたとSDGsをつなぐ「世界を正しく見る」習慣』の「おわりに」という章では、
「私たちの未来を最も脅かすものは、無関心である」
と書かれています。
まるで、教科書で英語の魅力に気がついた子どもが海外へ飛び出すように、引力の法則に魅了された子どもが物理学者になるように、社会問題を知ることで、何かできることを考えて行ける・・・
僕らを、無関心の状態から、自分の世界の出来事として知ることが出来たという状態に変化させてくれます。
僕は、原貫太さんのYouTubeチャンネルを見るようになってから、初めてある団体に寄付をしました。
同じように、この本を読んだら、読者のいつもの日常に何か変化が訪れるのではないか、と僕は思います。
そして、人を動かしたり、変化のきっかけになる本は紛れもない良書です。
是非、読んでみてください。
では、また!
転職エージェントや人材派遣会社へ就職してお悩みがある方、これから転職を考えている方、どちらでもない方、ご質問やご相談はこちら↓へお願いします。
※無料で全力でなんでも答えます。
僕のプロフィール↓
サポートいただいた分は、人材派遣で働く人のサポート、人材サービスで働く方のサポートの活動に使います!必ず、世の中の役に立てますね。
