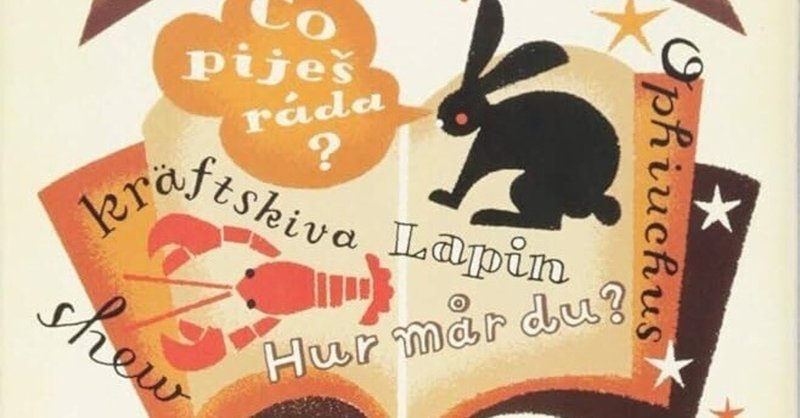
語学の散歩道#16 言葉の指紋
『物語を忘れた外国語』
初めて読んだのは10年程前で、本屋で立ち読みをした際、あまりの面白さに完読してしまった。
しかし、購入リストの一番上に積まれながら、どういうわけか衝動買いされた本たちに次から次へと追い越されていった。
先日、語学好きの友人が、そのまた友人から借りて面白かったと又貸してくれたのが、この本だった。縦に繋げば富士山よりも高くなるほど積まれた本たちのことを思うと、さすがに再読がためらわれる。
返すのはいつでもいいと言われたが、借りた以上は返さねばならぬ。いつまでも呑気に構えているわけにはいかない。
そこで、ランク付けを大幅に繰り上げて、再び本書のページをめくることにした。
面白かった。
いや、面白いなんてものじゃなかった。
黒田さんの話は、こんな具合にはじまる。
一般に外国語能力を向上させようと思ったら、現代日本では外国語学校と検定試験を利用するようだ。(中略)日本では一冊の本をボロボロになるまで使い倒すことが美徳とされるので、問題集は何回もくり返す。最初から最後まで勉強することを「一周」といい、人によっては三周したり五周したりする。このような表現はわたしに競技用トラックを走るアスリートの姿を想像させる。日本の外国語学習は体育会系なのである。
こう述べたうえで、
「だがスポーツとは縁のないわたしには、そういう発想が馴染めない」
と、日本の外国語学習と、「物語から離れ、検定試験漬けで空虚な外国語環境に身を投じる語学学習者」に対して一石を投じている。私もスポーツは好きだが性根が体育会系ではないから、おそらく前回も頷いた箇所でまた首を振っている。
そして、外国語で本を読む場合の心得を、次のように語られる。
外国語で読書をする場合、心がけるべきはすべてを分かろうとしないことである。あらゆる語彙と慣用表現と構文を理解しようなどと、大それたことを考えてはいけない。辞書を引くなんてもっての外。ときには分かんないなあと愚痴りながら、とりあえず先に進む。それが読書である。
なんだか、どこかで私も書いた記憶がある。
しかし、原書を読むといっても、ファンタジーやSFのようなジャンルだと筆者による造語や空想の場面も多く、外国語で理解するのは至難の業である。そういうときは先に映像を見ておくと、本を読むときの手ほどきになることがある。私の場合は、友人に借りたDVDを観たあとで原書を読んだのだが、結果的にこれが功を奏した。児童文学であるはずのハリーポッターは、予想外に難しかったからである。奇遇なことに、黒田さんも本書で同じアドバイスをされている。
さらに、日本の作品を外国語訳で読むという提案もある。
本書では、日本の映像作品が外国語へ進んだ例として横溝正史の作品が取り上げられている。私の祖母はホラーやオカルトものが大好きで、なかでも横溝作品がお気に入りだった。テレビで放送される時は、決まってチャンネル権を独占されたものである。私はといえば、ホラーやオカルトは大の苦手で、湖から突き出た二本の足や、スケキヨの白い面にすっかり恐れをなし、横溝正史の名前を聞くだけで震え上がっていた。もちろん菊人形も恐怖の対象でしかない。
その横溝作品に、なんと外国語訳があるらしい。
黒田さんは今から15年程前に洋書店で『犬神家の一族』の英語訳『The Inugami Clan』を見つける。ところが、横溝作品の英語訳は案外少なく、むしろフランス語訳の方が多かったそうだ。
こういう事情から、黒田さんはこの本をフランス語で読んでしまう。
外国語学習への意欲と、物語を読むという行為から、ときに言語の不思議な組み合わせが生まれる。ある言語で親しんだ作品を別の言語で読むことで、外国語の運用能力が滑らかになり、さらにドラマや小説が再び楽しめる。
まったく同感である。
高校卒業後、英語にはほとんど触れてこなかった私だが、不思議なことに英語の運用能力はそれほど落ちていない。もっとも、語彙や文法力は時間の経過とともにそれなりに剥落したものの、完全に忘れてしまったわけではない。
おそらくその理由としては、第二外国語のスペイン語を独学で続けていたこと(今は放置)、新たにフランス語の学習をはじめたこと、そしてこれらの言語を学ぶにあたり、英語を基準にしたことなどが考えられる。語彙も文法も、母国語である日本語よりも英語と比較した方が圧倒的にわかりやすい。
もちろん、ときに言語が混じって混乱することもあるけれど、総じて相乗効果が得られる場合が多い。これが多言語学習におけるメリットである。
いつからか、私も外国語を学ぶ楽しさを「点数」以外の視点から考えてみたいと思いはじめ、こうして記事を書いているわけだが、先日ある記事を読んでくださったdekoさんから「Ryéさんのエッセイは黒田さんの文章に似ていますね」といった内容のコメントをいただいた。
実を言うと、この記事を書くにあたって、私はようやく意を決して本書を購入したのだが、改めて読んでみてハッとなった。
似ている…。
文章も書いている内容も、驚くほど似ている。
いや、似ているといっても黒田さんは言語学者で、しかもロシア語が専門であるから、もちろん素人のフランス語学習者である私と同じであるはずはないのだが、それでもいろいろな点で相似していることに気がついたのだ。
では、私はいつのまにか黒田さんの筆を真似ていたのだろうか。ふとそんな疑念に襲われた。
これは、まずい。
しかし、正直なところ本書の内容は今回読み直すまでほとんど忘れていた。しかも、黒田さんの著作の中で手元にあるのは、わずか三冊。積読を含めた私の蔵書の中の氷山の一角でしかない。それに、ここ数年読んでいるのは洋書か新書、そしてたまに邦訳のミステリくらいだ。黒田さんの本はかなりの時間を空けて読んだから、文体を真似た可能性は万に一つもないはずだ。
いつだったか、dekoさんや吉穂みらいさんと、「文章には指紋がある」という話をしたことがある。
「指紋」というのは、フランスのドラマ『Astrid et Raphaëlle』の中でアストリッドが使った表現なのだが、書き手がいくら文体を変えても文章には「指紋」があり、書いた人物を特定できるということを主張したものである。
まったくその通りだと思う。
そう、文章には「指紋」があるのだ。
だからこそ、他人の文章が面白く、読み手の好みも分かれるのではないだろうか。
書くことが好きな人は、概して読むことも好きな人が多い。したがって、好きな作家に影響を受けるということは、まま起こり得る話だ。しかし、たとえ文体や思想に影響を受けたとしても、誰が書いた文章かということは案外わかるものである。「◯◯風」ではあっても、文章には書き手の指紋が紛れもなく残されている。
ところが、一方で、「口ぱく」のような文章もまた存在する。私はこういう文章を好かない。
実際、それが理由で読むのをやめたnoterさんもごく稀だが、いる。文章を書くときに大切なのは、その巧拙よりも、まず「自分の言葉」で書いているかどうかだと思う。ウケうりの情報や他人の言葉をコラージュして美文を気取ってみても、そこに指紋がない限り、どこか嘘くさく、薄っぺらい印象がある。もちろんこれは自分自身にもいえることだから、常に肝に銘じている不文律である。
では、一体どうしてこんなことになってしまったのか。そこで、自分の書くものについて少々検証してみることにした。
私が文章を書くときのポイントはいくつかある。
一つ目は、字数である。書き始めた当初はそれほど意識していなかったが、ある時点から原稿用紙10枚を目安に書くことにした。(以下リンクの記事に目を通していただかなくても、本文を読むのに支障はありません。)
次に、記事を書いてもすぐには投稿しないことである。つまり、記事を「寝かせる」のだ。
私は推敲が長い。時間的に長いというよりも、むしろその回数が多い。下書きから一つの記事を投稿するまで、100回以上は目を通す。
誤字脱字を確認するためでもあるが、下書きがあまりにもラフすぎるため、文章としての骨格を整えるのに何度も手直しをする必要があるからだ。
推敲の際は、必ず頭の中で繰り返し音読をする。そうすることで文章が読みづらくないか、わかりにくい点はないかを確認する。
そして、できるだけ簡潔でわかりやすく書くこと。語学のような必ずしも日常的でないテーマを語るには、簡潔でわかりやすい文章が不可欠だ。
こうして考えてみてわかったことは、黒田さんと私の共通点が「多言語学習」にあるということだ。このたった1つの交差点が、結果的に同じような視点と文体をもたらしたのではないだろうか。文章が似ているのではなく、そもそも価値観そのものが似ているのではないか。
そう思ったとき、私の頭から「パクリ」という付箋がパックリと音を立てて剥離した。
ところが、最後に気がついたことが三つある。
まず、いただいたコメントを再度確認すると、「似ている」とは一言も書かれていなかったこと。
黒田龍之助氏の『外国語の遊園地』を少しずつ楽しんでいるのですが。
そのエッセンスを彷彿とさせてくれるエッセイでした。
まったく、記憶違いも甚だしい。
どうして記憶がすり替わってしまったのだろう。
とはいうものの、やはり似ている気がするのは気のせいか?
二つ目。奥付を見ると、この本の出版は2018年だったこと。
初めて読んだ時から5年しか経っていなかった…。
一体どんな勘定で10年前だと錯覚したのか、自分の記憶力が心配になる。
月日が経つのはどうやら思っているほど早くなかった。なんだか得をした気がしないでもない。
そして、三つ目。
読み終わった本書を書棚へ並べようとしたとき、すでに買ってあったことに気づいたこと。
私の記憶は、大丈夫なのだろうか…。
<語学の散歩道>シリーズ(16)
※このシリーズの過去記事はこちら↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
