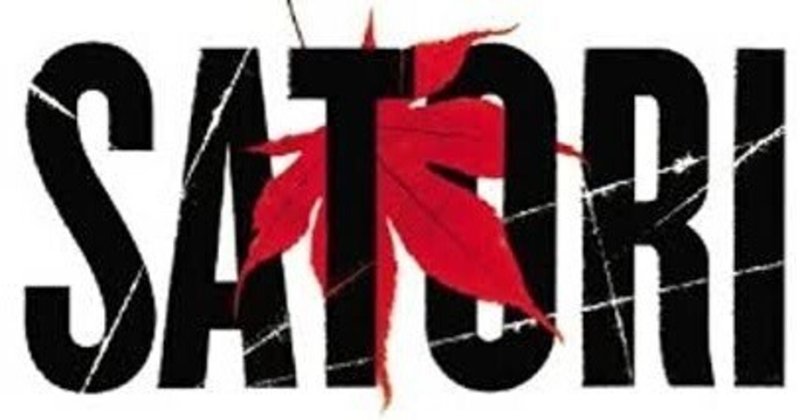
語学の散歩道#14 サトリに諭された話
Nicholai responded, ’I don’t suppose that you could organize an acceptable cup of tea.’
’In fact,’ Haverford said, ’I’ve arranged a modest cha-kai. I hope you find it acceptable.’
ずっと黒原敏行さんのことを書きたいと思っていた。
私は海外文学を読むとき、翻訳者のことはほとんど気に留めない。もちろん翻訳によって原文のニュアンスが変わることはあるし、なかには原文を読んだ方がよほどわかるのではないのか、と思う翻訳もたしかになくはない。
自分の語学力なんてたかが知れているが、それでも原書を読もうと思いたったのは、翻訳の是非よりも原文のニュアンスを自分で確かめたい、という好奇心が勝ったからだと思う。そこで、原書で読み始めたのだが、これがまあ、なかなかハードルが高い。
しかし、たとえ百パーセント理解できなくても、肌触りを自分で確認するのは、語学に触れるという点で役割は大きいはずだと、何の根拠もなく確信している。
TOEICで高得点を取るという目標があるわけでも翻訳者を目指しているわけでもないから、原書を読んでいる時、私はほとんど精読することはない。そのまま原文で読み、わからない部分は読み飛ばすこともある。日本語の本でもつまらない箇所は斜め読みすることもあるし、それでも全体として問題はないから、あまり気にしないようにしている。もちろん「和訳」もしない。
ところが、時々美しい文体などに出会ったとき、思わず日本語の表現を探してしまうことがある。
結局、原書を読むときも日本語の表現を基準としているのだなと気づく。そういうわけで、日本語力が乏しいと、原書を読む場合でもお粗末な翻訳しかできない、ということになるのだろう。
外国語に触れるたびに母国語について考えさせられるというのは、カウンターカルチャーとでもいおうか、とても面白い体験である。
※原書についてはこちらのシリーズで紹介↓
さて、このシリーズは、言葉についてのあれこれを語る一話読切の連載である。今回は翻訳における「日本語」について、注目してみたいと思う。
というわけで、冒頭に戻って、黒原敏行さんの話である。
私が黒原さんの翻訳と出会ったのは、アメリカの人気作家Don Winslow ドン・ウィンズロウの『Satori』(サトリ)だった。
原書は丸善書店の洋書セールで、300円で偶然手に入れた。ドン・ウィンズロウの作品はいつか読んでみたいとは思っていたが、買うほどのものかどうかというところで、随分迷っていた。
そこへ、たったコイン3枚で原書が手に入る幸運に恵まれた。冒頭のページを見ると、比較的読みやすい英語である。これなら案外読了できるかもしれない、という期待に胸が膨らんだ。
予想に違わず、大半が辞書なしで理解できる英語だった。全体としては七割程度の理解したにすぎないのだが、それでも私は十分だった。
とはいうものの、自分の読解力を確認することもときには必要である。
そこで、近所の図書館の蔵書を確認したところ、邦訳が見つかった。文庫本ではないため持ち運びが不便だが、原書と比較してみたい箇所がいくつかあったので、通勤カバンに邦訳と原書を詰め込み、昼休みや電車の中で読み比べてみた。
目から、鱗が落ちた。
私は思わず翻訳者の名前を確認した。
ー【訳】黒原敏行ー
それが、黒原敏行さんとの出会いだった。
そもそも、英語と日本語とでは文の構造が異なるから、言語の置換は容易ではない。それをいちいち頭の中で「和訳」していたら、ちっとも読み進まないし、面白くない。わからないところは多少読み飛ばしても、内容はある程度理解できる。
こんな具合にいい加減な読み方をしていたのだが、黒原さんの翻訳を見て、日本語の底知れぬ可能性を知ったのである。
たとえば、冒頭に挙げた英文を黒原さんの訳とともに読んでみる。
場面は、巣鴨拘置所から出所したばかりのニコライ・ヘルがCIAのハヴァフォードの突然の出迎えに面して、何か欲しいものはあるかと尋ねられるシーンである。
’ I don’t suppose that you could organize an acceptable cup of tea.’
「まずまずのお茶を飲ませてもらうことなど無理だろうな」
’In fact,’ Haverford said, ’I’ve arranged a modest cha-kai. I hope you find it acceptable.’
「じつを言うと、ささやかな茶会の手配をしている。まずまずのお茶と思ってもらえるといいんだがね」
サラッと訳してある。
実にサラッと。黒原訳のこの軽さは、私にとって衝撃以外のなにものでもなかった。
実際には決して「サラッ」と訳されたわけではないのだろうが、黒原さんの翻訳はその重さを全く感じさせない。
たとえば、an acceptable cup of tea を「まずまずのお茶」という日本語に、いとも簡単に訳してある。これに続くI’ve arranged a modest cha-kai も「ささやかな茶会の手配をしている」と、こちらも仮名書道でも書くかのようにサラサラと訳されている。
私が翻訳した場合、「ささやかな茶会を手配した」という程度にはなる。ところが、黒原さんの訳は「ささやかな茶会の手配をしている」と、私とは「てにをは」が違う。たったこれだけのことだが、黒原さんとの日本語力の差を見せつけられた気がした。
黒原さんが持つ日本語のセンスの良さは、本書だけでも例を挙げればキリがない。
Nicolas savoured each sip of the cha-noyu as he sat cross-legged on the tatami floor next to the lacquered table.
ニコライは、漆器の膳を脇へ置いて、畳の上であぐらをかき、抹茶のひと口ひと口を味わった。
each sip を「ひと口ひと口」、lacquered tableを漆塗りの膳とせずに「漆器の膳」と訳してしまうセンス。このあたりには、安西徹雄氏の『翻訳英文法』の影響があるように思われる。
To enter the cha-shitsu, the tearoom, they had to pass through a sliding door, that was only three high, forcing them to bow, an act that symbolized the divide between the physical world and spiritual realm of tearoom.
茶室へは躙り口から入る。この入り口は高さが60センチほどしかなく、自然と頭を下げることになる。この動作は物質的な世界から茶室の精神的な世界へ移るときの敬意を象徴している。
a sliding door は単なる引き戸ではなく、これに続く説明で間口が狭いことから「躙り口」だとわかる。しかし、これは茶の湯の文化が分かっていなければ到底思いつかない日本語である。
さらに茶道具に関しては、a tea whisk 茶筅、a tea scoop 茶杓、a cloth 茶巾と茶道用語で訳されているうえ、こんな翻訳もある。
…then filled the bowl with hot water, rinsed the whisk, then poured the water into a waste bowl and carefully wiped the tea bowl again.
茶碗に湯を注いで茶筅を洗い、湯を建水(たてみず)に捨て、ふたたび茶碗を丁寧に拭いた。
作者であるドン・ウィンズロウ自身が、茶道の知識をある程度獲得しているらしいことも素晴らしいが、これらをこともなげに日本語に訳される黒原さんの知識の広さに、すっかり感動してしまった。しかも、苦心して翻訳した、という足跡がどこにも見当たらないのである。それはまるで、水面下では懸命に水を掻いているであろう姿が想像できない優雅な白鳥のようである。
そして、
‘It’s garbage,’ Haverford answered pro forma.
「つまらないものだが」とハヴァフォードが作法どおりに謙遜する。
という訳にいたっては、私にはもはや神業としか思えなかった。
驚くのは日本文化への造詣の深さだけではない。(もしかしたら、翻訳のために一時的な情報収集で得られた知識なのかもしれないが…。)
本作の舞台は日本だけではなく、中国や東南アジアも舞台になっていて、さらにフランス人の美女ソランジュや道化役のド・ランドなどが登場する国際色豊かなストーリーが繰り広げられる。
たとえば、出所後のニコライに、CIAのスパイとしてフランス語を偽名に使う出身地の方言レベルにまで習得させるという任務のために配属されたソランジュの次の台詞がある。
“ The proper response would be to say, ‘je vous en prie,’ but the -comment vous dites- the ‘vernacular’ would be ‘il n’y a pas de quoi’ or simply ‘ pas de quoi.’ Vous voyez?”
太字部分がフランス語であるが、これを黒原さんは次のように訳されている。
「正式には“どういたしまして”だけどーつまりそのー“くだけた”言い方だと“いえいえ”とか“いいえ”でいいの。わかる?」
ニュアンスと発音を同時に伝えているが、ここもフランス語の素養があれば別として、フランス語が未知の言語だと、なかなか苦しむ箇所である。
しかし、黒原さんの凄さはこの程度にとどまらない。
It was all done with subtlety and style at places like the House of the Golden Flower to Little Fengxian’s.
〈金華家〉や〈小鳳翔〉のような一流の娼館には、趣深い作法があった。
He used to prowl the street of Shanghai, knew the “Reds” from the “ Greens”,(…)
よく上海の街を歩いたので、(国民党に協力した犯罪組織の)青幇(チンパン)と紅幇(ホンパン)の見分け方も知っていた。
英語と日本語で単語の順番が逆になっているのも、日本語の発音を鑑みれば黒原さんの訳がとても自然だということがわかる。さらに面白いのは、英語ではGreenとなっているのが、中国では「青」色になっており、「緑」と「青」の混同が日本と同じであるということだ。
この日本語の面白さについては、数学科の国語教師おにぎりさんが熱く語ってくださっている。
最後に紹介したい極めつけの訳は、毎回大袈裟な言い回しでオペラの格調を著しく貶めていると思われるド・ランドの長広舌である。
(いや、これは全然オペラではないけれども。)
‘By the blue veins on Jane Rusell’s sainted breast, that was spectacular! For a moment I thought that the admittedly fat-clogged arteries of my overburdened heart -which more resemble pâté de foie gras than actual blood- bearing vessels- were about to burst! Thor’s throbbing member, man, you terrified me! But I am happy, happy -no, overjoyed- how your exemplary good fortune. Santé!’
「ジェーン・ラッセルの神聖なる乳房の青い静脈にかけて、前代未聞の華麗なる大勝利だった!脂肪が溜まって循環器の中枢と言わんよりはフォアグラに近いわが心臓が爆発するかと思ったぞ!雷神トールの脈打つ男根にかけて、きみはわたしを恐怖させたよ!だが嬉しい。じつに嬉しい。いや、きみの途方もない幸運をまのあたりにして欣喜雀躍・狂喜乱舞の心境だ。乾杯!」
私が手も足も出ず読み飛ばしてしまった箇所を、黒原さんは見事にド・ランド節で歌い上げている。黒原さんの桁違いの日本語力に私はすっかり舌を巻いてしまった。
こんな具合に、外国語に触れるたびに私は黒原さんの翻訳を思い出し、本の内容よりも黒原さんの日本語に魅せられて邦訳を読むようになっていった。つまり、本の内容よりも黒原さんの日本語が私の興味の大半を占めているわけだ。
しかしながら、こうして日本語の奥行きの深さを学ぶこともまた、語学であると悟ったのである。
<語学の散歩道>シリーズ(14)
※このシリーズの過去記事はこちら↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
