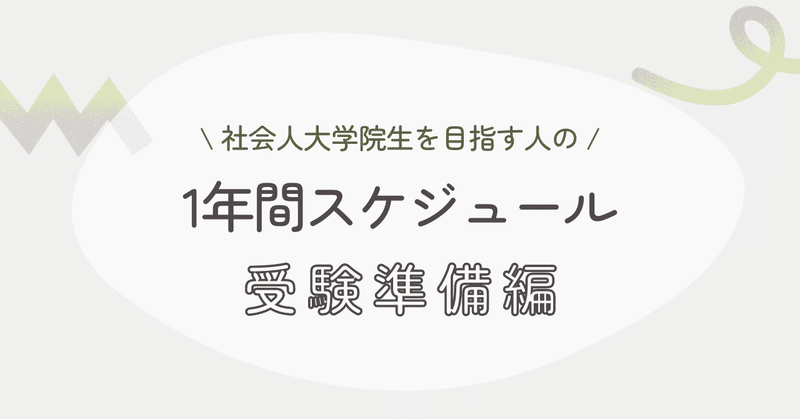
社会人大学院生を目指す人の1年間スケジュール(受験準備編)〜なぜ1年かかったか?〜
この記事は研究経験がない文系大学出身の筆者が技術系の理系社会人大学院を受験するまでの1年間の過ごし方まとめです。私自身が1年前に受験を志した際に周囲に相談できる方がおらず、情報収集にも苦労しました。ですから、私の1年間の過ごし方をまとめることで同じように困る方へのヒントにしたいと考えております。
また私自身「どうしてそんなに準備時間が必要なんだろう」と不思議に思っていたのですが、実際に体感してみると時間がかかることに対して納得ができています。こういった体験談も交えながらお伝えしていきますが注意事項もございます。本記事執筆時点では「受験前」段階であり合否がないことから、学習の質を問うものではないことをご承知おきください。また過ごし方について焦点を当てているので私自身の研究内容は最低限になっております。
長くなりますが、まずは受験背景についても改めてまとめます。
まず私の簡単な略歴です。
・34歳、男性、独身
・出身は三重県、在住は神奈川県
・現職はSIerのソリューション企画職
・副業的に新規事業開発の支援
・猫が好き、朝が弱い、参謀タイプ
❖ なぜ受験をしようと思ったのか
さて、今は「社会人大学院生」という手段を取ろうとしているわけですが、そのそもなぜ受験をしようと思ったのかという前段の事情をまとめます。
事業側での取り組みの興味を失ったから
私はフリーランスを始め、小規模事業者、中堅企業、IPO企業、大企業という幅広い組織に所属した経験があり、その中で、開発、商材企画、店頭運営、施策立上げ、新規事業、情報管理にインターン運営と、34歳にしては上下左右の幅のある職務経験を持っています。あれやこれや、時には会社に振り回されながら自分なりに学習をしたりMBAを取ったりして達成感を味わってきましたが、30歳を超えてからは風向きが変わり、もう少し自分自身の興味関心と向き合いたいと思うようになりました。ただ私自身は「ビジネスの仕組みを作る」ことに興味があるわけではなく、根本的な作用や反応といった根底にあるものに興味を持っています。事業部門では多くの場合このような要素ではなく、もう少しステップの進んだ話をすることがほとんどですので、どうしても興味を持てなくなってきています。
例を挙げるならばDX。企業がDXを進めること自体には反対ではないですが、DXをする際に無視できない人間同士の作用やウェルビーイング追求のような要素は無視されがちです。でも工場で問題が起きることに対する根本的な原因がチームの仲の悪さに起因していたとき、DXの成果って最大化されないはずですのでもう少し人間が技術を使うという行動背景にも着目をしたほうがいいんじゃないか、ということに注目するようになってきました。(社会心理学の領域ですね!)
他者都合で進められないことが多すぎるから
上記のような興味関心のシフトもあり、32歳のときに大きな事業会社の企画寄りの技術部門へ転職しDX推進にチャレンジできる環境に身を置きました。いや、正確には置いたつもりだったのですが、実際には取組みを進める前段階で障壁がありました。ほとんどの場合、大きな会社では技術部門と営業部門は別れており役割分担があり、営業部門が顧客のニーズや課題を広いながら、技術部門がそれを元に課題解決をするための技術や実現方法を考えます。
ですが、私の現在の周辺環境では、営業部門が課題を引き出すことができず御用聞き営業にとどまっているのが現状です。技術部門でXRやAIなどどれだけ面白みのあるものを出しても、営業部門の方が喋れないと顧客にタッチしてニーズ検証することすらできません。これではどれだけ新しいことをやろうにも開拓しようとするときに止まりますし、10年以上在籍のベテラン役職者クラスがこの状況では、少なくとも事業を運営する側の部門にいては新しい取組みをするのが難しそうだという結論を得ました。
このような事情があり、自分のやりたいことは会社に頼らず自分でやってみようということで「研究」を思いつき、社会人大学院の道を考えたのですが実際には他の道もありました。
❖ 実現するための3つの方法
自分の興味関心を仕事の原動力にするという状態を作り出すためには3つの達成方法がありそうでした。
転職をして研究開発職につく
前段にも書いていますが「そもそも事業部門ではなくR&D部門ならどうか」という線です。たしかに研究開発の部門であれば、やりたいことを実行できますし、その内容が企業のミッションと合致していれば予算もおります。ただしこれはすでにドクターを取られていて一般的な研究活動や学会発表などを経験されている方が取る選択肢だと思います。実際に採用条件はほとんどのケースで博士前提ですし、加えて私の場合は具体的にどう進めていくかという部分が決まっておりませんので、この選択肢は取りづらいです。
離職して大学院(全日制)にいく
これも少し考えました。ただし職を手放して全日制でやろうにもコスト面で大きな負担ですし、私の興味がある「人間の作用や反応」といった部分で技術的な面で進学しようとすると理系の基礎知識が必須の試験を受けることになり時間軸としても現実的ではありませんでした。手に職を活かしてITエンジニアとしてフリーランスをしながらという線もなくはないですが、それなら次に示す手段のほうが良いと思いました。
在職しながら大学院(夜間・土日)にいく
結果、この選択肢を取ろうとしています。収入=学費、教材費、研究費含めた投資できる余力の確保ですから、一定の収入を保持することは絶対条件です。また社会人をやめてしまうと人脈の幅にも影響がありそうでしたので、仕事は続けながら並行して研究ができないかを深めていくことにしました。
❖在職しながら大学院に行く場合の人生プラン
さて在職しながら博士課程で研究活動を行う場合にどんな人生プランになるんだろうかということも少し考えていました。
博士課程を終えてドクターを取れたとして40歳を超えている
まず博士課程は5年間です。私の場合はMBAで修士を持ってはいますが技術的な研究活動実績がないので博士前期課程からのスタートになることを念頭に置いており、研究成果を上げてドクターを取れることには40歳を超えることになります。(まだ見込みはありませんが)結婚や将来の妻子のことを考えると、体力的にもこのタイミングを逃してはいけないと感じています。たまたま社会人大学院を修了しドクターを取られた方に話をうかがえる機会があったのですが、実際は7〜8年かかるということもあるようで、できるだけ早くステップを進めるためのテコ入れは必須に感じました。
私自身の研究には技術系の要素がありますので、研究で使う方法やITスキルについても事前に習得しておくことで学習効率を高めることができますので、この部分は並行して考えて行こうと思っています。
最速で進むために職自体を研究に近いものに触れておくべき
少し前の節で「研究開発職につくのは難しい」と書いたばかりですが、人間の行動を分析しようとするとデータの処理や解析作業のスキルが必要です。これは何もR&D部門だけでしか経験できるものではないですし、例えばデータサイエンティストとしての職を得て分析スキルを磨き込んでいくことも重要なステップであると感じました。そのためにG検定を取得し、E資格の学習にも力を入れていまます。
❖ この1年間の大まかな流れ
さて、私が研究活動への興味を持って大体1年ぐらいでしょうか。ChatGPTを触っていて可能性を感じたことも影響していますが、受験に向けた準備としてどんなことをしてきたか、時間軸とイベントをまとめてみましょう。
大まかな過ごし方
1~3月
大学院受験に必要な資金や準備、受験について情報収集
受けられる大学院の種類や教授について調べる
4〜6月
東京工業大学の説明会を聞いてイメージを掴む
世の中の研究や実現状況について調べて解像度を上げる
7〜9月
自分のやりたいことを言語化して、知人に伝えながら整理
北陸先端科学技術大学院大学の説明会を聞き受験準備を整理
10〜12月
先行研究を調査しながら、教授に話を伺い研究計画をまとめる
データ分析の学習のためG検定取得、E資格勉強開始
私の場合「人間の無意識をデータで可視化できないか、活用できないか」というテーマを持っていたので、それを具体化させていくことや近い領域の先生が誰かというところでかなり調べる時間を取りました。一見するとbヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)や人間工学の領域ではありますが、私は集団を扱いたいので社会心理学の領域も被っており、いわゆる学際的な研究になることがわかってきたため周辺の研究にも目を通すようにしました。
計画の反省点
実はこの記事を書いている時点では研究計画書はまだ完成できていません。本来であればブラッシュアップ期間があるべきなので受験月の2〜3か月前にはある程度方針をFIXさせておきたかったですが、家族・親族の予想外のイベント発生や自分自身が自分の考えを言語化するのが苦手であることから、かなりの時間を要してしまいました。また夏頃は本業でメンタルをやられていたこともあり、あまり積極的に進められなかった事情もありました。働きながら研究準備をすることも研究することも、どちらも仕事の影響は大きく受けるわけですから、できるだけ自分らしくいられる場所を選んでおくほうが加速度が大きく違いそうだということも感じました。
❖ なぜ1年かかったか?
一言で言えば「知らない世界に行くためには時間がかかる」です。今ついている仕事とは違う仕事を得るためには資格取得の勉強が必要でそれには6ヶ月〜1年くらいは時間が必要です。営業職をしていた人がエンジニアになるためには、プログラミング言語を学ぶだけでなくチームでの連携方法や暗黙知になっている文化的なものも知っておく必要があります。昨今エンジニアは引く手数多ですが、仮に職につけたとしてもなれるまでには1年以上相当の時間(経験)が必要です。
私の場合は研究に対する馴染みがあまりないということから、その準備に時間がかかったということが言えます。研究計画書を書いたことがないが、研究計画書を書かないと受験ができないとなれば情報収集はもちろんのこと、その中に記載する内容の言語化も細部まで追求する必要があります。正直、4月以降リモートワークを使える割合が一気になくなったこともあり、学習や実践に時間を使えなくなったということもあったため1年でも足りなかったなと感じています。私のような門外の人間は特に、できるだけ早く「研究」という領域の情報を知ることや感覚を掴むことが需要です。
ただし言うまでもなく、研究というのは人類の知識の総和を広げる活動です。自分の興味関心がどう世の中に貢献できるかという社会とのつながり意識は常に持ちながら、前向きに取り組んでいきたいですね。これを見たあなたがなにか一歩を踏み出すための後押しになれば幸いです。
詳細を知りたいよ、少し話がしたいよという方はX(旧Twitter)のDMよりご連絡いただければお話できますので、お気軽にどうぞ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
