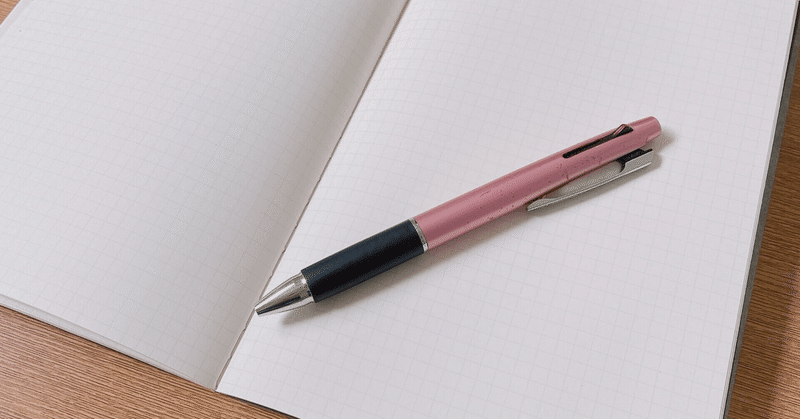
何度も読み直し、文章に手を加える。
言葉は伝え方次第
たった一行の文でも、伝え方次第で、読み手の反応は何十倍も違ってくる。
名文、名言、名キャッチコピーがそうであるように、十数文字の文でも、言葉の選び方次第で、相手のこころに刺さるかどうかが、信じられないほど左右されます。
【参考記事】
表現を改良する
だからnoteを書き終えたら終わりではなく、何度も文章を練り直す。
繰り返し、手を加えると、読まれるnoteに進化します。
気軽な投稿も大事
もちろん、気軽に投稿したいときは、無理に文章を練らなくてもいい。
いちいち手直しに労力をつかっていては、身がもちません。
文章はどんなに文章術を学んでも、書き続けないと絶対にうまくならない。
ライティングの最良の師は「書く練習」そのものです。
ですから、モチベーションを保つ意味でも、毎回手直しする必要はないと言えます。
文章力を底上げしたいなら手直しが大事
でも、文章力を高め、読まれるnoteを追求したいなら、書き上がった作品を何度も手直しする作業をした方が成長が早い。
なぜならプロの作家の多くが、手直しにかなりのエネルギーをつかっているからです。
プロですら書き終えた文章を何度も練り直すのですから、素人ならなおさら、見直しに時間をかけるべきです。
また文章を客観的に分析すると、悪い癖が見えてきます。
手直しする習慣を身に付けないと「何が悪いのか?」に気づくのは難しい。
そのため、何度も見直すことは文章力を引き上げる近道です。
推敲(すいこう)の方法
文章を何度も読み直して、表現を改良し、不要なものを削っていく作業を推敲(すいこう)といいます。
推敲する理由は、書いているときは、自分の作品を客観的にながめられないから。
つまり、推敲とは他人の目で、自分の作品を読んで、修正を重ねる作業と言えますね。
●推敲の基本は削ること
そして推敲の基本は「半分に削ること」です。
1000文字書いたら500文字にするイメージで、無駄なものをできるだけ削る。
思いきりの良さが大切です。
さらに、一文一意になるよう、短文を心がけると役立ちます。
短文の目安は50文字以内。
一文を短くすることは読み手の負担を軽くすることだからです。
●説明を加える
説明不足で伝わらない箇所には、解説を付け加えます。
自分にとっては普通でも、読者からすると馴染みのない言葉かも!?
なので、補足的に説明を加えることが必要なときもあります。
●読者の気持ちで文章を推敲する方法
①時間をおく
文章を1日寝かせると、欠点を発見しやすくなります。
書き上がった直後は、客観的になるのが難しいからです。
1日寝かせるのが難しいなら、1時間離れるだけでも有効。
客観視しやすくなるので、修正ポイントを見つけやすくなります。
②印刷する(スマホから見る)
印刷すれば客観的に文章を見直すことができます。
また、印刷以外にも、PCで書いたものをスマホから読むだけでも、読者目線に近づく効果は期待できます。
③音読する
音に変換すると、文章の問題点を発見しやすくなります。
音読してみて、ひっかかるところや、噛んでしまう箇所は、修正した方がいいポイントだと言えます。
大抵は一文が長すぎるのが原因。
音読で短文に直します。
④推敲支援ツールを使う
無料で手軽に使える推敲ツールにリライトマーカーがあります。
同じ表現の乱用を教えてくれる超便利ツール。
下書きをコピペするだけで修正点が見えてきます。
使ってみると、予想よりも何倍も効果があって驚きますよ!
●構成を推敲する
表現の推敲も大事ですが、構成(組み立て)の推敲も大切です。
「一番言いたいこと」をちゃんと伝えられるよう、順序よくアイデアを配置できているか検討します。
たとえば、冒頭で伝えた方が説得力のあるアイデアを、最後の方に書いてしまうのはよくあるミス。
そういうときは、情報を伝える順番を見直します。
まとめ
書き続ければ必ず書けるようになるのと同じで、推敲も何度もしているうちに、コツがつかめてきます。
念入りな推敲で文章の完成度は大きく違ってくる!
是非、推敲の習慣を身に付けてはいかがでしょうか。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました!
あわせて読みたい
いただいたサポートは、よりよい教育情報の発信に使わせて頂きます!
