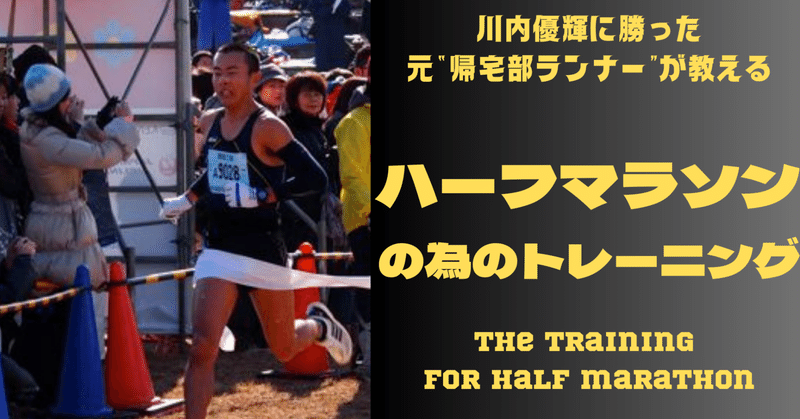
ハーフマラソンが速くなるための5つの運動生理学的観点
突然ですが、あなたはハーフマラソンが速くなりたいと思っておられますでしょうか?
私が聴きたいのは「ハーフマラソンを完走したいのか」それとも「ハーフマラソンが速くなりたいのか」ということです。もしも、後者であるならば私と立場を一にします。ハーフマラソンという距離は距離に対する不安が顕著になる一番短い距離だと思います。
どういうことかといいますと、10000mや10キロのレースまでは練習で非常にコンスタントに走る距離だと思います。
例えば、10キロの低強度走とか今日は疲労抜きの10キロジョギングとかあるいは今日は追い込む練習ではないけれど、走力アップの為の10キロの中強度走をしようとかそういうことが普通にある距離だと思います。
つまり、何が言いたいかといいますと、10キロまでの距離はある程度練習をしている人からすれば、何度も頻繁に走る距離であり、レースで問題になるのはその距離をどれだけ速く走れるのかという質の部分のみであるということです。
もちろん、反論として800mを専門にやる人は1500mという距離に対しても距離的な不安を感ずることは珍しいことではないという反論もあるかと思います。それはそれで理解できるのですが、大きな違いとしては5キロや10キロくらいの距離は先ず頻繁に走れる距離であるということと、疲労抜きの8キロジョギングとか10キロジョギングというのは普通に有り得る練習であるのに対し、21.0975キロという距離はそこまで頻繁に走ることはなく、大抵のアマチュアランナーにとってはせいぜい週に1回程度しか走らない距離であり、疲労抜きの21キロジョギングというのもなくはないけれど、多くの人にとってはゆっくり走っても21キロは疲労抜きの練習にならないという点です。
実際に、1500mを3分台で走る高校生の大半にとって20キロは長い距離であり、20キロ走のことを距離走と呼ぶことは普通にあります。しかも、ハーフマラソンというのは長い距離をゆっくり走れば良い種目ではなく、800mや1500mと同じように1秒を争う競技だということです。
速いペースで走り切れるかどうか分からないという不安があることは800mも1500mも同じでしょう。
ただ、大きな違いはハーフマラソンからはそもそも普段そんなに走る距離ではないにも関わらず、それをなるべく速く走らなければいけないという点にあります。そういう意味ではフルマラソンと同じ要素があると言えるでしょう。
逆に、ただ単にゴールにたどり着けば良いということに関して言えば、フルマラソンでもそんなに大した練習は必要ありません。
健康な人間はちょっと練習すれば42.195キロ程度の距離は移動出来るように生まれてきています。ハーフマラソンにしても、フルマラソンにしても普段はそんなに頻繁に走る訳ではない長い距離をなるべく速く走れと言われるところに難しさがあります。
従って、その練習はある程度距離が短くてペースが速いものから、ある程度距離が長くてある程度ペースが速いものまで何通りにもなります。では、そんなハーフマラソンですが、どうすれば速くなるのでしょうか?
今回はとりあえず出発点として運動生理学的な観点から言えば、どのような能力が求められるのかを解説させて頂きます。
ハーフマラソンが速くなるのに必要な運動生理学的観点その1:最大酸素摂取量
やはり、何をもっても先ず第一義的に必要になるのは最大酸素摂取量でしょう。最大酸素摂取量は通常は一分間あたりに体重1キロあたり何ミリリットルの酸素を摂取するかで表され、数字で表記すると76ml/kg/mのように表記されます。これは私のブログを読んで下さるくらいのレベルの方であれば、百も承知の内容かなと思います。
ですが、ここで改めて考えて頂きたいのですが、何故1分間に体重1キロあたり何ミリリットルの酸素を摂取できるかが重要なのでしょうか?
長距離走、マラソンを速く走ることと一体どのような関係性があるのでしょうか?
答えは単純に考えると明快な答えが出ます。そもそも論ですが、私達の体は物体です。物体ですから、この世の他の全ての物体と同様に物理の法則が働きます。物理の世界で最も有名な法則の一つに慣性の法則があります。慣性の法則とは外部からの力が働かない限りはこの世の全ての物体は等速直線運動をするという法則です。
もしかすると、慣性の法則を習う時に、運動している物体は等速直線運動し、静止している物体は静止する法則だと中学校で習った人もいるかもしれませんが、この説明の後半部分は不要です。
何故ならば、静止している物体は速度0で等速直線運動を続けているからです。ですから、静止している物体と運動している物体で分けて考える必要はないのです。
ただし、中学生にはまだその理屈を理解するのが難しい場合もあるので、静止している物体は静止し続けているという説明をする先生がいても全く間違いではなく、寧ろ親切な先生なのだと思います。
この法則が我々人間にも当然働くので、必ず等速直線運動を続けます。つまり、夜ベットに横たわったら、そこから動けないのです。外部からの力を加えなければ。
人間とその他の物体の大きな違いの一つは、この力が外部ではなく、内部から生まれることです。この内部より生み出す力こそがエネルギーであり、生物学的にはこの体内でエネルギーを生み出す一連の化学反応のことを代謝といいます。
重さ60キロの物体を分速300mで移動させるのに必要なエネルギーは本来は一定です。「本来は」という書き方をしたのは人間の場合は走技術によって若干の差があるからですが、所詮は若干の差でしかありません。走技術、つまり走り方で若干の違いが生まれたとしても重さ60キロの物体を分速300mで動かすのに必要なエネルギー量は基本的に等しいのです。
そして、このエネルギーを生み出す方法には酸素を使う方法と酸素を使わない方法があります。
そして、このうちの酸素を使わない方の代謝系の優劣は個人差がほとんどありません。
一方で、酸素を使う方の代謝系の優劣は個人差が非常に大きいです。この個人差は遺伝子的な差異と後天的なトレーニングの両方によって決まりますが、基本的には後天的なトレーニングによって決まります。
中長距離走の競技能力が後天的に大きく変わるのはこの酸素を使ってエネルギーを生み出す代謝系がトレーニングによって非常に大きく改善されるからです。
そして、酸素を使わない代謝系と酸素を使う代謝系の関係性はどうなっているのかというと、基本的には酸素を使う代謝系を使わなければなりません。
しかしながら、速度が上がると単位時間あたりに必要となるエネルギー量が大きくなります。例えば、1分間に重さ60キロの物体を300m動かすのと1分間に重さ60キロの物体を350m動かすのと2パターン比べると、後者の方が1分間にたくさんのエネルギーを必要とします。
そうすると、その人の酸素を使ってエネルギーを生み出す代謝系の性能によっては、必要なエネルギーをまかないきれません。そこで酸素を使わない代謝系も動員してエネルギーを借りてくるのです。これはあくまでも借金であり、この時酸素を使う代謝系だけでは生み出せなかったエネルギーの分(酸素を使わない代謝系から借りてきたエネルギー)を酸素負債を抱えると表現したりします。
これはあくまでも借金なので、遅かれ早かれ利子をつけて返さなければなりません。皆さんもそれが1000mであれ、5000mであれ、全力で走り終わった後は立ち止まってもしばらくはハーハーと荒い呼吸を続けていると思いますが、あれが借金を返済している状態です。
物理的に言えば、立ち止まっているということは必要なエネルギーは呼吸や心臓を動かすなどの最小限だけで良いはずですが、運動中に借りてきているものを返すためには、しばらくはたくさん酸素を体内に取り入れないといけないのです。
ところが、この酸素を使わない代謝系にも貸せる額に限度があります。この限度額に達するとそれ以上は貸してくれません。貸してくれないだけではなく「お前ちょっと浪費しすぎだ、馬鹿野郎」ということで強制的に出費の額を抑えられます。これがペースダウンです。ペースダウンするというのは要するに60キロの重さの物体が移動する速度を落とすことで1分間に必要となる力の量(エネルギー量)を抑えさせるということです。
これはあくまでも例え話ですが、実際に体内で起きている現象を説明すると酸素を使わずにエネルギーを生み出す代謝系の方ではその副産物として乳酸という物質が生じます。乳酸の一部はピルビン酸に再変換され、酸素を使う代謝系の方でエネルギーとして生み出されるのですが、エネルギーとして使われる乳酸の量を生み出される乳酸の量が上回ると血中乳酸濃度が上昇し続けます。
そして、ある程度上昇すると血液のpH値が下がり、最適pHの値から大きく外れます。血液pH値が最適pHから大きく外れると代謝が阻害されます。代謝が阻害されるということは単位時間あたりに生み出されるエネルギーの量が減るということであり、単位時間あたりに生み出されるエネルギー量が減るということは重さ60キロの物体を1分間に移動させられる距離が短くなるということであり、ということは速度が落ちるということであり、つまりペースダウンするということです。
話をもう一度整理すると、この物理世界の法則としてある重さの物体を1分間の間にたくさん移動させようと思えば思うほど、より多くの力が必要になります。その力を外部から持ってくる方法もありますが、陸上競技の試合では外部からの助力行為は禁止されているので内部から生み出すしかありません。
体内でその力を生み出すには酸素を使う方法と酸素を使わない方法の二種類があり、トレーニングによって後天的に大きく改善されるのは酸素を使ってエネルギーを生み出す代謝系の方です。
そして、基本的には酸素を使ってエネルギーを生み出す代謝系の方が基本であり、それを全力で回してもエネルギーが足りない時のみ酸素を使わない方の代謝系からエネルギーを借りてきます。
ただし、借りられる額には限度があり、ある一定の限度額に達するとペースダウンを余儀なくされます。だからこそ、中長距離の能力を測る一つの大きな指標としては1分間にどれだけ酸素を使ってエネルギーを生み出せるかが大きな指標となるのです。
ところが、実際には酸素を使ってどれだけのエネルギーを生み出せるかを計測する器具がありません。そこで、考えられたのは酸素の摂取量を計測するという方法です。
基本的には、たくさん酸素を摂取しているということはそれだけたくさん酸素を使ってエネルギーを生み出されるだろうという仮説に基づいている訳です。そして、その仮説は基本的には正しいです。
ですから、最大酸素摂取量が70ml/kg/mの選手と71ml/kg/mの二人を5000mのレースに出してどちらが速いかまでは分かりませんが、50ml/kg/mの選手と70ml/kg/mの二人を5000mのレースに出せばほぼ100%後者の方が良い記録を出します。「ほぼ」と書いたのはそれでも肉離れや痙攣、テロなどの不測の事態も有り得るからですが、そういった不測の事態を除けば100%後者が勝ちます。
そして、もう一つ説明しておかなければならないのは、体重1キログラム当たりで表されるからです。これは単純な理由があって、重さ40キログラムの物体を1分間に300m移動させる際に必要となる力と重さ60キログラムの物体を1分間に300m移動させる際に必要となる力を比べると後者の方が必要となる力が大きいからです。
つまり、単純な理屈として体重が重い選手と体重が低い選手が同じ1分間に300m移動する場合、前者の方が必要となるエネルギー量が大きくなります。従って、最大酸素摂取量は常に1分間に体重1キログラム当たり、何ミリリットルの酸素を消費するかで表されるのです。
ハーフマラソンを速く走るために必要な運動生理学的能力その2:乳酸性閾値
先ほど、酸素を使ってエネルギーを生み出す代謝系で必要なエネルギーがまかないきれない場合、酸素を使わずにエネルギーを生み出す代謝系からエネルギーを借りて来るが、この酸素を使わない代謝系を使うと乳酸という物質が生成され、その乳酸の一部はピルビン酸(焦性ブドウ糖)に変換され、酸素を使う代謝系の方に送られてエネルギーとして使われるが、そうやってエネルギーとして再利用される乳酸の量を生み出される乳酸の量が上回ると血中乳酸濃度が上昇し続けるということを書きました。
そして、そのエネルギーとして再利用される乳酸の量と生み出される乳酸の量が一致するところが乳酸性閾値です。別の言葉で言い換えると、処理される乳酸の量と生み出される乳酸の量が重なり合うところが乳酸性閾値です。これよりも速度を落とすと基本的には血中乳酸濃度は上昇しないし、この閾値を上回ると血中乳酸濃度は上昇し続けます。
「基本的には」と書いたのは実際には厳密に全か無かの法則にしたがう訳ではないからです。そもそも閾値という言葉は全か無かの法則にしたがうものに用いられる言葉です。
例えば、人間の筋繊維が収縮するか収縮しないかは全か無かの法則に従います。脳から発射される電気信号が閾値を超えるとその先に繋がる筋繊維は全て収縮します。ちょっとだけ収縮するというようなことはないのです。
ところが、乳酸性閾値を下回るペースでも非常に緩やかではありますが、血中乳酸濃度は上昇するのです。そして、血中乳酸性閾値をやや上回るペースであったとしても血中乳酸濃度の上昇分は緩やかです。というよりは、はっきりとここが乳酸性閾値ですと言えるようなはっきりとした閾値は存在しないのです。
ただ、一つ言えることはなんとなく乳酸性閾値と呼べるものは存在し、そのペースを大幅に上回ると指数関数的に苦しくなるということです。これは次の事実を考えてみると分かります。
よく鍛えられた競技者であれば、10000mのレースペースに非常に近いペースでハーフマラソンを走るということはよくありますし、ハーフマラソンの記録に1分半くらい足せば2倍の距離であるフルマラソンを走る選手も中にはいます。これは驚異的なことです。たった1キロ5秒落とすだけで21.0975キロも長く走れるようになるのですから。
ところが、800mから1500mのたった700mに関しては、なかなか1000m5秒程度落としたペースで走り切れるものではありません。普通は10秒程度落とさないと走り切れませんし、中には1000mあたり15秒程度落とさないと走り切れない選手も少なくありません。
これは中高生を指導している方ならお分かり頂けると思います。800m2分ちょうどの選手で1500m4分ちょうどというのはごく普通というか寧ろ、1500mが強いかなという感じだと思います。800m2分ちょうどで1500m4分7秒というのはごく普通で、なんならそれよりも遅い選手もいます。
まあ、並みの選手と超一流の選手を比較するのは公平ではありませんが、超一流選手同士の比較で言えば、中距離の一流選手田中希実選手は800m2分2秒に対し、1500mが3分59秒なのでおよそ1000mあたり+7秒です。片方では、1000mあたり5秒落とすだけで21.0975㎞も長い距離が走り切れるのに対し、もう片方では1000mあたり7秒落とさないと700m長く走ることすら出来ないのです。
その理由は単純で、乳酸性閾値を大きく上回っているのか、それとも乳酸性閾値くらいでレースが進むのかの違いです。乳酸性閾値を大きく上回ると血中乳酸濃度が指数関数的に上昇するので、たった700m長く走るのにも1000mあたり10秒くらいペースを落とさないと走り切れないのです。
この事実を考えると乳酸性閾値がなるべく速いペースで出現する方が望ましいことがお分かり頂けると思います。
乳酸性閾値の向上とはすなわち、より速いペースで走ったとしても血中乳酸濃度が大きく上昇しないということです。
例えば私が今指導している東山高校の生徒たちは、私の指導力不足もあって一番速い子でも5000mが16分25秒でしか走れません。5000m16分25秒ということは1000m3分17秒ペースです。
そして、このペースで5000mしか走れないという事実を鑑みるに、この選手にとっての1000m3分17秒ペースは乳酸性閾値を大きく上回り、走れば走るほど血中乳酸濃度が上昇し、どこかのタイミングで借金取りが来て「おい、お前もうええ加減にせえよ」と怒鳴られてペースダウンを余儀なくされるペースです。
一方で、私の場合はどうかというと1000m3分17秒ペースは乳酸性閾値くらいのペースです。おそらくやや下回るでしょう。
ですから、このペースでは血中乳酸濃度がほとんど上昇しません。ですので、走り始めて15分くらいで限界近くまで行っているこの選手を尻目に同じペースで1時間でも2時間でも走り続けることが出来るのです。
この乳酸性閾値がなるべく速いペースで登場するようになるということもハーフマラソンの記録の向上には非常に大きな役割を果たします。
ハーフマラソンの記録を伸ばすのに必要な運送生理学的観点その3:換気性閾値
換気性閾値は非常に乳酸性閾値に近く、またその理由も考えてみると明快です。
そもそも、換気性閾値とは何かということですが、ペースを上げていくと呼吸が有意に乱れ始めるポイントです。ゆっくりと走り始めて徐々にペースを上げていった時に、初めの方は1キロ10秒上げようが、5秒上げようが呼吸はほとんど変わりません。
ところが、ペースを上げるにつれて呼吸は荒れていき、有意に呼吸が乱れ始めるポイントがあります。会話をするのが急激に難しくなるポイントといっても良いと思います。
換気性閾値はたまに短い会話が出来る程度とも言われますが、私の感覚で言えば、ハーハー言い始めるポイント、自分の呼吸が耳で聞こえはじめるポイントです。
そして、この換気性閾値が非常に乳酸性閾値に近い、というよりはほぼ等しい理由は単純で、血中乳酸濃度が上昇するということは酸素負債を抱えているということだからです。つまり、酸素が足りていないという状態なので体は酸素を求めて呼吸を荒げるのです。
厳密に言えば、酸素はたくさんあるので酸素が足りない訳ではありません。酸素を使って生み出せるエネルギーの量が不足しているのですが、体の方はそんな理屈はどうでも良くて自分が今直面している問題を全力で解決しようとするので、呼吸を荒げるのです。ですから、換気性閾値が向上するとはどういうことかというと、ハーハー言わずに走れるペースが速くなるということです。
ちなみに、これも閾値と呼ばれるのには訳があります。この閾値を大きく超えている場合、それよりも大きくペースを上げたとしてもそれ以上激しくハーハー言う訳ではないのです。800mのレースは1500mのレースよりもハーハー言っているかと言うとそんなことはありません。どちらも全力で走っているので同じくらいハーハー言っています。3000mのレースのラストも5000mのレースのラストも1500mのレースのラストと同じくらいハーハー言っています。何故なら、どちらも自分の限界に達しているからです。
つまり、走行速度に比例して呼吸が乱れていくのではなく、あくまでも閾値があるのです(厳密に言えば、閾値のようなものだけれど)。換気性閾値を頭に入れておくことは非常に有用です。
何故ならば、血中乳酸濃度を測るのには特殊な器具を必要とするのに対し、呼吸を計測するのに特殊な器具は必要じゃないからです。よほど寝ぼけた人でもない限り、自分がどのくらいハーハー言っているのか分からないということはありません。
ですから、乳酸性閾値の話をする人が多い割に、換気性閾値の話をする人は少ないのですが、より実践的で有用なのは換気性閾値です。ハーフマラソンが距離に対する不安を覚え始める最も短い距離であるならば、換気性閾値に到達する走行速度は呼吸的な不安を覚え始める最も遅いペースであるということが出来るでしょう。
ハーフマラソンはもしもイーブンペースで走れば、ちょうどハーハー言い始めるくらいの強度でレースが進むので、激しくハーハー言わずに走れるペースを徐々に速めていくことがハーフマラソンの記録向上に大きく関わるのです。
ハーフマラソンを速く走るために必要な運動生理学的観点その4:ランニングエコノミー
このブログ記事の冒頭で「重さ60キロの物体が1分間に300m移動する際に必要なエネルギー量は基本的に同じである」と書きましたが、「基本的に」と書いたのは厳密に言えば微妙に異なるからです。
何故異なるのかと言うと走技術による差があるからです。走技術が悪ければ、無駄なエネルギーを使うことになります。つまり、推進力に繋がらない無駄な力を使っているということです。
ですから、ある意味では理想的な走り方というのはプラス点を稼ぐことではなく、マイナス点をきれいさっぱり消せる走り方です。そういう意味では、大企業型、あるいは官僚型と言えるでしょう。減点方式で評価していき、マイナス点を出すと昇進に響くけれど、プラス点を出しても別にそんなに査定に影響ないみたいな感じです。
私が走り方を変えても大して速くはならないと色々なところに書いているのは以上の理由があるからです。
ただし、知らず知らずのうちに大きなマイナス点を出している人もいるので、走り方指導も否定はしません。否定はしませんが、やはり私は大きなプラス点を稼ぐ方に興味があります。
もしかしたら、多少は性格の問題もあるかもしれません。私は絶対につつがなく過ごしていれば年齢と共に昇進していく大企業よりも1万回失敗しても良いから1万回の成果が求められる起業家の方が性に合っていますから。
そんな話はどうでも良いのですが、やはり生み出したエネルギーを経済的に使うことも必要です。これは燃費の向上に該当します。あるいは、電化製品で言えば、昔の電化製品ってすぐに熱くなったり「ブーン」というような謎の音もしてましたが、最近はそうでもないですよね?
これは技術の向上によって生み出されたエネルギーが本来の目的にたくさん使われるようになったからです。熱エネルギーや音エネルギーに変換されるというのは本来の目的ではないものにエネルギーが使われてしまっているエネルギーの無駄遣いの状態なのです。
人間の体も同じで生み出したエネルギーは全て進行方向へと変換したいのですが、なかなかそうもいきません。この前も東山高校の選手の試合を観に行ったら、上にばっかりぴょこぴょこ跳ねている選手が一人いました。こういうのがエネルギーの無駄遣いであり、ランニングエコノミーは決して高くないと言えるでしょう。
市民ランナーの方に一番多いのは無駄な力が入っているということです。本来も意識しないうちに無駄な力がどこかに入ってしまっています。それから、無意識のうちにブレーキがかかってしまっている人も多いです。この現象は「つま先接地で走ると速く走れる」「体の真下に足をついて地面からの反発をもらう」という二大言説が広まってから特に顕著になりました。
上記二つを全否定はしませんが、誰もがつま先接地が向いている訳ではないし、体の真下に足をついて地面からの反発をもらう」ということを意識しすぎて必要以上に力が入っている人も多いです。ペースが遅いのに必要以上に地面に力を加えれば、その力をどこかに逃がすか、自分でブレーキをかけないといけません。力をどこかに逃がすのが上にぴょこぴょこ跳ねるパターンで、そうでなければアクセルを踏みながら自分でブレーキをかけるという器用なことをする羽目になります。
つま先接地に関して言えば、基本的には人間は踵からつま先へと抜けていく動きしかしていません。何故ならば、基本的には歩いている時間の方が長いからです。歩く時は必ず踵からついてつま先へと体重が抜けています。
短距離走に関して言えば、終始踵を地面につかずにつま先で地面を蹴り続けるということも出来ますが、それは走る時間が短いからです。基本的には、長時間動き続ける場合には、踵から入ってつま先へと体重が抜けていくという動きしかしていないのに、いきなりつま先からつけと言われても誰もが出来る訳ではありません。筋力的にも大抵は持ちません。
そのため、ブレーキがかかったり、余分な力が入ったりしてしまう方が大半なのです。つま先接地を自然に出来ている市民ランナーさんはサウルスジャパン社長の嵜本さんと弊社のオンラインスクールを受講し、イベントなどにもご参加下さっている横浜のさとちゃんしか知りません。数百人(多分そろそろ1000人)の市民ランナーさんを見てきてそんなものです。特殊な走り方と言って良いでしょう。
ハーフマラソンを速く走る為に必要な運動生理学的観点その5:筋持久力
ハーフマラソンはなんだかんだ言っても長いです。しかも、その長い距離を速く走らなければならないことを考えれば、筋持久力は必須の項目になります。
では、筋持久力とは何かというと筋肉の耐久性です。例えば、体重60キロの私がハーフマラソン63分ちょうどで走ると考えると重さ60キログラムの物体Aを1分間に334m動かし続ける訳です。
物理的に言って、この際に必要な力(内部から生み出す場合にはエネルギー)が必要であることは説明しましたが、仮に必要なエネルギーを生み出したとしても、脚の筋肉や体幹の筋肉、腕の筋肉がこれに耐えられなければ動き続けられません。
ハーフマラソンの距離になると往々にして起こるのが呼吸的には楽だけれど、もう脚がへたってしまってペースダウンを余儀なくされるという現象です。厳密に言えば、筋肉だけではなく、靱帯も腱も最後まで持たないといけませんし、ごくまれにレース中に疲労骨折するケースもあります。だから、耐久性が求められるのです。
そして、この耐久性は質と量の両方から考えられなければなりません。
何故ならば、そもそも力とは重さ×速さで表され、それの合計移動距離によってかかる力の合計が決まるからです。つまり、体重が何キロで、1キロ何分ペースで(分速何メートルで)、何キロ走るのかで筋肉、靱帯、腱にかかる負荷の総量が決まるということです。
同じハーフマラソンを走るのでもゆっくり走ればかかる力は少なくなるのです。体重は一定であるので、走行速度が遅くなればなるほど、かかる力は少なくなり、従って求められる筋持久力も少なくなります。逆に、走行速度が速くなればなるほど、かかる力の合計が増すので求められる筋持久力も増します。
ここまで、ハーフマラソンを速く走るために必要な運動生理学的観点5つを紹介させて頂いたのですが、いかがでしょうか?
私自身はそこまで運動生理学のファンではありませんが、たまには物理の法則というものを再確認しておくと物事が単純明快になります。
そして、単純明快な思考は集中力と適切な戦略を生み出します。走り方を変えれば速くなる、否、速くなるには走り方が大半を占めると思っている人も多いですが、この物理世界に住む以上は物理の法則には逆らえないので、物理的な法則をこうやってもう一度整理し直してみると、走り方ばかり変えてマイナス点を減らしてもプラス点が決して生み出される訳ではないことがお分かり頂けると思います。
つまり、走り方の方ばかり考えて肝心の代謝系を改善するためのトレーニング方法について学ぶ時間やお金が減ってしまうという愚を避けることが出来るのです。
では、肝心の代謝系の改善、呼吸循環器系の改善、筋持久力の改善には何をすれば良いのでしょうか?
実はそれを徹底解説する約2時間半の講義動画を作りました。講義の目次は以下の通りです。
1:57 ハーフマラソンってどんな距離?
15:02 ハーフマラソンに関するよくある誤解
26:38 ハーフマラソンのトレーニングに対する考え方
32:37 呼吸面と筋持久力の違い
43:07 最終的に核となる練習
49:03 具体例
52:16 大前提
56:56 日本におけるハーフマラソンの実際
59:24 フルマラソンとの関連性
1:05:50 特異的に準備することの重要性
1:17:05 ハーフマラソントレーニングにおける矛盾
1:22:42 具体的なハーフマラソンに向けての16週間のトレーニング
1:25:39 初めの4週間
1:28:24 次の4週間(2か月目)
1:29:30 次の4週間(3か月目)
1:32:50 次の4週間(4か月目)
1:33:22 具体的な16週間のトレーニング
1:42:53 1週目
1:49:23 2週目
1:49:29 3週目
1:49:35 4週目
1:50:48 5週目
1:52:27 6週目
1:52:33 7週目 8週目
1:54:31 9週目
1:56:35 10週目
1:57:24 11週目
1:59:01 12週目
2:01:23 13週目
2:03:38 14週目
2:05:19 15週目
2:08:56 16週目
2:12:02 個人の練習に応用する際の注意点
2:18:54 ハーフマラソンにとって理想のレースとは?
2:27:18 最後に
2:30:38 皆さまの成功を祈っております
こちらの講義を受講して頂いてあなたが得られるメリットは以下の通りです。
・ハーフマラソンが速くなる
・長期にわたって着実にハーフマラソンの記録を伸ばし続けられる
・ついでにフルマラソンも速くなる
・ついでに走るのが楽しくなる
これだけの講義が詰まった内容がたった3500円の自己投資で受講して頂けます。受講手続きは非常に簡単で、お支払い方法をクレジットカード、ペイパル、銀行振込よりお選びいただき、講義をお届けさせて頂くメールアドレスとお名前をご入力頂くだけで5分ほどで完了します。
また、こちらの講義には全額返金保証をつけており、あなたの満足を保証します。もしも、最後まで講義を受講して頂き、何らかの理由でご満足いただけない場合には全額返金致しますので、いつでもこちらをクリックして問い合わせページに入り、ご連絡下さい。
さて、最後にもう一度はっきりと申し上げさせて頂きます。こちらの2時間半の講義には私自身がセルフコーチングでハーフマラソンの自己ベストを63分09秒まで伸ばし、過去四年間でのべ約7000人のアマチュアランナーさんを顧客としてお迎えさせて頂いた私がハーフマラソンが速くなるコツと要素を単純明快に解説させて頂いた講義動画で絶対に絶対にあなたに満足して頂けます。
本日あなたにお願いしたいことは1%だけ私を信じて受講して頂くことだけなのですが、いかがですか?
今すぐ約2時間半の講義動画にアクセスする
よくある質問とそれに対する回答
質問:講義動画を見られる期間はいつまででしょうか?
回答:一度お申込み頂けますとそのあと一生ご覧いただけます。
質問:講義動画はどのようにして試聴できますか?
回答:ユーチューブに限定公開しておりまして、お申込み下さった方にのみURLをお渡ししております。
質問:倍速再生は出来ますか?
回答:はい、出来ます。
質問:講義はどのようにして届きますか?
回答:クレジットカードもしくはペイパルでお支払い下さった方には自動返信メールですぐにお申し込みの際にご入力いただいたメールにお届けさせて頂きます。銀行振り込みをお選びいただいた方には入金を確認次第、手動でメールをお送りさせて頂きます。
質問:全額返金して欲しい場合はどこから連絡すれば良いですか?
回答:こちらをクリックして頂いて、問い合わせページに入り、そこから「ハーフマラソンの為のトレーニング返金希望」と入力して送信して下さい。
質問:ウェルビーイング株式会社ってどんな会社ですか?
回答:オンラインにランナーの為の日本一の学び場を作り、無料コンテンツの利用者は月間のべ10万人以上、有料コンテンツはこれまでのべ7000人以上にご利用頂き、ロンドンオリンピック男子マラソン代表の藤原新さんを初め、多くの方より「ここでしか学べない質の高い講義」と高評価を頂いております。
質問:どうしてこんなに安いんですか?
回答:前々回の講義動画「800mからフルマラソンで結果を出すためのトレーニングの原理」は受講して下さった方もたくさんいらっしゃる一方で、「物凄く興味があって受講したけれど、ついつい金額を見て二の足を踏んでしまった」という方もいらっしゃったので、今回はお求め頂きやすい金額に致しました。
他にも、受講前に気になる点や疑問点等ありましたら、こちらをクリックして問い合わせページよりご質問ください。
今すぐ約2時間半の講義動画にアクセスする
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
