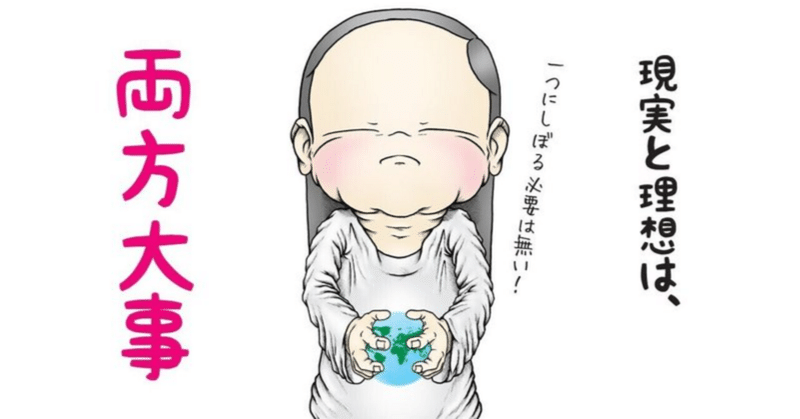
理想を言わせてもらえば▪▪▪⁉️
私ができるなら、 こんな教育環境、仕組み、考え方を
広めたい😊
もし私に地位があり、予算や人材が十分にあるなら、こんな理想があります。
あくまで「私の価値観」なので、「へぇ~、そうなんだ~。」くらいの気持ちで読んでくださいね😁長いです😅
ちなみに、心身に支援の必要な保護者や子どもは「できる範囲で」になります。
①妊婦とその家族への指導体制
(「子育ての心構え」を指導)
「将来は、自立して、継続できる仕事につき納税できるように、子どもを教育していく」覚悟をする。
「できたほど」では、学校や仕事を選びにくい。仕事に就かなければ、ずっと保護者が養っていくことになる。また、納税者が減れば、高齢化に税収減少が合わさり、日本が立ちゆかなくなる。
自らのマナーや常識を振り返り、修正すべきところは修正しておく。
周りに迷惑をかけない大人が、そのような子どもを育てることができる。
「出産前より出産後、時間もお金も体力も、子ども優先になる(ならざるを得ない)」ことを覚悟する。必要な範囲で手をかけた分、子どもの心は満たされ、問題行動は少ない傾向にある。
最低でも、高校卒業までに必要な費用を考え、計画的に暮らす習慣をつけていく。
②出産後~就学前の保護者に、定期的な指導体制(子どもに対して、「こう教育すべき」という指導)
小学校にあがるまでは、リモコンやスマホの操作はさせない(ゲームも❗)。
動画やテレビは1日1時間(休日でも3時間)まで。周りの大人も、子どもが起きている時間は、できるだけ使わないようにする。
話は黙って聞かせる(大事な話は、周りの映像や音を消してから聞かせる)。
指示や禁止を出したら、従うまで折れない(お菓子を買わないと約束したなら、泣いても叫んでも買わない。何度か繰り返せば言わなくなる。折れると、ずっと約束を守らなくなる)。我慢の耐性をつけることにもなる。
わからないことは質問できる、質問には答えられるように、日頃からコミュニケーション力を意識しておく。
他人が子どもに向けて話しかけている時に、保護者が答えてしまわない。アドバイスしながら、子どもに話をさせる。
また、子どもの「なんで?どうして?」に、できるだけ向き合う。
公共の場では、スマホなどがなくても静かにできるようにしていく(身内が思うほど、周りは寛容ではない。マナーは、幼い頃から繰り返し教えることが大切)。
事前に約束したり、絵本や静かにできる遊び道具を持参するなどの工夫をする。
言葉が理解できるようになったら(「ダメよ。」がわかり始めたら)、ダメと言うことをしたときには、きちんと叱る。
家とその他の区別は難しいので、「その他でダメなことは、家でもダメにする」と、理解しやすい。
叱る=短い言葉と行動で制止する。
(スーパーで走った時、捕まえて、「ここは走る場所ではないよ。」と目を見て伝え、約束をする。守れない時にはカートからおろさない など)
椅子に姿勢よく座れるようにしておく。
いつもゴロゴロしていたり、下に座る時間が長かったりすると、椅子にきちんと座れない。実際、背骨が曲がっている子どもが増えている。
体や、手や頭を使う遊びをさせる。
(外遊び、ごっこ遊び、ブロック、パズル、折り紙、工作、お絵かき など)
手先が不器用だと、「ひも結び、プリントたたみ、服たたみ、片付け、定規類やコンパスの扱い、裁縫など」様々な面で苦労する。
時計(アナログ)をよんだり、数を数えたり、増えたり減ったりを考えるなどの活動を取り入れる(算数脳の下地を作る)。
特に時計は、学校の学習時間だけでは身に付かない。
毎日でなくていいので、読み聞かせをし、小学校にあがるまでには、平仮名が読めるようにしておく。できる子は書けるとよい。また、読み聞かせにより、語彙力も伸びる。
興味のある分野からでいいので、図鑑や事典を見せる機会をつくる(図書館なども利用して)。知っていることが多いと、興味関心がある分野が多くなり、学習意欲が高まる。
小学校にあがるまでに、準備、片付け、トイレ、着替えは一人でできるようにする。
「急ぐ」ことができるようにしておく。
いつものペースと、早いペースの使い分けが必要。
保護者だけでなく、まわりの大人も子どもを指導する。可愛がるだけではダメ🙅
叱らない大人がいると、叱る大人が嫌な人になり、指導が入らなくなる。
結果、自分だけが嫌われるのは嫌だと、誰も叱れなくなる=自分勝手な子どもになる。
③小学校以上の保護者への指導
②の指導の不十分なところや、小学校以上でも必要なところを、家庭で継続して指導する。
~学校関連~
担任のやり方や方針を理解しようと努力する。わからない時には、連絡帳などで質問する。
子どもの話をよく聞いてやり(作業をしながらも、きちんと聞く)、教師に疑問を持った場合は、子どもの前で批評せず、担任や管理職に直接連絡する。
新採や若手が、ベテランとは違うのは仕方ないことなので、要望があれば学校に伝えるとともに、保護者のできるフォローをしていく(宿題や準備を一緒にするなど)。
自宅学習習慣がつくまでは(3年生くらいまで)、できるだけ近くで学習させる。
また、3年生までは、どの教科も土台作りになり、4年生から土台を使って知識を積み上げていくことになる(3年の小数の概念を使って、4年以上で小数の計算をしていく など)。
だから、3年生までの国語と算数は、特に取りこぼしがないように、家庭学習での補強が重要になる。どうしても教えきれない時には、担任に連絡して「個別指導」をお願いすることもできる。
~友達付き合い~
基本、天気のいい日に外で遊ばせる。家にあげると、いろいろなトラブルのもとになる。
おやつは食べてから集まるか、それぞれ自分の分を持って集まる。買い物に行くと、持ってきた金額の違いや、おごり行為などのトラブルになる。また、アレルギーのある子どもへの配慮にもなる。
できるだけ、参観日や懇談会に参加して、クラスの保護者と知り合いになる。ちょっとしたトラブルは、誤解なく、すぐに解決できる。
~習い事~
小中学校のうちは、学習の妨げになるほどの習い事は、控える(ことを薦める)。
習い事で将来食べていくのは、かなり厳しいし、その方向でやっていて挫折した時に、最低限の知識がないと自立できない。
③教師育成の仕組みと若手教師への指導
教育学部の4年生は、院に行かない場合は卒論ではなく、学校の具体的な流れを学ぶ。(小学校課程なら、出勤から朝の会までの過ごし方、朝の会のやり方、国語の平仮名や新出漢字の指導方▪▪▪など、すぐに実践可能なこと)
新採は、3年間は副担として(小学校では低▪中▪高、中学校▪高校では1▪2▪3年)、ベテランについて学ぶ。
新採の研修はオンライン可能なものはオンラインで行う。朝の時間や給食、放課後の時間はいつも通りなので、移動時間短縮と自習監督の人員削減、何かあった時の対応が早くできる。
「働き方改革」は良いが、若いうちに技術を磨かないと、経験年数が経てば仕事が更に増えたり、結婚すれば家事が増えたりして、スキルアップが難しくなる。
せめて、「週末に、次週の全時間の指導計画はする」は習慣化させ、平日は宿題や授業中に書かせたものチェックしたり、不測の事態にそなえたりする。
もっと細かく書けば、まだまだありますが、上記のようになれば、
小学校が本来重点をおくべき
「学習指導、集団生活指導」に力を入れることができ、高校卒業時点で社会に入りやすい素地ができていると思います。
また、新採教師が育ち▪育てやすくなり、学力の底上げもはかれます。
裏を返せば、今のやり方では「学習指導や集団生活指導に重点をおけない」ということです。
学校では、「基本的生活習慣、基本的学習環境、子ども同士のトラブル、家庭との連絡」で手一杯❗授業準備は二の次です。
私の考え方は、今の時代に合わないところもありますが、今のままでは「多様性に合わせて、我慢してまでやらなくてよい」「誉めて伸ばすから、怒られたことがない」という中で育ち、「耐性のない、子ども扱いしないとすぐに心が折れる大人」だらけになります。もう、なっています。
「私にできる効果的なことはなんだろう?」と考えながら、若手にアドバイスする日々です。
打っても響かない(理解できてない)、または、無視されたり反発されたりすることもありますが、愚痴りながら折れずにやってます👍
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
