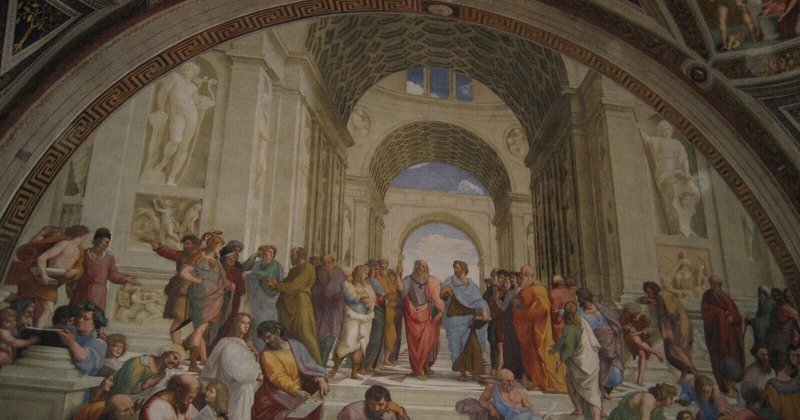
的確な批判をするために留意すべきこと
SNSでは様々な言論が飛び交っています。その中には他者の言説への批判も含まれていることは、今更、私が指摘することでもないでしょう。
しかし、です。そういった他者の言説への批判には、批判のやり方そのものが間違っているものもあります。
前回の記事の末尾で「次回は、何故、人身攻撃がダメなのかや間違いの指摘の仕方、中立派を巻き込まないメリットなどを説明したい」と書きましたが、今回は、「何故、人身攻撃がダメなのか」にあたるものを説明していきたいと思います。ただし、幾つかの追加点もあります。
ちなみに前回記事はこちら。
今回の記事内容と繋がりのあるものではありますが、今回の記事は独立した内容でもありますので、前回の記事を御読みいただかなくとも今回の記事の内容を理解するには差し障りはありません。
相手の主張を正確に理解する
他者の主張に的確な批判を行うためのファーストステップです。ここで躓いてしまうとあなたの他者への批判は全く意味のないものになってしまいます。また、相手の主張を曲解した上で批判を加えることはStraw manという詭弁にも該当します。
他者の主張に的確な批判を行うためには、批判対象となる他者の主張そのものを正しく理解(≠賛同)しなければなりません。
そうでなければ、あなたが行う批判は的外れなものになってしまいます。
A 「Xについては、ある状況下ではYとなると考える。その理由としては~~」
B 「Aは「Xについては、如何なる状況下でもYとなると考える」と主張しているが、それは間違いだ。何故ならば、Sという状況下ではXはTとなるからだ」
この文例において、Bが言っている「Sという状況下ではXはTとなる」が事実であったとしましょう。しかし、それでもBの主張は、Aへの批判としては全く機能し得ないのです。
何故ならば、Bは、Aの主張である「Xについては、ある状況下ではYとなる」を「Aは「Xについては、如何なる状況下でもYとなる」と考えると主張」と誤解し、それを前提として論を展開しているからです。
これでは、Aに「私はそんなことは言っていない」と言われただけで話が終わってしまいます。また、この場合、Aの主張とBの主張とは対立しているとは限りません。Aが想定している状況とBが指摘している「Sという状況」が別々のものであった場合、A・B両者の主張は共に正しいということもあり得るのです。
SNSにおける議論においては第三者が飛び入りで議論に参加してくることもあります。あなたが第三者の立場から参加することもあるでしょう。
ですが、この時は、一層の注意が必要です。議論全体へのチェックが行き届かないまま、一部だけに反応して軽々に参加したり、あるいは、対立してはいない事項までをも対立しているものだと勘違いして自説を述べてしまったりしても、議論を混乱させるだけ。
まして、議論の前提となっている事柄に対して理解がないままに参加してしまうのは論外です。
第三者の立場から議論に参加するのであるならば、そもそもの議論を始めた両者の主張を正確に理解する必要があります。
C 「表現の自由は憲法や法令に反しない限りは守られなければならない」
D 「Cは「どんなときでも表現の自由は守られなければならない」と言っているが、これは極端な意見だ」
勿論、この文例におけるDの主張も的外れです。Cの主張を無視しています。(意図的に行っているならば、Straw manという詭弁)
E 「どんな身体的特徴を持っている人でも差別されない社会になって欲しい」
F 「暴言を吐く人も生きやすい社会にしようと思わないのは何故なのか?」
Fの主張は、Eの主張とは文脈が違うものであり、論点のすり替えという詭弁に堕してしまっています。論外です。
どの文例でも、最も効果的な再反論は、
「私はそんなことは言っていない」
となります。そして、この再反論には、批判者(上記の文例においては、B・D・F)は、本来、反駁することすら出来ません。無理に反駁しようとしても破綻が拡大していくばかりです。
相手の主張を読み間違えてしまったとき、相手の主張とは文脈が違うことを批判として使ってしまったとき……こんな時には「ごめんなさい。あなたの言っていることを誤解してしまいました」とちゃんと謝罪しましょう。
間違っても「相手の文章が拙いせいだからだ!」などと誤読の責任を相手に押し付けてはいけません。相手の主張を理解できかったのも、理解しないまま批判を展開したのも、批判者自身の責任に帰することです。
相手の主張の意味が理解できないのであるならば、「わからない」と素直に言えばいい。また、判断が付かないのであるならば、保留しておけばいいのです。
用語の意味は文脈で変化する
同じ単語でも文脈が違えば、意味が違ってきます。相手の主張を理解するうえで、特に注意すべきポイントです。
例えば、民族という単語には、二つの意味があります。その二つとは、NationとEthnic group。この二つは全く意味が異なります。
Nation……国民国家における国民。
Ethnic group……文化によって区分される集団。
本来ならば、もっと詳しく説明したいところですが、今回の記事の眼目ではないので、省略。かなり大雑把な説明ですが、この二つが違うものだと理解して頂ければそれで十分です。(他にもTribeも民族と訳されることがあるようですが、こちらは部族が定訳)
さて、次のような文例において、”民族”はどちらの意味で使われているでしょうか?
「○○という民族には集団主義的な傾向が強い」
どうでしょうか? 判断出来ますか?
前後の文脈をしっかりと読み取らなければ、判断するのは難しいでしょう。Nationのことなのか、それともEthnic groupのことなのか、この一文だけでは判断するの至難です。
用語の意味するところは文脈によって変化します。相手はその用語を(その文脈上では)正確に使っているのかもしれません。どんな文脈である用語が使われているのかには注意が必要です。
詭弁を使ってしまうのは論外!
これも重要なポイントです。
詭弁とは、一見して正しそうではあるが、実は間違っている虚偽の推論のことを言います。
つまり、詭弁を使ってしまったら、その時点で、あなたの相手への批判は論理的には成立し得ないものになるのです。
意図してのものではないのであるならば、ただの誤謬で済みますが、それでも、論理的には間違っていることには変わりありません。(こういった論理的な誤謬の代表的なものには前後即因果の誤謬というものがあります)
相手からすれば、詭弁であることを指摘した上で再反論を行うことが可能になり、批判者の主張には、批判として妥当であるか否かという以前の問題が提起されてしまうことになります。要は、批判者の主張の弱点、それも致命的な弱点となってしまうのです。
詭弁の例
では、詭弁の実例を幾つか見ていきましょう。
1 未知論証
この記事より平沢勝栄議員による発言のうち、詭弁に該当するものを以下に引用します。
「実在児童の人権救済とは関係ないが、海外では漫画も規制対象だ。漫画やアニメに影響されて青少年らが性犯罪に走る例も、警察の資料によれば実際にある。可能性が否定できない以上、規制の話が出るのは当然だ。日本がこうした漫画の輸出国と批判される状況も踏まえ、漫画などの規制についても検討する規定は入れた方がいい」
「漫画やアニメに影響されて青少年らが性犯罪に走る例も、警察の資料によれば実際にある。可能性が否定できない以上、規制の話が出るのは当然だ。」の個所が未知論証。
未知論証とは「A=Bではないと断言できないので、A=Bである」というタイプの詭弁のことです。「A=Bではないと断言できない」という前提からは、如何なる結論も導出できません。A=Bかもしれないし、A≠Bかもしれない。何とも言えないわけです。ならば、A=Bという結論は導出できない。当たり前の話ですね。
「漫画やアニメが性犯罪を惹起する可能性はあるので、漫画やアニメは規制すべきだ」と平沢氏の発言を要約することが出来ますが、この「可能性はある」という言い回しがポイント。つまりは、平沢氏自身も「漫画やアニメが性犯罪を惹き起こす」とは断定していないのです。「漫画やアニメが性犯罪を惹き起こすかもしれないし、そうではないかもしれない」と「可能性が否定できない」という個所を言い換えるとこれが未知論証であることがハッキリします。
ちなみに、「漫画やアニメに影響されて青少年らが性犯罪に走る例も、警察の資料によれば実際にある」と平沢氏は発言していますが、創作物によって性犯罪が惹き起こされたことを証明するためには、因果関係があることを証明しなければなりません。ある性犯罪者が「オレがこんなことをしたのは、漫画の影響だ!」なんて主張したとしても、それは何の根拠にもならないのです。
2 媒概念不周延の虚偽
文例1 「表現規制反対派は右派・保守派でアンチポリコレ・アンチフェミ・反差別に反対である。
— るーでる@柏葉(( ゚∀゚)o彡°AMD!AMD!) (@rudel101) November 25, 2021
指摘 媒概念不周延の虚偽である。この場合、例えば「表現規制反対派」⊆「特定の思想的傾向」⊆「反ポリコレ・差別的・体制・権力に親和的」といった部分集合が成立していなければならない。
(実例としてあげることの出来る言説を幾つか確認しておりますが、下品なものであったり、既に削除されていたり、アカウントそのものが凍結されていたりと問題があるものが多かったので、私自身が過去に挙げた文例を実例に代えさせて頂きます。悪しからず)
表現規制反対派を何等かの思想・傾向などに紐付けて論じようとする言説は散見されますが、これは媒概念不周延の虚偽と呼ばれる論理的な誤謬に陥っています。
無理矢理に定型化すると
「ミソジニー・反ポリコレ・反リベラルかつ差別的な人は自民党支持者だ。表現規制反対派は自民党支持者だ。よって、表現規制反対派はミソジニー・反ポリコレ・反リベラルかつ差別的だ」
となるでしょう。
ミソジニー・反ポリコレ・反リベラルかつ差別的な人=X
自民党支持者=Y
表現規制反対派=Z
としたとき、「X=Yであるとき、Z=Yなので、Z=X」と簡易に表すこともできますが、これは、Z⊆X⊆Yが成立していない限り間違い。実際には、表現規制反対派は様々な立場の人々を内包しており、与党支持者もいれば野党支持者もいます。(私のような、どの政党も支持していない人もいます)
実際、表現規制反対派の政治家は与野党に散らばっています。表現規制反対派の政治家が与党にも野党にもいるということは、表現規制反対派にも与党支持者と野党支持者とがいるということを意味しています。
3 人身攻撃
興味深いのは、こうした箸にも棒にも掛からない反応の大半が特定のパターンに陥っている点です。誤読は理論上無限のパターンで誤ることができるはずなのに、その誤りの形式がこうも固定的であるというのは、彼らの脳内活動を反映しているような気もします。
このような、相手の主張ではなく相手の人格・属性などを攻撃し、以て相手の信頼性を貶める論法を人身攻撃と言います。勿論、相手の主張への反論ではないために有効なものにはなりません。
相手の主張に反対するならば、相手を攻撃しても意味はありません。相手の主張をちゃんと検証した上で反論しましょう。
また、相手の主張をちゃんと検証した上で反論できるのであるならば、相手の人格・属性・思想などなどを攻撃する必要はありません。相手を攻撃するのは無駄であるばかりか有害です。(人間には感情があるのだ、ということをお忘れなく)
4 Straw man
これについては、上記した
A 「Xについては、ある状況下ではYとなると考える。その理由としては~~」
B 「Aは「Xについては、如何なる状況下でもYとなると考える」と主張しているが、それは間違いだ。何故ならば、Sという状況下ではXはTとなるからだ」
と
C 「表現の自由は憲法や法令に反しない限りは守られなければならない」
D 「Cは「どんなときでも表現の自由は守られなければならない」と言っているが、これは極端な意見だ」
という二つの例を挙げております。相手が主張してもいないことを批判しても無意味なのは言うまでもありません。
5 論点のすり替え
ドイツ、フランス、イタリアの首脳がウクライナを訪問し、ゼレンスキー大統領と会談している。相も変わらずゼレンスキー大統領は「武器供与」を訴えている。どの歴史を見ても、自前で戦えないならやめるのが当然ではないか。ドイツ、フランス、イタリアもゼレンスキー大統領に「私たちが中に入るから、ここは停戦だ」と何故呼びかけないのか。戦争にはそれぞれの言い分、理屈がある。かつての日本もそうだった。これ以上、戦争を継続し、犠牲者を出すことは許されない。
典型的な論点のすり替えです。2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵略戦争において、侵略者はロシアであり、ウクライナは被害者。これは動かしようがない事実です。
「戦争を継続し、犠牲者を出すことは許されない」と主張するならば、ロシアへウクライナからの撤兵を呼び掛けるべきなのは、言うまでも無いでしょう。ウクライナは自衛権を行使しているだけです。
2月23日以前のウクライナにも問題があったとしても、それはロシアによる侵略を正当化するものではありません。
にも関わらず、鈴木氏は、「戦争にはそれぞれの言い分、理屈がある」とロシアとウクライナのそれぞれの立場を無理に対等化することによって、ロシアを弁護しています。
要は、ロシアの侵略者としての立場を糊塗して、本来の論点(=ロシアによる侵略)から遠ざけようとしているわけです。
ちなみに、歴史上の事実として、「どの歴史を見ても、自前で戦えないならやめるのが当然」とは言えません。第二次世界大戦に限っても、イギリスやソ連はアメリカからの軍需物資の援助にかなり助けられています。所謂、レンドリースです。イギリスへの援助は有名ですが、ソ連へのレンドリースも莫大なもので、特に兵站の維持に関しては、アメリカ製トラックの果たした役割は極めて大きいものがあります。(45年時点で赤軍が保有するトラックの3分の2がアメリカ製)
侵略を受けた国が友好国や利害関係が一致した国へ援助を求めることこそ当然と言うべきでしょう。
他にも様々な詭弁があります。私としても一つ一つ実例を挙げて、それらを説明したいところなのですが、キリがありませんし、私の観測範囲において散見される詭弁のうち、代表的なものは解説しましたので、詭弁の例の列挙とその説明はここまでにしておきます。
表現規制反対派として
表現規制反対派として意見を表明していれば、論争に巻き込まれることもあるでしょうし、また、表現規制派の言説に批判を加えることもあるでしょう。
しかし、相手の言っていることを誤解した上で批判したり、人身攻撃などの詭弁・誤謬に陥ってしまったりすれば、第三者からは表現規制反対派の主張にも説得力が無いように見られてしまいます。
表現規制派に対しては、その主張を正確に理解(≠賛同)した上で、人身攻撃などの詭弁に陥ることなく、冷静に批判を続けていくことこそが肝要です。
また、文脈を正確に把握し、相手の言っていることがただの感想なのか、それとも、表現規制派としての意見なのかをも判断する必要もでてくるでしょう。第三者を不必要に巻き込んで表現規制反対派への悪印象を広めないようにしようということでもあります。
終わり
今回はここまでで。本当はもっと詭弁の実例と説明を充実させたかったのですが、余りに煩雑過ぎて断念致しました。次回以降の記事で改めて触れることもあるかもしれません。その時は、宜しくお願い致します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
