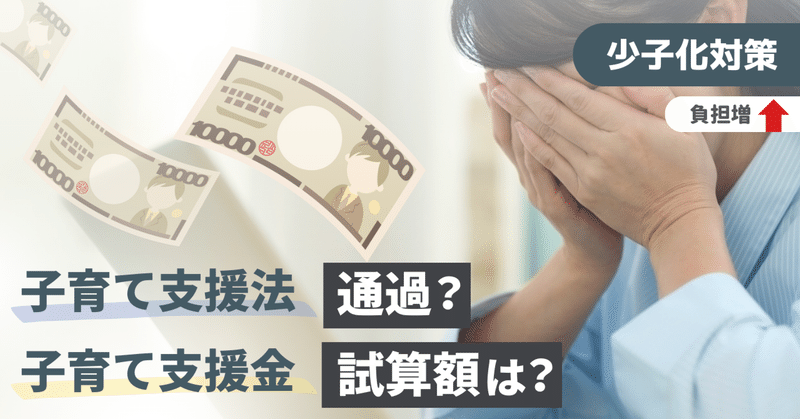
少子化対策の今、子ども・子育て支援法改正と支援金徴収の現状に迫る
先月4月、少子化対策の強化を盛り込んだ「子ども・子育て支援法」の改正案が衆議院で可決され、また「子ども・子育て支援金」の負担額についても具体的に明らかになってきました。子どもの有無に関わらず、全国民の未来と生活に密接に関わるこれら政策について、最近の動向を把握してみたいと思います😃
✅️子ども・子育て支援法の改正案が衆議院通過
政府が積極的に推進する少子化対策の一環として、改正が検討されている子ども・子育て支援法。この改正案の中身としては、児童手当の拡充や育児休業給付の拡充(両親が共に14日以上の育児休業を取った場合に、育児給付を最大28日間、実質10割に引き上げる)等が挙げられます。また、この財源確保のための新たな「支援金制度」を創設し、公的医療保険料に上乗せして国民から徴収すると発表して話題になりました。

この改正案が、4月19日の衆議院本会議で与党の賛成多数で可決、衆議院を通過し参議院へと送られます。野党側は事実上の子育て増税だとして法案に反対しておりますが、政府・与党は早期成立を図る方針で積極的に進めている状況です。

結局は国民の負担増、これで本当に子どもは増えるのか?少子化対策につながるのか?子育て支援は確かに必要だが、少子化対策としては疑問が残る形となりました。では、これら政策の実現のために、実際に国民の負担として課せられる「支援金」についての現状をもう少し深堀りしてみます。
✅️子ども・子育て支援金、負担額の試算公表
少し前に話題になった「子育て支援金」について前回も記事にしていました。(前回の記事はこちら👇️)
これは岸田総理が掲げる”次元の異なる”少子化対策を推進するための財源確保として国民に負担を課すものでした。具体的な使い道については、「児童手当拡充」「出産手当」「共働き・子育て支援」などが挙げられます。

さて、2月当初には1人当たりの徴収金額はワンコイン=月平均「500円弱」を徴収すると謳っていましたよね。この徴収金額についても正確ではない、少額に見せかけている、など当時国民からは様々な意見が寄せられていました。さらには3月に政府は扶養家族を除いた被保険者の平均負担額は「800円」になる、と公言。次々と変わる金額になんとも不信感が募る一方ですが‥実際のところどうなのでしょうか?ついに今月、政府が「年収ごとの負担額」を初めて具体的に明らかにしました。
やはり、所得に応じて負担額が変わる見込みとなっており、当初の500円を超える場合もかなり多くなりそうです。予想通りワンコインでは収まらないですね😢

今回発表された金額に対しては、やはり「高い」「上がった」のような否定的な反応が大多数であり、世代や子どもの有無により異なる反応を見せているものの、政府に対する厳しい批判の声が目立つ印象となっています。
また、この金額自体もどんどん上がっていくという可能性もあるとのことで、どこまで国民の負担が大きくなるか、不安な面も隠しきれませんよね。少子化は日本の解決すべき重要課題であることは間違いないですが、国民としてはその他の増税や物価の上昇など生活に対する不安も相まって、いろいろな負担が増えていくことに対して懸念せざるを得ない展開になっています。
政府が特に重点的に取り組んでいる少子化対策・子育て支援に関して日々新しいニュースが報道されていますが、働きながら子育てに奮闘する働くママ・パパ、もしくは近い将来結婚・出産・育児などを想定している若い世代には良くも悪くも非常に重要な情報になるかと思います。未来の働き方、子育ての在り方など、人生を左右するこれら政策・ニュースについてこれからも引き続き、追っていきたいと思います。
✅少子化対策!柔軟な働き方を実現するビジネスツールを利用しよう
✅リモートアクセスツールやWeb会議ツールなどを活用して、いつでもどこでも効率的に働こう
✅「働き方」を変えてより充実した人生を送ろう

👇👇👇在宅勤務で特に活躍する2つのツールとは👇👇👇

📌RemoteView(リモートビュー)
インストール不要でWebブラウザから簡単に!いつでもどこからでも遠隔地のデバイスにスムーズに接続・操作ができるリモートアクセスツールです。企業や大規模の団体などで特に使いやすい管理・セキュリティ機能が充実!【公式サイト】noteマガジンはこちら👇
📌RemoteMeeting(リモートミーティング)
Webブラウザで簡単に始められるWeb会議ツールです。初心者でもすぐに使い始めることができる分かりやすいデザインに加え、豊富なレイアウトや3Dアバターモード、AI自動議事録、さらに双方向のコミュニケーションと共同作業を可能にする様々な便利機能が充実しています。【公式サイト】
noteマガジンはこちら👇
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
