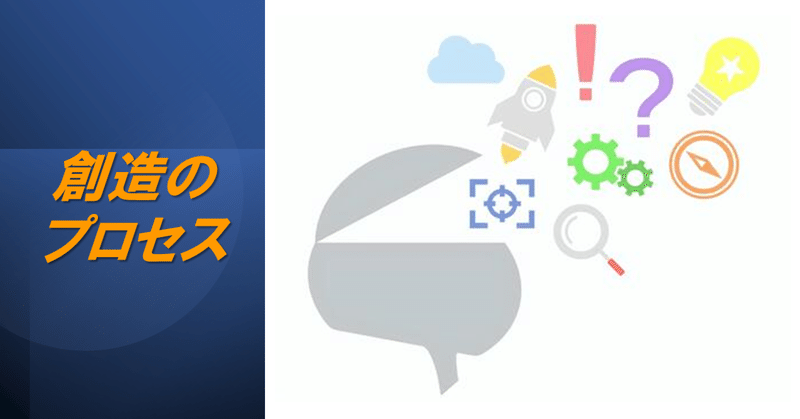
『稲盛和夫一日一言』 5月14日
こんにちは!『稲盛和夫一日一言』 5月14日(火)は、「創造のプロセス」です。
ポイント:創造とは、意識を集中し、潜在意識を働かせて深く考え続けるという苦しみの中から、ようやく生まれ出てくるもの。
2015年発刊の『稲盛和夫経営講演選集 第1巻 技術開発に賭ける』(稲盛和夫著 ダイヤモンド社)の中で、創造的な仕事をするということについて、稲盛名誉会長は次のように述べられています。
創造していく最初の段階は、たいへん楽天的に自由奔放な発想で目標設定し、それを制約すべき条件というのはあまりつけないほうがいいと思います。
ただし、それは単なる空想や夢に終わるものではなく、実現できそうだと信じられるものでなければなりません。そのようなものであれば、それをやろうと躊躇なく決めてもいいはずです。
もちろん、企業における研究開発であれば、会社の方針にのっとったものでなければなりませんし、将来でき上がったときの採算という問題もあるでしょう。会社が出せる予算にも制約があるかとは思いますが、それらを踏まえた上で、奔放に発想すべきなのです。技術者にとって、そうした自由奔放な発想で最初に目標を決めるときが、最も喜びを感じるときかもしれません。
一方、目標を実行に移していく段階というのは、すさまじく厳しい状況が続きます。だからこそ、超楽天的な人間であっても、修羅場を耐えて意志を貫いていくという精神状態が必要です。
そのような人間性を持った人間にやらせなければ、資金だけ使って何の成果も出ないということになりかねません。その結果、初めからそんな研究などしなければよかったということになってしまいます。
つまり、目標を立てるときは超楽観的でいいのですが、実行に移していく段階では、目つきまで変わってくるような、すさまじいばかりの精神状態になっていなければなりません。来る日も来る日も過酷な研究を続けるわけですから、タフな神経がなければノイローゼになってしまいます。
ですから、自分ですぐに気分転換できるタイプの人でなければ続かないでしょう。長時間の修羅場を耐え抜いていくには、ごく簡単に自分で気分転換できる手法も必要です。
そのような人が自分の意志を貫いていくと、研究開発は必ずできます。できないわけがないのです。それは、最初にできると信じたわけですから、できるまでやるわけです。
「そんなバカな」と笑う方もおられるかもしれませんが、その意味ではやはり、「できると思う」ことが大切なのです。(要約)
今日の一言には、「創造というものは、決して単なる思いつきや生半可な考えから得られるものではない」とあります。
2001年発刊の『京セラフィロソフィを語るⅠ』(稲盛和夫著 京セラ経営研究課編/非売品)「自らを追い込む」の項で、名誉会長は次のように説かれています。
大学を卒業して何年か経ったある日、私は久し振りに母校を訪ねました。そのころの私は、京セラでカリカリになって研究をし、また会社経営にも全力を注いでいました。
先生からは、「稲盛さん、そんな調子では身体が持ちませんよ。人間、余裕がなければいいアイデアなど出せないものです。あなたみたいな技術者は、素晴らしいアイデアを次から次へと出して開発をしていかなければならないのだから、そんなにギリギリまで追い詰めてはいけません」と諭されました。
ところが私は先生に向かって、「先生、それは違うと思います。素晴らしいアイデア、閃きというものは、追い込まれてギリギリのところで研究をしているときにしか出てこないのです。余裕があるときに出てくるアイデアは単なる『思いつき』であって、その程度の思いつきでは最先端の研究などできるわけがないのです」と言い返したのです。
やはり、ノーベル賞をもらうような素晴らしい成果を残した研究者は、ギリギリのところで研究をした人なのだと思うからです。
自らを追い込むということは、それに熱中するということです。熱中して、他のすべてが見えなくなってしまって、ただそれだけに没頭する。
つまり、精神、意識が集中している状態にまで自らを追い込んでいくことによって、精神的な閃きと同時に、自分でも想像がつかないような物理的な力をも発揮することができる。
そうやって精一杯自分を追い込んで、「もうこれ以上はやれない」と思えるところまでいくと、「自分は精一杯やった」という自負がありますから、あとは「天命を待とう」という心境に辿り着けるはずです。
中途半端にしてしまうのではなく、一生懸命に力を出し尽くし、「ここまでやったのだから」と達観して、あとは「天命を待つ」。つまり、安心立命の境地に到るまで、自らを追い込むことが重要なのです。(要約)
世の中にない、前例のないことにチャレンジする際には、決して易きに流されることなく、常にこれ以上後には引けないという精神状態に自らを追い込んでいかなければなりません。
肉体的にも精神的にも追い込まれてもがき苦しむ、そうした修羅場を潜り抜けた先には、自分でも驚くような成果が必ずや待ち受けているはずです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
