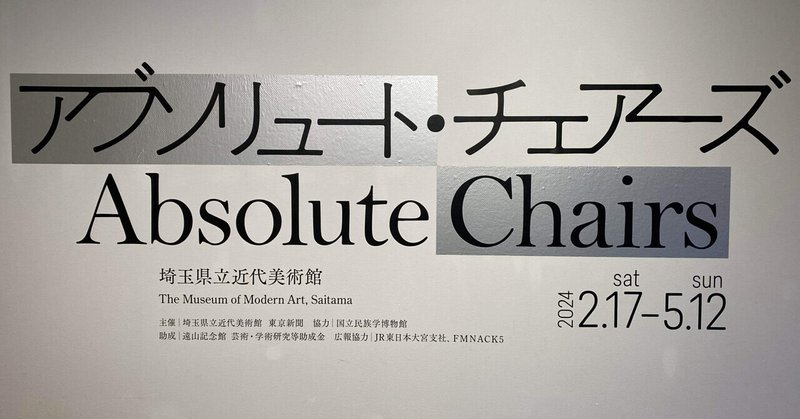
【じゃない方の椅子】アブソリュート・チェアーズ 埼玉県立近代美術館
椅子の展示??…
インテリア系?
インダストリアルデザイン?
プロダクト系?
ではない文脈の、椅子をテーマとした展覧会である。
このテーマの切り口がめちゃくちゃ面白かった。
身近だが、それ故に深く考えることもなく日々腰掛ける椅子。その椅子についてアートはどう関わってきたか。
うーーん、埼玉県立近代美術館はいつも多彩な変化球を投げてくる。
そんな概要はこちら。
椅子は多くのデザイナーや建築家の創造性を刺激する絶対的なテーマであると同時に、アーティストにとっても魅力的なモチーフとなってきました。玉座のように権威の象徴となることもあれば、車椅子のように身体の補助となることもあり、電気椅子のように死や暴力とも無縁ではない椅子。また、私たちが椅子に座って向き合えば、そこには関係が生まれます。この上なく身近でありながら、社会や身体との密接な関わりの中で幅広い意味や象徴性をまとった椅子は、まさに究極の日用品と言えるでしょう。 アーティストたちは椅子のもつ意味をとらえ、作品を通じて社会の中の不和や矛盾、個人的な記憶や他者との関係性などを浮かび上がらせてきました。アートのなかの椅子は、日常で使う椅子にはない極端なあり方、逸脱したあり方によって、私たちの思考に揺さぶりをかけます。
館内、写真バツマークのみ撮影禁止。他は可。
埼玉県立近代美術館の所蔵品を中心に他館からの借用作品もあり。おっ!と思ったのが高松市美術館から来ていたもの。なかなか行けない場所の作品が見れるのは嬉しい。
年代的にはデュシャンから現代をカバー。
座れる作品もあってちょっと体験もできる。
アーティストごとにほぼ解説付きなので作品数に対して読む時間はややかかるかもしれないが、キャプションがデカめで読みやすい。
目がシパシパする春めいた午後でも眼球に優しい。
作品ピックアップ

展示室に入って、遠目でまずこの作品が見え、その不安定さに(またまた〜笑)と思い、半笑いで近づいてしばし見つめていると(あれ?これはこれで安定しているのかも?)と考え始める。
そもそもこれ、このままレンガくっついたまま倉庫に仕舞われているのか?などと考え始めてしまい、はて?誰の作品か?と思ったら高松次郎。
わー!高松さんだー!
ハイレッドセンターの「ハイ」の人ですね。

「影シリーズ」や「この7つの文字」「○○の単体」などはよく見る機会があるが、この埼玉近代が所蔵する高松次郎作品はちょっと方向性が違う物もあり、たまに所蔵品展で遭遇すると物すごい嬉しい。今回も初めてみる作品のだった。
【椅子は座る為のものか?】


このミシンで縫われた絵画。
椅子に大量の衣服が積み上げられている様である。
場面に身に覚えがありすぎて悶絶してしまった。
私は今朝、椅子にデニムを引っ掛けたまま出かけて現在地に到着している。
椅子が、物掛け、物置になってしまっている。
でもこれ、結構皆あるあるなのではないだろうか?乾いた洗濯物をとりあえずとソファの上に置いたり。
子供達に引き出しに片づける様にと伝えると各々で衣服を畳みしまい込む。が、最後に未だ椅子に残った洗濯物は他ならぬ私の靴下(しかも片足だけ)だったりする。こういう時、自分自身に心の中で舌打ちをしている。
その感覚が蘇る。美術館に来て日常が炙り出される。
(私、非日常的な感覚を味わいたくて美術館に来ているのではなかったっけ?)と思いつつ、どこかでこの状況を可笑しんでいる自分もいる。
要は笑いたいのだ。
多彩な作品が続く
各テーマに沿って作品のジャンルも様々でどんどん投げてくる埼玉県立近代美術館。
この他にもウォーホルの電気椅子のシルクスクリーンや、宮永愛子氏のナフタリン作品。
名和さんのセル作品(でも椅子)などなど。


現代美術好きには特にオススメ、現代美術が「?」な方にもおすすめの企画展だ。
MOMASコレクション

毎回、魅力的な作品が出ている埼玉県立近代美術館の常設展示室。
コレクションの方向性も面白く企画展後は必ず立ち寄らねばならない!と時間をしっかり確保して出かける。
今回はリアリズムの話。
上田薫さんの所蔵品が見れて最初からニヤニヤ。
衝撃だったのは明治のリアリズム、倉田弟次郎の作品群。
この表現を明治時代にしていたのか、という。
脈々と現代につづくリアリズム絵画。
その源流に近いところ。
純粋に映し出そうとしたのか、それとも写真に対する挑戦だったのか。

どうやって描いたのだろうか?これまた解説がすごく面白かった。

やはり、その当時少しずつ出回り始めた写真から描き起こしたらしいのだが、それでもすごい。
紙の質も筆記用具のクオリティも今ほどではない時代…。
ここから上田薫氏の生卵までリアリズムの流れは続いていくのか。
上田薫氏が1928年生まれだから倉田弟次郎が亡くなった34年後か。と思うとなんだか、そんなに遠い話ではない?とも思ってしまった。

毎回、ほんとニクい展示をしてくれる埼玉県立近代美術館。ぜひ多くの方に訪れてほしい県立美術館の一つだ。

自分の手荷物を預けるのが好き。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
