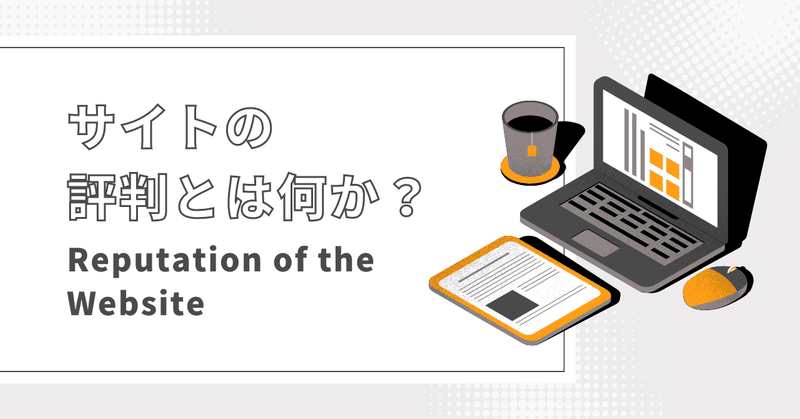
サイトの評判(Reputation of the Website)とは何か?
【Reputationという単語は検索品質評価者ガイドラインに199回も出現している】昨年のヘルプフルコンテンツアップデート、今回のコアアップデート、サイト評判の悪用に対する対策の裏側には何があるのか?検索品質評価者ガイドラインでReputationという単語が出現するポイントを吟味したのでシェアします。
サイトの評判(Reputation of the Website)は品質評価の重要なプロセス
そもそもGoogleが捉えるサイトの評判(Reputation of the Website)とは何か?ということを考えてみたいと思います。
Googleが公開している検索品質評価者ガイドラインはGoogleを理解する上で、非常に重要な文書ですが、最新版においては、Reputationという単語は199回出現し、そのうち、Reputation of the Websiteは28回出現します(いずれも目次含む)。
ページ品質評価の重要な部分の一つはサイトの評判を理解することだと冒頭から述べており、(An important part of PQ rating is understanding the reputation of the website. )そのサイトの評判を理解するための手法として「評判調査」(Reputation researchという言葉は11回出現します)と述べ、すべてのページ品質評価タスクにおいて、評判調査が必要としています。
評判調査とは何か
ここで重要なのが評判調査の対象です。以下の文章があります。
Reputation research applies to both the website and the actual company, organization, or entity that the website is representing.
WEBサイトを対象とするほか、実際の企業、組織、エンティティを対象とするとあります。ここでポイントになるのがエンティティです。評判の受け皿としては企業や組織を対象とされるのが分かりやすいですが、エンティティには個人も含まれます。検索結果画面にも表示されるナレッジパネルはほぼこのナレッジグラフにおけるノード、つまりエンティティとほぼ同義と見てよいと思います。
評判は「運転免許証」である、という考え方
今回のコアアップデートで個人ブログが順位を落としている背景として、この【エンティティに見なされていない運営者のサイト】の順位が下落しているというのが私の現時点の仮説です。
コアアップデートで定性分析をしていると、とあるクエリの検索結果上位30位のうち、公式サイトが26個入ってくるものがありました。特にYMYLのクエリでもありません。
裏を返せば、それまで上位に合ったメディアサイトや個人ブログが軒並み順位を落としているわけです。現にとあるクエリで4位に表示されていた某サイトは、運営者情報はナレッジパネル(≒エンティティ)が表示されず、公式サイトに押し流されず上位に留まっているメディアサイトは、運営元がナレッジパネル(≒エンティティ)がきちんと表示されていました。
YMYLであろうがなかろうが、評判調査の対象となる運営者かどうか、ここが今後のインターネット上で情報発信を行う上でのいわば運転免許のようになってくるのではないでしょうか。
評判調査をどのようにおこなっているのか?
検索品質評価者ガイドラインでは紙幅を割いて評判調査の手順も述べています。3.3.3 How to Search for Reputation Information about a Websiteがそれです。
[ibm -site:http://ibm.com] のようにウェブサイトや企業自身が書いたり作成したものではない情報源を見つけるようにしなさい、とあります。裏を返せば、その各種エンティティにおいて、運営者自身以外によって作成された情報が極めて少ない場合、その運営者の評判を調査することができないということです。これが先ほどの運転免許の正体です。
そのほかにもwikipediaやレビューを用いた手法なども細かに記載されています。
個人はどうすればいいのか?
それでは個人はどのようにエンティティとみなされるのか?
・オンラインフォーラム上のディスカッション
・学歴
・同業者による評価
・専門家の共著者
・引用(サイテーション)
これらが評判の証拠となるとされています。
つまり、その分野での専門家かどうか?ということが見極められるということになり、これは【匿名による情報発信】が今後ますます不利になるということだと思います。
Googleは評判に関する情報が見つからない時の場合も触れています。品質の高低を示すものではなく、評判情報"reputation information"が無くても高い評価を得ることができる、と記載はされているものの、一方で、他のページ品質の考慮事項に特に注意を払うべき、としています。
ここでひとつ分かりやすい例を示します。海外旅行をしたことのある方の場合、日本国のパスポートを持っていることによって、入国審査がスムーズだったことはなかったでしょうか?
評判調査の情報があるというのはこのイメージに近いように思います。その人が実際に問題があるかどうかを必ずしも判断できるものではないが、この評判調査ができない場合、その他の品質評価において基準値を上げざるを得ないということです。
この文脈で【サイト評判の悪用】について再考する
昨年のヘルプフルコンテンツアップデート、そして今回のコアアップデートにおいて、エンティティに紐づく評判ということが評価として重視されていたとするならば、今回のsite reputation abuse(サイト評判の悪用)を執行した意図がとてもよく分かるようになります。ここでもひとつ例を挙げます。
高品質(High Quality)および最高品質(Highest Quality )のページの事例として挙げられているもののうち、検索品質評価者ガイドラインで真っ先に挙げられているのは何のサイトでしょうか?
新聞社です。
今回、Forbesを始めとした、大手新聞社、出版社のクーポンディレクトリを手作業で処分していった取り組みも、この評判調査を今後のインターネット上のコンテンツの運転免許証としていくことのひとつの象徴のように思えます。
そもそも情報の信頼性とは何か?
今回のサイトの評判については、何をもって情報を信頼できるのか?という問いにつながります。
どのようにして情報源を見極めるのか、また情報発信者としての責任と、個人法人に限らず自らのエンティティにどのように評判を蓄積していくか。
いわば運転免許証がすべてではないので、エンティティに紐づかない媒体でも現時点では上位表示されているものはまだ存在します。ただし、Googleが構築し続けているナレッジグラフ(ナレッジパネルはこの一部を表示している)を前提にしていく大きな流れは不可逆なのではないだろうか、と思っています。
ぜひ考え続けていければと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
