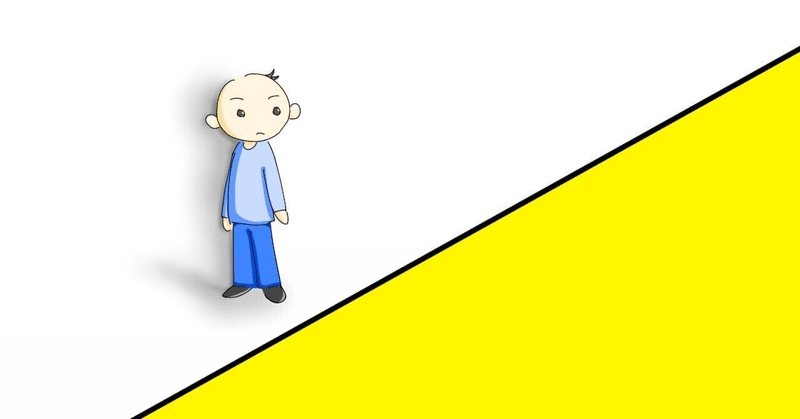
合理的と非合理的の境界線とは
テレビ番組なんかを観ていると、グルメ情報が無尽蔵に入ってくる。
都心のどこそこのお店が美味しいとか、関西のなんとかっていうお店が人気だとか、貧乏な北海道民はハンカチを噛みしめて観ることしかできない。
地域格差も甚だしいが、そもそも人の多い地域は得意ではないので、半ば諦めている。まぁそんなことは置いといて。
中には、「有名な高級ホテルのシェフを何年も勤めていた人が、一念発起してラーメン屋を開業した」なんていう話もある。
この手のエピソードはグルメ界に限らず、「大企業のエリートサラリーマンが、田舎で小さなカフェを始めた」みたいに、多様性の高い現代ではままあることだろう。
しかし、これらについて少し疑問に思ったことがある。
それは、なぜ現状を放棄してまで新たなチャレンジをするのか、ということだ。
高級ホテルなり大企業なり、そのままそこで働き続けていれば、それなりに生活は安定するだろうし、それなりに稼げる算段もつきそうなものだ。
一方、開業は時間もお金もかかるし、先行きがかなり不安定になる。
また、環境がガラリと変わるわけだから、精神的負荷も大きいだろう。ハイリスクにもかかわらずリターンが読めないというのは、なかなかハードルが高いように思う。
ところで、最近いろいろな本を読んでいる中で、行動経済学に興味を持ち始めた。
行動経済学とは、簡単に言うと経済学と心理学を融合させた学問で、人の心理や感情が市場にどんな影響を与えるかを研究しているものである。
行動経済学の概念として、「人は必ずしも合理的に行動しない」といったものがある。
たとえば、家から100m先にコンビニAが、500m先にコンビニBがあるとしよう。
売っている品物やその値段はまったく同じ場合、家から近いコンビニAを利用する方が合理的と言える。
しかし、中にはコンビニBを利用する人もいる。その理由は、コンビニBの方が店員の接客がいいとか、コンビニAまでの道は坂になっていて歩きにくいからとか、いろいろあるだろう。
このように、「単純なお金の損得勘定だけで経済を語ることは難しいよね」というのが行動経済学のキモとなっている。
ラーメン屋になったシェフの話に戻すと、これもある意味で行動経済学の一部を表しているのではないだろうか。
ずっとホテルで働き続けるよりラーメン屋になることを選んだ理由としては、多くは夢というか野心のようなものだと思う。「こっちの方が楽に稼げるから」という理由でラーメン屋を始める人は、そうそういないだろう。
つまり、稼ぎ云々よりも自分の感情を優先にした、非合理的な判断と言える。
しかし、非合理的というものは、決して損ばかりではない。
先ほどのコンビニの例で言うと、コンビニBは家から遠いけれどもそれを凌駕するだけのメリット(接客の質、道中の歩きやすさ)があるということになる。
合理的というのはあくまでもお金だけに注目した場合であって、感情やその他さまざまな要素を総合すると、非合理的な方がむしろトータルでメリットが大きくなるという逆転現象が起きる。
行動経済学とは、なんと奥の深い学問だろうか。
人は、理性と感情の両方で生きているからこそ、合理的でも非合理的でもあるような気がする。
仕事の主たる動機はお金だが、突き詰めていくとロマンとか社会貢献に収束していくのかもしれない。
本来お金は手段であって目的ではないのだから、よくよく考えてみれば当然のことなのだが、忘れてしまっていたようだ。
そう考えると、合理的と非合理的の境界線など、あってないようなものなのだろう。
なんと アルロンが おきあがり サポートを してほしそうに こちらをみている! サポートを してあげますか?
