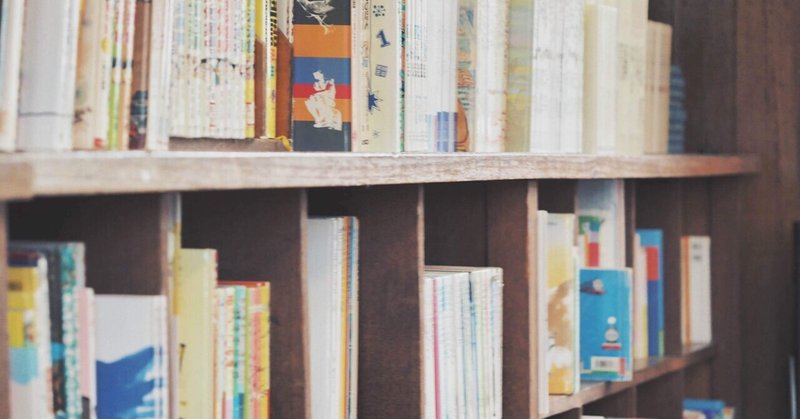
絵本を読んでもらえない非行少年たち
私の友人に、少年院で絵本の読み聞かせのボランティアをしている女性がいる。
国語の研究をしている彼女は、あるとき、少年院で「話し方教室」をしてほしいと頼まれた。
衝動性の犯罪に巻き込まれる少年は、おおむね対話力が低いのだそうだ。
自分の気持ちをことばにできず、他人の思いを推し量ることができない。
気持ちをことばにできないから、暴力に訴えることになってしまう。
そこで、社会復帰する前に、対話力をアップしようという施策で、彼女は呼ばれた。
しかしながら、少年たちは、一筋縄ではいかない。
彼女の働きかけに無反応で、「教室」が成り立たない。
苦慮した彼女は、ふと、「お母さんに絵本を読んでもらったことがある?」と質問してみたのだそうだ。
誰もが、首を横に振る。
中には虚勢を張っている子もいたかもしれないけど、多くが戸惑うような目をしていて、真実のように見えた、と彼女は言う。
そうして、彼女の「絵本の読み聞かせ」が始まった。
少年たちは、初めての絵本に、心を動かすのだという。
犯罪者と呼ばれ、おとなにも恐れられる大きな身体の男子が、『100万回生きたねこ』に涙を流す。
きっと、絵本は、いくつになっても、脳を開拓できるアイテムなのだろう。
息子のトリセツ (扶桑社新書)
育児休業中。
オムツを変えてミルクも飲ませてマッサージもした息子はスースーと寝息を立て始めた。
可愛らしい寝顔。
その近くで本を読む。
本のタイトルは「息子のトリセツ」
「妻のトリセツ」がめちゃくちゃ売れた人工知能などを研究している黒川伊保子(くろかわ いほこ)さんが書かれた本。
「トリセツ」シリーズは黒川さんの科学的知見と豊富な実体験をもとに描かれておりどれも好評。
「妻のトリセツ」でお世話になった私が息子を授かったので有れば「息子のトリセツ」を読み始めるのも不思議ではない。
読書はKindle派の私が読み始めるとハイライト(紙の本で言うマーカーみたいなもん)が止まらない。
・男子の器の大きさは母親が決める。そしてその母親を支えるのが夫の第一使命
・脳のスペックは男女で同じ。だが咄嗟の判断が違うだけ。
・男の子はぼんやりさせると空間認知力が育つ
などなど
ハイライトしたものは妻に「聞いてー!」と言って読む。
妻も「へー」「そっかー」と反応を返してくれる。
そんな中、まだ本の進捗35%だが一番心を動かされ読みながら泣いてしまったのが冒頭の文章だった。
子どもに絵本を読むのは当たり前だと思っていた私。
妻と事前にネットで調べてショッピングモールに行き「あれがいいか」「これはモンテッソーリおすすめだ!」とか実際に本を手に取って10冊弱買った出番を待ってる棚に並んだ絵本たち。
「どの本がお気に入りになるかなー」
「ワシもかーちゃんが絵本読んでくれてたのかな?」
などと思いを馳せる。
でも世の中には絵本も読んでもらえずに自分を理解できず理解されず悩みを打ち明けることも打ち明ける方法もわからずに日本の法を犯し少年院に行ってしまう少年たちがいる。
ただ本を読んでいて少年たちは自分が「わるいことをした」という情報を受け取るコミュニケーション能力が育ってないのではないか?と思った。
そうで有れば「何のために自分は少年院にいるのか?」ということを受け取る力が育ってないので有れば出所したとしても再犯に繋がってしまうだろう。
少年院から出所した後の再犯となればネット記事のPV稼ぎの材料となり正義に反応しちゃった人が群がることは容易に想像できる。
一番は被害者の保護が優先だと思うが少年院を題材とした本や漫画を読んでいると元を辿れば若くして法を犯してしまった少年たちもまた被害者だとわかる。
子どもにも人権がある。
ただ1人で自分のことができない子どもについて保護者が子どもの人権を尊重しなければ誰が子どもの人権を守ってくれるのだろうか。
子どもが育つ土台を作るためにも絵本を読もうと、寝相がエキセントリックな息子を見て思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
